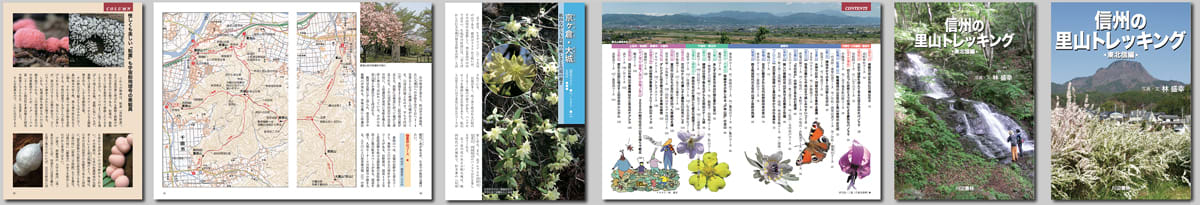台風2号の雨が降る前にと週末に妻女山へ下草刈りと除伐に行ってきました。主に刈るのは山藤の幼木です。放っておくと一日に8センチ成長し、樹木に絡み付いて、やがては木を立ち枯れさせてしまいます。藤の花は、藤棚を作って愛でたり(これは山藤ではなく野田藤)、日本舞踊や歌舞伎の「藤娘」などの演目にもあるように、日本人にとってはなじみ深いものですが、里山にとっては他の木を絞め殺してしまうような少々厄介なつる植物なのです。
妻女山の駐車場には、真っ白な房が美しいトゲナシニセアカシアが咲いています。トゲナシハリエンジュともいいます。花はかなり強い香りがあり、天ぷらで食べられますが、美味しいかといわれると・・・。白粉臭い香りが私はちょっと苦手かな。結構大変だった作業が一段落して、陣場平方面へ。森の奥の倒木で大量のキクラゲを採りました。普通は乾物のキクラゲを水でもどして料理しますが、生のキクラゲは洗ってそのまま使えます。水でもどしたものより瑞々しく弾力があります。これは、中華料理でお馴染みのキクラゲとトマトの卵炒めにします。これは美味です。
帰りに獣害対策で間伐された森にさしかかると、林道下の倒木に鮮やかな朱色が見えました。はじめはバッカク菌か樹液酵母かなと思ったのですが、もしやと思い下りて確かめてみました。粘菌(変形菌)でした。この5月は低温の日が多く、粘菌の出現はほとんど見られませんでしたから、興奮して撮影に臨みました。それが掲載の写真です。粘菌が出ているとは思わなかったので、スーパーマクロ専用のカメラを持って来なかったのが残念でしたが、そこそこのカットが撮影できました。粒の大きさは1ミリぐらいです。残念なのは、その夜から雨ということで、この変形体はおそらく胞子を飛ばす前に雨で流されてしまうだろうということです。雨後のわずかな晴れ間の刺激で出てきたのでしょうが、そういうこともあるわけです。少々の雨なら崩れても元に戻るのですが、激しい雨だと流されてしまいます。といって死んでしまうとも限りません。環境さえ合えば子実体を形成して胞子を飛ばすこともあるでしょう。
帰って調べてみると、トビゲウツボホコリらしいということが分かりました。これは赤松の倒木に発生していました。しかし、目にも鮮やかな見事な朱色です。まるで地上の珊瑚礁。この色素の成分はなんなのでしょう。粘菌が放射能に対してどれほどの耐性があるかは知りませんが、細胞性粘菌の放射線による分化異常のしくみに関する研究などが行われているようです。また、タンザニアで放射性物質を吸い取る細菌が発見されたり、中国で耐放射能性の真菌と放射菌が発見されたりしています。いずれにしても放射性元素を壊す事はできないので、遠い宇宙かとんでもなく深い地中に埋めるしかないのですが・・。詳細な情報は、「放射性物質、放射線、放射能除去技術まとめ」NAVERを参照してください。
原発事故は、ある意味日本の戦中戦後の社会病理が顕在化したカタストロフィー現象といえるかもしれないと思っています。そんなことを端的に表現された、大阪大学の深尾葉子さんの呟きが秀逸と感じたので紹介させていただきます。
-----この世の中は、「まともな脳みそ」を持とうとする人は生きるのが本当に難しい。自らの「感覚」にフタをして、「利権」や「保身」をめざし「役割」を演じて生きることが有利であり、「仕事」であると錯覚されている。しかしそのような生き方こそが、人類を滅ぼす。原発問題はそれを極端に示している。-----
また、ノーベル賞に最も近い経済学者と海外では評価の高い割に日本では、マスコミも経済学者も無視するために一般的には知られていない東京大学名誉教授の宇沢弘文氏を紹介したいと思います。この方も戦後60年余りの日本の問題点を鋭く分析しています。
なぜマスコミが無視するかというと、「日本は米国に搾取されている植民地である」と公然と主張しているからです。興味のある方は、名前で検索してみてください。岩波書店などから著書も多数出版されています。東電や電事連から多額の広告費をもらい天下りを受け入れている堕落した大手マスコミが全く信用できない今、TwitterやUstream、海外メディアなどを利用しないと真実は得られなくなっています。情報リテラシーが求められているわけですが、逆に今ネットがなかったら、大本営発表と噂しか情報源はないわけで、それは本当に恐ろしい事だと思わずにはいられません。
最新の確かな原発情報が欲しいという方は、ぜひTwitterを初めてください。私をフォローする必要はありませんが、私がフォローしている人の中から精査すると、かなり詳細な情報が得られると思います。使い方はツイナビや検索で。大震災で携帯が繋がらないときもこれで安否が確認できました。
また、まだ危険情報に懐疑的な人は、この記事を読むべきです。「安全基準を超えた「内部被曝」(要精密検査)すでに4766人、異常値を示した人1193人」現代ビジネス






★ネイチャーフォトは、【MORI MORI KIDS Nature Photograph Gallery】をご覧ください。キノコ、変形菌(粘菌)、コケ、花、昆虫などのスーパーマクロ写真。滝、巨樹、森の写真、森の動物、特殊な技法で作るパノラマ写真など。ニホンカモシカの写真も。
妻女山の駐車場には、真っ白な房が美しいトゲナシニセアカシアが咲いています。トゲナシハリエンジュともいいます。花はかなり強い香りがあり、天ぷらで食べられますが、美味しいかといわれると・・・。白粉臭い香りが私はちょっと苦手かな。結構大変だった作業が一段落して、陣場平方面へ。森の奥の倒木で大量のキクラゲを採りました。普通は乾物のキクラゲを水でもどして料理しますが、生のキクラゲは洗ってそのまま使えます。水でもどしたものより瑞々しく弾力があります。これは、中華料理でお馴染みのキクラゲとトマトの卵炒めにします。これは美味です。
帰りに獣害対策で間伐された森にさしかかると、林道下の倒木に鮮やかな朱色が見えました。はじめはバッカク菌か樹液酵母かなと思ったのですが、もしやと思い下りて確かめてみました。粘菌(変形菌)でした。この5月は低温の日が多く、粘菌の出現はほとんど見られませんでしたから、興奮して撮影に臨みました。それが掲載の写真です。粘菌が出ているとは思わなかったので、スーパーマクロ専用のカメラを持って来なかったのが残念でしたが、そこそこのカットが撮影できました。粒の大きさは1ミリぐらいです。残念なのは、その夜から雨ということで、この変形体はおそらく胞子を飛ばす前に雨で流されてしまうだろうということです。雨後のわずかな晴れ間の刺激で出てきたのでしょうが、そういうこともあるわけです。少々の雨なら崩れても元に戻るのですが、激しい雨だと流されてしまいます。といって死んでしまうとも限りません。環境さえ合えば子実体を形成して胞子を飛ばすこともあるでしょう。
帰って調べてみると、トビゲウツボホコリらしいということが分かりました。これは赤松の倒木に発生していました。しかし、目にも鮮やかな見事な朱色です。まるで地上の珊瑚礁。この色素の成分はなんなのでしょう。粘菌が放射能に対してどれほどの耐性があるかは知りませんが、細胞性粘菌の放射線による分化異常のしくみに関する研究などが行われているようです。また、タンザニアで放射性物質を吸い取る細菌が発見されたり、中国で耐放射能性の真菌と放射菌が発見されたりしています。いずれにしても放射性元素を壊す事はできないので、遠い宇宙かとんでもなく深い地中に埋めるしかないのですが・・。詳細な情報は、「放射性物質、放射線、放射能除去技術まとめ」NAVERを参照してください。
原発事故は、ある意味日本の戦中戦後の社会病理が顕在化したカタストロフィー現象といえるかもしれないと思っています。そんなことを端的に表現された、大阪大学の深尾葉子さんの呟きが秀逸と感じたので紹介させていただきます。
-----この世の中は、「まともな脳みそ」を持とうとする人は生きるのが本当に難しい。自らの「感覚」にフタをして、「利権」や「保身」をめざし「役割」を演じて生きることが有利であり、「仕事」であると錯覚されている。しかしそのような生き方こそが、人類を滅ぼす。原発問題はそれを極端に示している。-----
また、ノーベル賞に最も近い経済学者と海外では評価の高い割に日本では、マスコミも経済学者も無視するために一般的には知られていない東京大学名誉教授の宇沢弘文氏を紹介したいと思います。この方も戦後60年余りの日本の問題点を鋭く分析しています。
なぜマスコミが無視するかというと、「日本は米国に搾取されている植民地である」と公然と主張しているからです。興味のある方は、名前で検索してみてください。岩波書店などから著書も多数出版されています。東電や電事連から多額の広告費をもらい天下りを受け入れている堕落した大手マスコミが全く信用できない今、TwitterやUstream、海外メディアなどを利用しないと真実は得られなくなっています。情報リテラシーが求められているわけですが、逆に今ネットがなかったら、大本営発表と噂しか情報源はないわけで、それは本当に恐ろしい事だと思わずにはいられません。
最新の確かな原発情報が欲しいという方は、ぜひTwitterを初めてください。私をフォローする必要はありませんが、私がフォローしている人の中から精査すると、かなり詳細な情報が得られると思います。使い方はツイナビや検索で。大震災で携帯が繋がらないときもこれで安否が確認できました。
また、まだ危険情報に懐疑的な人は、この記事を読むべきです。「安全基準を超えた「内部被曝」(要精密検査)すでに4766人、異常値を示した人1193人」現代ビジネス
★ネイチャーフォトは、【MORI MORI KIDS Nature Photograph Gallery】をご覧ください。キノコ、変形菌(粘菌)、コケ、花、昆虫などのスーパーマクロ写真。滝、巨樹、森の写真、森の動物、特殊な技法で作るパノラマ写真など。ニホンカモシカの写真も。