晩秋から初冬へと移りゆく信州ですが、とにかく暖かい。27日には初雪が舞ったのですが、すぐに雨に変わりました。冬型にならないため、晴れの日がほとんどありません。干し椎茸が乾かなくて困っています。そんな週末、僅かな晴れ間を逃すまいと撮影に出かけました。アンダーに長袖のTシャツ一枚なんですが、登って行くと軽く汗ばむほど。
妻女山から長坂峠へ。左の写真は、旧道が乗っこす東風超えから長坂峠と斎場山を振り返ったところ。妻女山駐車場から右の林道を登って15分ぐらいで着きます。長坂峠から斎場山とは逆の方向へ250mほど歩きます(中)。林道が右へ曲がる手前に、左へ踏み跡(右)。矢印の方向へ50mほど歩くと、そこが陣馬平です。第四次川中島合戦の際に、上杉謙信が七棟の陣小屋を建てたと伝わる平地です。標識がないので分かりにくいのですが、矢印の右の幹に←陣場平の文字があります。
大河ドラマ『真田丸』が始まるためか、妻女山や斎場山へ訪れる人が増えています。斎場山までは、ハイキング気分でも大丈夫ですが、鞍骨山へはトレッキングの格好と装備で登ってください。拙書では地形図と共に詳しく説明しています。
陣場平。手前は菱形基線測点。雪が降ってススキなどが全部潰れると、広大な平地が浮かび上がってきます。前方の落葉松林を抜けて右方向へ50m歩くと、林道に戻れます。拙書に写真を載せていますが、ゴールデン・ウィークの頃には、貝母(編笠百合)が見事な花を咲かせます。
そこから道無き道を歩いて30分。まずヒラタケを見つけました(左)。そしてなんとハタケシメジの群生も(中)。11月末に採れたのは初めてです。さらに奥山でナラタケの群生を発見(右)。コナラの倒木の樹皮と幹の間にたくさん生えていました。これも例年なら終わっているキノコ。これらは、次回の妻女山里山デザイン・プロジェクトの手打ちキノコうどんの具材になります。いい出汁が出るでしょう。菌根菌ではないし、放射能もほぼ心配ないのですが、一応塩湯に浸けて茹でこぼして除染してから使います。
戻って今は亡き山仲間のKさんのログハウスで休憩。ヤマツツジが狂い咲きしています(左)。ログハウスの庭は青々としていてまるで早春の様です(中)。雨が多いので、イシクラゲが大発生(右)。実はこれ食べられます。洗って味噌汁や和え物に。山のワカメです。
日溜りにシダ類のリョウメンシダ(左)。葉の裏には胞子が(中)。青っぽいですが、やがて茶褐色へと変わります。右はヤブソテツ。ニホンカモシカは、冬になるとこういったものも食べます。この日も林道を歩いていたら「シュッ!」っと威嚇音が。見上げるとすぐそこにニホンカモシカがいました。双子を産んだメスのシロでした。
長坂峠に戻って樹間から善光寺平の景色。中央に、AC長野パルセイロのホームスタジアムが見えます。手前に千曲川の流れ。堤防がまだ緑色をしています。1742年の戌の満水の大災害の後、幕府より一万両を借りて松代藩が大改修したため、戦国時代の流路とは全く異なります。
◉上杉謙信が妻女山(斎場山)に布陣したのは、千曲川旧流が天然の要害を作っていたから(妻女山里山通信)
山を下りて買い物に松代方面へ。帰りに上信越自動車道の松代PAに寄りました。そこから南の風景。鞍骨山の山脈が見えます。上杉方の村上義清の傍系ですが、武田方についたこの地の土豪、清野氏の山城、鞍骨城跡があります。全国から山城マニア、歴史マニアや歴女が訪れます。この山も拙書では詳しく紹介しています。
城跡左の深いコルは、元々鞍部があったものを更に掘り崩したものの様です。昔は石の階段があったと聞いたことがあります。象山方面から攻められた時の駒返しでしょうか。城跡の右、天城山(てしろやま)方面には、深い三つの空堀があります。
松代PAから松代方面の眺め。下り(写真)の天ぷらそばととろろ飯のセットはお勧めです。下の一般道からも入れます。上りと下りは階段で行き来できます。上りは、郷土料理のお煮かけそばがお勧め。西を見ると妻女山と斎場山が。天気が良ければ北アルプスが見えます。北には戸隠連峰と飯縄山。景色のいいPAです。お土産には、名産の長芋やりんごをどうぞ。郷土料理「おしぼりうどん」に使う辛味大根など地物の野菜も上りでは買えます。
◉「妻女山」「妻女山 行き方」「妻女山 地図」「斎場山」「さいじょざん」「さいじょうざん」
◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。でも、できれば地元の書店さんを元気にして欲しいです。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。分かりやすいと評判のガイドマップも自作です。その山の名前の由来や歴史をまず書いているので、歴史マニアにもお勧めします。
本の概要は、こちらの記事を御覧ください。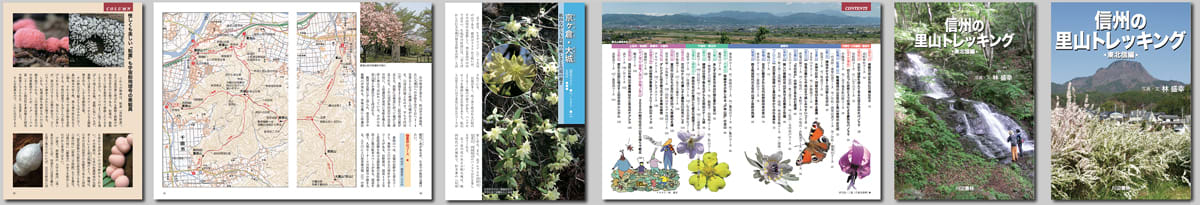
★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
■『国分寺・国立70Sグラフィティ』村上春樹さんの国分寺「ピーター・キャット」の想い出。はてなブログに移動しました。
勤労感謝の三連休は、久々に妻女山の山の手入れをしました。椎茸栽培のホダ木の点検や除草、斎場山登山の林道入口の看板に置く杖の伐採など。すると県内外から思いの外大勢の人が訪れました。妻女山のみならず、斎場山や鞍骨城跡まで行く人も結構いました。妻女山だけで帰ろうという人には斎場山の話をしたり、これから行こうという人達には、拙書の地図を見せて、行き方を説明したり。色々な方とお話をすることができました。地形図が載っている里山ガイド本は他にないので分かりやすいと好評でした。
まず陣馬平の除草へ(左)。林道から離れているので、標識代わりに木の幹に矢印と陣馬平の文字を書き入れました。除草と言っても枯れ草を刈るだけなのでほどなく終わりました。菱形基線測点の上に何かの糞が。陣馬平の北西の端には一基だけ積石塚古墳があります(中)。陣馬平が上杉謙信の陣城として使われる前は、ここは大室古墳群の様に積石塚古墳群があったのかも知れません。
何かの糞ですが、テンの高糞といってホンドテンはこういう目立つ所に糞をするのです(右)。種はこの近くにあるシナノガキ(信濃柿・豆柿)のものです。落ちた実を食べたのでしょう。鞍骨城跡から下りてきたご夫婦をここに案内しましたが、木に成ったまま干し柿になるシナノガキを食べてもらいました(笑)。渋柿なんですが、濃紺になると甘くて美味しいのです。
長坂峠に戻って見つけた植物(左)。センニンソウやボタンヅルの様な種ですが違います。葉はサルトリイバラみたいですが、葉脈が5本なので違います(中)。実はクコの実みたいです(右)。
草本かと思ったら、幹は木本で一センチぐらいの太さがあります。もちろん草本のシオデでもありません。幹にはノイバラの様な棘も見られます。近くにはその幼木が(中)。字書き虫(絵描き虫)が、葉の中に入って食べた跡です。ハモグリバエやハモグリガなどの仲間の幼虫です。右上の葉には幼虫が見えています。左下の様に食べ尽くして真っ白になると、他の葉に移っていくわけです。別に字を書いているわけでも絵を描いているわけでもないのですが、面白いと見入ってしまいました。さて、この植物はなんでしょう。まだ同定できていません。ご存じの方いますか?引き続き調べますが。
【追記】いや、絶対これ可笑しいでしょうと、後日再確認に。シオデでした。1センチの木本とクコの実みたいなのは別の木で、それに絡みついていたのでした。やれやれ。で、その木本なんですが、まだ未同定です。この山にはシオデとタチシオデがありますが、これはシオデかな。山のアスパラなんて言われますが、癖がなく食べやすい山菜です。でもたくさん集めるのが結構大変です。
そこから西へ斎場山へ長尾根(長坂)を登ります。シラカバ(左)。高原の木のイメージですが、北信濃では標高500mぐらいでも普通に見られます。尾根の北面にあることが多く、南面にはヤマナラシがあったりします。広葉樹はコナラやクヌギが主ですが、アベマキも見られます。
長坂峠から数分で斎場山。峠からもすぐ前方に山頂が見えます。登ると林道右手に円墳の斎場山古墳(左)。古代科野国の史跡で二段の墳丘裾があり、山頂は丸く平らです(中)。第四次川中島合戦の際には、上杉謙信が最初ここを本陣とし、盾を敷き陣幕を張って床几を置き、鼓を打ち謡曲を舞ったと伝わるところです。地元では謙信台ともいいます。
その近くで見つけた出始めのカワラタケ(瓦茸)。抗癌作用が高いと注目されているキノコです。煮だして飲んだり、焼酎漬けにして飲用します。
ヒヨドリジョウゴ(左)。全草が毒で、特にこの果実の毒性が強いのです。成分はステロイド系のアルカロイド配糖体ソラニン。誤って食べると、頭痛、嘔吐、下痢、運動中枢、呼吸中枢麻痺により死亡する場合もあります。ただ、生薬としても用いられます。抗腫瘍作用のある成分が含まれているそうです。中国では癌の治療にも使われているとか。
ユリ科シオデ属のヤマガシュウ(山何首烏)の実(中)。別名はサイカチバラ。雌雄異株の落葉蔓性木本。互生する葉には5、7本の葉脈があり、茎には針のような刺があります(右)。初めは柔らかい刺ですが、木本化すると非常に堅くなり、これが登山道を塞ぐと前に進めません。カマやノコギリでは切れないため、剪定ばさみを携帯します。鞍骨山への登山道にはこれが多く、登山道整備のために何度も通って切りました。実はムラサキシキブ同様に毒性がなく食べられますが、食べるところがあまりありません。味は美味しくない干しぶどう。
斎場山から西へ長尾根を辿ります。100mほど歩いて広い御陵願平を過ぎ、標高差30mほど急坂を下ります(左)。下ると高低差のほとんどない尾根道(中)。100mほど進むと土口将軍塚古墳の前方部が見えてきます(右)。
乗り越えて後円部から見たところ。長野県史跡の標柱と看板がありますが、現在は埴科古墳群(森将軍塚古墳・有明山将軍塚古墳・倉科将軍塚古墳・土口将軍塚古墳)として国指定史跡となっています。この古墳は、5世紀中頃のものと考えられています。森将軍塚古墳を始めとして、古代科野国を治めた代々の大王の墓ということでしょうか。
前方後円墳で、全長67.7m。後円部直径40.5m。後円部高さ8.1m。前方部幅30.5m。前方部高さ3.9m。周辺にこの山地の石英せん緑岩を施してあります。古墳頂部と中断テラスには約70本の埴輪があったと推定されています。特に叩きの技法を使った埴輪が出土し、全国的にも類例の少ない資料として注目されています。後円部中央に竪穴式石室が二基確認されています。大王夫妻のものでしょうか。岩野では、土口荘厳塚といい、この山を荘厳山と称しています。
薬師山(笹崎山)へ向かう100mほどの途中で北を見下ろすと岩野橋と千曲川の流れ(左)。奥は篠ノ井方面。ほどなく薬師堂琉璃殿(中)。目の神様で、おやくっしゃんといわれ親しまれています。
◉「笹崎山薬師如来の縁起」
ここから北に下りると岩野の千曲川の土手へ。南へ下りると土口の古大穴神社。いずれも駐車スペースがあり拙書で紹介していますが、神社の行事の日は避けてください。千曲川の土口水門のところにも駐車スペースがあるので、そこから歩くといいでしょう。上信越自動車道薬師山トンネル上の崖は、トンネルの工事で削られたものではなく、1742年(寛保2年)の戌の満水の後の河川工事のために削られたものです。
薬師堂の裏から斎場山方面の眺め。平坦な尾根であることが分かります。川中島の戦いの折には、陣馬平と同様にここにも兵士がたくさんいたのでしょう。
初夏に可憐な花を咲かせるイカリソウの葉も暖冬でまだ緑です(左)。秀吉の好物だったということで別名を藤吉郎というモミジガサ(中)。下って妻女山松代招魂社(右)。戊辰戦争以後の戦没者を祀った神社です。川中島合戦とは無関係。右奥の山が陣馬平方面。斎場山へ行きたいという家族や青年達、カップルに行き方を説明しました。いまの落葉期は、オオスズメバチも蛇も熊もいないし見通しもいいので、歴史探索には最適です。私は積雪期も好きですが。
千曲川の堤防の、岩野橋と赤坂橋の中間辺りから妻女山、斎場山、長尾根、薬師山を見たパノラマ写真です。この尾根上と麓に上杉方の大軍が布陣していたと想像するといいでしょう。戦国当時は、千曲川は堤防もなく、現在より遥かに激しく蛇行していました。高速道路ができる前は、展望台の真下に蛇池という千曲川の旧流の跡の池がありました。山の形は戦国当時と激しく変わってはいないはずですが、千曲川の流れは全く違うものでした。特に戌の満水の後に松代藩が行った大規模な河川工事で流路は大きく変わりました。
会津比売神社の祭神である会津比売命は、この地の産土神といわれます。古くは御陵願平にあったが、上杉謙信が庇護していたため、武田軍の兵火に遭い、その後山陰にひっそりと再建されたと伝わっています。
◉上杉謙信も庇護した妻女山(斎場山)の祭神、会津比売命について(妻女山里山通信)
◉妻女山の位置と名称について「妻女山の真実」
◉「妻女山」「妻女山 行き方」「妻女山 地図」「斎場山」「さいじょざん」「さいじょうざん」
上のパノラマ写真は、7枚の写真をフォトショップで繋げて合成しました。最初はこんな感じです。今回は三脚を持って行かなかったので手持ちでの撮影です。ご覧の通りそれぞれのカットの露出が違うので揃えなければいけません。太陽が真後ろにあれば容易なんですが、これが大変な作業です。また、つなぎ目を揃えるのも大変です。カメラ内臓のパノラマ機能はおもちゃなので原則プロは使いません。広角で撮ると左右が歪むので、望遠で撮るのが綺麗につなぐためのコツです。
以前、ウェザーニュースの季刊誌にブナの大木を上下につないだ画像を提供しましたが、それは至難の技でした(リンクは画質を落としてあります)。山の達人も大変ですが、デザインの達人も大変です。もちろん専門分野のエディトリアル・ディレクションのノウハウも。拙書には何点ものパノラマ写真を掲載していますが、こんなテクニックも若い人に教えられたらなと思います。
さて、北信濃にも雪の予報が出ました。平野部は舞う程度かもしれませんが、山間部は積もるかもしれません。いよいよ長い信州の冬の到来です。
◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。でも、できれば地元の書店さんを元気にして欲しいです。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。分かりやすいと評判のガイドマップも自作です。その山の名前の由来や歴史をまず書いているので、歴史マニアにもお勧めします。
本の概要は、こちらの記事を御覧ください。
★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
今年の晩秋は天気がぐずつき気味で気温は高め。年内はこのまま暖冬になりそうですが、2013年から14年がそうだったように、また早春のドカ雪が来るのではと戦々恐々としています。そんな雨上がりの先日、妻女山奥へ撮影トレッキングに行きました。こんな日なのに東京からハイキングに来た家族がいたのには驚きました。大河ドラマ『真田丸』が来年から始まるためか、週末になると県内外から観光客やハイカーがたくさん訪れます。
鞍骨城跡まで行く人も少なくないのですが、天城山(てしろやま)周辺は、尾根が十字に出ているため標識があるにも関わらず非常に迷う人が多いので、できれば下記で紹介の『信州の里山トレッキング 東北信編』をお買い求めいただいて、地図をコピーして携帯してください。それとコンパス。コンパスで北を調べて、地図の上を北に向けると、正しい方向や現在地が分かります。市販の地形図には登山道は必ずしも載っていません。 略図やイラストでは正確な距離や方向が分かりません。

妻女山松代招魂社奥の駐車場に停めて、右の林道を登ります(左)。このカットは、二つ目のカーブから下を見たところ。この間で私は仲間と椎茸の原木栽培をしています。四駆ですから上まで行けないことはないのですが、雨後に枯れ葉が積もるともの凄く滑るのです。なまじABSが効くとズルズル滑って山肌に激突。先日それをやってバンパーを凹ましたのは私です。熱湯をかけて直しましたが。
10分ほどで長坂峠(中)。正面は斎場山(旧妻女山)。山頂は円墳で、第四次川中島の戦いの時に、上杉謙信が最初に本陣としたと伝わるところです。東京から家族が訪れていました。やはり妻女山の展望台だけでなくここまで訪れて欲しいですね。できれば陣馬平も。
突然轟音がしたので見上げると、ジェット機が(右)。かなり低空飛行です。まあ長野市も日米地位協定で決めさせられた米軍の「横田空域」の中なので、よく米軍機や自衛隊機が飛びます。いずれオスプレイも飯山、戸隠の訓練空域へ行くために飛ぶ可能性があります。

その長坂峠からの北の展望。毎年、シルエットになった紅葉が着物の柄みたいだと思います。中央に見える山のシルエットは、拙書でも紹介している飯縄山。長野市民の山です。手前に善光寺平が広がっているのですが、この日は曇りなので朝霧が昼になっても消えずに漂っていました。一番手前に横に曲がって見える線は千曲川です。川中島の霧は、夜に川で発生し川中島を埋め尽くします。もっとも酷い時は、10m先さへ見えなくなり、フォグランプも効かず非常に危険です。

菱形基線測点のある陣馬平(左)。第四次川中島合戦の際に、上杉謙信が七棟の陣小屋を建てたという平地です。上の長坂峠から10分足らず。林道から外れますが標識は今のところありません。拙書の地形図では行き方を説明しています。
その陣馬平の中央にあるクマノミズキの実(中)。森のサンゴと私は呼んでいます。小鳥の重要な餌にもなります。今年は里の柿も豊作でしたが、山のシナノガキ(信濃柿:豆柿)も豊作だったようです(右)。ぽんぽこたぬきもこの冬は一安心でしょう。6月に青い実を水に浸けておくと柿渋ができます。

長野森林組合の人達が獣害防止のために除伐した森(左)。ずいぶん明るくなりました。撹乱したことで森が活性化します。松枯れの赤松も伐採しています。
先日倒れた赤松(中)。高さ1m位のところで折れ、掛かり木になっています。この処理は非常に危険です。グラップルで保持して伐採して引きずり下ろして玉切りが一番安全ですが、グラップルがないと、結構難儀です。まだ生木なので数トンの重さがあります。林道を外れて森の中へ(右)。キノコを探して倒木を当たってみます。

なんと季節外れのヤマツツジ(山躑躅)が咲いていました。通常は4~6月が開花期ですから狂い咲きです(左)。暖冬の影響でしょう。僅かに残ったコムラサキ(小紫)の実(中)。有毒ではないので食べられます。熟しきって柔らかくなったものは、はんなりとした甘みがあります。いや実が少ないからムラサキシキブ(紫式部)でしょうか。この山には両方あるので迷います。
ノブドウ(野葡萄)の実(右)。 果実は、ブドウタマバエやブドウガリバチの幼虫の寄生(虫えい・ゴール)により虫こぶ状になり、異常に脹らみ、白緑色、淡紫色、瑠璃色、赤紫色などに変色、形も大小不揃いになります。美味しそうですが、虫が入っているし、不味くて食べられないそうです。ノブドウ酒は、糖尿病、肝臓病、腰痛・関節痛などに効き目があるとか。中国では蛇葡萄といい、漢方薬。

ムラサキシメジのシロへ(左)。6本ぐらい隠れているのですが分かりますか。現地で実際に見るとキノコ目のない人にはまず分かりません。踏んでしまうでしょう。枯葉をどけたところ(中)。フランスではピエブルーという高級キノコ。和風にお澄ましは絶品ですが、バターやクリームソースとも相性抜群。20本ほど採りました。
深い谷でナラタケの株を見つけました(右)。すこし古いですが、この程度なら全く問題ありません。4株ほど採りました。塩湯に浸けてゴミを取り、一回茹でこぼして除染します。その後ざるで湯を切ってジップロックに詰めて冷凍しました。いずれ妻女山里山デザイン・プロジェクトのバーベキューで手打ちキノコうどんになる予定です。

小枝に白い綿のようなものがびっしり付いています(左)。カイガラムシの一種でしょうね。園芸では害虫ですが、安易に農薬を使わないことです。必ず自分に還って来ます。切り落として焼くことです。ネオニコに限らず日本人は安易に農薬や殺虫剤を使いすぎます。中も何かの卵でしょう。小枝を抱き込むように付いています。
落葉松の倒れた穴を何年もかけてイノシシが掘ったヌタ場(泥浴び場)(右)。一辺4~5mある大きなものです。前夜浴びた足跡がありました。周囲の幹には、体を擦り付けた泥がたくさん残っています。2年前に140キロのオスが罠にかかったことがあります。

昼は友人のログハウスへ。大事な山仲間の彼が急逝したのは2年前の今頃でした。妻女山里山デザイン・プロジェクトの活動では、いつも重機を出してくれて非常に助かりました。ここまでの林道も本来なら長野市と千曲市が整備をしないといけないのですが、彼がやっていました。彼が亡くなったことで林道は荒れ放題です。ヘビースモーカーでコンビニの弁当を食べていたので危ないと忠告していたのですが。猛毒のラウンドアップも使っていたようです。食べて応援なんかしていたら、地井武男さんや川島なお美さん、阿藤快さんの様に必ずなります。質量でいうとセシウムは青酸カリの2000倍の毒性があります。少しぐらい平気だろうなんて言語道断。
ログハウスから見る天城山方面(中)。山頂手前の清野古墳の尾根が見えています。落葉松の黄葉が最盛期。これから木枯らしが吹く度に落葉松の葉の雨が降り注ぎます。ログハウス脇にある堂平大塚古墳(右)。古墳時代後期のもので横穴式なので何度も埋葬ができます。彼の生家がここにあった頃は、野菜の貯蔵庫だったそうです。夏でもひんやりしています。

ログハウスから西方の眺め。彼が幼少の頃から毎日見ていた、最も愛する風景です。この日は生憎北アルプスが見えませんでしたが、晴れていれば爺ヶ岳や鹿島槍ヶ岳の秀麗な姿が見られます。そんな風景を眺めながら、薪ストーブで暖まりながら話をするのが楽しみでした。ここは彼が高2まで暮らした生家があったのですが、その前は乃木希典将軍に使えた山岸軍曹が独居していました。その話は父から聞いて知っていましたが、戦後は男装の麗人、川島芳子が隠れ住みたいと申し出た曰く付きの場所なんです。実際住むことはなかったのですが、彼からその話を聞いた時は本当に驚きました。

帰りに立ち寄った妻女山松代招魂社。戊辰戦争以降の戦没者を祀る神社です。川中島合戦とは無関係。後ろの小さな本殿の背後に、戊辰戦争で亡くなった人の石碑が並んでいます。夏はこの拝殿の屋根にたくさんのオオムラサキが集まります。どうやら暖冬の様ですが、こういう年に限って早春にドカ雪が降るのです。2014年の豪雪がまさにそれでした。この冬はそれに似ています。豪雪のあった前年の2013年の冬にもヤマツツジが狂い咲きしていました。さあどうなるのでしょう。備えだけはしておきましょう。
◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。でも、できれば地元の書店さんを元気にして欲しいです。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。分かりやすいと評判のガイドマップも自作です。その山の名前の由来や歴史をまず書いているので、歴史マニアにもお勧めします。 本の概要は、こちらの記事を御覧ください。
★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

管社バス停のあるT字路に登山者休憩所があります(左)。背後には台形の子檀嶺岳。休憩所の裏の牧場では、サフォーク種の羊が餌を食べていました。左に曲がって登って行くと、栗林の右手に登山者駐車場(中)。平日にも関わらず既に5台の車が停まっていました。さすが人気の山です。県外ナンバーも2台。その駐車場からも子檀嶺岳の山頂が見えます(右)。

駐車場から登るとすぐに獣害よけのゲート。ロックを開けて入りますが必ず閉めること。少し登るとすぐに登山口(左)。ここにも2台ほど停められます。さらに舗装路を数十メートル登った左にも駐車スペースがあります。GWなどには登山者で溢れるので地元の人に聞いて迷惑にならないように駐車してください。登山口から右へ下りて行き川を渡り竹林の道へ(中)。獣害対策の高圧電流の流れる電線があるので、誤って感電しないように注意。右へ曲がって尾根に取り付きます(右)。秋はキノコの留山で、テープが張られています。

尾根を右左と交互につづら折れで登って行くと畳石公園(左)。板状節理の岩が現れます。登山道に畳石(中)。公園といっても何か特別な施設があるわけではありません。強清水(右)。枯葉が積もっていて音は聞こえど水の流れは見えず。里山の水場は涸れることも多いので基本あてにしないことです。赤松の間から山頂が見え隠れします。

尾根を登って林道出合い(左)。昼でもちょっと薄暗い檜の植林地を歩きます。この右手に阿鳥川から登ってくる尾根があるのですが、見たところ明瞭な登山道や山道はありませんでした。下からは尾根の高みをひたすら登るのでしょうか。平坦な林道を進んでベンチのある場所(中)。ここから左手へ山頂への最後の登りが始まります。登るとすぐに子檀嶺岳の鳥居(右)。斜めに登って植林地を抜けるとつづら折れの急登が始まります。

登山道を横切るように、昔の牛馬道の窪みが横切っています(左)。北面はホウノキがたくさん自生し、大きな枯れ葉が地面を覆っていました。ある場所で山葡萄の実がたくさん落ちていました(中)。一粒食べてみると、甘酸っぱい味。山頂に近づくとコイワカガミの群生(右)。花の時期は綺麗でしょう。

かなりの急坂を登ると主稜線の鞍部にのります(左)。山頂は山城なので、これは堀切でしょう。山頂は右ですが、左へ少し登ると見張り台の少ピーク(中)。その少ピークの東側は木が横に生えている様な絶壁。鏡台山や四阿山、浅間山方面が見えます。1時間40分ほどで山頂。途中、下りてきた何組もの人達と出合い、その度に拙書をお見せしてパンフレットを渡しましたが、女性は花やパノラマの写真が綺麗と、男性は地形図が載っている里山の本は珍しい、分かりやすいという意見でした。地形図もその度に買うと結構高いしという意見。それに国土地理院は、ネットでの無料ダウンロードやプリントアウト地図の販売に切り替えてきています。いずれ印刷の地形図はなくなるでしょう。古い地形図を持っている人は大切にした方がいいです。
山頂には、厳しい急登の村松西洞コースを登ってこられた80歳の男性が。昔、渓流釣りをしていたという共通の話題もあり、色々楽しい話ができました。

始めは雲にすっかり隠れていた北アルプスですが、午後一時頃になると、やっと姿を現してくれました。中央に白馬鑓ヶ岳が白く光っています。手前の台形の山は、拙書でも紹介している聖山。ここも360度の大展望が見事な山です。

山城だった狭い山頂には、青木村の田沢、村松、当郷の里宮の奥宮が鎮座(左)。地元の霊山として尊崇を集めています。山頂の南面は、200m以上の断崖なので要注意。北方には大林山が見えます(中)。山頂の縁には、秋の七草のひとつ、カワラナデシコが数輪咲いていました(右)。開花期の全草を瞿麦(くばく)、種子を乾燥したものを瞿麦子(くばくし)といい、利尿作用や通経作用がある薬草です。

山頂の南側へは、何本もの尾根が延びています。右は夫神岳。左奥にノコギリ状の独鈷山。その手前に女神岳。麓には清少納言が好ましいと言った七久里湯という別所温泉。今回は寄れませんでしたが、そのあまりの美しさに「見返りの塔」と呼ばれる大法寺の三重塔や安楽寺の八角三重塔へ寄るのもお勧めです。別所温泉の三つの外湯も超お勧め。

北西には鹿島槍ヶ岳が雲の上に姿を現しました。諦めて早めに下山された方が多かったのですが、当日は午後から晴れるという予報だったので遅めに登り始めたのが功を奏しました。

山頂から当郷の登山口を見下ろしたカット(左)。中央右に登山者休憩所の青い屋根とその手前にサフォーク牧場、左下に登山者駐車場が見えます(左)。下山途中の紅葉(中)。ソヨゴの赤い実(右)。

下山後は、「道の駅あおき」に寄りました。拙書で表紙に使ったカットとほぼおなじ位置での撮影です。事務所の方に本のパンフレットを置いてもらえないかとお願いしました。快く了承していただきました。左側手前に延びる尾根が、村松西洞コースですが、非常に厳しい登りで、主稜線手前は木につかまらないと登れないほどの急登ですが、なんと地元の小学生が遠足で登るコースだそうです。駐車場はこちらの方が広くゆったりしています。是非一度挑戦してみてください。車が2台あればループコースを組めますし、この日は道の駅を起点としてループコースを組んだ人達もいました。
◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。でも、できれば地元の書店さんを元気にして欲しいです。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。分かりやすいと評判のガイドマップも自作です。その山の名前の由来や歴史をまず書いているので、歴史マニアにもお勧めします。
本の概要は、こちらの記事を御覧ください。
★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。

大田の水車小屋(左)。以前はこの前の駐車スペースに駐車して、さるすべりコースへ向かったのですが、現在は登山禁止なので、不動滝へ向かいます。そこから数百メートル左へ行った所にあるハイカーの案内所「虫倉山道しるべ」。綺麗なトイレもあります。そこに貼りだされていた虫倉山登山コース案内(中)。現状で登れるコースは、不動滝コース、不動滝コースに合流する柏鉢城跡コース、小虫倉までの小虫倉コースのみです。さるすべりコース、岩井堂コース、小虫倉から虫倉山へは、いずれも行けません。
そんなわけで、今回は不動滝手前の駐車場まで車で上がりました(右)。数台駐車可ですが、満車の時はさらに不動滝前を通って少し進むとトイレもある駐車場があり、林道を少し南へ辿るとすぐに円山公園の広い駐車スペースがあります。

不動滝すぐ向こうの登山口から滝上の寒沢を登っていきます。振り返ると聖山と左奥に美ヶ原(左)。樹皮の模様が美しいケヤキ(欅)の大木(中)。こういうケヤキは、板材にすると美しい杢(もく)が現れるため、高度経済成長期に乱伐されました。空平の四阿は倒壊していました(右)。風が吹くと落葉松の黄葉がチリチリと降ってきます。拙書にも書いていますが、ここは昔大きなブナ林だったそうです。

その空平からの北アルプス。残念ながら稜線は雲に覆われていました。眼下に見えるのは小川村。以前、仲間と虫倉山に登った帰りに「星と緑のロマン館」の風呂に入り、北アルプスに沈む夕日を愛でたことがあります。その模様は下記のリンクで。その向こうの里山の規則的に斜めの尾根が美しいリズムを刻んでいます。

脚を痛めていたので、私的にはかなりゆっくりと登ったのですが、1時間15分で山頂に着きました(左)。正面が山頂なのですが、これは下山専用で左に登りルートができていました。右側が崩壊しているので賢明な措置だと思います。崩壊した山頂(中)。右側(東側)が崩壊した部分。大理石の標柱も望遠鏡もありません。4割が崩壊したそうですが、残りの部分にも写真の様にクラック(割れ目)が入っています。先に登られたご夫婦も、以前との変わり様に驚かれていました(右)。常ならず。地球も生き物だと思わずにはいられません。帰路に、友人に今のうちに登っておいた方がいいよと言われて来た青年と遭い、帰りに彼の車まで送って行きましたが、あの山頂を見てどう思い友人に告げたでしょうか。

読者からの現状の問い合わせに正確に応えるために崩落箇所を見てみましたが、オーバーハングしているので、クラックが入っているのでしょう。崩壊した部分はマムシの巣でしたが、大量のマムシも一緒に落ちたのでしょう。崖下には下りられる窪地もあったのですが、全部崩落しました(中)。茶臼山から見た崩落部分(右)。頂上とさるすべりコースの東側が崩れているのがはっきり分かります。思っていたよりも非常に厳しい状況で、ショックを受けました。霊山と尊崇する地元の方々の心の痛みは計り知れないものがあります。恐らくクラックした先は、大地震でなくても崩壊する可能性があり、非常に危険な状態といえるでしょう。
後から登ってきた女性は、一ヶ月前に始めて登ったそうで、気に入ってまた来た様ですが、以前の山頂の事を話すと、非常に驚いていました。もともと岩が積み上がった様な山なので、積み木崩しの様な崩壊は運命なのかもしれません。善光寺地震でも大規模な崩落を起こしていますし。しかし、残念です。さるすべりコースは、当分の間登山禁止とありますが、再開は可能なのでしょうか。拙書でも紹介していますが、非常に魅力的なコースだったので、復旧を願います。

山頂からの素晴らしい眺めは何も変わりません。槍ヶ岳が綺麗に見えました(左)。こちらは浅間山(中)。思いの外激しい噴煙をあげていました。手前に皆神山、右に象山、妻女山、一重山の山脈のシルエット。手前の丸い山は茶臼山。北アルプスは雲に隠れていましたが、待っていると鹿島槍ヶ岳が姿を現しました(右)。

鹿島槍ヶ岳の雄姿。右に日本5番目、信州では初の氷河かと調査がされた、平家の落人が隠れ住んだといわれる「かくね里」の大きな谷が見えます。

北東を見ると長野市民の山、飯縄山。麓に飯綱高原が広がります。山頂北側にあったという山名の元となったという藍藻類の天狗の麦飯は絶滅しましたが、相変わらず県内外のハイカーから人気の山です。ただ、山頂付近は政府の調査でも放射能汚染がやや高めなので要注意です。

虫倉山の山頂に飛来したキアゲハ。日向ぼっこをしていました(左)。山頂近くにはイワカガミの群生があちこちに(中)。山頂の少し手前に新しくできた「いっぷく虫倉」という展望台(右)。狭くなった山頂がいっぱいなら、ここでお昼もいいでしょう。

紅葉はピークを過ぎていましが、それでもハウチワカエデなどが艶やかに色付いて魅せてくれました。下山後、不動滝でハコネサンショウウオを探しましたが見られませんでした。拙書では、その貴重な写真を載せていますが、これを撮影するのに3回通いました。いやむしろ3回目で撮影出来たのが幸運だったのかもしれません。

下山後は、皆さんすぐに帰られるのですが、実は不動滝すぐ先の円山公園は紅葉が非常に美しいのです。紅葉の季節なら是非立ち寄ることをお勧めします。滝から歩いても2,3分ですから。

帰路の道すがらで撮影した虫倉山。これは西側の生々しい崩壊跡。拙書では、虫倉山の山名や歴史についても記していますが、虫倉山に関しては、『むしくら』という非常に優れた研究書があり(県立歴史館や図書館で)、私の文章の中にも、村史と共にいくつか参考にさせていただいています。松代藩が尊崇していた山としても知られています。
◉フォトルポ 虫倉山トレッキング 2010.11.7 錦秋の虫倉山
◉フォトルポ 虫倉山トレッキング 2010.8.13 真夏の虫倉山
★いずれもYoutubeにハイビジョンのスライドショーをアップしています。是非ご覧ください。
◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。もちろん虫倉山も載っています。Amazonでも買えます。でも、できれば地元の書店さんを元気にして欲しいです。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。分かりやすいと評判のガイドマップも自作です。その山の名前の由来や歴史をまず書いているので、歴史マニアにもお勧めします。
本の概要は、こちらの記事を御覧ください。
★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。
■『国分寺・国立70Sグラフィティ』村上春樹さんの国分寺「ピーター・キャット」の想い出。はてなブログに移動しました。順次アップしていきます。ブックマークの更新をお願いします。

今年一番の冷え込みとかで、気温は2度あるかないか。長い林道歩きから森に入り、道なき林下を下って、ひとつ目のポイントへ。ムキタケがそこそこ採れました。毒キノコのツキヨタケと紛らわしいのですが、ツキヨタケは標高1000m以上に行かないとないので、この辺りでは心配する必要はありません。雨が降ると巨大化するのですが、今回は大型のものはあまりありませんでした。ムキタケは地元でもあまり市販もされませんが(ネットでは買えるようです)、非常に美味しいキノコです。木材の白色腐朽を起こす腐朽菌の一種で、腐朽力が強いためシロの消耗が早く、2、3年、長くても4、5年でそこからは出なくなります。

10基ぐらいあるでしょうか、積石塚古墳(左)。しかし、ここに来る道もないため、地元の人でも知っている人はほとんどいません。馬の生産をしていた渡来人のものでしょう。大室古墳群のものと似ています。中はイノシシのヌタ場。直径1.5m位のわりと小型のもの。周囲には泥をこすりつけた木があります。乾いた森を抜けて次のポイントへ(右)。案内する私は、どこを歩いているか全部分かっていますが、おそらく皆は、全く分かっていないでしょう。

森はこんな感じで、この辺りは山道もありません。林道もずっと離れたところにあります。林下は意外と暗いので、こういうところで迷ったらパニックになるでしょう。イノシシやニホンカモシカに出遭うこともあります。先日、友人に象山でイノシシのオスに追いかけられて、竹藪に逃げ込んで助かったという話を聞いたばかりです。晩秋、初冬と早春には月輪熊が出ることも。私は拙書にも書いていますが、鏡台山で三回ほど熊に遭遇しています。その内、山頂での出来事は本にも書いていますが、緊迫したものでした。この山域の主な樹種は、高木がコナラ、ヤマザクラ、オニグルミ、エンジュ、落葉松、赤松など。低木は、ガマズミ、クサギ、ヤマコウバシ、ヤマツツジ、コムラサキなどです。湿った林床には、イノデやヤブソテツも群生。猛毒のヤマトリカブトの群生地もあります。

陽があまり差し込まない薄暗い深い谷へ。ひとりではあまり来たくないところかも知れません。オニグルミの大木に、ミツバアケビやヤマフジのつるが絡みついています。そんなある場所で、ムラサキシメジをゲット。撮影のためにどかしましたが、本当は枯れ葉でほとんど見えていませんでした。いわゆるキノコ目がないと、枯れ葉に覆われたキノコは、普通の人には見えません。この尾根の反対側は、ネオニコチノイド系農薬の空中散布をするため、山菜もキノコも一切食べられません。昆虫もいません。死の山です。

森を抜けて「菱形基線測点」のある陣馬平へ(左)。NO.16 基本 建設省国土地理院と記されています。地球の歪み計測した名残り。茶臼山にあるものの場所が不明なのですが、だいたい目星がついたので、落葉期に探しに行こうと思います。シナノガキ(信濃柿)(中)。渋柿なんですが、この様な色になると渋味が抜けて甘くなります。木になったまま干し柿になるのですが、落果したものはタヌキがよく食べに来ます。青い柿を水に浸けておくと柿渋ができます。昼近くになって、やっと日差しが暖かくなってきました。約3時間かけて、いくつものポイントを回って、やっと4キロ弱のムキタケが採れました。
ムキタケ、クリタケ、ムラサキシメジともに腐生性キノコで、セシウムを10倍溜めるという菌根性ではありませんが、念のためたっぷりの塩水に浸けた後、流水でよく洗ってから、茹でこぼしましょう。塩水に浸けるのは虫を追い出すためですが、セシウムと結合するので除染効果もあるようです。また、酢やクエン酸を加えるとより効果があるそうです。(ベラルーシのベルラド放射能安全研究所)

まだまだ、緑が目立ちます。落葉松の黄葉も始まったばかり。皆シナノガキの味見をしています。毒草や薬草の研究をしているK医師は、わざわざ渋柿を食べて味見をしていました。かなり渋いです。家の柿酢も白いコロニーができはじめました。今年もいい柿酢ができそうです。

昼餉の準備。今回はイタリアンということで、N氏はアクアパッツァを準備。キノコ狩りには不参加だったK氏が自家製の小麦で作った手打ちパスタを持参。S氏は地粉でくるみパンを焼いてきました。私は、ニシンのアヒージョ(オリーブ油煮)を。イチジクの焼酎漬けも。K医師にはブルーチーズ系を幾つか持ってきてもらいました。T氏には鶏肉を。これは我々が栽培している椎茸とソテーして、S氏が作ってきたトマトソースと合わせてパスタソースに。

出来上がりを見るとアクアパッツァというよりカチュッコですね(左)。パンを浸して食べても旨い。いい出汁が出ています。真ん中は私が持ってきたムラサキシメジをパスタに絡めて。オリーブ油で炒めましたが、これはバターの方が合いますね。生クリームを少し入れると良かったかも。右は前記の鶏肉入りトマトソースにゴルゴンゾーラを少し加えて。なかなかのボリュームです。くるみパンにゴルゴンゾーラ・チーズと私が持参したブラックオリーブのペーストとニシンのアヒージョ、またはイチジクを挟んだサンドウィッチも馬鹿旨でした。今回はちょっとやり過ぎたようです。次回はキノコうどんとダッチオーブンの予定。作業は登山道や林道の伐倒処理があるかもしれません。

妻女山松代招魂社の桜の葉も随分と落ちました(左)。この日は、10台以上観光客の車が訪れていました。大河ドラマ『真田丸』で、また増えるでしょう。鞍骨城跡へ向かったハイカーもいました。以前、天城山(てしろやま)付近で迷ったそうです。拙書の地図を見せて説明しましたが、天城山は尾根が十字に出ているので、標識をよく確認しないと迷い易いのです。地形図が載った私の本とコンパスは必須です(笑)。イラストや略図や立体地図では正確な位置や距離、方向が確認できません。最近、地図を読めないハイカーが増えているそうですが、読図力は養っておくべきです。私の講座では、そういう話もします。
クサギ(臭木)の青い実も落ち始めています(中)。雨も降っていないのにハナイグチが。信州ではジコボウ(時候坊)といいますが、7本ほど採れました。虫が全く入っていない綺麗なものでした。

妻女山展望台から、松代方面のパノラマ写真。4枚の写真を繋げてあります。中央左は奇妙山。左手前に重なって尼巌山。いずれも拙書で紹介しています。奇妙山から右へ、堀切山・立石山(立石岳)・保基谷岳と続きます。手前に皆神山。その右手前の尾根が象山。手前に高速の松代SAの塔が見えますが、その左向こうの森が松代城(海津城)です。信州の秋はどんどん深まっていきます。
◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。でも、できれば地元の書店さんを元気にして欲しいです。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。分かりやすいと評判のガイドマップも自作です。その山の名前の由来や歴史をまず書いているので、歴史マニアにもお勧めします。サイクリストやトレランの人にも買っていただいています。
本の概要は、こちらの記事を御覧ください。
★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。
■『国分寺・国立70Sグラフィティ』村上春樹さんの国分寺「ピーター・キャット」の想い出。はてなブログに移動しました。順次アップしていきます。















