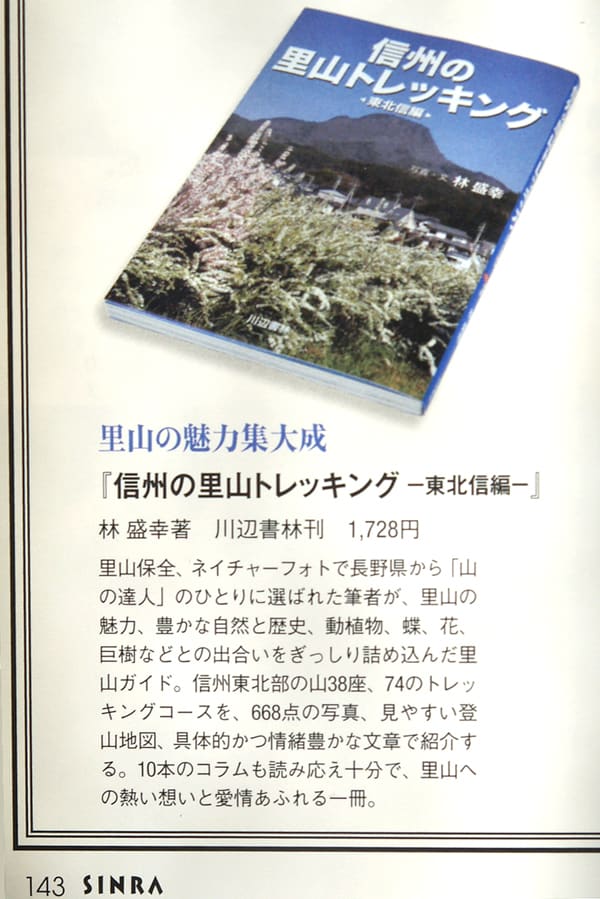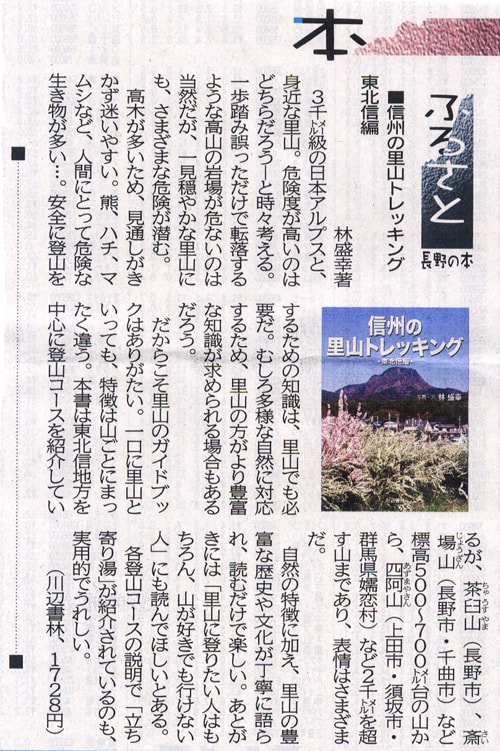駒ヶ根市赤穂の旧赤須村にある美女ヶ森大御食神社(おおみけじんじゃ)を訪れました。実は私の叔母が、神社の社家である小町谷家の出身で、その話を聞いてからずっと訪ねてみたいと思っていたのです。信州は、善光寺のある長野と、松本城のある松本が中心で、伊那谷などはなにもない田舎と思ったら大間違いなのです。元善光寺もありますし。古い歴史と伝統を持った里なのです。

日本武尊が当地に立ち寄った際に饗応した里長が「御食彦(みけつひこ)」の名を賜り、後に日本武尊を祀った当社を創建したものという。118年(景行天皇48年)の創建と伝わる。(美しの杜社伝記)という非常に由緒ある古社で、その社家の小町谷家は、なんと日本最古の家系といわれているのです。神社には、神代文字(阿比留草文字)で書かれた社伝記が伝えられています。社伝記読み下し文。

訪れた日はちょうど例大祭の日で、神社では厳かに儀式がとり行われていました。こういう機会もめったにないことなので、見学させていただきました。祭神は日本武尊(やまとたけるのみこと)・五郎姫神(いついらつひめのみこと)・誉田別尊(ほんだわけのみこと)。

儀式を執り行う人達は平安時代の装束で、頭には烏帽子ではなく冠を被っていました。笙と笛の演奏をバックに三宝に載せられた供物の奉納などが拝殿から本殿へと行われます。祝詞が挙げられ、後に供物を取り下げ、太鼓を打ち鳴らして儀式は終了しました。氏子の皆さんが、判で押したようにダブルの黒の礼服に、黒白グレーのレジメンタルタイをしていたのが、ちょっと面白かったです。皆同じ店で買ったのでしょうか。見学する人が少なかったのですが、集落の人は祭りの準備で忙しいのでしょう。余韻の残る非常にいい儀式でした。

文久3年の棟札に「大工キソ(木曽)斎藤常吉、彫工下スワ(諏訪)立木音四郎」とあり、大工棟梁が天才と呼ばれた立川和四郎冨昌の一番弟子の斎藤常吉、彫工が同じく立川弟子の立川音四郎種清(本名立木音四郎)ということで、見事な木彫が見られます。

獅子の顔や象や龍なども、冨昌のものとは違い、よりダイナミックで動きが派手です。下諏訪町誌によると、種清は率直な磊落(らいらく)な人で、よく人の世話をした。「声の大きい人で、種清さの内緒話はむこう山でひびく」と人が笑ったという。と書かれています。そんな人となり(為人)を表すような木彫です。明治41年没。
なぜこの地にこれだけのものが残り得たのか。時代の変遷、幾度もの戦乱、特に戦国時代。数々の自然災害もありました。それらを熟考すべきです。

境内には、天狗やひょっとこ、おかめや狐の格好をした村人がお練りをする画が掲げられています。このお練りは、現在も行われていて老若男女がお練りをする動画が、Youtubeにもアップされています。

次に訪れたのは、霊犬早太郎説話でも知られる宝積山(ほうしゃくさん)光前寺(こうぜんじ)。天台宗の別格本山の寺院で、天台宗信濃五山(戸隠山の顕光寺・善光寺・更科八幡神宮寺・津金寺・光前寺)のひとつ。仁王門から三門までの両側は石垣ですが(左)、その内部にヒカリゴケが自生しています(中)。ヒカリゴケは自発光しているのではなく、原糸体にレンズ状細胞が暗所に入ってくる僅かな光を反射することによる。またレンズ状細胞には葉緑体が多量にあるため反射光は金緑色(エメラルド色)になる。(出典:Wikipedia)浅間山の鬼押し出しの溶岩の間にも見られます。三門の木漏れ日(右)。

杉の大木に囲まれた本堂(左)。南信州唯一の三重塔で、寺院のサイトには、木彫は立川和四郎作と書かれていますが、父の富棟が64歳、息子の冨昌が26歳。どちらが手掛けたのでしょう(中)。境内の杉林には遊歩道があります。杉林の中の賽の河原。親地蔵を中心に三十数体の小地蔵が立っています(右)。

ゼロ磁場のパワースポットで有名な分杭峠(左)。そこから秋葉街道(152号)を北上して中沢峠の先で林道へ(中)。森林組合に勤める息子の仕事現場に立ち寄りました(中)。どえらい急斜面でした。途中停車して森の中へ。サクラシメジとホウキタケを採りました。夜は、私が採った天然の舞茸で天ぷらを堪能しました。持って行ったウラベニホテイシメジにホウキタケや豆腐を入れて煮物に。これも絶品でした。

152号に戻り、三峰川(みぶがわ)沿いに長谷の谷を北上。国重要文化財の熱田神社に寄りました(左)。本殿は、拝殿の背後の覆屋の中ですが、非常に華麗な作りです。彫刻部は上州(群馬県)勢多郡の関口文治郎、彩色は武州(埼玉県)熊谷在の森田清吉と案内板にあります。伊那市指定有形文化財の舞宮(中)。美和ダムの美和湖畔にある道の駅下の公園に咲いていた秋明菊(右)。菊とつきますがアネモネの仲間で茶花にも用いられます。古い時代の中国からの帰化植物ですが、「秋牡丹」「しめ菊」「紫衣菊」「加賀菊」「越前菊」「貴船菊」「唐菊」「高麗菊」「秋芍薬」など、非常に多くの別名があります。花弁に見えるのは萼片です。
◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。でも、できれば地元の書店さんを元気にして欲しいです。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。分かりやすいと評判のガイドマップも自作です。この夏は、信州の里山や亜高山を歩いてみませんか。
本の概要は、こちらの記事を御覧ください。
★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応は不可能です。






■『国分寺・国立70Sグラフィティ』村上春樹さんの国分寺「ピーター・キャット」の想い出。はてなブログに移動しました。順次アップしていきます。ブックマークの更新をお願いします。

日本武尊が当地に立ち寄った際に饗応した里長が「御食彦(みけつひこ)」の名を賜り、後に日本武尊を祀った当社を創建したものという。118年(景行天皇48年)の創建と伝わる。(美しの杜社伝記)という非常に由緒ある古社で、その社家の小町谷家は、なんと日本最古の家系といわれているのです。神社には、神代文字(阿比留草文字)で書かれた社伝記が伝えられています。社伝記読み下し文。

訪れた日はちょうど例大祭の日で、神社では厳かに儀式がとり行われていました。こういう機会もめったにないことなので、見学させていただきました。祭神は日本武尊(やまとたけるのみこと)・五郎姫神(いついらつひめのみこと)・誉田別尊(ほんだわけのみこと)。

儀式を執り行う人達は平安時代の装束で、頭には烏帽子ではなく冠を被っていました。笙と笛の演奏をバックに三宝に載せられた供物の奉納などが拝殿から本殿へと行われます。祝詞が挙げられ、後に供物を取り下げ、太鼓を打ち鳴らして儀式は終了しました。氏子の皆さんが、判で押したようにダブルの黒の礼服に、黒白グレーのレジメンタルタイをしていたのが、ちょっと面白かったです。皆同じ店で買ったのでしょうか。見学する人が少なかったのですが、集落の人は祭りの準備で忙しいのでしょう。余韻の残る非常にいい儀式でした。

文久3年の棟札に「大工キソ(木曽)斎藤常吉、彫工下スワ(諏訪)立木音四郎」とあり、大工棟梁が天才と呼ばれた立川和四郎冨昌の一番弟子の斎藤常吉、彫工が同じく立川弟子の立川音四郎種清(本名立木音四郎)ということで、見事な木彫が見られます。

獅子の顔や象や龍なども、冨昌のものとは違い、よりダイナミックで動きが派手です。下諏訪町誌によると、種清は率直な磊落(らいらく)な人で、よく人の世話をした。「声の大きい人で、種清さの内緒話はむこう山でひびく」と人が笑ったという。と書かれています。そんな人となり(為人)を表すような木彫です。明治41年没。
なぜこの地にこれだけのものが残り得たのか。時代の変遷、幾度もの戦乱、特に戦国時代。数々の自然災害もありました。それらを熟考すべきです。

境内には、天狗やひょっとこ、おかめや狐の格好をした村人がお練りをする画が掲げられています。このお練りは、現在も行われていて老若男女がお練りをする動画が、Youtubeにもアップされています。

次に訪れたのは、霊犬早太郎説話でも知られる宝積山(ほうしゃくさん)光前寺(こうぜんじ)。天台宗の別格本山の寺院で、天台宗信濃五山(戸隠山の顕光寺・善光寺・更科八幡神宮寺・津金寺・光前寺)のひとつ。仁王門から三門までの両側は石垣ですが(左)、その内部にヒカリゴケが自生しています(中)。ヒカリゴケは自発光しているのではなく、原糸体にレンズ状細胞が暗所に入ってくる僅かな光を反射することによる。またレンズ状細胞には葉緑体が多量にあるため反射光は金緑色(エメラルド色)になる。(出典:Wikipedia)浅間山の鬼押し出しの溶岩の間にも見られます。三門の木漏れ日(右)。

杉の大木に囲まれた本堂(左)。南信州唯一の三重塔で、寺院のサイトには、木彫は立川和四郎作と書かれていますが、父の富棟が64歳、息子の冨昌が26歳。どちらが手掛けたのでしょう(中)。境内の杉林には遊歩道があります。杉林の中の賽の河原。親地蔵を中心に三十数体の小地蔵が立っています(右)。

ゼロ磁場のパワースポットで有名な分杭峠(左)。そこから秋葉街道(152号)を北上して中沢峠の先で林道へ(中)。森林組合に勤める息子の仕事現場に立ち寄りました(中)。どえらい急斜面でした。途中停車して森の中へ。サクラシメジとホウキタケを採りました。夜は、私が採った天然の舞茸で天ぷらを堪能しました。持って行ったウラベニホテイシメジにホウキタケや豆腐を入れて煮物に。これも絶品でした。

152号に戻り、三峰川(みぶがわ)沿いに長谷の谷を北上。国重要文化財の熱田神社に寄りました(左)。本殿は、拝殿の背後の覆屋の中ですが、非常に華麗な作りです。彫刻部は上州(群馬県)勢多郡の関口文治郎、彩色は武州(埼玉県)熊谷在の森田清吉と案内板にあります。伊那市指定有形文化財の舞宮(中)。美和ダムの美和湖畔にある道の駅下の公園に咲いていた秋明菊(右)。菊とつきますがアネモネの仲間で茶花にも用いられます。古い時代の中国からの帰化植物ですが、「秋牡丹」「しめ菊」「紫衣菊」「加賀菊」「越前菊」「貴船菊」「唐菊」「高麗菊」「秋芍薬」など、非常に多くの別名があります。花弁に見えるのは萼片です。
◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。でも、できれば地元の書店さんを元気にして欲しいです。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。分かりやすいと評判のガイドマップも自作です。この夏は、信州の里山や亜高山を歩いてみませんか。
本の概要は、こちらの記事を御覧ください。
★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応は不可能です。
■『国分寺・国立70Sグラフィティ』村上春樹さんの国分寺「ピーター・キャット」の想い出。はてなブログに移動しました。順次アップしていきます。ブックマークの更新をお願いします。