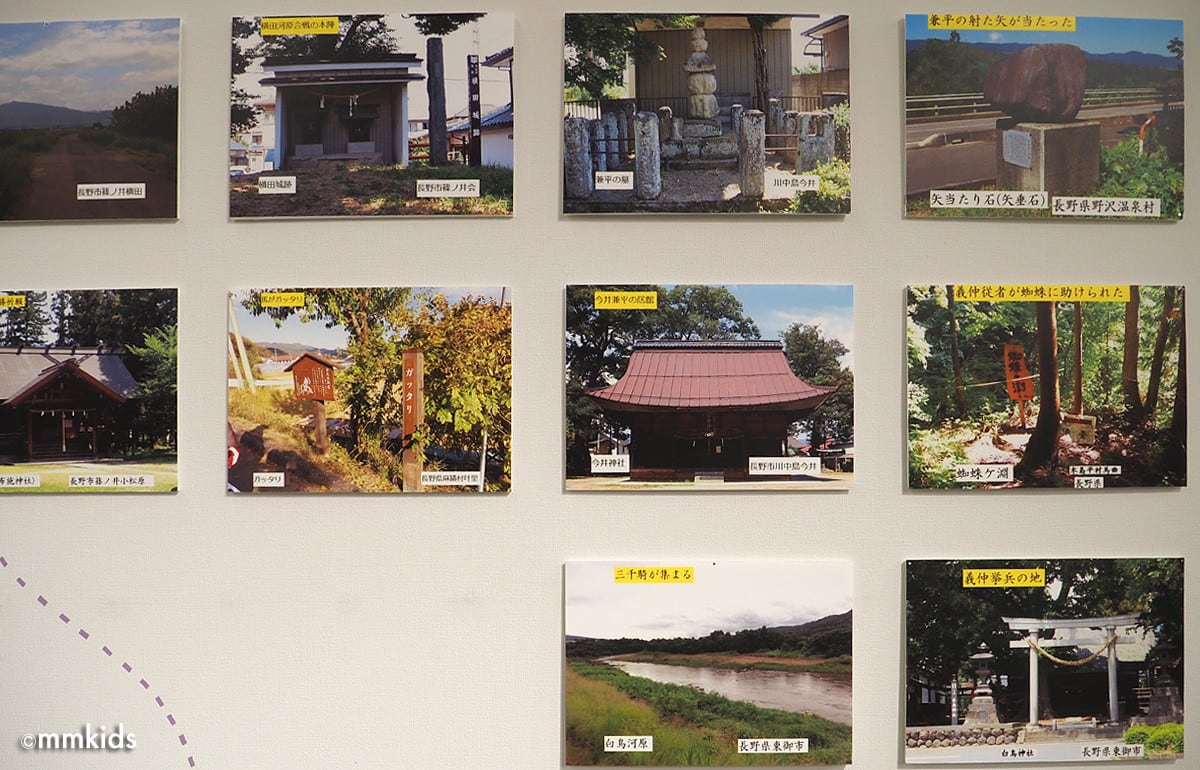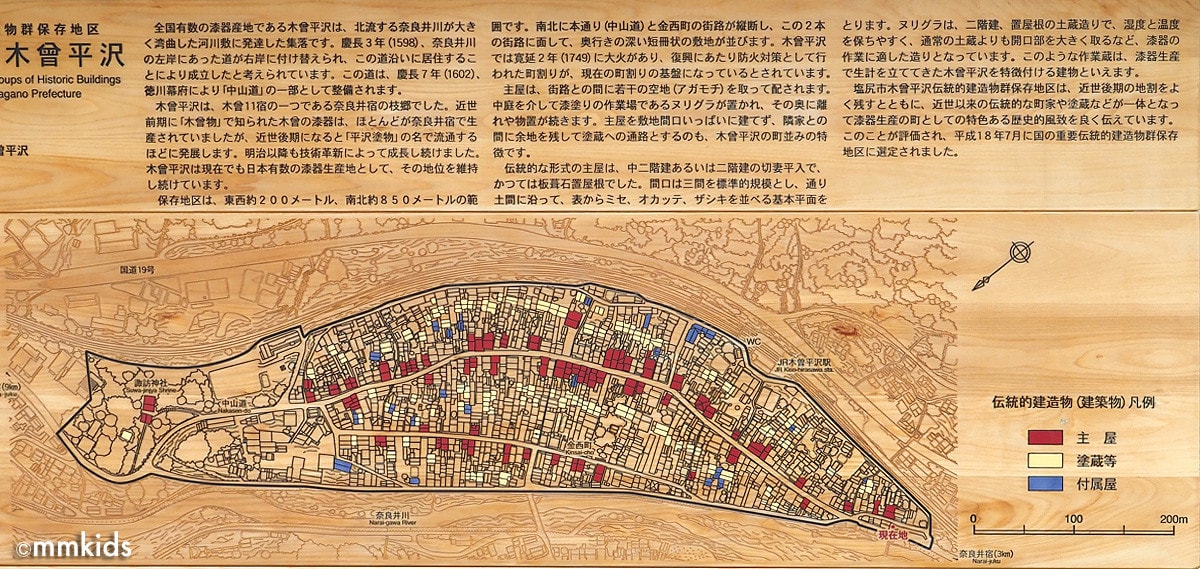朝からピーカンなので、8時には撮影現場に到着。予想通り、既にオオミドリシジミのオスは舞っていました。ただ数は少ない。原因は分かりませんが、ここ数年で最も少ない発生数です。下りてきてくれるでしょうか。とにかく観察と忍耐が必要です。テリトリーの専有行動でオス同士は体当りしたり、クルクルと円を描いて回ったり。しばらくすると散って休憩します。そんなチャンスを狙います。

オオミドリシジミは、陽のあたっている葉に必ず止まります。なので、何箇所か確認しておきます。しかし、太陽は動くので日当たりのいい葉も変わります。ちょうど止まってくれたので、逃げられないように後から接近。マクロレンズなのでフードの先端から蝶までは20センチもありません。気配を殺して撮影。

オオミドリシジミの翅の輝きは、鱗粉の色ではなくオオムラサキと同様に構造色です。なので専有行動のバトルで痛むとこんな感じになります。初見が10日前ですから、傷むのも当然なのです。ちなみにメスの翅の色は、オスの後翅の様な茶褐色です。
●梅雨の森の宝石オオミドリシジミを探して妻女山山系へ。雨上がりの粘菌二種を発見。虫こぶも(妻女山里山通信):作年のオオミドリシジミの記事です。梅雨明けが例年並みだったので発生も例年並みでした。この時は十数頭が激しい専有行動をしていました。

なかなか下に下りてこなくなったので、望遠レンズに替えて撮影。ここまでの三枚は同じ個体です。

別の個体。何を見ているのでしょう。専有行動は、10時前に終わりました。

休憩に堂平大塚古墳へ。鹿島槍ヶ岳。例年より雪解けが早いですね。

貝母の群生地がある陣場平へ。最高気温は36度の予報ですが、24度。セミは鳴いていません。サンコウチョウの鳴き声が聞こえます。目ぼしい昆虫は見られません。ヒカゲイノコズチを刈ったので、例年よりスッキリしています。

中央にあるクマノミズキの花。例年なら昆虫がたくさん吸蜜に訪れているのですが。猛暑のせいでしょうか。

貝母(ばいも・編笠百合)は全て枯れました。実もほとんど枯れて弾けていますが、こんな風にまだ緑のものもあります。

貝母群生地から林道方向。山椒の実も終わりなので、来る人はいません。暑さに慣れてくるとハイカーが来る様になります。例年なら見られるヒメウラナミジャノメやミドリヒョウモンもいません。

下ってご天上の、先日クヌギに傷をつけたところに樹液が出ていました。白い結晶がそれです。シロテンハナムグリやハエやアブの仲間など。オレンジ色の甲虫は、イタドリハムシ(虎杖葉虫)でしょうか。なにかの幼虫もいますね。これらの同定は、非常に困難です。

ヒヨドリバナ(鵯花、山蘭)のつぼみ。キク科フジバカマ属の多年草です。咲くとアサギマダラが吸蜜に訪れます。

ヤマアジサイ(山紫陽花)。別名は、サワアジサイ。周辺は装飾花で、中心部は両性花。ガクアジサイに比べると、花の色が色々あります。万葉集の二首。
「言問はぬ木すら味狭藍(紫陽花) 諸弟(もろと)らが練の村戸(むらと)にあざむかえけり」(大伴家持 巻4 773)
(恋を語らない木ですら、紫陽花のように移ろいやすい。巧みな言葉に私は騙されてしまいました。)
「味狭藍(紫陽花)の 八重咲く如 やつ代にを いませわが背子 見つつ思はむ(しのはむ)」(橘諸兄 巻20 4448)
(紫陽花が八重に咲くように、ますます長い年月を生きてください。紫陽花を見ながらあなたをお慕いします。)

アサギマダラ。しかし、吸蜜する花がなく止まってくれません。次の機会を待ちましょう。

ウワミズザクラ(上溝桜)の実。つぼみや熟す前の実を塩漬けや酢漬けにして利用します。夏に熟して赤から黒くなる実は、美味しい果実酒になります。新潟や秋田などでは、熟す前の青い実を塩漬けにするそうで、アンニンゴ(杏仁子)というそうです。今回、塩漬け用に少し採りました。

ヤマハギ(山萩)が咲き出しました。ゼフィルスが好きな花です。妻女山にはマルバハギもあります。万葉集で最も多く詠まれている植物は萩で141種です。鹿が男性の象徴とすると、萩は女性の象徴とされた様です。萩は芽子(めこ)という言葉で出てきますが、妻子のことでも女性器のことでもあるようです。
「さを鹿の朝たつ野べの秋萩に玉とみるまでおける白露」(大伴宿禰家持)
ひょっとしてルリボシカミキリが出ているかなと椎茸のホダ木へ行ったら、右胸と右の二の腕にバチバチっと痛みが。ムモンホソアシナガバチの巣が近くにある様です。車に戻ってポイズンリムーバーで毒を抜きました。腫れませんでしたが、痛みは薬を塗ってもなかなか取れません。

オカトラノオ(丘虎乃尾)サクラソウ科オカトラノオ属。花は穂の下の方から咲いていきます。低山や野原ならどこにでも見られるような花ですが、清楚で心引かれる花です。オカトラノオは、みな同じ方向を向いて咲きます。大きな群生地では、花穂(かすい)の波うつ様子がまるで波の文様の青海波(せいがいは)のように見えるほどです。そしてこの後で、オオムラサキのオスを初見しました。

(左)夏のグルメ。新じゃがと牡蠣の燻製とベーコンのスパニッシュ・オムレツ。バックのセミ柄の布は、プロバンス地方の伝統柄です。(右)奥は信州人のソウルフード、塩イカとスギヨのビタミンちくわ、新玉ねぎ、ピーマン、ニンジンのかき揚げ。左下は塩イカの天ぷら。本来は国産の塩丸イカなんですが、不漁でもの凄く高いので、チリ産です。右下は、大分県の郷土料理、とり天。実は、とり天と唐揚げ、竜田揚げの違いが調べてもよく分かりません。
◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。地形図掲載は本書だけ。山の歴史や立ち寄り温泉も。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。10本のエッセイが好評。掲載の写真やこのブログの写真は、有料でお使いいただけます。

★本の概要は、こちらの記事を御覧ください。
★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせか、メッセージからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。
インタープリターやインストラクターのお申込みもお待ちしています。好評だったスライドを使用した自然と歴史を語る里山講座や講演も承ります。市民大学などのフィールドワークを含んだ複数回の講座も可能です。左上のメッセージを送るからお問い合わせください。

オオミドリシジミは、陽のあたっている葉に必ず止まります。なので、何箇所か確認しておきます。しかし、太陽は動くので日当たりのいい葉も変わります。ちょうど止まってくれたので、逃げられないように後から接近。マクロレンズなのでフードの先端から蝶までは20センチもありません。気配を殺して撮影。

オオミドリシジミの翅の輝きは、鱗粉の色ではなくオオムラサキと同様に構造色です。なので専有行動のバトルで痛むとこんな感じになります。初見が10日前ですから、傷むのも当然なのです。ちなみにメスの翅の色は、オスの後翅の様な茶褐色です。
●梅雨の森の宝石オオミドリシジミを探して妻女山山系へ。雨上がりの粘菌二種を発見。虫こぶも(妻女山里山通信):作年のオオミドリシジミの記事です。梅雨明けが例年並みだったので発生も例年並みでした。この時は十数頭が激しい専有行動をしていました。

なかなか下に下りてこなくなったので、望遠レンズに替えて撮影。ここまでの三枚は同じ個体です。

別の個体。何を見ているのでしょう。専有行動は、10時前に終わりました。

休憩に堂平大塚古墳へ。鹿島槍ヶ岳。例年より雪解けが早いですね。

貝母の群生地がある陣場平へ。最高気温は36度の予報ですが、24度。セミは鳴いていません。サンコウチョウの鳴き声が聞こえます。目ぼしい昆虫は見られません。ヒカゲイノコズチを刈ったので、例年よりスッキリしています。

中央にあるクマノミズキの花。例年なら昆虫がたくさん吸蜜に訪れているのですが。猛暑のせいでしょうか。

貝母(ばいも・編笠百合)は全て枯れました。実もほとんど枯れて弾けていますが、こんな風にまだ緑のものもあります。

貝母群生地から林道方向。山椒の実も終わりなので、来る人はいません。暑さに慣れてくるとハイカーが来る様になります。例年なら見られるヒメウラナミジャノメやミドリヒョウモンもいません。

下ってご天上の、先日クヌギに傷をつけたところに樹液が出ていました。白い結晶がそれです。シロテンハナムグリやハエやアブの仲間など。オレンジ色の甲虫は、イタドリハムシ(虎杖葉虫)でしょうか。なにかの幼虫もいますね。これらの同定は、非常に困難です。

ヒヨドリバナ(鵯花、山蘭)のつぼみ。キク科フジバカマ属の多年草です。咲くとアサギマダラが吸蜜に訪れます。

ヤマアジサイ(山紫陽花)。別名は、サワアジサイ。周辺は装飾花で、中心部は両性花。ガクアジサイに比べると、花の色が色々あります。万葉集の二首。
「言問はぬ木すら味狭藍(紫陽花) 諸弟(もろと)らが練の村戸(むらと)にあざむかえけり」(大伴家持 巻4 773)
(恋を語らない木ですら、紫陽花のように移ろいやすい。巧みな言葉に私は騙されてしまいました。)
「味狭藍(紫陽花)の 八重咲く如 やつ代にを いませわが背子 見つつ思はむ(しのはむ)」(橘諸兄 巻20 4448)
(紫陽花が八重に咲くように、ますます長い年月を生きてください。紫陽花を見ながらあなたをお慕いします。)

アサギマダラ。しかし、吸蜜する花がなく止まってくれません。次の機会を待ちましょう。

ウワミズザクラ(上溝桜)の実。つぼみや熟す前の実を塩漬けや酢漬けにして利用します。夏に熟して赤から黒くなる実は、美味しい果実酒になります。新潟や秋田などでは、熟す前の青い実を塩漬けにするそうで、アンニンゴ(杏仁子)というそうです。今回、塩漬け用に少し採りました。

ヤマハギ(山萩)が咲き出しました。ゼフィルスが好きな花です。妻女山にはマルバハギもあります。万葉集で最も多く詠まれている植物は萩で141種です。鹿が男性の象徴とすると、萩は女性の象徴とされた様です。萩は芽子(めこ)という言葉で出てきますが、妻子のことでも女性器のことでもあるようです。
「さを鹿の朝たつ野べの秋萩に玉とみるまでおける白露」(大伴宿禰家持)
ひょっとしてルリボシカミキリが出ているかなと椎茸のホダ木へ行ったら、右胸と右の二の腕にバチバチっと痛みが。ムモンホソアシナガバチの巣が近くにある様です。車に戻ってポイズンリムーバーで毒を抜きました。腫れませんでしたが、痛みは薬を塗ってもなかなか取れません。

オカトラノオ(丘虎乃尾)サクラソウ科オカトラノオ属。花は穂の下の方から咲いていきます。低山や野原ならどこにでも見られるような花ですが、清楚で心引かれる花です。オカトラノオは、みな同じ方向を向いて咲きます。大きな群生地では、花穂(かすい)の波うつ様子がまるで波の文様の青海波(せいがいは)のように見えるほどです。そしてこの後で、オオムラサキのオスを初見しました。

(左)夏のグルメ。新じゃがと牡蠣の燻製とベーコンのスパニッシュ・オムレツ。バックのセミ柄の布は、プロバンス地方の伝統柄です。(右)奥は信州人のソウルフード、塩イカとスギヨのビタミンちくわ、新玉ねぎ、ピーマン、ニンジンのかき揚げ。左下は塩イカの天ぷら。本来は国産の塩丸イカなんですが、不漁でもの凄く高いので、チリ産です。右下は、大分県の郷土料理、とり天。実は、とり天と唐揚げ、竜田揚げの違いが調べてもよく分かりません。
◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。地形図掲載は本書だけ。山の歴史や立ち寄り温泉も。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。10本のエッセイが好評。掲載の写真やこのブログの写真は、有料でお使いいただけます。

★本の概要は、こちらの記事を御覧ください。
★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせか、メッセージからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。
インタープリターやインストラクターのお申込みもお待ちしています。好評だったスライドを使用した自然と歴史を語る里山講座や講演も承ります。市民大学などのフィールドワークを含んだ複数回の講座も可能です。左上のメッセージを送るからお問い合わせください。