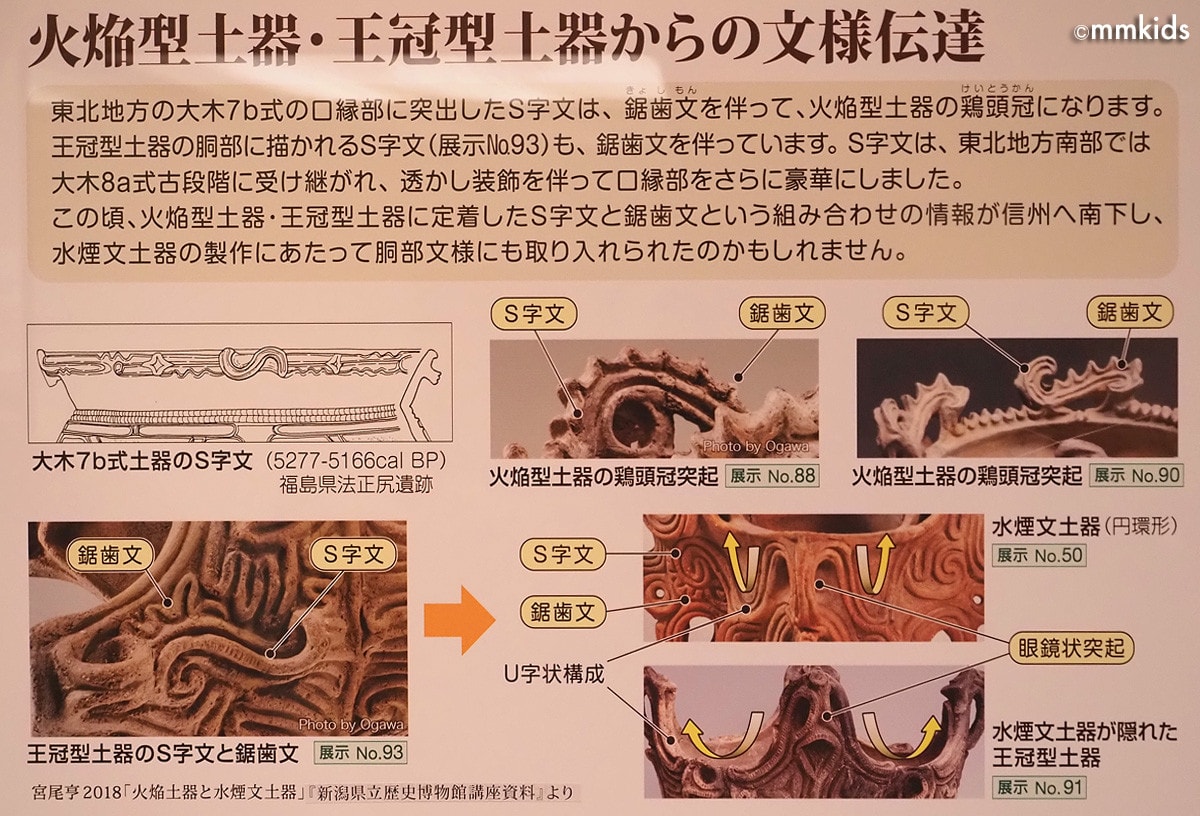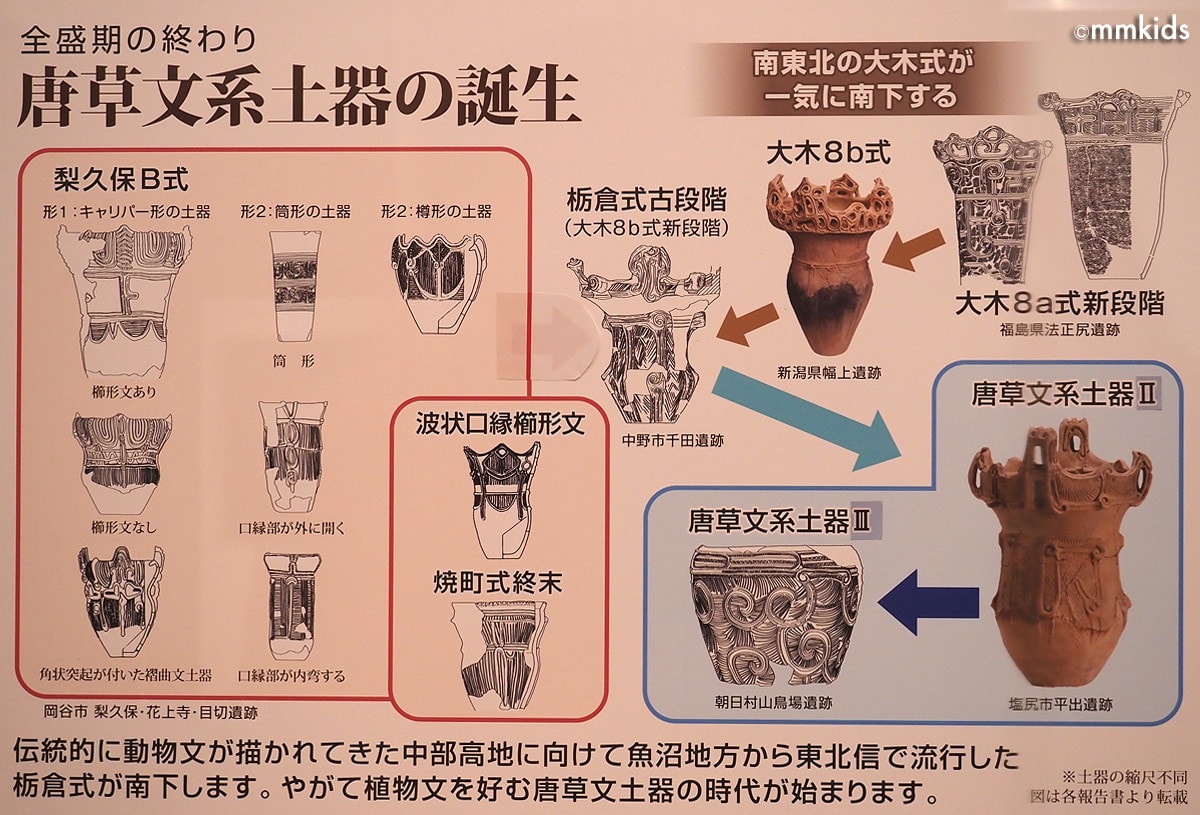3年ぶりにある山へキノコ狩りに出かけました。昨年と一昨年は、今の時期は、秋山郷や上越、糸魚川、宇奈月温泉などに車中泊の撮影の旅に出ていましたから。ここは標高1000m前後の里山です。

山は色づき始めています。曇から晴れの予報ですが、小雨が降り始めました。ただ森の中なので濡れません。気温は8度。空気が澄んでいて気持ちのいい森です。月の輪熊の生息域真っ只中なので熊鈴をつけました。実はこの山では3回ほど熊と遭遇しています。一度は追い払いました(笑)。里山は野生動物のテリトリーなので、お邪魔しているという謙虚な姿勢が大事です。と同時に彼らの生態や感情も考慮しないといけません。それは拙書の「猫にマタタビ、月の輪熊に石油」という不思議に思われるでしょうタイトルのコラムで詳細に記しています。

(左)早速クリタケを発見。何度も書いていますが、クリタケと分かっていても必ず噛んで確認します。猛毒のニガクリタケの可能性があるからです。クリタケは無味。ニガクリタケは、本当に嫌な苦味があります。(右)大きな赤松の倒木の根っこからクリタケ。これは老菌なので採りませんでした。食菌でも老菌を食べると食中毒になることもあります。

ここから左下の暗い森に入っていきます。普通は右の広葉樹の森を探すでしょうね。しかし、この暗い森の向こうにキノコのシロがあるのです。それを知っているのはおそらく私だけでしょう。

(左)スギゴケ(杉苔)の一種ですね。苔のテラリウムでも使われる人気の苔です。(右)マムシグサ(蝮草)の実。誤って食べると口内が激しくただれます。毒草ですが、薬草です。

薄暗い森を抜けてクリタケを発見。ハラタケ目モエギタケ科モエギタケ亜科クリタケ属のキノコです。細胞が球形なので壊れにくく、旨味を引き出すには冷凍するといいといわれています。おすすめは炊き込みご飯や鍋、煮込みうどん。

こんな風に株で出ます。これでひと株です。根本でつながっています。

こんな風に栗色のものもあります。なぜ違いが出るのかは分かりません。日当たりの違いでしょうか。

少し顔を出していたので木の皮を剥ぐと出てきました。こんな風に根本でつながっているので、小さなキノコを残しておくということができません。ですから本当に小さなものも無駄にせずありがたくいただきます。

360度こんな風景の森を抜けて登山道に戻ります。知らないと必ず迷うでしょう。この後で、チャナメツムタケ(ジナメ・ジナメコ)のシロに行きましたが出ていませんでした。10月の高温が影響していると思います。紅葉もやや遅めです。木肌が出ている倒木は、虫を探してイノシシが剥いだものです。

(左)やっと見つけたハナイグチ(じこぼう・時候坊)。結局2本しか採れませんでした。(右)山を下ります。黄葉が美しい。

下って帰りの林道から見る景色。北アルプスは雲の中でした。向こうの里山のあちこちに集落があるのが見えます。これが信州の里山です。高齢者が多いのですが、若い夫婦や子供達もいます。都会から移り住んだ人もいます。街までは車で30分以内で行けるので、想像するほど不便ではありません。空気が綺麗で星空が素晴らしい。こんな山間部に世界的なミュージシャンが住んでいたり、都会では味わえない地元の食材を使った美味しい蕎麦屋やベーカリーがあったりするのです。
移住希望の県に信州は一番だそうですが、いいことばかりではありません。移住自治体の移住者支援を調べること。諏訪の様に御柱の様な伝統的大祭があるところはそれなりに大変です。保守的で閉鎖的になりがちな村にどう溶け込むかはあなた次第です。でも、溶け込んだら家族以上の付き合いになったりもします。遠くの親戚より近くの他人の世界です。
古典的な共同体が残っている地域もあります。ただ盆地の平坦部は都市部に勤める人が多く、地域への結びつきは薄く、東京とあまり変わりません。私は高校卒業後上京し、40年の東京生活で帰郷しましたが、今は心地よい”よそ者”でいます。近所のおじいちゃんおばあちゃんは昔を覚えていて、親しく声をかけてくれます。地域の役職とかには参加しませんが、地方にはない経歴からアドバイスを求められたり、里山保全や講演、インタープリターなどで地味に故郷に貢献していると思います。

少し下って標高800mぐらい。紅葉や黄葉が始まっています。左の落葉松林が黄色に染まるのは、11月中旬過ぎです。散り始めると、チリチリと雨が降るような音がします。ただ、枯れ葉はスリップします。雪より怖いのです。地元の人はそれをよく知っています。

今回最も鮮やかだった紅葉。ハウチワカエデです。朝の雨に濡れて儚く哀しく美しい。しばらく佇んで観ていました。ハイ・ファイ・セットの『燃える秋』という曲が脳内を流れました。調べると、1978年12月23日に公開された五木寛之の同名小説を映画化したもので、作詞は彼で作曲がなんと武満徹。主演は真野響子。どんな映画だったのでしょう。
■ハイ・ファイ・セット 燃える秋 19781127

(左)コナラの黄葉。(右)ヤマドリ(山鳥)のつがい(番)がいました。売買が禁止されているので、食べるには知り合いの猟師から分けてもらうしかありません。キジ(雉)より美味です。山中で出会うと、巣が近い時はメスが自傷行為をして歩き回り、気を引いて子がいる巣を守ります。

今回の成果。真ん中がハナイグチ。ボウルの深さが20センチはあるので数えてはいませんが200本はあるでしょう。天然キノコはこの後の掃除が大変なのです。慣れているので30分足らずで済みましたが、ビギナーなら1時間はかかるでしょう。今夜食べる分以外は冷凍保存します。

煮込みうどんにしました。二つのハナイグチとたっぷりのクリタケ。肉はジンギスカンのラム肉。在京時代から何十年も天然キノコを食べてきましたが、どうしてこんなに美味しい出汁が出るのだろうと思います。樹と腐葉土や大地の深い旨味なのでしょう。まさに自然の恵みをいただく。そういうことですね。我々は生きている。生かされている。決してひとりではない。だれもが存在のすべてが自然と宇宙とつながっている。
◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。郷土史研究家でもあるので、その山の歴史も記しています。地形図掲載は本書だけ。立ち寄り温泉も。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。でも、できれば地元の書店さんを元気にして欲しいです。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。分かりやすいと評判のガイドマップも自作です。『真田丸』関連の山もたくさん収録。

★本の概要は、こちらの記事を御覧ください。
★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせか、メッセージからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。
インタープリターやインストラクターのお申込みもお待ちしています。好評だったスライドを使用した自然と歴史を語る里山講座や講演も承ります。市民大学などのフィールドワークを含んだ複数回の講座も可能です。左上のメッセージを送るからお問い合わせください。

山は色づき始めています。曇から晴れの予報ですが、小雨が降り始めました。ただ森の中なので濡れません。気温は8度。空気が澄んでいて気持ちのいい森です。月の輪熊の生息域真っ只中なので熊鈴をつけました。実はこの山では3回ほど熊と遭遇しています。一度は追い払いました(笑)。里山は野生動物のテリトリーなので、お邪魔しているという謙虚な姿勢が大事です。と同時に彼らの生態や感情も考慮しないといけません。それは拙書の「猫にマタタビ、月の輪熊に石油」という不思議に思われるでしょうタイトルのコラムで詳細に記しています。

(左)早速クリタケを発見。何度も書いていますが、クリタケと分かっていても必ず噛んで確認します。猛毒のニガクリタケの可能性があるからです。クリタケは無味。ニガクリタケは、本当に嫌な苦味があります。(右)大きな赤松の倒木の根っこからクリタケ。これは老菌なので採りませんでした。食菌でも老菌を食べると食中毒になることもあります。

ここから左下の暗い森に入っていきます。普通は右の広葉樹の森を探すでしょうね。しかし、この暗い森の向こうにキノコのシロがあるのです。それを知っているのはおそらく私だけでしょう。

(左)スギゴケ(杉苔)の一種ですね。苔のテラリウムでも使われる人気の苔です。(右)マムシグサ(蝮草)の実。誤って食べると口内が激しくただれます。毒草ですが、薬草です。

薄暗い森を抜けてクリタケを発見。ハラタケ目モエギタケ科モエギタケ亜科クリタケ属のキノコです。細胞が球形なので壊れにくく、旨味を引き出すには冷凍するといいといわれています。おすすめは炊き込みご飯や鍋、煮込みうどん。

こんな風に株で出ます。これでひと株です。根本でつながっています。

こんな風に栗色のものもあります。なぜ違いが出るのかは分かりません。日当たりの違いでしょうか。

少し顔を出していたので木の皮を剥ぐと出てきました。こんな風に根本でつながっているので、小さなキノコを残しておくということができません。ですから本当に小さなものも無駄にせずありがたくいただきます。

360度こんな風景の森を抜けて登山道に戻ります。知らないと必ず迷うでしょう。この後で、チャナメツムタケ(ジナメ・ジナメコ)のシロに行きましたが出ていませんでした。10月の高温が影響していると思います。紅葉もやや遅めです。木肌が出ている倒木は、虫を探してイノシシが剥いだものです。

(左)やっと見つけたハナイグチ(じこぼう・時候坊)。結局2本しか採れませんでした。(右)山を下ります。黄葉が美しい。

下って帰りの林道から見る景色。北アルプスは雲の中でした。向こうの里山のあちこちに集落があるのが見えます。これが信州の里山です。高齢者が多いのですが、若い夫婦や子供達もいます。都会から移り住んだ人もいます。街までは車で30分以内で行けるので、想像するほど不便ではありません。空気が綺麗で星空が素晴らしい。こんな山間部に世界的なミュージシャンが住んでいたり、都会では味わえない地元の食材を使った美味しい蕎麦屋やベーカリーがあったりするのです。
移住希望の県に信州は一番だそうですが、いいことばかりではありません。移住自治体の移住者支援を調べること。諏訪の様に御柱の様な伝統的大祭があるところはそれなりに大変です。保守的で閉鎖的になりがちな村にどう溶け込むかはあなた次第です。でも、溶け込んだら家族以上の付き合いになったりもします。遠くの親戚より近くの他人の世界です。
古典的な共同体が残っている地域もあります。ただ盆地の平坦部は都市部に勤める人が多く、地域への結びつきは薄く、東京とあまり変わりません。私は高校卒業後上京し、40年の東京生活で帰郷しましたが、今は心地よい”よそ者”でいます。近所のおじいちゃんおばあちゃんは昔を覚えていて、親しく声をかけてくれます。地域の役職とかには参加しませんが、地方にはない経歴からアドバイスを求められたり、里山保全や講演、インタープリターなどで地味に故郷に貢献していると思います。

少し下って標高800mぐらい。紅葉や黄葉が始まっています。左の落葉松林が黄色に染まるのは、11月中旬過ぎです。散り始めると、チリチリと雨が降るような音がします。ただ、枯れ葉はスリップします。雪より怖いのです。地元の人はそれをよく知っています。

今回最も鮮やかだった紅葉。ハウチワカエデです。朝の雨に濡れて儚く哀しく美しい。しばらく佇んで観ていました。ハイ・ファイ・セットの『燃える秋』という曲が脳内を流れました。調べると、1978年12月23日に公開された五木寛之の同名小説を映画化したもので、作詞は彼で作曲がなんと武満徹。主演は真野響子。どんな映画だったのでしょう。
■ハイ・ファイ・セット 燃える秋 19781127

(左)コナラの黄葉。(右)ヤマドリ(山鳥)のつがい(番)がいました。売買が禁止されているので、食べるには知り合いの猟師から分けてもらうしかありません。キジ(雉)より美味です。山中で出会うと、巣が近い時はメスが自傷行為をして歩き回り、気を引いて子がいる巣を守ります。

今回の成果。真ん中がハナイグチ。ボウルの深さが20センチはあるので数えてはいませんが200本はあるでしょう。天然キノコはこの後の掃除が大変なのです。慣れているので30分足らずで済みましたが、ビギナーなら1時間はかかるでしょう。今夜食べる分以外は冷凍保存します。

煮込みうどんにしました。二つのハナイグチとたっぷりのクリタケ。肉はジンギスカンのラム肉。在京時代から何十年も天然キノコを食べてきましたが、どうしてこんなに美味しい出汁が出るのだろうと思います。樹と腐葉土や大地の深い旨味なのでしょう。まさに自然の恵みをいただく。そういうことですね。我々は生きている。生かされている。決してひとりではない。だれもが存在のすべてが自然と宇宙とつながっている。
◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。郷土史研究家でもあるので、その山の歴史も記しています。地形図掲載は本書だけ。立ち寄り温泉も。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。でも、できれば地元の書店さんを元気にして欲しいです。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。分かりやすいと評判のガイドマップも自作です。『真田丸』関連の山もたくさん収録。

★本の概要は、こちらの記事を御覧ください。
★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせか、メッセージからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。
インタープリターやインストラクターのお申込みもお待ちしています。好評だったスライドを使用した自然と歴史を語る里山講座や講演も承ります。市民大学などのフィールドワークを含んだ複数回の講座も可能です。左上のメッセージを送るからお問い合わせください。