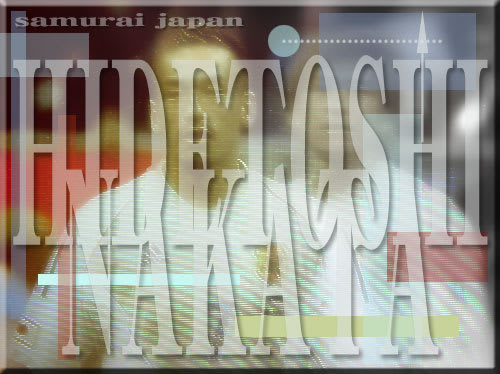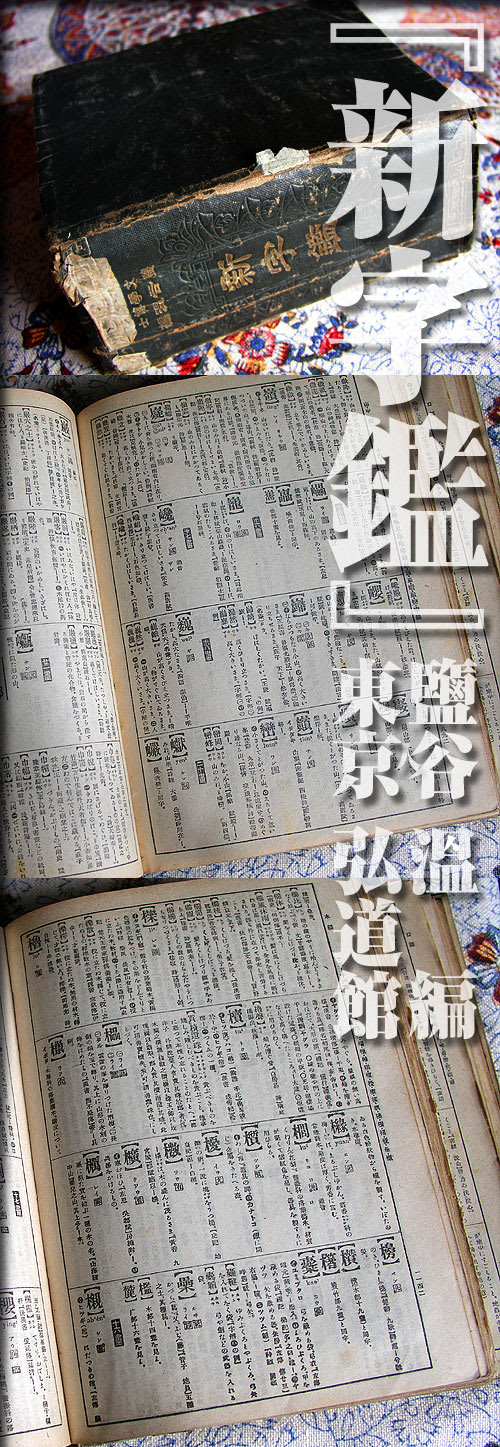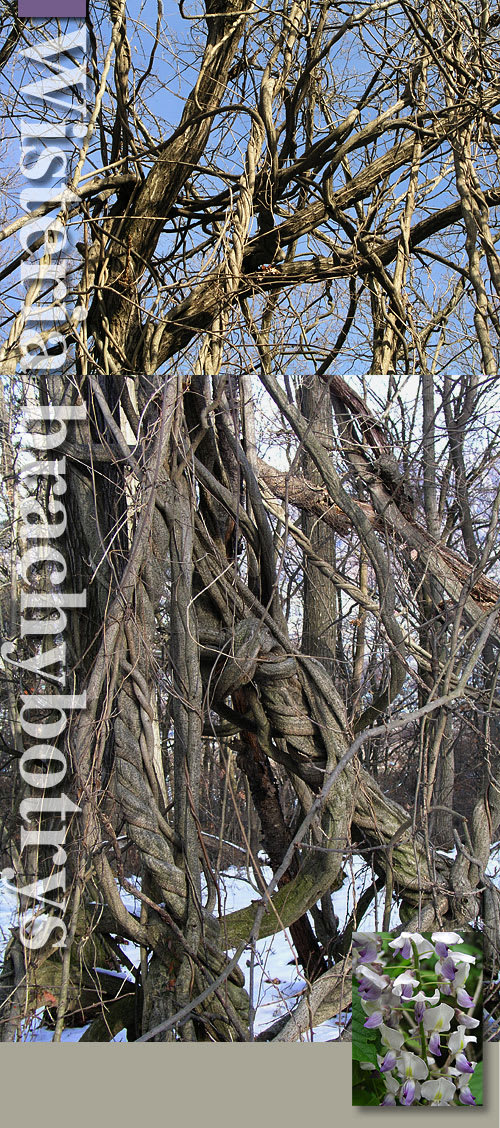まず、松代の古名である海津についてですが、『松代町史』(上巻)第二節には、この地の産土神(うぶすながみ)と伝わる皆神山にある皆神神社(熊野出速雄神社)の祭神で、諏訪の健御名方命の子でこの地の開拓を任じられた出速雄命(伊豆早雄)と、その御子である斎場山(旧妻女山)の麓にある会津比売神社の祭神・会津比売命(出速姫神)の、会津(あいづ)または出(いづ)が転訛して松代の古名である海津となったという説が記されています。
会津とは、崇神天皇10年9月9日、崇神天皇の伯父大彦命(おおひこのみこと)を北陸道へ、その子武淳川別命(たけぬなかわ わけのみこと)を東海道へ遣わせた。日本海側を進んだ大彦命は越後から東に折れ、太平洋側を進んだ武淳川別命は南奥から西に折れた。二人の出会った所を相津(會津、会津)という。『日本書紀』
相津と想定される会津坂下町青津。能登南部からの移住者を想定される弥生時代終末期の男壇遺跡・宮東遺跡があり、亀ヶ森古墳等がある。(会津学研究会サイトより引用)
會津比賣神は、貞観八年六月に妹の草奈井比売命と共に従四位下を授かっています。
その後、出速雄神は、貞観十四年(872年)四月に従五位上に、元慶二年(878年)二月に正五位下を授くとなっています。『日本三代實錄』
松代城(海津城)お膝元の長野市松代町の小中学校では、運動会に「真田節」を踊ります。中学校の時も白い鉢巻をして白扇を持ち踊りました。真田まつりに訪れると城跡や街に「花な~らば~、花な~らば~」とか「仰ぐ不滅の至誠こそ 燃える真田の心意気」などという歌詞の真田節が流れ、踊りも見られます。
その整備された松代城址ですが、昭和40年頃は海津城址と呼び石垣以外はなにもない寂れた古城でした。たしか城内に檻があって近隣の山で捕らえられた月の輪熊が一頭、手持ちぶさたにグルグルと狭い檻の中を廻っていました。フリークライミングよろしく石垣をよじ登って遊んだものです。
海津城の起源については、清野村誌の記述により清野氏という説があります。
●清野屋敷・禽(とり)の倉屋敷
村の北の方、字中沖にあり。往古本村領主清野氏数代之に居す。年月不詳。清野某海津に移り、該地に倉庫を建つ。此時より禽の倉屋敷と称す。天文、弘治中、清野山城守武田氏に敗られ、越後に逃走するに及び武田氏の有となり、天正十年三月武田勝頼滅び、織田信長の臣森長可の有となり、六月信長弑せされ長可西上するに至り、七月上杉景勝の所有となり、某幕下清野左衛門尉宗頼、該地に移り居住すと言ぅ。管窺武鑑に七月四郡(埴科・更級・水内・高井)上杉景勝の有となり、清野左衛門尉を、猿ケ馬場の隣地、竜王城に移とあり。一時此処に居せしか不詳。後真田氏領分の時に至り寛永中焼亡す。後真田氏の臣高久某此域に居住し、邸地に天満宮を観請す。弘化二乙己四月村民清野氏の碑を建つ。(清野村誌)
●清野氏について(清野氏については、「
清野氏と戦国時代」をお読みください。)
清和天皇の皇子貞純親王五代の後裔仲宗は京都の院の庁に仕え、殿上人として栄えていたが、白河上皇の関する事件で、仲宗は讃岐へ、子の惟清、顕清はそれぞれ伊豆、信濃に流された。顕清の弟盛清は惟清の養子となり、顕清の子の為国は信濃国村上郷に住み、為国の子惟国が清野に住み清野氏と称したという。(埴科郡誌)
関東管領の職についた上杉憲実は伊豆にいたが、幕命によって鎌倉に入り、弟の清方と上杉持朝に命じて結城城攻撃に当らせ、自らも兵を率いて鎌倉を発した。
憲実は信濃守護小笠原正透に陣中奉行を命じた。正透はこれにより信濃国中の諸士を三十番に分かち、陣中の取締りや矢倉の番をさせた。この中に、屋代、雨宮、生仁、関屋、寺尾、西条氏等があった。こうして正透らの攻撃により結城城は落城した。1441年(嘉士口元)のことであった。清野氏は永寿王を送り届けると、清野へ帰ったようであるが、その後の行動については詳らかでない。その頃の足利尊氏以来の年初恒例の射場始めの射手選びとか、諏訪社の流鏑馬や御射山頭役などに屋代氏、村上氏などが見えるが清野氏の名は見あたらない。
1467年(応仁元)清野正衡は入道して徳寿軒といい鞍骨城を築き、後1510年(永正年間)頃同城の鬼門除けに離山神社を創建したという。
1488年(長享2)清野氏(正衡の頃か)諏訪社の下社秋宮宝殿造営の郷と定められている。
1495年(明応4)清野伊勢守長続(伊勢守国基か)の頃、英多庄(松代、東条、西条、豊栄)を支配していたことが記されている。16世紀のはじめ(国俊の頃か)節香徳忠和尚を請し森村に禅透院を建てた。
1540年(天丈九)武田信虎は信濃国を攻略しょうと始めて佐久郡に攻め入り、小県郡毎野棟網を攻めた。海野氏は敗れて棟綱と子の幸隆は上野国に逃れ、関東管領上杉憲政に頼った。憲政は武田氏の勢力を佐久地方から排除し、海野氏を故地に還してやるために兵三千を率いて佐久に攻め入った。村上義清はこれを聞くと直ちに諏訪頼垂と武田暗信に急報し救援を求めた。諏訪頼重はさっそく兵を率いて小県郡に入り上杉陣に対した。しかし義清、晴信は頼重を助けようとしないので、頼重は単独に憲政と講和しそれぞれ領国に帰った。晴信は頼重が単独講和したことを怒り、諏訪郡に入り頼重を攻め滅し、続いて伊那、筑摩方面を攻めてこれを征服した。 (埴科郡誌)
●信州に進出した武田信玄は、上杉謙信の攻撃に備え、山本勘助に命じて1560(永禄3)年頃に「海津城」(後の松代城)を完成させたようです。『甲陽軍艦』には、1553(天文22)年に山本勘助が構築したとありますが、当時この辺りが武田氏の勢力下にあったことはなく、1555(弘治元)年影虎、晴信が長く対陣した際にもこの城を利用した記録はないそうです。ただこのすぐ後に、北信濃攻略の足がかりとして清野氏館跡に目をつけ「海津城」を築城したものと思われます。
信玄は重臣・高坂昌信(香坂弾正虎綱)を完成した「海津城」に置き、上杉謙信に対峙しました。第四次川中島合戦ではここに本陣を置き、有名な啄木鳥(きつつき)戦法で戦ったといわれています。啄木鳥戦法は、江戸時代の命名です。確認された史実ではありません。啄木鳥戦法については、「
啄木鳥戦法の検証」をお読みください。
1578(天正6)年高坂昌信が没すると、春日信達が二代目の城将となります。
●武田氏滅亡後、1582(天正10)年、織田信長の部将・森長可が2ヶ月のみ在城。しかし、信長の急死(同年)により、芋川氏らの一揆により、京に逃げ帰らざるを得ず手放します。
本能寺の変後は上杉景勝の領するところとなりました。
上杉方の春日信達(武田氏の旧臣・春日弾正忠)が治めましたが、北条氏への内通の嫌疑を掛けられ上杉景勝に殺されました。
北条氏直の小県侵入で、武田氏の旧臣の多くがこれに従ったので、春日信達は真田昌幸と密かに通じ、氏直を川中島方面に引入れ景勝と戦わせ、自身は海津城から氏直に呼応して景勝に叛き、氏直に勝利を導こうとしました、しかしこれは事前に発覚し。弾正忠は捕えられ殺されました。このとき景勝は氏直の川中島出陣に備えて海津城を出て清野鞍掛山(鞍骨山)の麓赤坂山(妻女山)に陣したとも伝えられています。
すると上杉景勝は村上義清の子、国清(景国)に任せました。
しかし、1584(天正12)年に国清の副将屋代秀正が家康に内通して出奔したため罷免されます。
そして景勝の一族・上城宜春(義春・宣順)が入りました。
しかし、秀吉が景勝に人質を要求したため景勝は妹婿である上条義春の子を人質に出すことにし、その代りとして義春の諸役をゆるめ、海津城将としての勤務を免除しました。義春の後役として、景勝は越中国に在陣していた須田相模守満親を城将としました。
1585(天正13)年から入った須田満親は、1598(慶長3)年までと比較的長く治めます。
●1598(慶長3)年、上杉景勝が秀吉の命で会津移封となり、この地方が豊臣秀吉の蔵入地となると、田丸直昌が海津城主に封ぜられました。
このとき景勝の分国であった北信濃四郡には、海津城に須田相模守満親、長沼城に島津淡路守忠直、飯山城に岩井備中守信能、牧島城の芋川越前守親正らが在職していましたが、これらの諸将にはそれぞれ会津藩の新領地に配置を定め、その他の地士たちにも、謙信以来の勲功に報ゆるために、それぞれ高禄を給しました。
このとき海津城将だった須田満親には二万三千石、清野助次郎長範には一万四千石、その他西条氏、寺尾氏、大室氏らも優遇して禄を給せられています。 北信濃四郡からは、この地の地名を有する土豪とその家臣が全ていなくなりました。須田満親は、上杉氏とともに国替えで会津に行った後になぜか自害しています。
●豊臣秀吉から徳川家康へと政権が移り、家康は1600(慶長5)年に森長可の弟忠政を入れます。忠政は「海津城」を改修し、兄の長可が自分が来るのを待っただろうと「待城」と改名したのですが、領地に過酷な総検地を行ったため農民の恨みを買いました。度重なる出陣や城の改修で家臣への俸禄が充分に払えず、上田の陣では、足軽たちが暇を請うという事態に発展、家老・林為忠が自らの具足櫃から俸禄を出して引き留めたといいいます。(先代実録)
1603(慶長8)年、森忠政が美作へと加増転封されると、家康の六男・松平忠輝の領地となり、「松城」と改名されました。
1610(慶長15)年、花井吉成。1613(慶長18)年、花井義雄。1616(元和2)年、松平忠昌。1618(元和4)年、酒井忠勝。と城主が転々と代わります。
1622(元和8)年に徳川秀忠の命で上田城から真田信之が移封され、1711(宝永8/正徳元)年、孫の幸道のときに「松代城」と改名されました。以後明治まで10代真田氏十万石の領地となりました。真田信之の霊屋は、城の西方の長国寺にあり、破風の鶴は左甚五郎作と伝えられています。
★写真は、城内から見た太鼓門と太鼓門表門(橋詰門)から見た武田別働隊が越えたとされる戸神山脈。
その2へ続きます。江戸時代から明治へ。