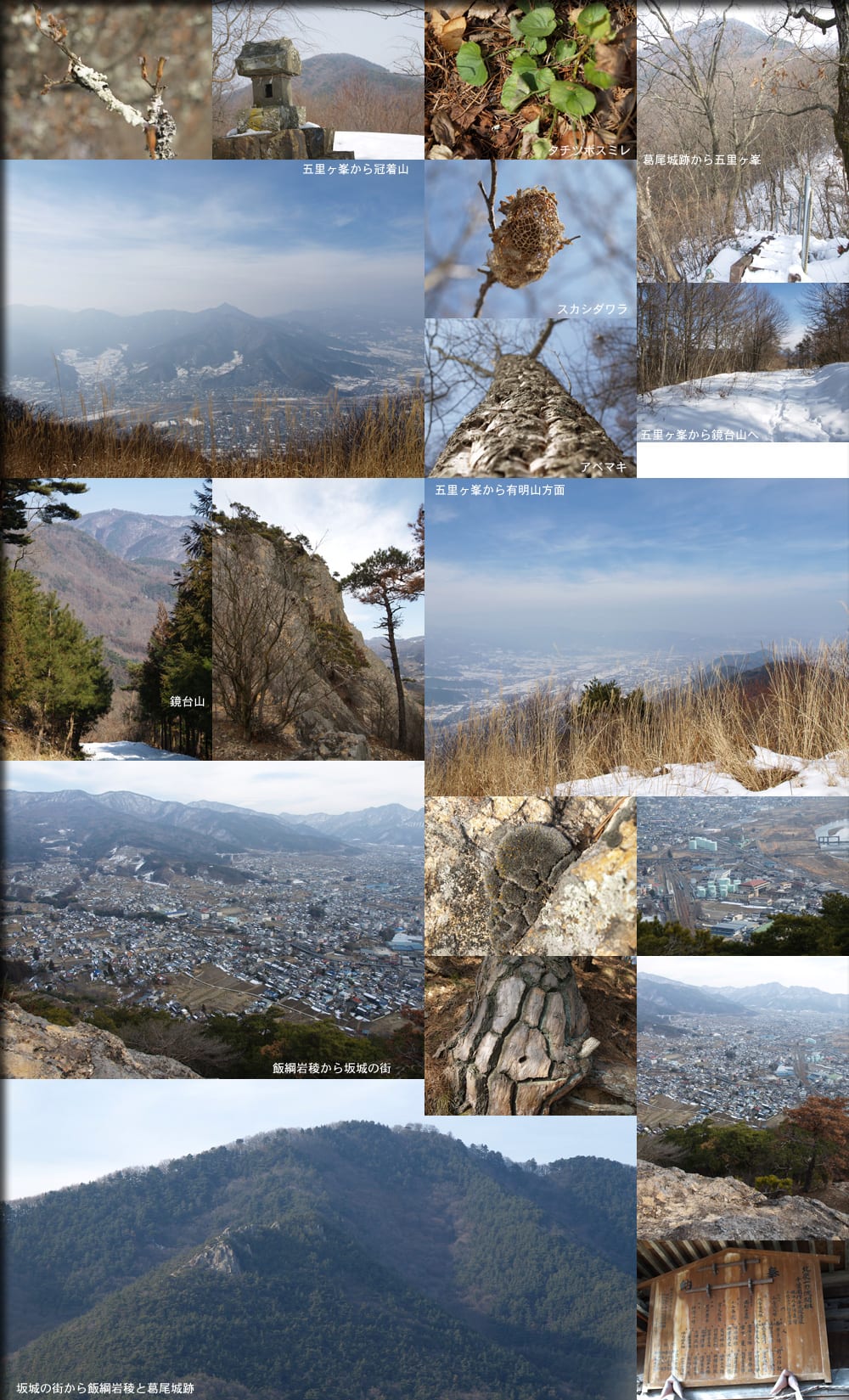昨年の夏に登った日本のギアナ高地と呼ばれる信州の米子大瀑布から、真夏の根子岳・四阿山・浦倉山へ22.5kmカルデラロング周回コースのスライドショーをYoutubeにアップしました。
コースは、米子大瀑布P1284m--米子鉱山跡--根子岳・浦倉山分岐--ザレ岩1992m--小根子岳2127.9m--根子岳2207m--十ガ原(大すき間)2039m--四阿山2354m--浦倉山2090.6m--根子岳・浦倉山分岐--米子不動奥宮--不動滝--米子大瀑布とかなり長めです。トレランで走る人達もいるようですが、百名山の四阿山にたくさんの人が登る菅平側と違いこのルートは足を踏み入れる人は極めて稀で、カルデラの中では熊に遭遇することはあっても、まず人に出会う事はありません。その分大自然を堪能できます。
コースは標識もほとんどなく、迷い易いところも何カ所かあるので、事前の下調べが必須です。また、地形図やコンパスは必携です。もちろん熊鈴も。浦倉山から下りた米子大瀑布の上には、米子鉱山の遺構も残っています。郷土史を知るという面でも面白いコースです。
ハイビジョンでご覧になりたい方は、この文章をクリックしてください。






★ネイチャーフォトは、【MORI MORI KIDS Nature Photograph Gallery】をご覧ください。キノコ、変形菌(粘菌)、コケ、花、昆虫などのスーパーマクロ写真。滝、巨樹、森の写真、森の動物、特殊な技法で作るパノラマ写真など。
コースは、米子大瀑布P1284m--米子鉱山跡--根子岳・浦倉山分岐--ザレ岩1992m--小根子岳2127.9m--根子岳2207m--十ガ原(大すき間)2039m--四阿山2354m--浦倉山2090.6m--根子岳・浦倉山分岐--米子不動奥宮--不動滝--米子大瀑布とかなり長めです。トレランで走る人達もいるようですが、百名山の四阿山にたくさんの人が登る菅平側と違いこのルートは足を踏み入れる人は極めて稀で、カルデラの中では熊に遭遇することはあっても、まず人に出会う事はありません。その分大自然を堪能できます。
コースは標識もほとんどなく、迷い易いところも何カ所かあるので、事前の下調べが必須です。また、地形図やコンパスは必携です。もちろん熊鈴も。浦倉山から下りた米子大瀑布の上には、米子鉱山の遺構も残っています。郷土史を知るという面でも面白いコースです。
ハイビジョンでご覧になりたい方は、この文章をクリックしてください。
★ネイチャーフォトは、【MORI MORI KIDS Nature Photograph Gallery】をご覧ください。キノコ、変形菌(粘菌)、コケ、花、昆虫などのスーパーマクロ写真。滝、巨樹、森の写真、森の動物、特殊な技法で作るパノラマ写真など。