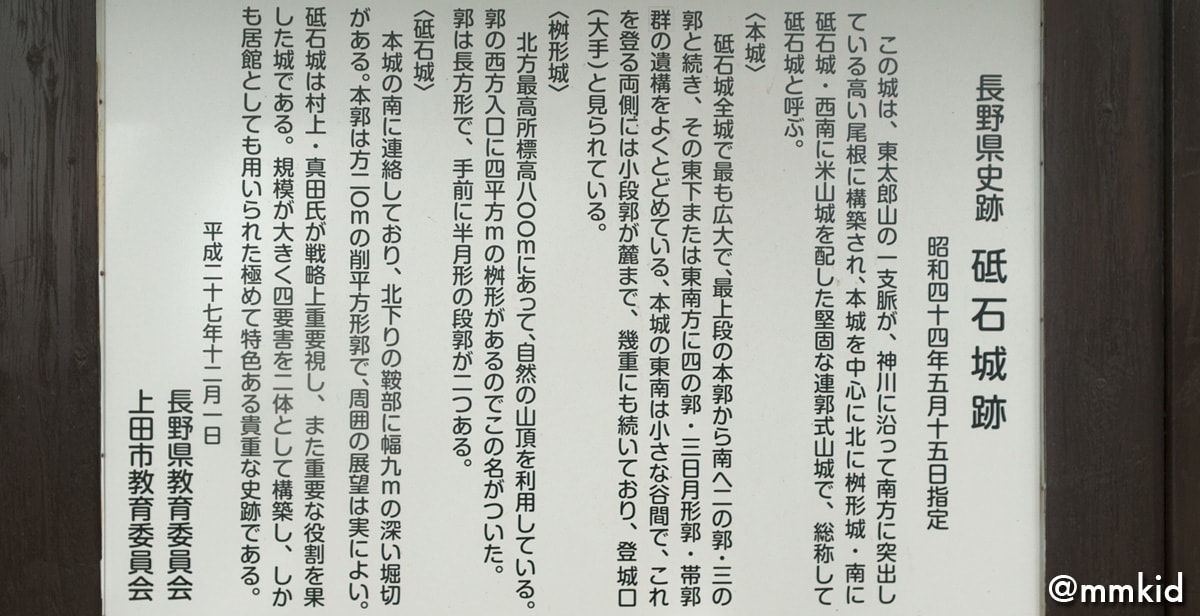小春日和の週末の昼近く、斎場山(旧妻女山)へ久しぶりに登ってみました。狩猟が始まったので、イノシシ狩りのハンターが2グループ入っていました。猟犬がどこかへ行ってしまったというハンターと長坂峠で談笑。途中で採ったというヒラタケとナラタケを見せてくれました。陣馬平を知らないというので拙書を見せて説明。犬は戻ってきたのですが、リードがなくて繋げません。仲間の車が来るのを待ちました。
この季節、ハイカーは目立つ服装でホイッスルを携行し、銃声が聞こえたら吹いて存在を知らせてください。上から撃つので尾根の登山道を歩いているなら大丈夫です。妻女山山系では、主に天城山北西部の谷で狩猟が行われます。ハンターに出会ったら、これから向かうルートを説明し、仲間に無線で知らせてもらってください。

(左)斎場山山頂。山頂は、第四次川中島合戦で上杉謙信が本陣としたと地元で伝わる場所です。(中)山頂は古代科野国の古墳。円墳なので丸く平らです。落葉して北面の飯綱山や戸隠連峰が見える様になりました。(右)南方を見ると、右奥に天城山(てしろやま)、左に謙信が七棟の陣城を建てたと伝わる陣馬平の高い落葉松林。

北側に戻ると下から視線を感じました。見下ろすと白いニホンカモシカが一頭。まだ子供です。グレーの子供を陣馬平で目撃したので、2月に出会った時に、お腹が非常に大きかったシロはやはり双子を産んだ様です。シロの母親も、シロとクロ(オス)の双子を産みました。シロはおそらく2007年生まれで、2011年に双子、2014年に一頭、そして2016年にまた双子を産んだというわけです。シロは夏毛が白いのでシロと呼んでいますが、冬毛は濃い灰色です。この子供は既に冬毛ですが、凄く白っぽい。とりあえずマッシロと呼ぶことにしました。個体識別のためです。しかし、野生動物なので触れたり餌付けは絶対にしてはいけません。
◉妊娠中のシロ(2016年2月)ニホンカモシカのスライドショー2本も

警戒心よりも好奇心の方が強い様で、じっと私を見ています。レンズを替えるから待っててねと話しかけながら古墳を下りて近寄ってみました。目の下の涙袋の様なものは眼下線で、蹄間線からも出す粘液を木の幹や岩などにこすりつけて縄張りを主張します。同性の縄張りは重なりませんが、成獣のオスの縄張りは広く、メスのそれと重なることもあります。ニホンカモシカといいますがシカではなくウシ科。しかし、これだけ白いとヤギと間違えそうです。

(左)少し飽きたのか横を向いたり。(中)何か気になるのか別の方向を見たり。(右)オーイと呼ぶと振り返りました。額に茶色い毛があるのは、母親のシロと同じです。

大丈夫そうなのでさらに近づいてみました。距離は4mぐらいです。最初の方のカットより、表情が柔らかくなっているのが分かるでしょうか。この個体がオスなのかメスなのか気になります。なんとなくこの柔らかい表情からメスかなと思いました。ニホンカモシカは、オスメス共に角があるので、判別が難しいのです。体長は100〜120センチで、体重は30〜45キロほど。昔は標高1500〜2000mの深山へ行かないと見られないといわれましたが、標高400mほどの妻女山でも見られるということは。天然記念物になったり、天敵だった狼も絶滅して個体数がかなり増えているのでしょう。長野県や岐阜県では、林業被害防止のために一定数が駆除もされています。

(左)すると、腰を下げて小便をし始めました。これで分かりました。間違いなくメスです。オスは立ったまま用をたします。たくさん溜まっていた様で、かなり長い時間していました。(中)終えると少し歩いて足元の枯葉を食べました。妻女山山系での冬の餌は、ヤブソテツやリョウメンシダ、青い三葉木通の葉やヒノキの葉など。ひとつのものを集中的に食べることはしません。(右)別に笑っているのではなく、反芻しているのです。
秋に交尾をし、初夏に出産します。半年で離乳するそうですが、夏頃一頭で草を食べ歩く、双子のもう一頭を見かけたので、授乳されながらも採食歩行も始める様です。2〜3歳まで母親と一緒にいますが、採食歩行のルートは別々の場合もあり、ある時間になると同じ場所に集まっているのを見かけます。

彼女の祖母は、マダムと呼んでいました。初見が2002年の夏で、その年に生まれた様です。2011年の1月にはシロと一緒のところを目撃しました。2012年には見なくなったので、寿命は約10年ということでしょう。カモシカの毛皮は保温性や防水性が高く、尻皮として利用され、肉は食用となりました。カモシカの呼び名は全国各地に沢山あり、アオジシ、アオ、踊り獅子とか肉馬鹿、単に肉なんていうのもあります。

反芻はこの様に立ったまますることもありますが、普通は座ってします。しかし、積雪が深い時は立ったまますることが多く、これを「アオの寒立ち」といいます。ニホンカモシカはまず鳴きません。近づきすぎるとシュッ!と威嚇音を出しますが、これは強い鼻息で鳴き声ではありません。以前一度だけ子供が母親を呼ぶ鳴き声を聞いたことがありますが、グエーッ!という様な、ヤギかヒツジがだみ声で鳴いたような感じでした。

(左)そろそろ私にも飽きた様で、歩き出しました。そこで「ちょっと待って!」と声をかけると立ち止まって振り向きました。(中)しばらく口をモグモグさせながらそこにいましたが。(右)やがてゆっくりと谷底へ下りて行きました。30分もモデルをやってくれて感謝です。
下記の拙書『信州の里山トレッキング 東北信編』の『「森の哲人」ニホンカモシカの好奇心』というコラムの中で、「昔、ニホンカモシカは群れを作っていたのではないか」という仮設を、『遠山奇談』を取り上げて書いています。興味のある方はぜひお読みください。

(左)陣馬平の落葉松の黄葉も風が吹く度にチリチリと雨を降らせます。(中)江戸時代の峠、東風越えに戻って、現在の峠、長坂峠を右に見て、左奥に斎場山。(右)長坂峠から北方の川中島方面。落葉して飯縄山や戸隠連峰がよく見える様になりました。

妻女山(旧赤坂山)から、茶臼山と右奥の虫倉山、北アルプスの白馬三山。左から白馬鑓ヶ岳、杓子岳、白馬岳が綺麗に見えました。
◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。郷土史研究家でもあるので、その山の歴史も記しています。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。でも、できれば地元の書店さんを元気にして欲しいです。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。分かりやすいと評判のガイドマップも自作です。『真田丸』関連の山もたくさん収録。

★本の概要は、こちらの記事を御覧ください。
★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。
インタープリターやインストラクターのお申込みもお待ちしています。長野県シニア大学や自治体などで好評だったスライドを使用した自然と歴史を語る里山講座や講演も承ります。大学や市民大学などのフィールドワークを含んだ複数回の講座も可能です。左上のメッセージを送るからお問い合わせください。






この季節、ハイカーは目立つ服装でホイッスルを携行し、銃声が聞こえたら吹いて存在を知らせてください。上から撃つので尾根の登山道を歩いているなら大丈夫です。妻女山山系では、主に天城山北西部の谷で狩猟が行われます。ハンターに出会ったら、これから向かうルートを説明し、仲間に無線で知らせてもらってください。

(左)斎場山山頂。山頂は、第四次川中島合戦で上杉謙信が本陣としたと地元で伝わる場所です。(中)山頂は古代科野国の古墳。円墳なので丸く平らです。落葉して北面の飯綱山や戸隠連峰が見える様になりました。(右)南方を見ると、右奥に天城山(てしろやま)、左に謙信が七棟の陣城を建てたと伝わる陣馬平の高い落葉松林。

北側に戻ると下から視線を感じました。見下ろすと白いニホンカモシカが一頭。まだ子供です。グレーの子供を陣馬平で目撃したので、2月に出会った時に、お腹が非常に大きかったシロはやはり双子を産んだ様です。シロの母親も、シロとクロ(オス)の双子を産みました。シロはおそらく2007年生まれで、2011年に双子、2014年に一頭、そして2016年にまた双子を産んだというわけです。シロは夏毛が白いのでシロと呼んでいますが、冬毛は濃い灰色です。この子供は既に冬毛ですが、凄く白っぽい。とりあえずマッシロと呼ぶことにしました。個体識別のためです。しかし、野生動物なので触れたり餌付けは絶対にしてはいけません。
◉妊娠中のシロ(2016年2月)ニホンカモシカのスライドショー2本も

警戒心よりも好奇心の方が強い様で、じっと私を見ています。レンズを替えるから待っててねと話しかけながら古墳を下りて近寄ってみました。目の下の涙袋の様なものは眼下線で、蹄間線からも出す粘液を木の幹や岩などにこすりつけて縄張りを主張します。同性の縄張りは重なりませんが、成獣のオスの縄張りは広く、メスのそれと重なることもあります。ニホンカモシカといいますがシカではなくウシ科。しかし、これだけ白いとヤギと間違えそうです。

(左)少し飽きたのか横を向いたり。(中)何か気になるのか別の方向を見たり。(右)オーイと呼ぶと振り返りました。額に茶色い毛があるのは、母親のシロと同じです。

大丈夫そうなのでさらに近づいてみました。距離は4mぐらいです。最初の方のカットより、表情が柔らかくなっているのが分かるでしょうか。この個体がオスなのかメスなのか気になります。なんとなくこの柔らかい表情からメスかなと思いました。ニホンカモシカは、オスメス共に角があるので、判別が難しいのです。体長は100〜120センチで、体重は30〜45キロほど。昔は標高1500〜2000mの深山へ行かないと見られないといわれましたが、標高400mほどの妻女山でも見られるということは。天然記念物になったり、天敵だった狼も絶滅して個体数がかなり増えているのでしょう。長野県や岐阜県では、林業被害防止のために一定数が駆除もされています。

(左)すると、腰を下げて小便をし始めました。これで分かりました。間違いなくメスです。オスは立ったまま用をたします。たくさん溜まっていた様で、かなり長い時間していました。(中)終えると少し歩いて足元の枯葉を食べました。妻女山山系での冬の餌は、ヤブソテツやリョウメンシダ、青い三葉木通の葉やヒノキの葉など。ひとつのものを集中的に食べることはしません。(右)別に笑っているのではなく、反芻しているのです。
秋に交尾をし、初夏に出産します。半年で離乳するそうですが、夏頃一頭で草を食べ歩く、双子のもう一頭を見かけたので、授乳されながらも採食歩行も始める様です。2〜3歳まで母親と一緒にいますが、採食歩行のルートは別々の場合もあり、ある時間になると同じ場所に集まっているのを見かけます。

彼女の祖母は、マダムと呼んでいました。初見が2002年の夏で、その年に生まれた様です。2011年の1月にはシロと一緒のところを目撃しました。2012年には見なくなったので、寿命は約10年ということでしょう。カモシカの毛皮は保温性や防水性が高く、尻皮として利用され、肉は食用となりました。カモシカの呼び名は全国各地に沢山あり、アオジシ、アオ、踊り獅子とか肉馬鹿、単に肉なんていうのもあります。

反芻はこの様に立ったまますることもありますが、普通は座ってします。しかし、積雪が深い時は立ったまますることが多く、これを「アオの寒立ち」といいます。ニホンカモシカはまず鳴きません。近づきすぎるとシュッ!と威嚇音を出しますが、これは強い鼻息で鳴き声ではありません。以前一度だけ子供が母親を呼ぶ鳴き声を聞いたことがありますが、グエーッ!という様な、ヤギかヒツジがだみ声で鳴いたような感じでした。

(左)そろそろ私にも飽きた様で、歩き出しました。そこで「ちょっと待って!」と声をかけると立ち止まって振り向きました。(中)しばらく口をモグモグさせながらそこにいましたが。(右)やがてゆっくりと谷底へ下りて行きました。30分もモデルをやってくれて感謝です。
下記の拙書『信州の里山トレッキング 東北信編』の『「森の哲人」ニホンカモシカの好奇心』というコラムの中で、「昔、ニホンカモシカは群れを作っていたのではないか」という仮設を、『遠山奇談』を取り上げて書いています。興味のある方はぜひお読みください。

(左)陣馬平の落葉松の黄葉も風が吹く度にチリチリと雨を降らせます。(中)江戸時代の峠、東風越えに戻って、現在の峠、長坂峠を右に見て、左奥に斎場山。(右)長坂峠から北方の川中島方面。落葉して飯縄山や戸隠連峰がよく見える様になりました。

妻女山(旧赤坂山)から、茶臼山と右奥の虫倉山、北アルプスの白馬三山。左から白馬鑓ヶ岳、杓子岳、白馬岳が綺麗に見えました。
◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。郷土史研究家でもあるので、その山の歴史も記しています。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。でも、できれば地元の書店さんを元気にして欲しいです。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。分かりやすいと評判のガイドマップも自作です。『真田丸』関連の山もたくさん収録。

★本の概要は、こちらの記事を御覧ください。
★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。
インタープリターやインストラクターのお申込みもお待ちしています。長野県シニア大学や自治体などで好評だったスライドを使用した自然と歴史を語る里山講座や講演も承ります。大学や市民大学などのフィールドワークを含んだ複数回の講座も可能です。左上のメッセージを送るからお問い合わせください。