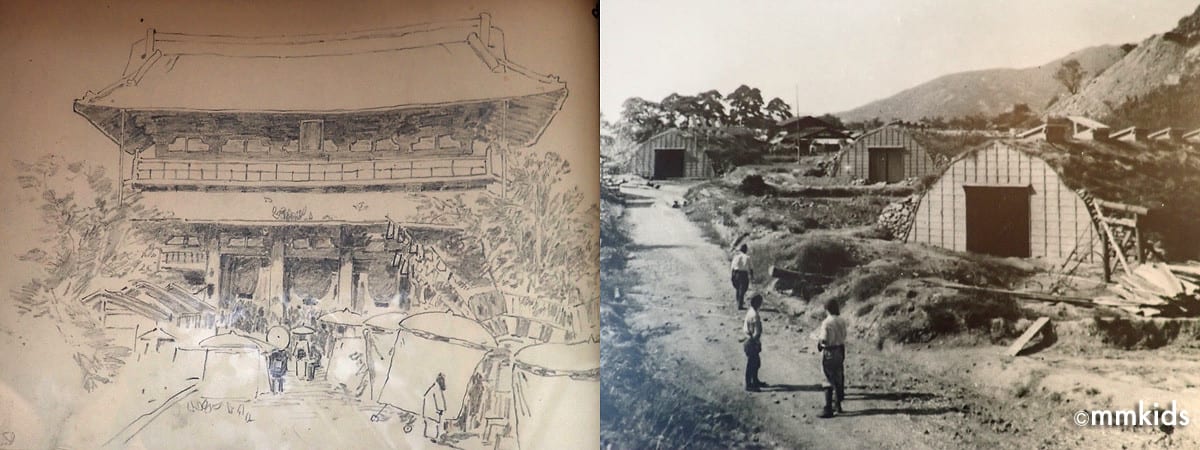茶臼山へ行く前に、まず妻女山の御天井にある樹液バーへ。林道はグチャグチャの泥濘状態で、タイヤがスリップして危険でした。長雨の後なので期待はしていませんでしたが、やはり。

カナブンとその右下には頭を突っ込んだきりの、おそらくコクワガタのメス。上にいるのはヤドリバエ科の一種かと。右下にいるのは、キボシテントウダマシ。雨上がりで湿度100%。オオムラサキは葉の陰で休んでいるでしょう。数カット撮影してから千曲川を渡り、茶臼山へ向かいました。

(左)拙書でも紹介している信里小の校門の向かいの道を100mほど入ったところにある駐車場へ。大正時代に立てられた川中島の戦いの石碑があります。ただ信玄がここに布陣したという史料はないのでフィクションでしょう。この下に耕心庵という寺がありますが、戦いの後信玄がここから川中島を見渡し、いいところだなと言ったという伝説が書いてあります。その前に布陣していたら、既に知っているわけで、そんなことは言いませんよね。(右)その周囲に並ぶ通称旗塚。川中島の戦いで旗を立てたとか埋めたとかいわれる塚ですが、これも作り話で、おそらく薄葬令以降のこの地の有力者の墓だと思われます。妻女山や五一山脈の古墳の近くにもいくつも見られます。

(左)毒々しい紅色の傘。チシオタケでしょうか。辛くて不食。(右)傘の裏が網状でイグチ科のキノコ。ニガイグチの仲間でしょうか。苦くてとても食べられません。在京時代に誤って一本入ってしまい、キノコ鍋を全部捨てたことがあります。この時期のアカヤマドリやヤマドリタケモドキ(欧州のポルチーニやセップ)は、ありませんでした。信州新町道の駅では、チチタケなどとともに売っている様です。

(左)伐採木の断面に最初は粘菌かと思いましたが、撮影して拡大するとシロキクラゲの幼菌と分かりました。キノコムシでしょうか、小さな甲虫が食べている様です。(右)長雨で苔は生き生きしています。

(左)ノアザミ(野薊)キク科アザミ属。花弁が5枚の筒状花がたくさん集まって頭状花を形成しています。総苞が粘ることでノハラアザミと区別できます。(中)5,6ミリぐらいの小さな花、よく見ると林道脇にたくさん。未同定。(右)ユリ科ヤブランの蕾。

アオイトトンボ(青糸蜻蛉)トンボ目イトトンボ亜目アオイトトンボ科アオイトトンボ亜科。トンボの翅は4枚が複雑な動きをしてホバリングができます。筋肉が4枚の翅の基部につながっていて、それぞれを別々に動かせるからです。これを直接飛翔筋型昆虫といいます。翅は、細いパイプ状の翅脈(しみゃく)と、透明な薄い膜でできていますが、全体重の2パーセントほどしかありません。

トンボは不退転の勝ち虫と呼ばれ、武士の兜の前立によく使われました。他にも昆虫を使った兜は多く、蝶、百足(ムカデ)、スズメバチなどもあります。戦場では昆虫食も普通だったでしょう。どれが食べられる美味しい虫か知っていたはずです。

(左)茶臼山動物園入り口左の道を抜けて植物園へ。自然植物園中腹にある展望台。(右)その上にある英国風庭園。絵本作家のターシャ・テューダーとかビアトリクス・ポターの児童書「ピーターラビット」を思い出します。もう少し広い面積で作ってもいいと思います。

吸蜜の後、休憩中のベニシジミ。夏型なので翅の表が黒い。数頭見られました。

(左)ヤノトガリハナバチに似ているのですが、脚の色とか胸部の横の黄班とか違うのです。未同定。花はオミナエシ(女郎花)。(右)オオハナアブが吸蜜中。ラウンドアップや草退治などの毒薬除草剤で、ミツバチ、ハナアブが激減し、果樹園も野菜畑も自然のままでは受粉が難しくなっています。中枢神経を冒し癌、脳の発達障害、多動性症候群、奇形などを引き起こします。当ブログでも何度も記事をアップしています。ブログ内検索を。

吸蜜中のツマグロヒョウモンのオス。メスも我が家の庭でもたまに見られます。

(左)コオニユリ。(小鬼百合)ユリ科。(右)ヤナギラン(柳蘭)アカバナ科。山火事の跡に最初に群生するため英名はFireweed(火の草)。種子は白く長い毛があり風で飛んでいきます。

(左)アジサイ(紫陽花、八仙花)。(右)キキョウ(桔梗・Platycodon grandiflorus)キキョウ科。多年性草本植物。万葉集のなかで秋の七草と歌われている「朝貌の花」といわれています。根はサポニンを多く含むことから生薬(桔梗根)として利用されます。

園芸種には疎いので、写真だけを載せます。自然植物園には園芸種の花もたくさん植えられています。下の恐竜公園から登ってアスレチックを過ぎて、藤棚をすぎると茶臼山へ登れます。拙書にも載せているコースで、ファミリー向けです。

善光寺平の眺め。右奥に三角の笠岳がそびえています。緑色の帯は犀川と河川敷。左奥にエムウェーブが見えます。手前に北陸新幹線の高架。雨が降り出したので帰りました。久しぶりに戸倉上山田温泉の万葉超音波温泉に入りました。
◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。郷土史研究家でもあるので、その山の歴史も記しています。地形図掲載は本書だけ。立ち寄り温泉も。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。でも、できれば地元の書店さんを元気にして欲しいです。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。分かりやすいと評判のガイドマップも自作です。『真田丸』関連の山もたくさん収録。

★本の概要は、こちらの記事を御覧ください。
★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせか、メッセージからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。
インタープリターやインストラクターのお申込みもお待ちしています。シニア大学や自治体などで好評だったスライドを使用した自然と歴史を語る里山講座や講演も承ります。大学や市民大学などのフィールドワークを含んだ複数回の講座も可能です。左上のメッセージを送るからお問い合わせください。

カナブンとその右下には頭を突っ込んだきりの、おそらくコクワガタのメス。上にいるのはヤドリバエ科の一種かと。右下にいるのは、キボシテントウダマシ。雨上がりで湿度100%。オオムラサキは葉の陰で休んでいるでしょう。数カット撮影してから千曲川を渡り、茶臼山へ向かいました。

(左)拙書でも紹介している信里小の校門の向かいの道を100mほど入ったところにある駐車場へ。大正時代に立てられた川中島の戦いの石碑があります。ただ信玄がここに布陣したという史料はないのでフィクションでしょう。この下に耕心庵という寺がありますが、戦いの後信玄がここから川中島を見渡し、いいところだなと言ったという伝説が書いてあります。その前に布陣していたら、既に知っているわけで、そんなことは言いませんよね。(右)その周囲に並ぶ通称旗塚。川中島の戦いで旗を立てたとか埋めたとかいわれる塚ですが、これも作り話で、おそらく薄葬令以降のこの地の有力者の墓だと思われます。妻女山や五一山脈の古墳の近くにもいくつも見られます。

(左)毒々しい紅色の傘。チシオタケでしょうか。辛くて不食。(右)傘の裏が網状でイグチ科のキノコ。ニガイグチの仲間でしょうか。苦くてとても食べられません。在京時代に誤って一本入ってしまい、キノコ鍋を全部捨てたことがあります。この時期のアカヤマドリやヤマドリタケモドキ(欧州のポルチーニやセップ)は、ありませんでした。信州新町道の駅では、チチタケなどとともに売っている様です。

(左)伐採木の断面に最初は粘菌かと思いましたが、撮影して拡大するとシロキクラゲの幼菌と分かりました。キノコムシでしょうか、小さな甲虫が食べている様です。(右)長雨で苔は生き生きしています。

(左)ノアザミ(野薊)キク科アザミ属。花弁が5枚の筒状花がたくさん集まって頭状花を形成しています。総苞が粘ることでノハラアザミと区別できます。(中)5,6ミリぐらいの小さな花、よく見ると林道脇にたくさん。未同定。(右)ユリ科ヤブランの蕾。

アオイトトンボ(青糸蜻蛉)トンボ目イトトンボ亜目アオイトトンボ科アオイトトンボ亜科。トンボの翅は4枚が複雑な動きをしてホバリングができます。筋肉が4枚の翅の基部につながっていて、それぞれを別々に動かせるからです。これを直接飛翔筋型昆虫といいます。翅は、細いパイプ状の翅脈(しみゃく)と、透明な薄い膜でできていますが、全体重の2パーセントほどしかありません。

トンボは不退転の勝ち虫と呼ばれ、武士の兜の前立によく使われました。他にも昆虫を使った兜は多く、蝶、百足(ムカデ)、スズメバチなどもあります。戦場では昆虫食も普通だったでしょう。どれが食べられる美味しい虫か知っていたはずです。

(左)茶臼山動物園入り口左の道を抜けて植物園へ。自然植物園中腹にある展望台。(右)その上にある英国風庭園。絵本作家のターシャ・テューダーとかビアトリクス・ポターの児童書「ピーターラビット」を思い出します。もう少し広い面積で作ってもいいと思います。

吸蜜の後、休憩中のベニシジミ。夏型なので翅の表が黒い。数頭見られました。

(左)ヤノトガリハナバチに似ているのですが、脚の色とか胸部の横の黄班とか違うのです。未同定。花はオミナエシ(女郎花)。(右)オオハナアブが吸蜜中。ラウンドアップや草退治などの毒薬除草剤で、ミツバチ、ハナアブが激減し、果樹園も野菜畑も自然のままでは受粉が難しくなっています。中枢神経を冒し癌、脳の発達障害、多動性症候群、奇形などを引き起こします。当ブログでも何度も記事をアップしています。ブログ内検索を。

吸蜜中のツマグロヒョウモンのオス。メスも我が家の庭でもたまに見られます。

(左)コオニユリ。(小鬼百合)ユリ科。(右)ヤナギラン(柳蘭)アカバナ科。山火事の跡に最初に群生するため英名はFireweed(火の草)。種子は白く長い毛があり風で飛んでいきます。

(左)アジサイ(紫陽花、八仙花)。(右)キキョウ(桔梗・Platycodon grandiflorus)キキョウ科。多年性草本植物。万葉集のなかで秋の七草と歌われている「朝貌の花」といわれています。根はサポニンを多く含むことから生薬(桔梗根)として利用されます。

園芸種には疎いので、写真だけを載せます。自然植物園には園芸種の花もたくさん植えられています。下の恐竜公園から登ってアスレチックを過ぎて、藤棚をすぎると茶臼山へ登れます。拙書にも載せているコースで、ファミリー向けです。

善光寺平の眺め。右奥に三角の笠岳がそびえています。緑色の帯は犀川と河川敷。左奥にエムウェーブが見えます。手前に北陸新幹線の高架。雨が降り出したので帰りました。久しぶりに戸倉上山田温泉の万葉超音波温泉に入りました。
◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。郷土史研究家でもあるので、その山の歴史も記しています。地形図掲載は本書だけ。立ち寄り温泉も。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。でも、できれば地元の書店さんを元気にして欲しいです。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。分かりやすいと評判のガイドマップも自作です。『真田丸』関連の山もたくさん収録。

★本の概要は、こちらの記事を御覧ください。
★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせか、メッセージからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。
インタープリターやインストラクターのお申込みもお待ちしています。シニア大学や自治体などで好評だったスライドを使用した自然と歴史を語る里山講座や講演も承ります。大学や市民大学などのフィールドワークを含んだ複数回の講座も可能です。左上のメッセージを送るからお問い合わせください。