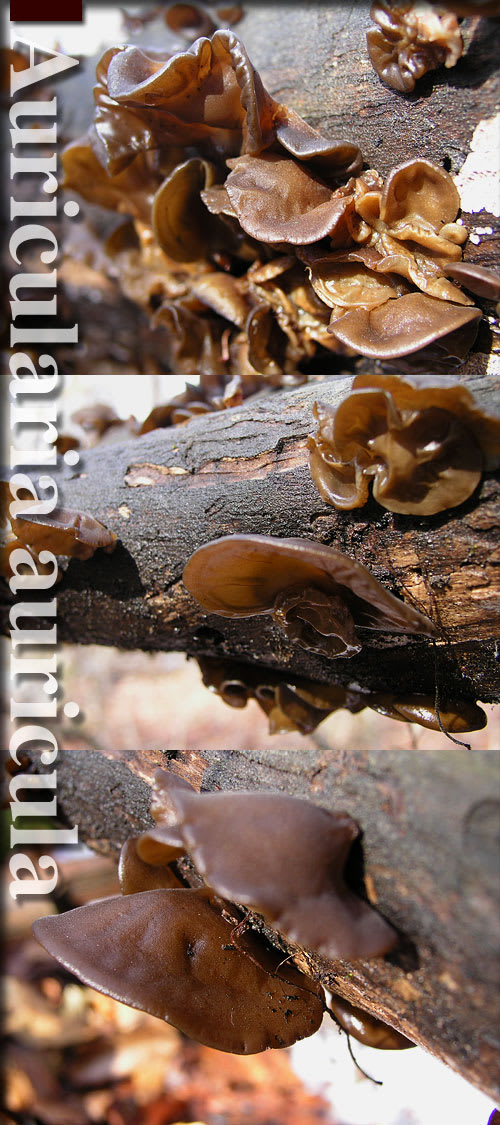日本氈鹿(ニホンカモシカ)も新芽が出てきたので、食糧の乏しい真冬に比べると心なしかゆとりがあるような振る舞いです。その昔、薬草園だった場所の貝母(バイモ)も蕾がずいぶんと膨らんできました。4月の上旬には咲き始めると思います。以前「俯いて 知らぬ間に消ゆ 貝母哉」と詠いましたが、蕾の状態の時は真上を向いています。これが開花すると俯いてしまうのです。そして開花後は、跡形もなく地上から消えてしまうというスプリング・エフェメラル(春の儚い命)なのです。
林道沿いには木五倍子(キブシ)が鈴生りに咲き始めました。江戸時代には、タンニンを含む果実がおはぐろ用の五倍子(フシ)の代用として使われました。接骨木(ニワトコ)の新芽も大きく開いています。まもなくオレンジ色のニワトコフクレアブラムシが大発生するでしょう。新芽は山菜ですが、食べ過ぎると当たります。招魂社裏手の梅林も満開になりました。
先日、陣場平に行った折りに、林道ではなく私が作った東側の道から登ってきたハイカーがいました。昨年は12月末に熊の足跡がありましたし、猪や羚羊も頻繁に現れます。こんな陣場平の奥へ来る人は、私とK氏と蕗を取りに来る東福寺の女性の三人だけのはず。道に迷ったのかしらと話しかけました。するとこの山域をよく歩かれている方と分かりました。しかも、数日前には知人のK氏のログハウスに立ち寄り、ちょうど居合わせた里山に自製の標識を立てておられるM氏とも、この辺りの山の話をされたとか。驚きました。
よくよくお話を伺うと信州山岳会の会長のIさんと分かりました。私もよく拝見して参考にさせていただいているサイトです。すると私のMORI MORI KIDS(低山トレッキング・フォトレポート)をよく見ていただいているとおっしゃるのです。実に光栄なことです。山が取り持つ出合いというのは、実に不思議だなと思うことがあります。前述のM氏との出合いもこの山中でした。こんなヤブ山の外れで偶然に出会うのですから奇跡というしかありません。山の神は洒落たことをしてくださるものだと思わずにはいられません。大切にしたいご縁です。
Iさんには、陣場平の片隅にある、まだ誰にも紹介していない積石塚古墳をお教えしました。ここ陣場平は川中島合戦の折りに上杉謙信が陣小屋を七棟建てたと伝わる高原の平地で、その一角にその古墳がひとつだけあるのです。陣小屋が史実だとすると、他の古墳は全て壊されたのかもしれません。その後は畑地になりましたから、現存するのは本当にこの一基だけ。しかも荒れた林と藪に埋もれたため地元でも知る人はいないと思います。この間も強風で高さ15mほどのカラマツが轟音と共に倒れました。そんな所です。
陣場平は、薬草畑と養蚕の盛んな頃は桑畑でしたが、現在は夏になるとバラが繁茂し酷い藪になるので入れません。それでも見通しの良い冬枯れの季節に来て、ここに兵共(つわものども)が闊歩していたのだと想像すると、毘沙門天の旗のたなびく音が聞こえてくるような気がします。陣場平について、詳しくは、上杉謙信斎場山布陣図をご覧下さい。また七つ前のブログ記事『上杉謙信布陣の斎場山と陣場平「今昔物語」』も合わせてお読み下さい。
里山も春ですねえと思っていたら、突然の雪景色。真冬に戻ってしまいました。エルニーニョのせいでしょうか。昨年の夏から異常な天候が続きます。なにか異変が起きなければいいのですが…。
★ネイチャーフォトは、【MORI MORI KIDS Nature Photograph Gallery】をご覧ください。キノコ、変形菌(粘菌)、コケ、地衣類、花、昆虫などのスーパーマクロ写真。滝、巨樹、森の写真、森の動物、特殊な技法で作るパノラマ写真など。ニホンカモシカの写真も[野生動物]にたくさんあります。
★陣場平は、フォトドキュメントの手法で綴るトレッキング・フォトレポート【MORI MORI KIDS(低山トレッキング・フォトレポート)】にいくつもルポがあります。