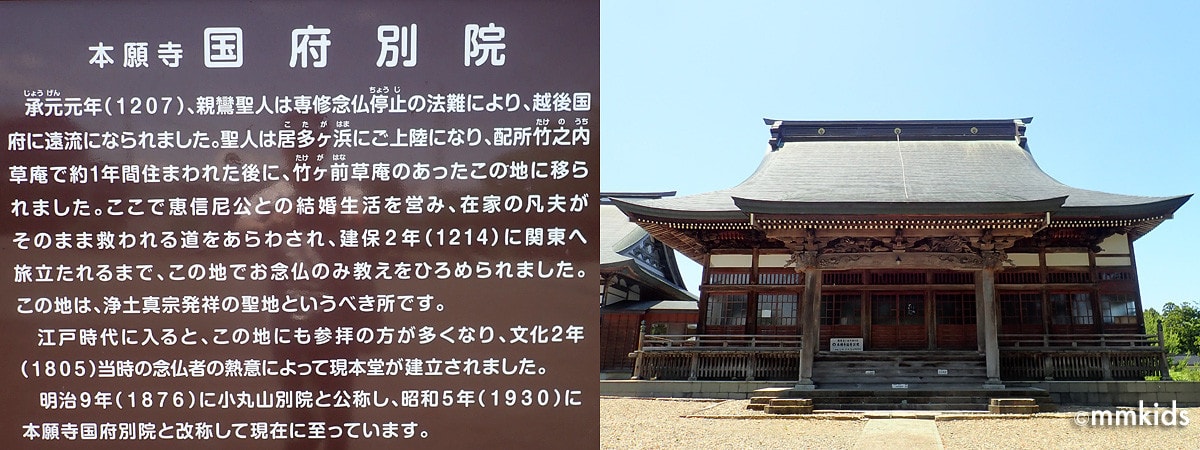翌日は6時頃起床。妙高山が綺麗です。爽やかなんですが、高原だというのに朝から微妙に気温が高いのです。夜になると駐車している地元の農産物直売所「いっさっさ」の下の小さな池でカエルが鳴き出すのですが、昨夜は少なかったのも気温が高かったから? 今日は戸隠方面へ向かいます。

(左)県道36号を西へ。黒姫山の古池登山口。2001年の夏に家族でここから黒姫に登りました。次男はまだ7歳で山頂まで4時間20分かかりました。下界の最高気温が35度の猛暑日で、山頂も暑かったのを覚えています。下から黒雲が湧いてきたので、大急ぎで下山しました。往復8時間の山行でした。息子達はかなり体力があったのだなと思います。まあ歩けるようになってからすぐに高尾山や近隣の里山に登っていましたし、保育園へも毎日1キロ往復していましたから。(右)ここは頑張っても5,6台が限度ですが、すぐ先の大橋は10数台止められます。

道すがら撮影した華奢で美しいアオイトトンボ。後で行った種池にもたくさんいました。

古池から仰ぎ見る黒姫山。北信地方には、数々の黒姫伝説があります。登山道は、池を右回りに半周して写真の正面あたりから上に続きます。
◉黒姫伝説(Wikipedia):岩倉池に住む竜蛇が高梨氏の姫君に思いを寄せるが実らず、仕返しとして水害をもたらしたというのが物語の大筋。黒姫の名の由来は、大国主命の妻であった奴奈川姫の母の黒姫命に由来するという伝説もあります。

(左)遊歩道は、池を周回しています。(右)湿原の重要性は、近年更に評価されています。

ノビネチドリ(延根千鳥)ラン科ノビネチドリ属の多年草。ハクサンチドリ、テガタチドリと並ぶ、赤いラン科の花の代表。

(左)池の北側には湿原があります。咲いていたのはアヤメ(菖蒲)ぐらいですが、初夏にはミツガシワ、夏にはコオニユリ、オオバギボウシなどが咲きます。(右)ヤマキマダラヒカゲらしき蝶が舞っていたのですが、撮影させてくれませんでした。レンゲツツジは残花。

三分の二ほど回ったところにギンリョウソウ(銀竜草)ツツジ科ギンリョウソウ属の多年草の群生地がありました。葉緑体を持たない腐生植物です。ベニタケ類の菌糸から栄養を得るため、光を必要としないので、薄暗い林下で見られます。別名は、ユウレイタケ(幽霊茸)。

帰りに種池に寄りました。この池は、水の流入口と流出口がなく枯れることはないそうです。干魃の年に年に、この水を汲んで戸隠神社に雨乞いを祈願すると、必ず雨が降るといわれています。

(左)モリアオガエルの卵塊がたくさん見られました。(右)初めて見るトンボです。トンボの同定はなかなか厄介です。ヨツボシトンボの様です。池や湿原で見られるトンボ。

(左)ハルジオンで吸蜜するコチャバネセセリ。(右)キマダラヒカゲとは分かったのですが、ヤマキマダラヒカゲかサトキマダラヒカゲか。眼状紋などから、ヤマキマダラヒカゲと同定しました。地面に染み込んだ水を吸っています。

戸隠森林植物園へ。中央広場から見上げる戸隠連峰。蟻の戸渡りが有名です。高所恐怖症の人には向かない山です。

みどりが池の近くにクリンソウ(九輪草)の群生地がありました。サクラソウ科サクラソウ属の多年草です。あまりに鮮やかで園芸種みたいですが、れっきとした野草です。

(左)ヤマオダマキ(山苧環)。キンポウゲ科オダマキ属の多年草です。苧環は、糸を巻いて玉状または環状にしたもので、それに形状が似ている花。(右)幼稚園児が先生の提案で人差し指をかざしてトンボを誘っています。止まったかな。子供達もこんにちわと挨拶してくれて可愛かったけれど、先生も可愛かった(笑)。

途中で知り合った長男と同じ大学卒の男性と色々話しながら「八十二 森のまなびや(戸隠森林館)」へ。なかなか充実した展示です。戸隠の森林を再現したジオラマも楽しい。プラスチックの環境への悪影響がいわれていますが、木材を原料としたセルロースナノファイバーが非常に注目されています。今後、森林の活用は進むでしょう。林業の未来は明るいと思います。

次に鏡池へ。車で行けますが、道幅が狭いのでカーブではクラクションを。曇の日はライトを点灯。鏡池越しに見上げる戸隠連峰西岳。左回りで周回コースを歩きましたが、道がなくなっていました。右回りでは、みどりが池や奥社方面へ行かれます。

山容を見ても分かる様に、高度な技術と体力が必要な山です。

(左)道の駅しなのへ戻る途中で遅いお昼と「そば処 たかさわ」へ。地震橋近くに咲いていたヤマボウシ。(右)今回は十割蕎麦と竹の子汁を。筍はこの時期旬の根曲がり竹。鯖の水煮缶詰とジャガイモ、タマネギが入っていました。満足。

(左)道の駅に戻るには早かったので杉の原へ。いもり池では、地元の人達が睡蓮を除去していました。年に二回ほど行うそうですが、大変そうでした。ブラックバスなどの有害外来魚もいるそうなので、一度池の水を全部抜くのもありかもですね。(右)隣の妙高高原ビジターセンターへ。展示は全く洗練されていませんが、展示内容は生物学、地学、民俗学と豊富で楽しいものです。私が興味を持ったのは、昔の鳥瞰図。鳥瞰図では、吉田初三郎が有名ですが、これらは誰の作でしょうか。素晴らしい。

「道の駅しなの」から見る夕焼け。左に黒姫山、右に妙高山。手前の中央に咲くのはマーガレット。お土産には、先週買って気に入った「信乃大地」という黒姫高原ヨーグルトのお酒と、この辺りの蕎麦屋で必ず出てくる「善光寺延命茶」。またまた、大好きなユキ・ラインハートのA・O・Rを聴きながら、ビールに赤ワインを。
◉A・O・R|ユキ・ラインハート|JFN PARK:長野ではFM長野で聴けます。
◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。郷土史研究家でもあるので、その山の歴史も記しています。地形図掲載は本書だけ。立ち寄り温泉も。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。でも、できれば地元の書店さんを元気にして欲しいです。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。分かりやすいと評判のガイドマップも自作です。『真田丸』関連の山もたくさん収録。

★本の概要は、こちらの記事を御覧ください。
★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。
インタープリターやインストラクターのお申込みもお待ちしています。シニア大学や自治体などで好評だったスライドを使用した自然と歴史を語る里山講座や講演も承ります。大学や市民大学などのフィールドワークを含んだ複数回の講座も可能です。左上のメッセージを送るからお問い合わせください。