10月26日の日曜日、毎年恒例の中尾山--茶臼山ハイキングが行われました。今年も私は、里山インタープリターとして、皆さんと歩きながら樹木や菌類など、茶臼山の生態系の説明をしました。当日参加も含めると100名以上となったため、三班に分かれて出発しましたが、途中で追いついてしまい大渋滞になったり、その後は間を空けすぎて最後が正午にお昼の会場に着けなかったりと、まあ色々大変でしたが、天気もよく楽しいハイキングができたと思います。★茶臼山トレッキングコース地図(今回歩いたコース以外も載っています。)
この時期は、スズメバチが攻撃的になるので、ハチの天敵の熊と同じ黒い色の服は、着てこないでください。香水や化粧品の甘い香り、フルーツのキャンディなどもハチをおびき寄せます。ミント系は大丈夫です。ハチに威嚇されたら悲鳴をあげたり手で払うと刺されます。姿勢を低くして速やかにその場を立ち去ることです。できれば、万が一刺された時のために毒抜き器、ポイズンリムーバーを携帯してください。

8時半から開会式です。インストラクターのSさんが、歩く際の注意事項とストレッチを。私がキノコがあった場合の注意事項などをお話しました。9時に出発。リンゴ畑の道を中尾山温泉に向かって登っていきます。ここ共和のリンゴは美味しいんですよ。ここで、後方からペースが速過ぎるよとクレームが。かなり遅く歩いていたつもりなんですが、それでも初心者には速過ぎた様です。遅く歩くのは、結構難しいものですね。お見合い風呂で全国的に有名になった中尾山温泉の松仙閣を過ぎて、山道に入ります。

9時50分頃、第一班が山の神に到着。すると、第二班、第三班も追いついてしまい、大渋滞になってしまいました。そこで、間を空けて順次出発。ウルシの赤い紅葉が鮮やかです。ここから、私は第二班、第三班を待って、順次山の説明をしました。そして、10時20分頃、一本松に到着。急な登りはここまで。小さな女の子も、途中の休憩でしゃがみ込んでいたので大丈夫かなと思いましたが、しっかり登ってきました。

なだらかな尾根道を歩いて、10時40分頃に新しく作られた東側の善光寺平が見える展望台へ到着。見える角度は広くありませんが、立ち位置を変えると、志賀高原の笠ヶ岳や横手山から四阿山まで見ることができます。眼下には登り始めの松仙閣や、老人ホームの豊寿苑、今井駅、ホワイトリングなどが見えます。真ん中のカットは、根子岳と四阿山。皆さんは、見える大きな建物などを同定していました。

続いて11時10分頃に、西側の北アルプス展望台へ。この日は白馬三山、仁科三山と、北アルプスのスカイラインが綺麗に見えました。雪はまだ少なめですが、大寒波が来ると一晩で真っ白になります。

右から白馬岳、杓子岳、白馬鑓ヶ岳の白馬三山。左へ天狗ノ頭に続いてW字型に切れ込んだ不帰ノ嶮。その手前は、右の虫倉山から続く尾根。点在する集落は、長野市中条(旧中条村)。その手前に犀川の流れる深い谷。一番手前は、山布施の集落。長閑な山村風景が広がっています。

11時25分に茶臼山山頂。展望はありません。ここに高い展望台があれば、もっと訪れる人も増えるのでしょうね。崩れている南面を回って植物園に下ります。

茶臼山自然植物園の上部は、ずいぶんと綺麗に整備されました。藤のトンネル、アスレチックを過ぎて展望台まで下ります。その下には、レッサーパンダで全国的に有名になった茶臼山動物園。そして恐竜公園。

展望台から東の風景。善光寺平(長野盆地)が広がっています。ここの標高が550mと低いので、横手山と根子岳の間にある草津白根山は、手前の山に隠れて見えないようです。あの群馬県との境にある2000m級の山々が、放射性プルームをブロックしてくれたのですが、軽井沢や北信にある1000m級の峠を越えて、一部がこの信州にも流れ込んだのです。

美味しいキノコ汁が振る舞われた昼食後は、まずインストラクターのSさんの講演の後で、次に私。昨年は郷土史研究家として茶臼山の歴史について絵図を使ってお話しましたが、今回はナチュラリストとして茶臼山のキノコについて、私が撮影したキノコの写真をお見せしながら、話をしました。どちらも里山インタープリターの範疇なんです。世界三大猛毒キノコが普通にあることや、皆さんが知らない夏キノコの話などをしました。実際に採ってきた方から、シロノハイイロシメジをお借りして、毒キノコであることを説明しました。キノコの同定というのは、本当に難しいものなのです。と、こんな話をしたわけですが、来年はもっと里山の根源的な話を、私の体験を元にお話したいと思います。毎回、初めての方が半分以上いるので、歴史についても話しましょう。
交流会は1時半頃にお開きになり、共和のリンゴ畑の中を出発地の黒木学園カレッジオブキャリア共和校の校庭へと戻ります。結構日差しが強くて汗ばむほどでした。リンゴ畑の農道から、今日歩いた中尾山から茶臼山の尾根が見えます。その後、参加した友人のSくんと松仙閣の温泉に入り、疲れを癒やしました。夜は、実行委員のNくんも交えて、篠ノ井の村さ来で慰労会をしたのでした。

数日後、用事のついでに中尾山と茶臼山に寄りました。最初のカットは、松仙閣から右の花井神社の方へ登ったリンゴ畑の上から撮影した中尾山です。裾花凝灰岩の白い崖がよく見える場所です。右後方の山頂が、村史にある中尾山の山頂ということになります。ついで下って茶臼山動物園の方へ。信里小の向かいを入った旗塚の駐車場から見た大池とその向こうに冠着山(姨捨山)。左奥へ八頭山、大林山と続きます。どちらも山頂からの見晴らしがよく、登ってとても楽しい山です。旗塚では、ダンコウバイの黄葉が輝いていました。
◉この中尾山や茶臼山も掲載の拙書『信州の里山トレッキング東北信編』川辺書林が発売中。平安堂やAmazonで。カラー668枚の写真と分かりやすいと評判のコース地図とガイド。初心者からベテランまで38山、74コースを収録。信濃毎日新聞の記事と書評に次いで新潮社『SINRA』の本のコーナーでも高い評価を頂きました 。
◉以下は、以前に茶臼山の歴史についてブログに記述したものですが、再び編集してみました。
茶臼山は双耳峰でした。信玄が布陣したと伝わるのは南峰で、地滑りで崩壊してしまった有旅茶臼山(うたびちゃうすやま)なのです。江戸時代後期の『甲越信戦録』を元にしたと思われる『松代町史』には、こう記してあります。
「武田晴信は同月十八日嫡子太郎信義、武田逍遙軒、同左典厩信繁を初めとし家臣長坂、飫富、山縣、山本、両角、馬場、真田、跡部等二万余人を引具して甲州石和城を発して信濃に入り更級郡茶臼山に陣を取り機を見て二十八日広瀬渡を渡りて海津城に入れば総勢実に二万五千に達すという。」ただし、江戸初期の小幡景憲の『甲陽軍鑑』には、信玄の茶臼山布陣の話は全くでてきません。恐らく、武田信玄茶臼山布陣は、後世の作り話でしょう。★上杉謙信斎場山布陣図
その茶臼山という名称ですが、茶臼岳、茶𥓙山、茶磨山などとも書かれ、全国に200以上あるもっとも多い山名です。茶臼(茶𥓙)とは甜茶を抹茶に挽く石臼です。抹茶が日本に入ってきたのは鎌倉時代。茶道が武将の間に広まったのは戦国時代にかけてといいますから、茶臼山という名称も室町時代以降といえるのではないでしょうか。戦国当時、名だたる武将は陣を張るとまず幕内に茶臼をしつらえ、抹茶を立てて一服するのが習わしだったそうです。抹茶を飲む事は、精神を落ち着けるとともに、相手を粉々に粉砕するという意味も含まれていました。
その茶臼を使わない時に布をかぶせると富士山のような形になります。その形に似ている山ということで、全国各地に茶臼山という山があるのですが、大阪の茶臼山(大阪夏の陣で真田幸村が布陣)のように武将が好んで布陣した山でもあります。武将にとって縁起のいい山名だったのでしょう。そのため、茶臼山には山城が築かれたところも多くあります。また、それより遥か昔には古墳だったところもあります。円墳や前方後円墳の後円部は茶臼の形をしています。そう考えると、武田信玄が茶臼山に布陣したというのも、そう荒唐無稽な話ではないかもしれません。
実際に茶臼山の頂上北側には、深くて長い堀切があり、郭(くるわ)のような段も見られます。鎌倉時代の土豪の山城があったのかもしれません。また、茶臼山という名称の語源は、アムール川流域のチャムス(佳木斯)に源を持つという説もあります。
その南峯の有旅茶臼山は善光寺地震で崩壊が始まり、大正時代末期から昭和にかけてに大崩壊して山頂がなくなってしまったのです。ですから現在茶臼山といわれているのは、標高730mの北峯です。ちなみに南峯は720mだったという説と、元々は740mだったという説があります。現在は地滑り防止の工事も終わり、跡地はレッサーパンダで有名な茶臼山動物園や恐竜公園、自然植物園などになって市民に親しまれています。
有旅茶臼山の南の尾根には、九基の塚(古墳)が、信玄茶臼山布陣の石碑の近くにあります。旗塚といって信玄が旗を埋めた塚と俗にいわれていますが、実際は古墳時代末期の墳墓で、群司や県司の墓といわれています。同じようなものが上杉謙信の布陣したと伝わる斎場山の円墳から続く尾根にも七基あります。また、同様な塚が川柳将軍塚古墳にも付随して六基あります。その類似性には興味深いものがあります。そう考えると有旅茶臼山の山頂にも、崩壊する前には、斎場山と同じように円墳があったかもしれないのです。里俗伝では、崩壊する前の山上には山城の跡があり、堀切もあったということです。江戸後期の『甲越信戦録』には、「茶臼ヶ城」と書かれています。
現在の茶臼山(北峯)は、木々に囲まれ眺望は全くありませんが(そのためハイカーにもうひとつ人気がでないのかも。松本の芥子坊主山のように展望台が欲しいところ。)、古い山城と思われる跡が見られます。山頂でには、南北に長く平坦地があり、東西と特に南側は急峻な構えになっています。北側では、大きく二段に分かれており、腰郭の跡かと思われるような広い段差があります。その北側には東西に長く掘切があります。現在の深さは2mぐらいですが、元々はかなりの深さがあったのではと思われます。戦国時代以前に、大塔合戦などもあったので、崩れてしまった南峰と共に、山城があったとしても不思議ではありません。
有旅茶臼山から川中島に下る中腹の柳沢集落に「耕心庵(甲信庵)」という古刹があります。「川中島合戦後に信玄が巡国の時、この地に立ち寄り、川中島合戦場を見下ろして、この處はまさに景勝地であると感嘆し、ここに禅寺を建立し、法性山甲信庵と名づくべしと高坂弾正に命じた。」と看板にあるのですが、有旅茶臼山に布陣したなら、川中島に下る際に、ここは既に通っているはずなんですが…。猿ケ馬場峠(旧北国西街道にある麻績宿と桑原宿の間の峠)から有旅茶臼山へは、またかなり登り返さなければならず、5日ばかりの布陣と考えると、実際は石川茶臼山(川柳将軍塚古墳)に布陣し、その後すぐに謙信のいる斎場山の千曲川対岸の横田城跡に移ったのではという説が現実的かもしれません。
★以下は、茶臼山関連の私のリンク集です。
◉10月26日(日)の中尾山--茶臼山ハイキングの下見に。黄金色の棚田で見つけた信州の秋:ワレモコウ、ノコンギク、アキアカネ
◉2013年の中尾山--茶臼山トレッキング
◉2011年の中尾山--茶臼山トレッキング
◉2010年の中尾山--茶臼山トレッキング
◉4月、満開の桜とショウジョウバカマの咲く中尾山--茶臼山:トレッキング・フォト・レポート
◉5月、リンゴの花とマルバアオダモの花が咲く中尾山--茶臼山:トレッキング・フォト・レポート
◉10月、旗塚から紅葉狩りとキノコ狩りの茶臼山:トレッキング・フォト・レポート
◉34度! 猛暑の茶臼山で真夏のキノコ狩り
◉早春の雪景色の茶臼山で地名考
★茶臼山や妻女山山系の自然については、【MORI MORI KIDS Nature Photograph Gallery】をご覧ください。キノコ、変形菌(粘菌)、コケ、花、昆虫などのスーパーマクロ写真。滝、巨樹、森の写真、森の動物、特殊な技法で作るパノラマ写真など。
【追記】◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。茶臼山への行き方や写真も載せています。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。でも、できれば地元の書店さんを元気にして欲しいです。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。分かりやすいと評判のガイドマップも自作です。その山の名前の由来や歴史をまず書いているので、歴史マニアにもお勧めします。
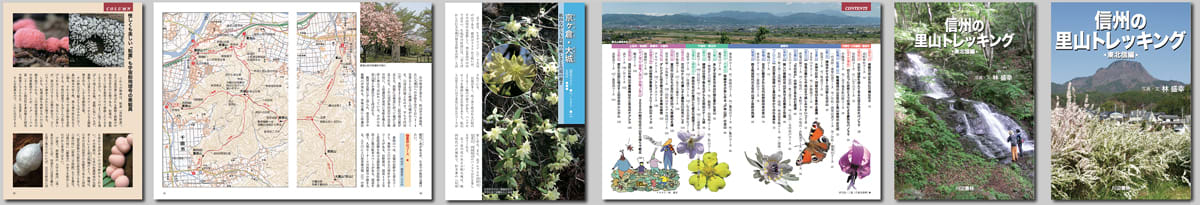
★本の概要は、こちらの記事を御覧ください。






必見!◆新農薬ネオニコチノイドが脅かすミツバチ・生態系・人間:JEPA(pdf)ネオニコチノイド系農薬は、松枯れ病だけでなく、水田の除草剤やカメムシの除虫、空き地の除草剤や家庭用殺虫剤に使われていますが、元はベトナム戦争の化学兵器の枯葉剤と同様で(代表的なのがラウンドアップ:グリホサート剤)、脳の発達障害、多動性障害(ADHD)を引き起こす強力な神経毒の『農薬』ではなく、『農毒』です。
★ネイチャーフォトのスライドショーは、【Youtube-saijouzan】をご覧ください。粘菌やオオムラサキ、ニホンカモシカのスライドショー、トレッキングのスライドショーがご覧頂けます。
この時期は、スズメバチが攻撃的になるので、ハチの天敵の熊と同じ黒い色の服は、着てこないでください。香水や化粧品の甘い香り、フルーツのキャンディなどもハチをおびき寄せます。ミント系は大丈夫です。ハチに威嚇されたら悲鳴をあげたり手で払うと刺されます。姿勢を低くして速やかにその場を立ち去ることです。できれば、万が一刺された時のために毒抜き器、ポイズンリムーバーを携帯してください。

8時半から開会式です。インストラクターのSさんが、歩く際の注意事項とストレッチを。私がキノコがあった場合の注意事項などをお話しました。9時に出発。リンゴ畑の道を中尾山温泉に向かって登っていきます。ここ共和のリンゴは美味しいんですよ。ここで、後方からペースが速過ぎるよとクレームが。かなり遅く歩いていたつもりなんですが、それでも初心者には速過ぎた様です。遅く歩くのは、結構難しいものですね。お見合い風呂で全国的に有名になった中尾山温泉の松仙閣を過ぎて、山道に入ります。

9時50分頃、第一班が山の神に到着。すると、第二班、第三班も追いついてしまい、大渋滞になってしまいました。そこで、間を空けて順次出発。ウルシの赤い紅葉が鮮やかです。ここから、私は第二班、第三班を待って、順次山の説明をしました。そして、10時20分頃、一本松に到着。急な登りはここまで。小さな女の子も、途中の休憩でしゃがみ込んでいたので大丈夫かなと思いましたが、しっかり登ってきました。

なだらかな尾根道を歩いて、10時40分頃に新しく作られた東側の善光寺平が見える展望台へ到着。見える角度は広くありませんが、立ち位置を変えると、志賀高原の笠ヶ岳や横手山から四阿山まで見ることができます。眼下には登り始めの松仙閣や、老人ホームの豊寿苑、今井駅、ホワイトリングなどが見えます。真ん中のカットは、根子岳と四阿山。皆さんは、見える大きな建物などを同定していました。

続いて11時10分頃に、西側の北アルプス展望台へ。この日は白馬三山、仁科三山と、北アルプスのスカイラインが綺麗に見えました。雪はまだ少なめですが、大寒波が来ると一晩で真っ白になります。

右から白馬岳、杓子岳、白馬鑓ヶ岳の白馬三山。左へ天狗ノ頭に続いてW字型に切れ込んだ不帰ノ嶮。その手前は、右の虫倉山から続く尾根。点在する集落は、長野市中条(旧中条村)。その手前に犀川の流れる深い谷。一番手前は、山布施の集落。長閑な山村風景が広がっています。

11時25分に茶臼山山頂。展望はありません。ここに高い展望台があれば、もっと訪れる人も増えるのでしょうね。崩れている南面を回って植物園に下ります。

茶臼山自然植物園の上部は、ずいぶんと綺麗に整備されました。藤のトンネル、アスレチックを過ぎて展望台まで下ります。その下には、レッサーパンダで全国的に有名になった茶臼山動物園。そして恐竜公園。

展望台から東の風景。善光寺平(長野盆地)が広がっています。ここの標高が550mと低いので、横手山と根子岳の間にある草津白根山は、手前の山に隠れて見えないようです。あの群馬県との境にある2000m級の山々が、放射性プルームをブロックしてくれたのですが、軽井沢や北信にある1000m級の峠を越えて、一部がこの信州にも流れ込んだのです。

美味しいキノコ汁が振る舞われた昼食後は、まずインストラクターのSさんの講演の後で、次に私。昨年は郷土史研究家として茶臼山の歴史について絵図を使ってお話しましたが、今回はナチュラリストとして茶臼山のキノコについて、私が撮影したキノコの写真をお見せしながら、話をしました。どちらも里山インタープリターの範疇なんです。世界三大猛毒キノコが普通にあることや、皆さんが知らない夏キノコの話などをしました。実際に採ってきた方から、シロノハイイロシメジをお借りして、毒キノコであることを説明しました。キノコの同定というのは、本当に難しいものなのです。と、こんな話をしたわけですが、来年はもっと里山の根源的な話を、私の体験を元にお話したいと思います。毎回、初めての方が半分以上いるので、歴史についても話しましょう。
交流会は1時半頃にお開きになり、共和のリンゴ畑の中を出発地の黒木学園カレッジオブキャリア共和校の校庭へと戻ります。結構日差しが強くて汗ばむほどでした。リンゴ畑の農道から、今日歩いた中尾山から茶臼山の尾根が見えます。その後、参加した友人のSくんと松仙閣の温泉に入り、疲れを癒やしました。夜は、実行委員のNくんも交えて、篠ノ井の村さ来で慰労会をしたのでした。

数日後、用事のついでに中尾山と茶臼山に寄りました。最初のカットは、松仙閣から右の花井神社の方へ登ったリンゴ畑の上から撮影した中尾山です。裾花凝灰岩の白い崖がよく見える場所です。右後方の山頂が、村史にある中尾山の山頂ということになります。ついで下って茶臼山動物園の方へ。信里小の向かいを入った旗塚の駐車場から見た大池とその向こうに冠着山(姨捨山)。左奥へ八頭山、大林山と続きます。どちらも山頂からの見晴らしがよく、登ってとても楽しい山です。旗塚では、ダンコウバイの黄葉が輝いていました。
◉この中尾山や茶臼山も掲載の拙書『信州の里山トレッキング東北信編』川辺書林が発売中。平安堂やAmazonで。カラー668枚の写真と分かりやすいと評判のコース地図とガイド。初心者からベテランまで38山、74コースを収録。信濃毎日新聞の記事と書評に次いで新潮社『SINRA』の本のコーナーでも高い評価を頂きました 。
◉以下は、以前に茶臼山の歴史についてブログに記述したものですが、再び編集してみました。
茶臼山は双耳峰でした。信玄が布陣したと伝わるのは南峰で、地滑りで崩壊してしまった有旅茶臼山(うたびちゃうすやま)なのです。江戸時代後期の『甲越信戦録』を元にしたと思われる『松代町史』には、こう記してあります。
「武田晴信は同月十八日嫡子太郎信義、武田逍遙軒、同左典厩信繁を初めとし家臣長坂、飫富、山縣、山本、両角、馬場、真田、跡部等二万余人を引具して甲州石和城を発して信濃に入り更級郡茶臼山に陣を取り機を見て二十八日広瀬渡を渡りて海津城に入れば総勢実に二万五千に達すという。」ただし、江戸初期の小幡景憲の『甲陽軍鑑』には、信玄の茶臼山布陣の話は全くでてきません。恐らく、武田信玄茶臼山布陣は、後世の作り話でしょう。★上杉謙信斎場山布陣図
その茶臼山という名称ですが、茶臼岳、茶𥓙山、茶磨山などとも書かれ、全国に200以上あるもっとも多い山名です。茶臼(茶𥓙)とは甜茶を抹茶に挽く石臼です。抹茶が日本に入ってきたのは鎌倉時代。茶道が武将の間に広まったのは戦国時代にかけてといいますから、茶臼山という名称も室町時代以降といえるのではないでしょうか。戦国当時、名だたる武将は陣を張るとまず幕内に茶臼をしつらえ、抹茶を立てて一服するのが習わしだったそうです。抹茶を飲む事は、精神を落ち着けるとともに、相手を粉々に粉砕するという意味も含まれていました。
その茶臼を使わない時に布をかぶせると富士山のような形になります。その形に似ている山ということで、全国各地に茶臼山という山があるのですが、大阪の茶臼山(大阪夏の陣で真田幸村が布陣)のように武将が好んで布陣した山でもあります。武将にとって縁起のいい山名だったのでしょう。そのため、茶臼山には山城が築かれたところも多くあります。また、それより遥か昔には古墳だったところもあります。円墳や前方後円墳の後円部は茶臼の形をしています。そう考えると、武田信玄が茶臼山に布陣したというのも、そう荒唐無稽な話ではないかもしれません。
実際に茶臼山の頂上北側には、深くて長い堀切があり、郭(くるわ)のような段も見られます。鎌倉時代の土豪の山城があったのかもしれません。また、茶臼山という名称の語源は、アムール川流域のチャムス(佳木斯)に源を持つという説もあります。
その南峯の有旅茶臼山は善光寺地震で崩壊が始まり、大正時代末期から昭和にかけてに大崩壊して山頂がなくなってしまったのです。ですから現在茶臼山といわれているのは、標高730mの北峯です。ちなみに南峯は720mだったという説と、元々は740mだったという説があります。現在は地滑り防止の工事も終わり、跡地はレッサーパンダで有名な茶臼山動物園や恐竜公園、自然植物園などになって市民に親しまれています。
有旅茶臼山の南の尾根には、九基の塚(古墳)が、信玄茶臼山布陣の石碑の近くにあります。旗塚といって信玄が旗を埋めた塚と俗にいわれていますが、実際は古墳時代末期の墳墓で、群司や県司の墓といわれています。同じようなものが上杉謙信の布陣したと伝わる斎場山の円墳から続く尾根にも七基あります。また、同様な塚が川柳将軍塚古墳にも付随して六基あります。その類似性には興味深いものがあります。そう考えると有旅茶臼山の山頂にも、崩壊する前には、斎場山と同じように円墳があったかもしれないのです。里俗伝では、崩壊する前の山上には山城の跡があり、堀切もあったということです。江戸後期の『甲越信戦録』には、「茶臼ヶ城」と書かれています。
現在の茶臼山(北峯)は、木々に囲まれ眺望は全くありませんが(そのためハイカーにもうひとつ人気がでないのかも。松本の芥子坊主山のように展望台が欲しいところ。)、古い山城と思われる跡が見られます。山頂でには、南北に長く平坦地があり、東西と特に南側は急峻な構えになっています。北側では、大きく二段に分かれており、腰郭の跡かと思われるような広い段差があります。その北側には東西に長く掘切があります。現在の深さは2mぐらいですが、元々はかなりの深さがあったのではと思われます。戦国時代以前に、大塔合戦などもあったので、崩れてしまった南峰と共に、山城があったとしても不思議ではありません。
有旅茶臼山から川中島に下る中腹の柳沢集落に「耕心庵(甲信庵)」という古刹があります。「川中島合戦後に信玄が巡国の時、この地に立ち寄り、川中島合戦場を見下ろして、この處はまさに景勝地であると感嘆し、ここに禅寺を建立し、法性山甲信庵と名づくべしと高坂弾正に命じた。」と看板にあるのですが、有旅茶臼山に布陣したなら、川中島に下る際に、ここは既に通っているはずなんですが…。猿ケ馬場峠(旧北国西街道にある麻績宿と桑原宿の間の峠)から有旅茶臼山へは、またかなり登り返さなければならず、5日ばかりの布陣と考えると、実際は石川茶臼山(川柳将軍塚古墳)に布陣し、その後すぐに謙信のいる斎場山の千曲川対岸の横田城跡に移ったのではという説が現実的かもしれません。
★以下は、茶臼山関連の私のリンク集です。
◉10月26日(日)の中尾山--茶臼山ハイキングの下見に。黄金色の棚田で見つけた信州の秋:ワレモコウ、ノコンギク、アキアカネ
◉2013年の中尾山--茶臼山トレッキング
◉2011年の中尾山--茶臼山トレッキング
◉2010年の中尾山--茶臼山トレッキング
◉4月、満開の桜とショウジョウバカマの咲く中尾山--茶臼山:トレッキング・フォト・レポート
◉5月、リンゴの花とマルバアオダモの花が咲く中尾山--茶臼山:トレッキング・フォト・レポート
◉10月、旗塚から紅葉狩りとキノコ狩りの茶臼山:トレッキング・フォト・レポート
◉34度! 猛暑の茶臼山で真夏のキノコ狩り
◉早春の雪景色の茶臼山で地名考
★茶臼山や妻女山山系の自然については、【MORI MORI KIDS Nature Photograph Gallery】をご覧ください。キノコ、変形菌(粘菌)、コケ、花、昆虫などのスーパーマクロ写真。滝、巨樹、森の写真、森の動物、特殊な技法で作るパノラマ写真など。
【追記】◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。茶臼山への行き方や写真も載せています。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。でも、できれば地元の書店さんを元気にして欲しいです。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。分かりやすいと評判のガイドマップも自作です。その山の名前の由来や歴史をまず書いているので、歴史マニアにもお勧めします。
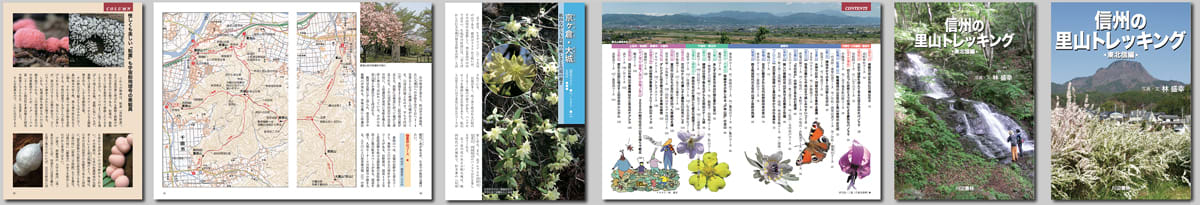
★本の概要は、こちらの記事を御覧ください。
必見!◆新農薬ネオニコチノイドが脅かすミツバチ・生態系・人間:JEPA(pdf)ネオニコチノイド系農薬は、松枯れ病だけでなく、水田の除草剤やカメムシの除虫、空き地の除草剤や家庭用殺虫剤に使われていますが、元はベトナム戦争の化学兵器の枯葉剤と同様で(代表的なのがラウンドアップ:グリホサート剤)、脳の発達障害、多動性障害(ADHD)を引き起こす強力な神経毒の『農薬』ではなく、『農毒』です。
★ネイチャーフォトのスライドショーは、【Youtube-saijouzan】をご覧ください。粘菌やオオムラサキ、ニホンカモシカのスライドショー、トレッキングのスライドショーがご覧頂けます。

































































