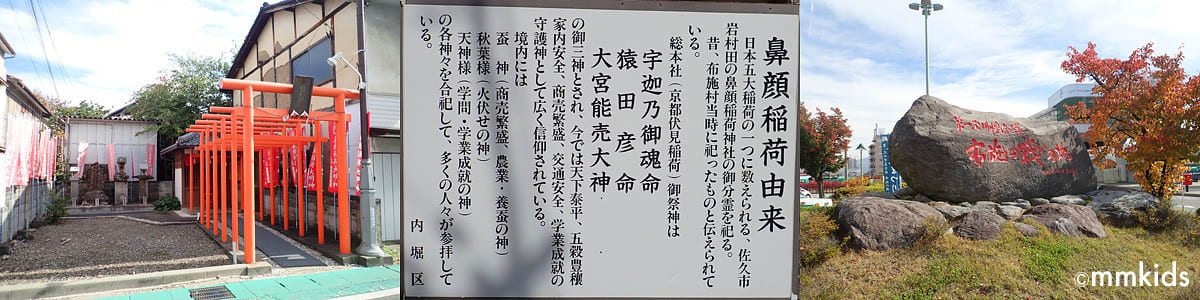11月20日の夜から21日朝にかけて善光寺平(長野盆地)周辺の里山にも雪が積もりました。初冬のこの時期が長野盆地の東西南北で最もその違いが分かるのです。やはり北部の山は積雪が多い。東山より西山の方が雪が多いのです。長い冬の訪れです。

妻女山展望台から松代方面の眺め。中央奥に見えるはずの根子岳と四阿山は雪雲の中。仲間が菅平のスキー場へスキーのインストラクターをしに行っているかもしれません。日差しも出てきて、翌日は10度以上になったので消えました。尼厳山は、土豪東条氏の山城。真田幸隆に攻略されました。奇妙山は、拙書で名前の由来や歴史を詳しく書いていますが、これも山頂は古い山城です。

千曲川の赤坂橋左岸からの鞍骨山(鞍骨城跡)。手前は上信越自動車道で、すぐ左に松代パーキングエリアがあります。中央の深いコルは、鞍骨城の防御のために窪んでいた尾根をさらに深く掘り下げたものの様で。昔は石段があったという話を聞いたことがあります。
先日、BS-TBSで放送された「諸説あり#24 川中島の戦い』の撮影で、スタッフと歴史作家の三池先生をガイドしたのは、この山脈です。象山から登り、深山、鞍骨城跡、天城山、陣馬平、斎場山、妻女山と案内しました。放送日は急用ができて見られませんでしたが、後日DVDが送られてきました。非常に面白い番組でした。

上のカットの鞍骨城跡から右(西)へ1キロちょっと行くと天城山(てしろやま)。山頂は円墳で、鞍骨城の支城の天城城跡です。右手前の山頂は天城山から妻女山へ伸びる尾根で、清野古墳があります。一番右の陣馬平は、第四次川中島合戦の際に、上杉謙信が七棟の陣城を建てたという広い台地です。妻女山里山デザイン・プロジェクトは、ここの貝母(ばいも・編笠百合)の保護活動をしています。4月の茶花で薬草ですが、かなり強い毒草です。百合根に似た球根を誤って食べると、死亡する場合もあります。美しいから家に植えたいと思って持ち帰るのは厳禁です。

引きのカットです。上杉軍は、左の月夜柵から陣馬平、斎場山、妻女山(当時は赤坂山)、御陵願平から右の薬師山と手前の平地の斎場原にかけて広域に布陣したと伝わっています。千曲川の流れは、江戸時代の大洪水『戌の満水』の後で松代藩が大規模な瀬直しをして変えました。昔は堤防も無く好き勝手に流れ、千曲川の名前の通りグニャグニャに蛇行していました。赤坂橋のすぐ上流に、十二ケ瀬(十二河原)という地名がありますが、それだけ分流していたということです。猫ケ瀬、戌ケ瀬という地名もある様に渇水期には、猫や犬でも渡れるほどの浅い瀬もあったということです。

妻女山展望台からの茶臼山。滋野御三家の望月氏の後裔の布施氏の山城です。信玄の茶臼山布陣は、江戸時代後期の創作だろうというのが定説です。左の有旅茶臼山は、右と同じくらいの高さがあり双耳峰でしたが、度々の地滑りで崩壊し山頂がなくなってしまいました。地滑り地域は、動物園や自然植物園、恐竜公園として市民に親しまれています。手前の街は篠ノ井。名前は、高句麗から来た豪族に篠井という性を下賜したことに由来します。手前の長芋畑もほぼ収穫が終わっています。
妻女山展望台へは積雪が10センチぐらいならスタッドレスで登れますが、それ以上になるとスタックします。また、一度溶けて凍った場合はスタッドレスでも登れません。毎年JAFの世話になる車がいます。高速のトンネル前に止めて徒歩で登ってください。

(左)勤労感謝の日に用事で松代に行ったついでに松代城址に立ち寄りました。櫓台です。(中)櫓台から妻女山や鞍骨城を見たところ。霧に覆われています。(右)櫓台から妻女山。右の低いところです。晴れていれば電柱の向こうに謙信が本陣としたと伝わる斎場山(旧妻女山・斎場山古墳)が見えます。

(左)城内にある海津城址の石碑。大正10年といえば、まだ幕末や明治初期生まれの人がいた時代。松代藩の財政を破綻させた真田氏への反感も大きかったのでしょう。詳しくは、下の松代城の歴史その1その2をお読みください。(中)太鼓門から象山。奥の鞍骨山は霧の中。(右)お堀の水では鴨が泳いでいました。
◉真田十万国「松代城(海津城)」の歴史 その1(妻女山里山通信) その2

江戸時代末期の松代城のイメージ図。外堀や三ヶ月堀などが残っていたら、いい観光名所になったでしょうね。花の丸御殿は放火で焼失しました。

妻女山展望台から松代城方面の眺め。霧に巻かれていますが、実はこれは雨上がりの霧で、前夜の放射冷却で発生した川霧と山霧ではありません。川中島の戦いで発生した霧とはでき方が違います。川霧と山霧が合わさると10m先も見えなくなります。ホワイトアウトしてフォグランプも効きません。

23日の夜は、長野のえびす講の煙火大会でした。厚着をして妻女山展望台へ撮影に行きました。先客が二人、あとから若者が二人、拙書のパンフを渡しました。音が遅れてくる遠花火は趣がありますが、寒い。1時間が限度でした。昨年同様に地味でした。アベノ糞ミクスのせいで不景気なんですね。この花火大会が終わると、善光寺平は長い本格的な冬に入ります。21日の早朝には赤坂橋の上で自損事故。積雪がなくても橋の上などは凍結しています。スタッドレスに履き替えていない人は早く!
「しずかさや 外山の花火 水をとぶ」小林一茶
「大名の 花火そしるや 江戸の口」小林一茶
「音もなし 松の梢の 遠花火」正岡子規
「死にし人 別れし人や 遠花火」鈴木真砂女
「遠花火 人妻の手が わが肩に」寺山修司
「遠花火 歓声もなく 温(ぬく)もなく」
「遠花火 記憶の底に 散る夜かな」
「君の名を 呟いてみる 遠花火」 林風
色々な想いが交錯する遠花火です。
信州では、祭りやイベントや運動会の合図に盛んに花火が打ち上げられます。これは東京から来た人には信じられないことなのですが、当の信州人は子供のころからそれが当たり前に思っているので、不思議には思いません。春秋にはあちこちで花火が打ち上がるのですが、地元の人はなんの合図か分かるのです。妻女山にも麓の小学校の校庭で打ち上げた花火の丸い殻がよく落ちているのですが、この「音花火」は非常に危険なんだそうです。
「花火情報館」の「花火の威力と危険度」に詳しく書かれています。火薬がたくさん詰まった花火が、こんなにたくさん一般商店で売られているのは、中国と日本ぐらいじゃないでしょうか。欧米ではあり得ないことです。武器が作れますからね。昔ノルウェーの友人を夏に訪れた時に花火を持っていったのですが、新年になる時でないとできないのよと言われた想い出。子供の花火だって実は危険なんです。手持ち花火の温度は1200~1500度だそうです。昔、よく花火を分解しましたが、絶対やってはいけないと言われていた意味が、これを読むとよく分かります。

用事ついでに寄った東福寺の385号沿いの「安心 そば処」でBランチを。二八の新蕎麦に蒸鶏飯、煮物に天ぷら。蒸鶏飯は山葵醤油をかけて、天ぷらは抹茶塩でいただきます。念願の新蕎麦を食べることができました。最後に濃厚な蕎麦湯を飲んで満足でした。十割蕎麦や胡桃蕎麦もお勧めです。これからは辛味大根の絞り汁に信州味噌を溶いていただく「おしぼりうどん」の季節です。信州でも旧埴科と更科にしかない古い郷土料理です。あまもっくらといわれるその甘さと辛さは、一度食べたら病みつきになります。うどんや蕎麦を食べる原点ともいわれています。これを食べずしてうどん通を名乗るなかれ。冬の、村上義清の坂城町、千曲市の戸倉上山田温泉や、茶臼山動物園のある篠ノ井に来られたらぜひ召し上がってみてください。
◉おしぼりうどんのレシピ:オリジナルレシピ
◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。郷土史研究家でもあるので、その山の歴史も記しています。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。でも、できれば地元の書店さんを元気にして欲しいです。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。分かりやすいと評判のガイドマップも自作です。『真田丸』関連の山もたくさん収録。

★本の概要は、こちらの記事を御覧ください。
★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。
インタープリターやインストラクターのお申込みもお待ちしています。長野県シニア大学や自治体などで好評だったスライドを使用した自然と歴史を語る里山講座や講演も承ります。大学や市民大学などのフィールドワークを含んだ複数回の講座も可能です。左上のメッセージを送るからお問い合わせください。







妻女山展望台から松代方面の眺め。中央奥に見えるはずの根子岳と四阿山は雪雲の中。仲間が菅平のスキー場へスキーのインストラクターをしに行っているかもしれません。日差しも出てきて、翌日は10度以上になったので消えました。尼厳山は、土豪東条氏の山城。真田幸隆に攻略されました。奇妙山は、拙書で名前の由来や歴史を詳しく書いていますが、これも山頂は古い山城です。

千曲川の赤坂橋左岸からの鞍骨山(鞍骨城跡)。手前は上信越自動車道で、すぐ左に松代パーキングエリアがあります。中央の深いコルは、鞍骨城の防御のために窪んでいた尾根をさらに深く掘り下げたものの様で。昔は石段があったという話を聞いたことがあります。
先日、BS-TBSで放送された「諸説あり#24 川中島の戦い』の撮影で、スタッフと歴史作家の三池先生をガイドしたのは、この山脈です。象山から登り、深山、鞍骨城跡、天城山、陣馬平、斎場山、妻女山と案内しました。放送日は急用ができて見られませんでしたが、後日DVDが送られてきました。非常に面白い番組でした。

上のカットの鞍骨城跡から右(西)へ1キロちょっと行くと天城山(てしろやま)。山頂は円墳で、鞍骨城の支城の天城城跡です。右手前の山頂は天城山から妻女山へ伸びる尾根で、清野古墳があります。一番右の陣馬平は、第四次川中島合戦の際に、上杉謙信が七棟の陣城を建てたという広い台地です。妻女山里山デザイン・プロジェクトは、ここの貝母(ばいも・編笠百合)の保護活動をしています。4月の茶花で薬草ですが、かなり強い毒草です。百合根に似た球根を誤って食べると、死亡する場合もあります。美しいから家に植えたいと思って持ち帰るのは厳禁です。

引きのカットです。上杉軍は、左の月夜柵から陣馬平、斎場山、妻女山(当時は赤坂山)、御陵願平から右の薬師山と手前の平地の斎場原にかけて広域に布陣したと伝わっています。千曲川の流れは、江戸時代の大洪水『戌の満水』の後で松代藩が大規模な瀬直しをして変えました。昔は堤防も無く好き勝手に流れ、千曲川の名前の通りグニャグニャに蛇行していました。赤坂橋のすぐ上流に、十二ケ瀬(十二河原)という地名がありますが、それだけ分流していたということです。猫ケ瀬、戌ケ瀬という地名もある様に渇水期には、猫や犬でも渡れるほどの浅い瀬もあったということです。

妻女山展望台からの茶臼山。滋野御三家の望月氏の後裔の布施氏の山城です。信玄の茶臼山布陣は、江戸時代後期の創作だろうというのが定説です。左の有旅茶臼山は、右と同じくらいの高さがあり双耳峰でしたが、度々の地滑りで崩壊し山頂がなくなってしまいました。地滑り地域は、動物園や自然植物園、恐竜公園として市民に親しまれています。手前の街は篠ノ井。名前は、高句麗から来た豪族に篠井という性を下賜したことに由来します。手前の長芋畑もほぼ収穫が終わっています。
妻女山展望台へは積雪が10センチぐらいならスタッドレスで登れますが、それ以上になるとスタックします。また、一度溶けて凍った場合はスタッドレスでも登れません。毎年JAFの世話になる車がいます。高速のトンネル前に止めて徒歩で登ってください。

(左)勤労感謝の日に用事で松代に行ったついでに松代城址に立ち寄りました。櫓台です。(中)櫓台から妻女山や鞍骨城を見たところ。霧に覆われています。(右)櫓台から妻女山。右の低いところです。晴れていれば電柱の向こうに謙信が本陣としたと伝わる斎場山(旧妻女山・斎場山古墳)が見えます。

(左)城内にある海津城址の石碑。大正10年といえば、まだ幕末や明治初期生まれの人がいた時代。松代藩の財政を破綻させた真田氏への反感も大きかったのでしょう。詳しくは、下の松代城の歴史その1その2をお読みください。(中)太鼓門から象山。奥の鞍骨山は霧の中。(右)お堀の水では鴨が泳いでいました。
◉真田十万国「松代城(海津城)」の歴史 その1(妻女山里山通信) その2

江戸時代末期の松代城のイメージ図。外堀や三ヶ月堀などが残っていたら、いい観光名所になったでしょうね。花の丸御殿は放火で焼失しました。

妻女山展望台から松代城方面の眺め。霧に巻かれていますが、実はこれは雨上がりの霧で、前夜の放射冷却で発生した川霧と山霧ではありません。川中島の戦いで発生した霧とはでき方が違います。川霧と山霧が合わさると10m先も見えなくなります。ホワイトアウトしてフォグランプも効きません。

23日の夜は、長野のえびす講の煙火大会でした。厚着をして妻女山展望台へ撮影に行きました。先客が二人、あとから若者が二人、拙書のパンフを渡しました。音が遅れてくる遠花火は趣がありますが、寒い。1時間が限度でした。昨年同様に地味でした。アベノ糞ミクスのせいで不景気なんですね。この花火大会が終わると、善光寺平は長い本格的な冬に入ります。21日の早朝には赤坂橋の上で自損事故。積雪がなくても橋の上などは凍結しています。スタッドレスに履き替えていない人は早く!
「しずかさや 外山の花火 水をとぶ」小林一茶
「大名の 花火そしるや 江戸の口」小林一茶
「音もなし 松の梢の 遠花火」正岡子規
「死にし人 別れし人や 遠花火」鈴木真砂女
「遠花火 人妻の手が わが肩に」寺山修司
「遠花火 歓声もなく 温(ぬく)もなく」
「遠花火 記憶の底に 散る夜かな」
「君の名を 呟いてみる 遠花火」 林風
色々な想いが交錯する遠花火です。
信州では、祭りやイベントや運動会の合図に盛んに花火が打ち上げられます。これは東京から来た人には信じられないことなのですが、当の信州人は子供のころからそれが当たり前に思っているので、不思議には思いません。春秋にはあちこちで花火が打ち上がるのですが、地元の人はなんの合図か分かるのです。妻女山にも麓の小学校の校庭で打ち上げた花火の丸い殻がよく落ちているのですが、この「音花火」は非常に危険なんだそうです。
「花火情報館」の「花火の威力と危険度」に詳しく書かれています。火薬がたくさん詰まった花火が、こんなにたくさん一般商店で売られているのは、中国と日本ぐらいじゃないでしょうか。欧米ではあり得ないことです。武器が作れますからね。昔ノルウェーの友人を夏に訪れた時に花火を持っていったのですが、新年になる時でないとできないのよと言われた想い出。子供の花火だって実は危険なんです。手持ち花火の温度は1200~1500度だそうです。昔、よく花火を分解しましたが、絶対やってはいけないと言われていた意味が、これを読むとよく分かります。

用事ついでに寄った東福寺の385号沿いの「安心 そば処」でBランチを。二八の新蕎麦に蒸鶏飯、煮物に天ぷら。蒸鶏飯は山葵醤油をかけて、天ぷらは抹茶塩でいただきます。念願の新蕎麦を食べることができました。最後に濃厚な蕎麦湯を飲んで満足でした。十割蕎麦や胡桃蕎麦もお勧めです。これからは辛味大根の絞り汁に信州味噌を溶いていただく「おしぼりうどん」の季節です。信州でも旧埴科と更科にしかない古い郷土料理です。あまもっくらといわれるその甘さと辛さは、一度食べたら病みつきになります。うどんや蕎麦を食べる原点ともいわれています。これを食べずしてうどん通を名乗るなかれ。冬の、村上義清の坂城町、千曲市の戸倉上山田温泉や、茶臼山動物園のある篠ノ井に来られたらぜひ召し上がってみてください。
◉おしぼりうどんのレシピ:オリジナルレシピ
◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。郷土史研究家でもあるので、その山の歴史も記しています。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。でも、できれば地元の書店さんを元気にして欲しいです。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。分かりやすいと評判のガイドマップも自作です。『真田丸』関連の山もたくさん収録。

★本の概要は、こちらの記事を御覧ください。
★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。
インタープリターやインストラクターのお申込みもお待ちしています。長野県シニア大学や自治体などで好評だったスライドを使用した自然と歴史を語る里山講座や講演も承ります。大学や市民大学などのフィールドワークを含んだ複数回の講座も可能です。左上のメッセージを送るからお問い合わせください。