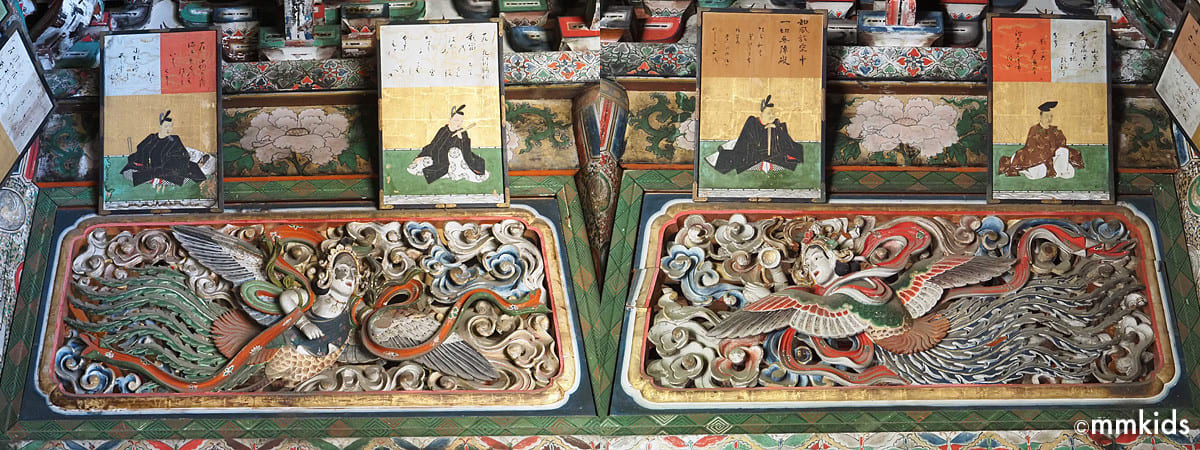長野市の最高気温は、最高気温32.7度だったそうです。ということで、妻女山の陣場平へ撮影に行きました。麓は既に28度でしたが、陣場平の木陰は21度でした。湿度も低くて快適です。ただ日差しは強く、日向に出るとジリジリと肌が焼ける感じがしました。撮影の前に、縮緬山椒を作るために山椒の実を1時間半ほど摘みました。

森の中から見る陣場平の貝母群生地。先日の強い雨で倒れたものもかなりあります。ハルゼミとエゾハルゼミの合唱がもの凄い。先日の作業の日と違ってクロメマトイが五月蝿い。まだヤブ蚊がいないのが救い。淡竹の筍を食べに熊が来るので、熊鈴やホイッスル、大きな音をたてるは必須です。先日はそれで聖山の熊を追い払いました。

枯れた貝母の間に繁茂してきたのは、ヒカゲイノコヅチ(日陰猪小槌)ヒユ科イノコズチ属の多年草。秋に花穂がひっつき虫(バカ)になり、茎に丸い赤紫の虫こぶ(虫えい・ゴール)ができる植物です。若葉は天ぷらやおひたし、胡麻和えなどで食べられるそうです。でも美味しかったら皆採って食べますよね。まあ、そういうことでしょう。多年草で根を張り巡らすので、貝母の繁殖を阻害しますが、どうも見ていると貝母の方が強いので、放置しています。
虫こぶは、イノコヅチクキマルズイフシといい、イノコヅチウロコタマバエによって作られます。虫こぶを切ってみると、小さなタマバエの黄色い幼虫がたくさん入っています。

陣場平の下の入口からの小道。オオブタクサがたくさん出る場所なので要注意なのです。里山保全は賽の河原に石を積む様な作業の繰り返しです。諦めたら終わり。人生は有限なのになぜそんなことをするのと思われるかもしれません。宇宙はなるようにしかならない。その通りです。それがレーゾン・デートル(存在理由)の証と思っているからでしょうからですかね。意識も物質の電気信号のひとつでしかない。存在を考えると宇宙とか、マクロの原子とか。その存在理由は何かと考えますね。たぶん大本の宇宙がその存在理由さえないのかも知れませんが。星が綺麗な信州の夜空を見ると、そんなことも思うのです。

陣場平ではハルジオンはすべて抜きますが、周囲ではウスバシロチョウが吸蜜するのである程度残しておきます。交尾をした印のスフラギスを付けたメスが吸蜜していました。元気な子孫を残すためにせっせと吸蜜して栄養を蓄えます。

この時期のメスは、吸蜜に夢中で近づいても逃げません。有害帰化植物のハルジオンを残すのは痛し痒しなのですが、この時期ほかに吸蜜できる花がないので仕方ありません。ウスバシロチョウが消えたら除草します。

蜘蛛の巣に引っかかったウスバシロチョウ。自然の営みには関与しないのが基本ですが、この巣は主が不在。放棄したものらしいので逃してあげました。自然にどこまで人間が関与していいのか、非常に難しい問題です。欧米ではこれを人間対自然の世界観で。日本、東洋は人間も自然の一部と。近年は後者がポピュラーですが、ではそのコンセプトは確立し普及していますか。意識の改革はそう簡単ではありません。

翅を広げても10ミリぐらいのマドガ(窓蛾)。この面白い名前は、ギリシア語の窓や入り口からで、翅の中室にある半透明の白色斑を窓に見立てたものだそうです。

山蕗の葉にヤマザクラかカスミザクラのサクランボ。渋くて食用にはなりません。ケバエの一種でしょうか。来ています。

ミヤマウグイスカグラ(深山鶯神楽)スイカズラ科スイカズラ属。赤い実は甘く食べられます。子供の頃の山のおやつでした。田舎なので1円キャラメルぐらいしかなかったですから。後はハイカラな明治生まれの「おはなはん」が大好きだった祖母の作るどこで覚えたのか中華菓子の麻花兒(まーふぁーる)とか、じゃがいも餡の饅頭とか。おはぎやこねつけ、よもぎ餅。甘い葛湯もよく作ってくれました。

湧き水の出る沢に下ってみました。ユキノシタ(雪の下)ユキノシタ科ユキノシタ属。虎耳草、鴨脚草、鴨足草、金糸荷などの別名があり、利尿作用のある硝酸カリウムや塩化カリウムを含み、むくみ解消に効果が。その他にきょ風、清熱、解毒などの効能がある民間の薬草です。葉は天ぷらで。

ワサビ(山葵)の葉。花が咲くのはこれからです。在京時代は山梨の秘密の谷へ自生の山葵を採りに行って妻にワサビ漬けを作ってもらいました。

フタリシズカ (二人静)センリョウ科チャラン属の多年草。静かは煩いの反対語ではなく、源義経の愛した静御前のことです。フタリシズカは、静御前の霊が取り付いた菜摘み女と霊が同じように舞うという、能の「二人静」から来ています。

ガマズミの花にコアオハナムグリ。体長は10ミリぐらい。妻女山山系ではよく見られます。前回撮影したのも遠くで分からなかったのですが、コアオハナムグリかも知れません。

ナヨクサフジ(弱草藤)マメ科ソラマメ属。ヨーロッパ原産です。元は飼料として輸入され、日本で帰化したもの。里山や河原などに普通に見られます。何か小さな蛹がついています。なんでしょう。

キバネツノトンボの生息地へ。一匹だけいました。メスでしょうか。交尾しそこなった個体でしょうか。自然というのは忖度なしの世界です。世襲とかタレントで有名とかありません。個の実力と運が全てです。

ニガナの上にキリギリスの仲間のヤブキリの幼虫が。ヒシバッタの幼虫も見かけました。

善光寺地震の松代藩が立てた罹災横死供養塔の下にもニガナの群生地があります。最近あちこちで地震が頻発しているので心配です。首都直下型地震の心配もあります。備えだけはしておきたいものです。

ヤマホタルブクロ(山蛍袋)キキョウ科ホタルブクロ属。昔、ホタルを入れて遊んだからの名前だそうですが、本当かなと思っていたら、生前父が子供の頃そうやって遊んだと言っていたと聞いて、へえ!って納得しました。

妻女山展望台からの松代方面の眺め。清滝から林道経由で尾根に登り、30mの崖を奇妙山へ登るコースは拙書でも紹介しています。奇妙山は行基にまつわる歴史の深い里山で、古い山城の遺構もあります。根子岳と四阿山の残雪もほとんど消えた様です。

山椒の実で縮緬山椒。佃煮にするのではなく薄味で煮物にします。採りたてでアクが少ないので一度茹でこぼすだけ。実も枝も柔らかく葉も入っていますが構いません。いつもはコウナゴですが、今回は食べる煮干しを使いました。干し椎茸とだし昆布、鰹出汁といりこ出汁に本味醂と友人が作った手作り醤油で煮ます。薄味で、これで素麺や蕎麦をいただいても絶品です。ピリピリと痺れる辛さがたまりません。梅雨時の食欲不振にぴったりです。こんな料理は、料亭でも出ることはないでしょうから貴重だと思います。
◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。郷土史研究家でもあるので、その山の歴史も記しています。地形図掲載は本書だけ。立ち寄り温泉も。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。でも、できれば地元の書店さんを元気にして欲しいです。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。分かりやすいと評判のガイドマップも自作です。『真田丸』関連の山もたくさん収録。

★本の概要は、こちらの記事を御覧ください。
★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせか、メッセージからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。
インタープリターやインストラクターのお申込みもお待ちしています。好評だったスライドを使用した自然と歴史を語る里山講座や講演も承ります。市民大学などのフィールドワークを含んだ複数回の講座も可能です。左上のメッセージを送るからお問い合わせください。

森の中から見る陣場平の貝母群生地。先日の強い雨で倒れたものもかなりあります。ハルゼミとエゾハルゼミの合唱がもの凄い。先日の作業の日と違ってクロメマトイが五月蝿い。まだヤブ蚊がいないのが救い。淡竹の筍を食べに熊が来るので、熊鈴やホイッスル、大きな音をたてるは必須です。先日はそれで聖山の熊を追い払いました。

枯れた貝母の間に繁茂してきたのは、ヒカゲイノコヅチ(日陰猪小槌)ヒユ科イノコズチ属の多年草。秋に花穂がひっつき虫(バカ)になり、茎に丸い赤紫の虫こぶ(虫えい・ゴール)ができる植物です。若葉は天ぷらやおひたし、胡麻和えなどで食べられるそうです。でも美味しかったら皆採って食べますよね。まあ、そういうことでしょう。多年草で根を張り巡らすので、貝母の繁殖を阻害しますが、どうも見ていると貝母の方が強いので、放置しています。
虫こぶは、イノコヅチクキマルズイフシといい、イノコヅチウロコタマバエによって作られます。虫こぶを切ってみると、小さなタマバエの黄色い幼虫がたくさん入っています。

陣場平の下の入口からの小道。オオブタクサがたくさん出る場所なので要注意なのです。里山保全は賽の河原に石を積む様な作業の繰り返しです。諦めたら終わり。人生は有限なのになぜそんなことをするのと思われるかもしれません。宇宙はなるようにしかならない。その通りです。それがレーゾン・デートル(存在理由)の証と思っているからでしょうからですかね。意識も物質の電気信号のひとつでしかない。存在を考えると宇宙とか、マクロの原子とか。その存在理由は何かと考えますね。たぶん大本の宇宙がその存在理由さえないのかも知れませんが。星が綺麗な信州の夜空を見ると、そんなことも思うのです。

陣場平ではハルジオンはすべて抜きますが、周囲ではウスバシロチョウが吸蜜するのである程度残しておきます。交尾をした印のスフラギスを付けたメスが吸蜜していました。元気な子孫を残すためにせっせと吸蜜して栄養を蓄えます。

この時期のメスは、吸蜜に夢中で近づいても逃げません。有害帰化植物のハルジオンを残すのは痛し痒しなのですが、この時期ほかに吸蜜できる花がないので仕方ありません。ウスバシロチョウが消えたら除草します。

蜘蛛の巣に引っかかったウスバシロチョウ。自然の営みには関与しないのが基本ですが、この巣は主が不在。放棄したものらしいので逃してあげました。自然にどこまで人間が関与していいのか、非常に難しい問題です。欧米ではこれを人間対自然の世界観で。日本、東洋は人間も自然の一部と。近年は後者がポピュラーですが、ではそのコンセプトは確立し普及していますか。意識の改革はそう簡単ではありません。

翅を広げても10ミリぐらいのマドガ(窓蛾)。この面白い名前は、ギリシア語の窓や入り口からで、翅の中室にある半透明の白色斑を窓に見立てたものだそうです。

山蕗の葉にヤマザクラかカスミザクラのサクランボ。渋くて食用にはなりません。ケバエの一種でしょうか。来ています。

ミヤマウグイスカグラ(深山鶯神楽)スイカズラ科スイカズラ属。赤い実は甘く食べられます。子供の頃の山のおやつでした。田舎なので1円キャラメルぐらいしかなかったですから。後はハイカラな明治生まれの「おはなはん」が大好きだった祖母の作るどこで覚えたのか中華菓子の麻花兒(まーふぁーる)とか、じゃがいも餡の饅頭とか。おはぎやこねつけ、よもぎ餅。甘い葛湯もよく作ってくれました。

湧き水の出る沢に下ってみました。ユキノシタ(雪の下)ユキノシタ科ユキノシタ属。虎耳草、鴨脚草、鴨足草、金糸荷などの別名があり、利尿作用のある硝酸カリウムや塩化カリウムを含み、むくみ解消に効果が。その他にきょ風、清熱、解毒などの効能がある民間の薬草です。葉は天ぷらで。

ワサビ(山葵)の葉。花が咲くのはこれからです。在京時代は山梨の秘密の谷へ自生の山葵を採りに行って妻にワサビ漬けを作ってもらいました。

フタリシズカ (二人静)センリョウ科チャラン属の多年草。静かは煩いの反対語ではなく、源義経の愛した静御前のことです。フタリシズカは、静御前の霊が取り付いた菜摘み女と霊が同じように舞うという、能の「二人静」から来ています。

ガマズミの花にコアオハナムグリ。体長は10ミリぐらい。妻女山山系ではよく見られます。前回撮影したのも遠くで分からなかったのですが、コアオハナムグリかも知れません。

ナヨクサフジ(弱草藤)マメ科ソラマメ属。ヨーロッパ原産です。元は飼料として輸入され、日本で帰化したもの。里山や河原などに普通に見られます。何か小さな蛹がついています。なんでしょう。

キバネツノトンボの生息地へ。一匹だけいました。メスでしょうか。交尾しそこなった個体でしょうか。自然というのは忖度なしの世界です。世襲とかタレントで有名とかありません。個の実力と運が全てです。

ニガナの上にキリギリスの仲間のヤブキリの幼虫が。ヒシバッタの幼虫も見かけました。

善光寺地震の松代藩が立てた罹災横死供養塔の下にもニガナの群生地があります。最近あちこちで地震が頻発しているので心配です。首都直下型地震の心配もあります。備えだけはしておきたいものです。

ヤマホタルブクロ(山蛍袋)キキョウ科ホタルブクロ属。昔、ホタルを入れて遊んだからの名前だそうですが、本当かなと思っていたら、生前父が子供の頃そうやって遊んだと言っていたと聞いて、へえ!って納得しました。

妻女山展望台からの松代方面の眺め。清滝から林道経由で尾根に登り、30mの崖を奇妙山へ登るコースは拙書でも紹介しています。奇妙山は行基にまつわる歴史の深い里山で、古い山城の遺構もあります。根子岳と四阿山の残雪もほとんど消えた様です。

山椒の実で縮緬山椒。佃煮にするのではなく薄味で煮物にします。採りたてでアクが少ないので一度茹でこぼすだけ。実も枝も柔らかく葉も入っていますが構いません。いつもはコウナゴですが、今回は食べる煮干しを使いました。干し椎茸とだし昆布、鰹出汁といりこ出汁に本味醂と友人が作った手作り醤油で煮ます。薄味で、これで素麺や蕎麦をいただいても絶品です。ピリピリと痺れる辛さがたまりません。梅雨時の食欲不振にぴったりです。こんな料理は、料亭でも出ることはないでしょうから貴重だと思います。
◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。郷土史研究家でもあるので、その山の歴史も記しています。地形図掲載は本書だけ。立ち寄り温泉も。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。でも、できれば地元の書店さんを元気にして欲しいです。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。分かりやすいと評判のガイドマップも自作です。『真田丸』関連の山もたくさん収録。

★本の概要は、こちらの記事を御覧ください。
★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせか、メッセージからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。
インタープリターやインストラクターのお申込みもお待ちしています。好評だったスライドを使用した自然と歴史を語る里山講座や講演も承ります。市民大学などのフィールドワークを含んだ複数回の講座も可能です。左上のメッセージを送るからお問い合わせください。