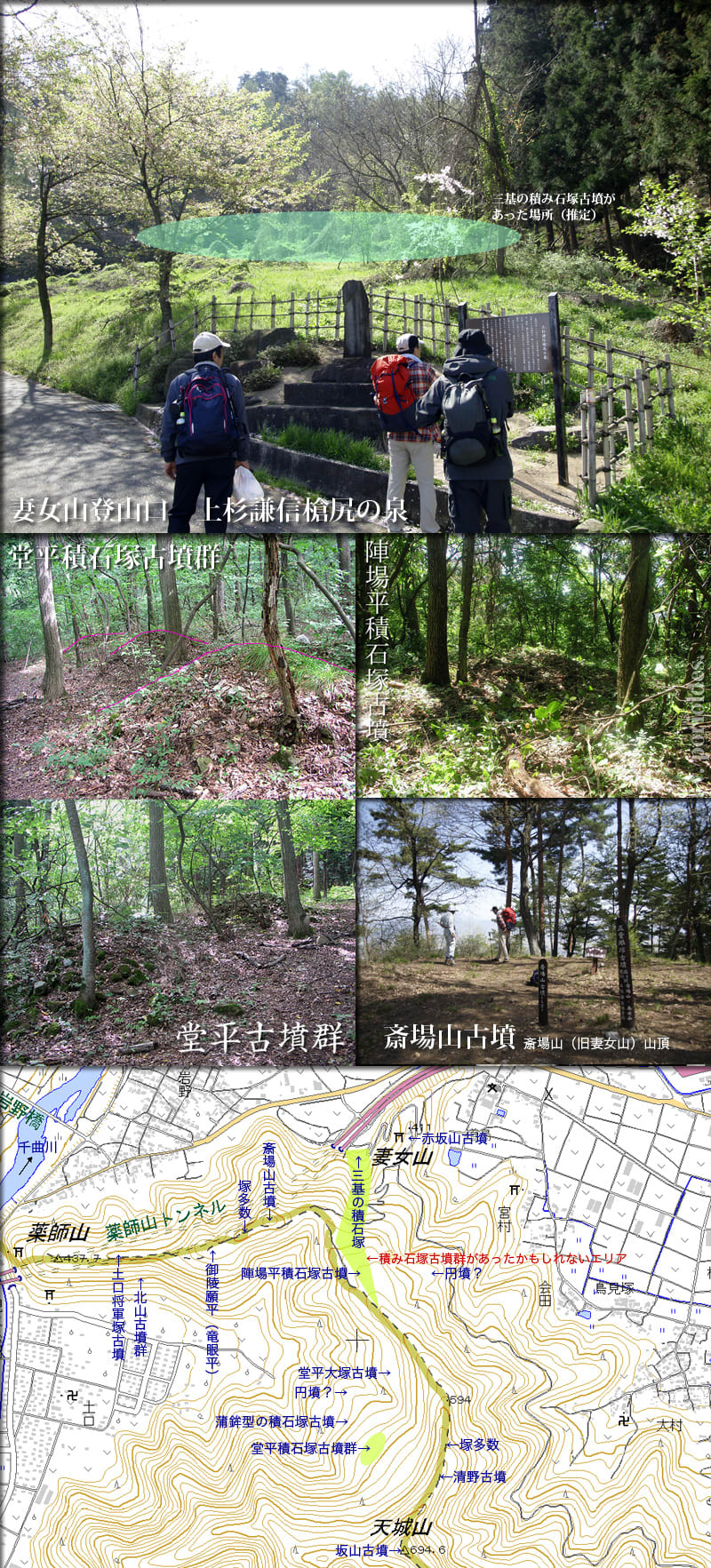日曜日の午前中、「妻女山 里山デザイン・プロジェクト」の作業をしました。前回除伐して残った枝をチップマシーンにかけて、カブトムシのコロニーを作ろうという計画。太い幹が複雑に絡み合ったカラコギカエデ。前回除伐しきれなかったので、今回はKさんが強力なグラップルつきバックホー(写真の重機)で参上。
まず頭領N氏が地上5mで交差した主幹を伐採。切った瞬間に跳ね上がることが分かっていたので、慎重に。それでも切った瞬間にブーン!と音をたてて跳ね上がった1トン以上はあるだろう幹の迫力には、思わずオーッと歓声が。それを恐竜のようなグラップルが挟んで引き抜きます。生木は、乾燥させた材木と比べると5~6倍の重さがあるのです。
生木は強い。これだけ強力なグラップルでひっぱっても絡まった枝葉は簡単には抜けませんでした。しかし、やはり重機。最後はなんとか抜き取ってしまいました。その後は我々の仕事。チェーソーや枝打ち鋸で切断し、チップマシーンに入れて行きます。これが大騒音。とても里ではできません。枝葉は次々とチップに変身していきました。
気温は21~23度位。時折爽涼な風が通り抜けて行きます。チップマシーンを止めると、ハルゼミ、エゾハルゼミの鳴き声。斎場山からはカッコウの鳴き声。作業する我々の周りをかすめる様に飛ぶのはウスバシロチョウ。チップマシーンやチェーンソーの騒音に、何事だと好奇心の強いニホンカモシカも見ていました。午前中で作業は終了。Kさんのログハウスでとろろ蕎麦を作りました。
大量のチップは、不要になった風呂桶に入れてカブトムシの産卵の場所とします。問題なのは猪。気づかれたら孵った幼虫を食べられてしまいます。まあ、少し位は分けてあげてもいいのですが。
ウスバシロチョウは、朝方は湿った草むらには留まらず、高い梢の葉で休みます。そこから滑空して来て低空飛行。観察していると朝方はあまり吸う蜜しないようです。日が昇り草が乾くと留まるのですが、気温が上がって来ると活性が高くなり、なかなか留まってくれません。昼近くなるとお腹がすくのか吸蜜を始めます。花はミツバツチグリやヒメオドリコソウ、ハルジオンなどで蜜が少ないためか、吸蜜の時間も短く、撮影が困難です。
曇り空で湿度が高い日は、翅が重くなるのでしょうか、頻繁に留まる様になります。午後になると、眠くなるのでしょうか、葉に脚の棘をひっかけてぶら下がり、昼寝をする姿が見られます。ヤエムグラの細い茎に留まって休むウスバシロチョウを真下から逆光で撮影してみました。ウスバシロチョウの透けた翅は逆光で撮ると最もその美しさが出ると思うのです。ヤエムグラは草高が低いので、下にカメラをそーっと気づかれない様に忍び込ませるのが大変でした。
翅を閉じているウスバシロチョウは、コツをつかめば手で捕獲できます。そうしたところ、腹部からラベンダー色の突起が出てきました。なんでしょうね。生殖に関係あるものだろうとは思いますが。卵嚢か精子嚢か、それ以外の生殖器官でしょうか。
*後日改めて調べてみると、これはメスの交尾板(受胎嚢)だと分かりました。やはり生殖に関係するものでした。交尾したオスが、メスがもう交尾できないように、分泌物の粘液でできた殻をメスの腹部に付けるのだそうです。言わば貞操帯。つまり、このメスは既に交尾が済んでいるということです。
まもなく梅雨に入ります。ゼフィルスやスミナガシが舞い始めるはず。粘菌も出てきます。じめじめした梅雨は、里山の生物にとっては、活動の最盛期でもあるのです。こんな美しい自然がある日本を、たかがお湯を沸かすために核分裂を使って住めない国にするのは、全くもって愚かなこと。






■ツイッターMORIMORIKIDSを左のサイドバーに表示するようにしました。主に原発情報、地震情報を呟いています。自然、歴史も。
まず頭領N氏が地上5mで交差した主幹を伐採。切った瞬間に跳ね上がることが分かっていたので、慎重に。それでも切った瞬間にブーン!と音をたてて跳ね上がった1トン以上はあるだろう幹の迫力には、思わずオーッと歓声が。それを恐竜のようなグラップルが挟んで引き抜きます。生木は、乾燥させた材木と比べると5~6倍の重さがあるのです。
生木は強い。これだけ強力なグラップルでひっぱっても絡まった枝葉は簡単には抜けませんでした。しかし、やはり重機。最後はなんとか抜き取ってしまいました。その後は我々の仕事。チェーソーや枝打ち鋸で切断し、チップマシーンに入れて行きます。これが大騒音。とても里ではできません。枝葉は次々とチップに変身していきました。
気温は21~23度位。時折爽涼な風が通り抜けて行きます。チップマシーンを止めると、ハルゼミ、エゾハルゼミの鳴き声。斎場山からはカッコウの鳴き声。作業する我々の周りをかすめる様に飛ぶのはウスバシロチョウ。チップマシーンやチェーンソーの騒音に、何事だと好奇心の強いニホンカモシカも見ていました。午前中で作業は終了。Kさんのログハウスでとろろ蕎麦を作りました。
大量のチップは、不要になった風呂桶に入れてカブトムシの産卵の場所とします。問題なのは猪。気づかれたら孵った幼虫を食べられてしまいます。まあ、少し位は分けてあげてもいいのですが。
ウスバシロチョウは、朝方は湿った草むらには留まらず、高い梢の葉で休みます。そこから滑空して来て低空飛行。観察していると朝方はあまり吸う蜜しないようです。日が昇り草が乾くと留まるのですが、気温が上がって来ると活性が高くなり、なかなか留まってくれません。昼近くなるとお腹がすくのか吸蜜を始めます。花はミツバツチグリやヒメオドリコソウ、ハルジオンなどで蜜が少ないためか、吸蜜の時間も短く、撮影が困難です。
曇り空で湿度が高い日は、翅が重くなるのでしょうか、頻繁に留まる様になります。午後になると、眠くなるのでしょうか、葉に脚の棘をひっかけてぶら下がり、昼寝をする姿が見られます。ヤエムグラの細い茎に留まって休むウスバシロチョウを真下から逆光で撮影してみました。ウスバシロチョウの透けた翅は逆光で撮ると最もその美しさが出ると思うのです。ヤエムグラは草高が低いので、下にカメラをそーっと気づかれない様に忍び込ませるのが大変でした。
翅を閉じているウスバシロチョウは、コツをつかめば手で捕獲できます。そうしたところ、腹部からラベンダー色の突起が出てきました。なんでしょうね。生殖に関係あるものだろうとは思いますが。卵嚢か精子嚢か、それ以外の生殖器官でしょうか。
*後日改めて調べてみると、これはメスの交尾板(受胎嚢)だと分かりました。やはり生殖に関係するものでした。交尾したオスが、メスがもう交尾できないように、分泌物の粘液でできた殻をメスの腹部に付けるのだそうです。言わば貞操帯。つまり、このメスは既に交尾が済んでいるということです。
まもなく梅雨に入ります。ゼフィルスやスミナガシが舞い始めるはず。粘菌も出てきます。じめじめした梅雨は、里山の生物にとっては、活動の最盛期でもあるのです。こんな美しい自然がある日本を、たかがお湯を沸かすために核分裂を使って住めない国にするのは、全くもって愚かなこと。
■ツイッターMORIMORIKIDSを左のサイドバーに表示するようにしました。主に原発情報、地震情報を呟いています。自然、歴史も。