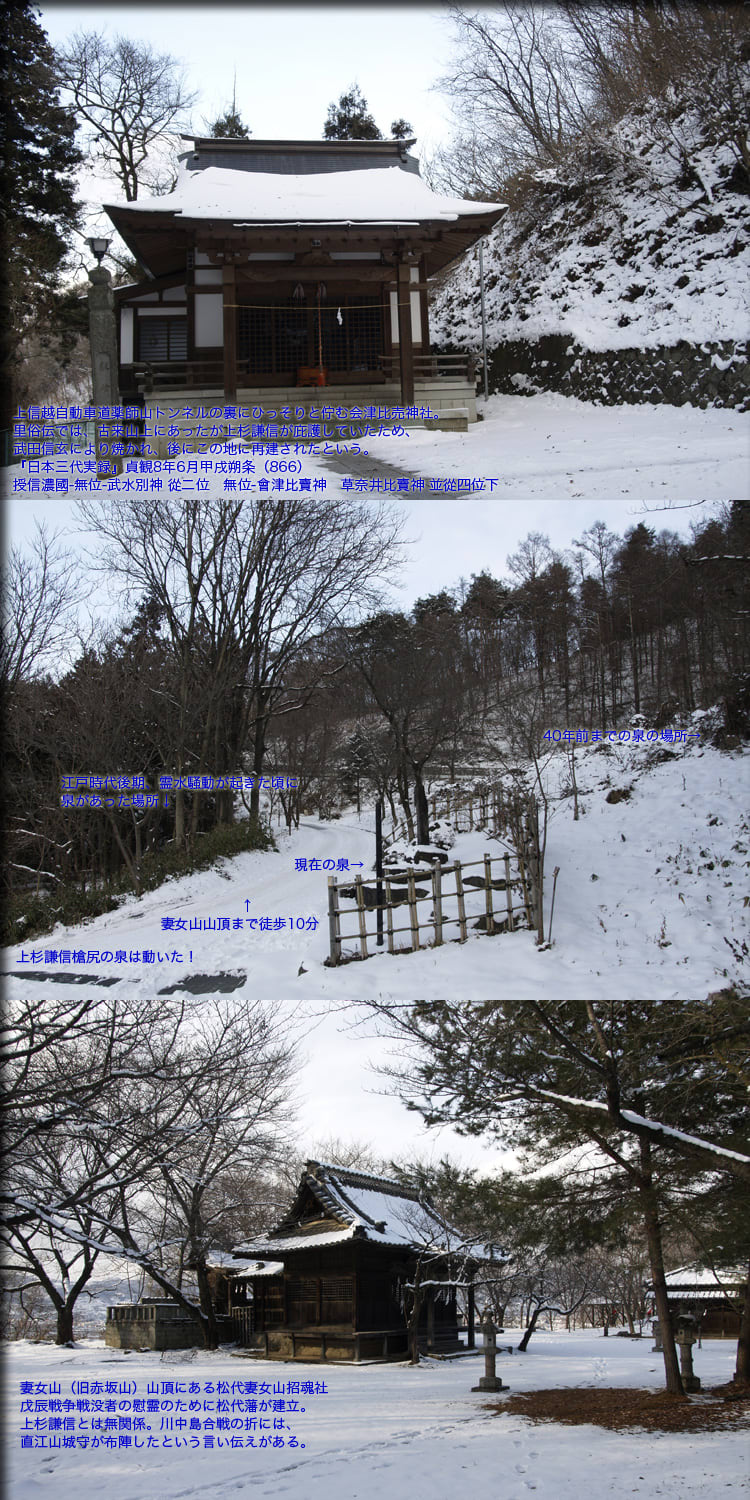@magosaki_ukeru 東京都千代田区
日本の元外交官、元防衛大学校教授、作家。著書:『日本の国境問題ー尖閣・竹島・北方領土』『日本人のための戦略的思考入門』『情報と外交』『『日米同盟の正体』、『日本外交 現場からの証言』(第2回山本七平賞受賞)、今、東アジアの安全保障執筆中。(Wikipedia)
【安保騒動】
これから書くことは頭の体操です。「頭の体操」の嫌な人は最初から読まないで下さい。
事実1:我々は鳩山氏が「普天間を最低でも県外」と言った時に、米国が日本の政治家、官僚、マスコミと一緒になって、これを阻止し、政権を潰しに回ったことを知っている(疑念のある人はウィキリークス等見て下さい)。
事実2:独裁者を打倒する時など米国はしばしばデモを利用する。例えばイランのシャーを倒す時には人権侵害でデモを誘導していった。イランで人権侵害のデモに参加した人は、シャーを倒す目的で米国がデモを支援していることは知らない。
事実3:岸は「旧安保は余りにも米国に一方的に有利なものである。形式として連合国の占領は終わったけれども、これに代わって米軍が日本の全土を占領している状態である」という認識を持っている。
事実4:1957年4月19日の参議院内閣委員会で「安保条約、行政協定は全面的に改定すべき時代にきてる」と答えてる。マッカーサー大使に「駐留米軍の最大の撤退、米軍による緊急使用のために用意されている施設付きの多くの米軍基地を日本に返還すること」を提案。
ここから考えましょう。鳩山首相の普天間ですら引きずり降ろしを計ったのです。「駐留米軍の最大の撤退」を述べる岸を降ろす工作をするのは自然ではないだろうか。その時デモを利用するということはないだろうか。勿論デモ参加者は悪人岸を引きずり降ろすことは正義とみている。Wikipedia「田中清玄、60年1月号『文藝春秋』に「全学連指導者諸君に訴える」を発表。全学連書記長島成郎が田中からの資金カンパ依頼。
後、中曾根平和研究所に行く小島弘、東原吉伸、篠原浩一郎も。」全学連の唐牛健太郎らはのちに田中の企業に就職。田中清玄は反岸。」安保騒動後、反安保の中心であった朝日新聞では反安保論調を書きまくった部長クラスは続々地方に飛ばされる。左派文化人も以降沈黙。
自民党内で岸を揺さぶったのは従米の池田勇人グループ。岸から池田の交代は米国にとって喜ばしいこと。反安保条約の論陣を張った人々、その後ほとんど、その後論陣を張らない、はれなくなつ現象をどう評価するか。戦後米国が独裁者を倒す有力武器がデモ。日本に適用は充分可能。
岸・池田:反応(孫崎先生、それは初耳でした。普通は、清和会の元祖の岸のほうが、宏池会の元祖の池田よりも従米でCIAの手下と思ってしまいますので)非常に重要な点を含んでいます。”岸でも”米軍撤退と行政協定(米軍への権利を規定)を米国に要求したという事実を一般国民に持たせない必要があったのです。米国に基地をおいてもいいですよといったのは誰かご存じですか。
吉田茂の代役、池田勇人蔵相(当時)です。1950年4月池田蔵相は宮沢喜一秘書官を連れて占領下の日本の閣僚として初めて訪米。目的は「アメリカの財政経済事情の視察」。同時に一行は吉田首相から「講和についての瀬踏みをしてくる」という密命。五月二日、池田蔵相とドッジを陸軍省のオフィスを訪問。ここで池田首相は次のように発言。 “自分は吉田総理大臣からの伝言として、次のことをお伝えしたい。『日本政府はできるだけ早い機会に講和条約締結を希望する。
このような講和条約ができても、米国の軍隊を日本に駐留させる必要があるであろうが、もし米国側からそのような希望を申し出にくいならば、日本側からそれをオファするような持ち出し方を研究してもよろしい』吉田・池田ラインの米国追随を薄める世論操作があったのです。今につながるから安保騒動が何であったか。相当書きました。
問題点の一つは岸退陣後、新聞はピタリと安保条約批判停止。騒動は本当に「安保条約批判」の動きか、或いは「岸打倒」の動きか。その際は左派と米国のつながり見る必要。終戦直後から関係あり。1945年10月11日マッカーサーと幣原首相の初会見時総司令部側から労働運動の助長を指示。労働組合法が1945年12月議会で可決。占領司令部は労働運動を奨励。1946年12月には組合数は1万7千,組合員数は484万名。
CIA元長官コルビー「秘密チャネルによる直接的な政治的、準軍事的援助によって“干渉”することは数世紀間国家関係の特徴。各国は自衛のために武力を行使する道徳的権利を持ち、その目的に必要な程度の武力行使は許されている。軍事的干渉が許されるなら、それ以下の形での干渉は正当化される。伊の民主勢力がソ連の支援する転覆運動に対抗できるように、民主勢力に支援を与えるのは道徳的活動CIAは自由労働運動の強化、競争的な協同組合の結成、各種の文化的、市民的、政治的団体の援助にも、多くの努力。マスコミも期待。
これらの作戦で根本的に重要なことは秘密維持。米国政府が支援しているとの証拠がでては絶対にいけない。金、助言等、援助は第三者経由。資金は実際には外部者経由。公認の米国公務員が渡したことは一回もない。」 どうでしょう。安保騒動時、左派の活動費が急に増大したことはなかったか。何故今これを論議しているか。米軍基地縮小を提言した政治家がどうなったかを見極める必要。そうでなければ日本が「前原」「野田」で溢れてしまう。
【日米の歴史】
米国が日本の指導者を取り替える時に如何なる選択があったか。易しい順から並べてみる。
1:閣内有力者を外すよう圧力をかけ政権瓦解、細川政権時の武村官房長官を外す圧力(この模様は小池百合子さんが記載)。
2:特定政策の強要を行うと共に、党内有力者に反対運動をさせる。
日米の歴史2:アフガンへの派遣で福田康夫首相(ウィキリークス内情暴露)。
3:主要政策で反対派動員、マスコミ動員で実施出来なくし瓦解させるー普天間問題での鳩山由紀夫内閣。
4:特定政策成就で花道引退の筋道を作る。マスコミ・反対派―鳩山一郎のソ連との共同声明。
5:検察に汚職等を追わせ 日米の歴史3:失墜―芦田内閣の招電事件、田中角栄のロッキード事件。
6:党内抗争、検察利用が出来ない時―まさに岸の時、大衆闘争(日本では稀。しかし世界的にみると米国が利用してきた独裁政権を倒す時にしばしば利用)。吉田茂、池田勇人、小泉純一郎等従米を徹底し、要望を実施なら長期政権。
【新聞と従米】
日本大手新聞の最大の問題は政治問題で米国に操られてること。読売は当然、朝日も。具体例。安保闘争。6月17日極めて異例な七社共同宣言(読売、朝日等)。「暴力を排し議会主義を守れ」「民主主義は言論をもって争われるべき。その理由のいかんを問わず暴力を用いて事を運ばんとする事は、断じて許されるべきではない」当時、安保騒動に関与した人は一様にこの七社共同宣言で流れ変わったと発言。
では、この七社共同宣言は新聞社独自で書いたか。米国の圧力か。朝日新聞の主筆、笠信太郎がこの宣言を書く中心。笠信太郎①1943年10月スイス、その地に滞在中の情報機関OSS(CIAの前身)の欧州総局長であったアレン・ダレス(安保騒動時のCIA長官)と協力。戦後は1948年2月帰社。同年5月論説委員、同年12月東京本社論説主幹。当時占領下。米国が冷戦後、日本を「共産主義に対する防波堤」にしようと言う時に朝日新聞社で活躍開始。米国との関係が密接でなければ、このポストにつけない。
米側書籍「マッカーサー(大使)は日本の新聞の主筆達に対し、米大統領訪日に対する妨害は共産主義の勝利と見なすと警告」「友好的、CIA支配下にある報道機関に、安保反対者を批判させ、米国との結び付きの重要性を強調させた」「「三大新聞では政治報道陣の異動により池田や安全保障条約に対する批判が姿を消した」。日本の大手新聞の従米は奧が深いのです。朝日新聞は一見リベラル装いながら、重要局面で従米ですから、読売新聞より時に深刻な被害を日本に与える。
【新聞と米国操作】
読売、朝日しばしば米国に操作されているのでないかとの疑念。歴史的に顕著に出たのが、何と安保条約反対運動の最中。60年安保闘争盛り上がる中、6月17日極めて異例な七社共同宣言(読売、朝日等)が出ます。「暴力を排し議会主義を守れ」という表題の下、「民主主義は言論をもって争われるべきである。その理由のいかんを問わず暴力を用いて事を運ばんとすることは、断じて許されるべきではない」。
これで運動の流れ一変。この七社共同宣言は新聞社独自で書いたか。米国の圧力があったか。
記述は朝日新聞主筆、笠信太郎が中心。笠信太郎①1943年スイスへ移動。その地に滞在中の米情報機関OSS欧州局長のアレン・ダレスと協力。ダレスは安保騒動時のCIA長官。②戦後1948年2月に帰社。同年5月論説委員、同年12月東京本社論説主幹、 米国が冷戦後、日本を「共産主義に対する防波堤」にしようと言う時に朝日新聞社で活躍開始。
当時占領下。米国との関係が密接でなければ、このポストにつけない。
そして安保時。米学者記述「マッカーサー大使は日本の新聞の主筆達に、大統領訪日妨害は共産主義にとっての勝利であると見なすと警告」「友好的なCIAの支配下にある報道機関に、安保反対者を批判させ米国との結び付きの重要性を強調させた」「三大新聞では政治報道陣の異動により池田や安全保障条約に対する批判が姿を消した」戦後の最も重要な政治的な動きの中で、大新聞は米国に操作された。そしてその後の人事まで影響した。米国に操作される体質は今日まで継続しているのです。
【TPP】
予想される条項の内、最も問題は投資家・国家訴訟制度(ISD)。この条項は極めて重要。しかし、経産省等は隠して政治家等に説明しない。だから野田首相も知らず、国会で質問されて紛糾したもの。国家(例えば日本)の規制で、投資家(米国企業)の販売チャンスが減少したら訴えられる制度。
例えば米国牛肉を売る。環境問題で制限したとしよう。販売チャンス減少させたと訴訟。この際、環境等の規制が公益上必要か否かの視点はほとんどない。この制度、米国の自由貿易協定で入っているが、一方的に米国企業が勝訴。これがTPPに入る。日本の公益配慮の法律、米国企業には適用除外と言うこと。この条項米韓FTAにある。今国民騒ぐ。事前説明無し。日本と同じ。
9日付朝鮮日報「韓米FTA:「政権を握ったら廃棄」「韓米自由貿易協定(FTA)再交渉を求める野党・民主統合党と統合進歩党は8日、再交渉が実現しない場合、FTAの廃棄に向けて行動を起こすという内容の書簡を米国大使館に提出。議員96人が連名の書簡は、オバマ大統領、下院議長宛。投資家・国家訴訟制度(ISD)、(協定内容の見直しを認めない)ラチェット規定等10項目についてFTAの発効前に再交渉に応じるよう求めた。」TPP推進の新聞はISD沈黙。国民無知。
新書(3月16日発売。講談社現代新書)
メインタイトル: 『不愉快な現実』
サブタイトル:中国の大国化、米国の戦略転換
オビのメインキャッチコピー:問題を直視できないこの国の瀬戸際
オビのリード:東アジアのパワーバランスの激変で、孤立化が進行している。何故『不愉快な現実』か。明治以来150年以上中国はある時は、軍事的に、ある時は経済的に、しかし常に日本の下だった。しかしその中国はGDPで日本の上へいった。
それだけではない。世界で世論調査をすれば、英、仏、独、露では世論の過半数が「中国は超大国として米国を抜く」と判断する時代に入った。米国もイスラエルも「中国が抜く」が「抜けない」を上回った。日本だけが「抜けない」。日本だけが正しくて、世界が間違っているか。日本だけが間違っているか。残念ながら日本だけが間違っているのです。日本の人が目を瞑っていても中国は米国を追い抜くのです。データで示します。その時、米国はどう反応するか。
米国にとって「東アジアで最も重要な国はどこか」の世論調査をうれば、過去ずーっと日本。しかし昨年は米国の大衆は中国を日本より重要と判断しはじめた。米国の指導者層は世論に先行し中国。日本人は「米国は日本を最も重要視している」と判断している。もうそういう時代は終わった。「米国に追随すれば日本は繁栄し平和」の時代は終わりに近づいてる。
簡単な質問。米国が重要度の低い国の為に「重要度の高い国と戦う?」。戦わない。「核の傘」はない。尖閣諸島の紛争時、米軍は戦うか。戦いません。軍事的に戦えない。これが現実。「不愉快な現実」です。
日本の国民は「問題を直視できない」。逃げたい。そして皆、必死になって「中国駄目」「中国けしからん」という本を読んで安心している。そこにこの本は「不愉快な現実」をつきつけます。そして対応策を考えます。本来は画期的な本です。あえて、直視しようとする読者がどれ位いるか?。私の国民への問です。
※読み易い様に文章をまとめ、句読点や誤打を修正してあります。