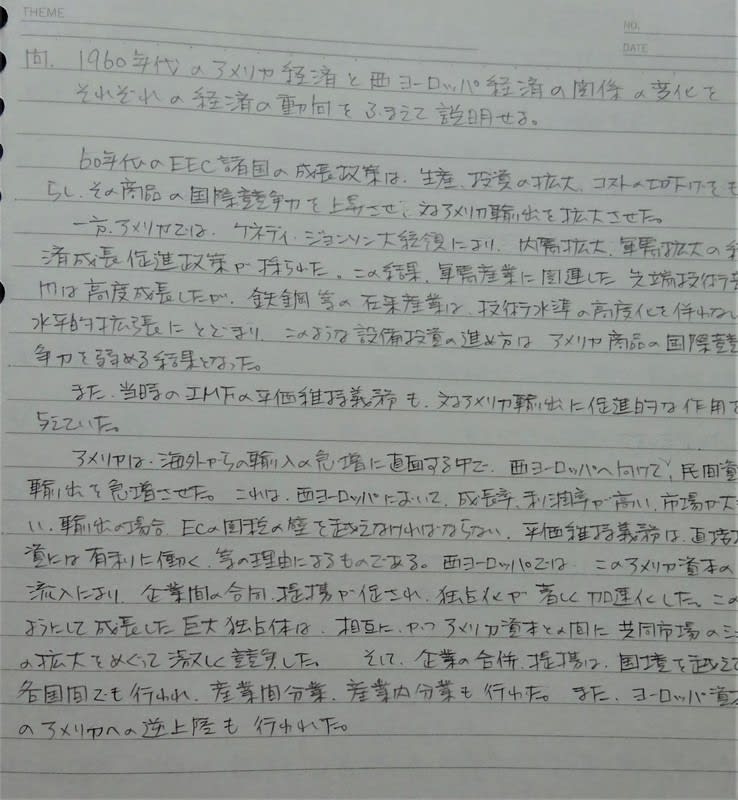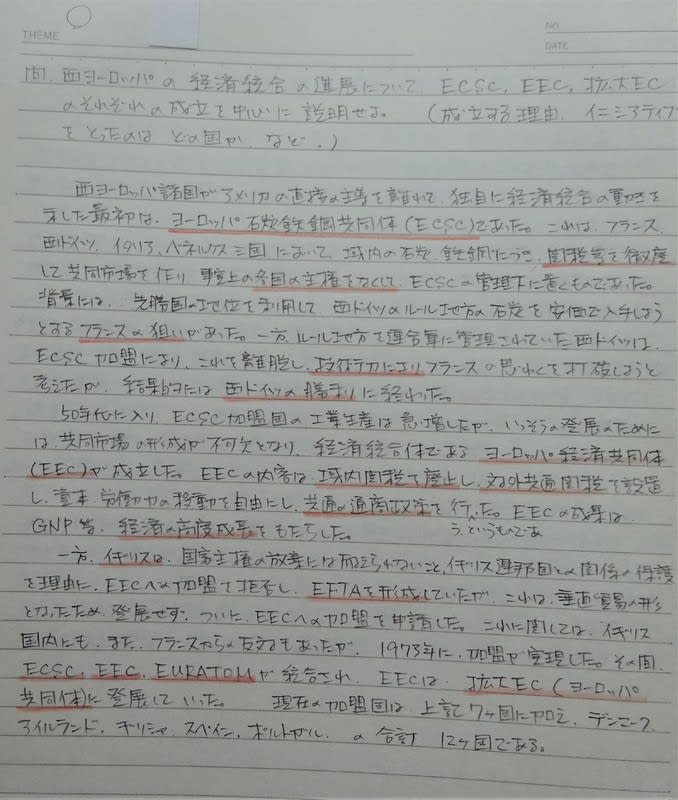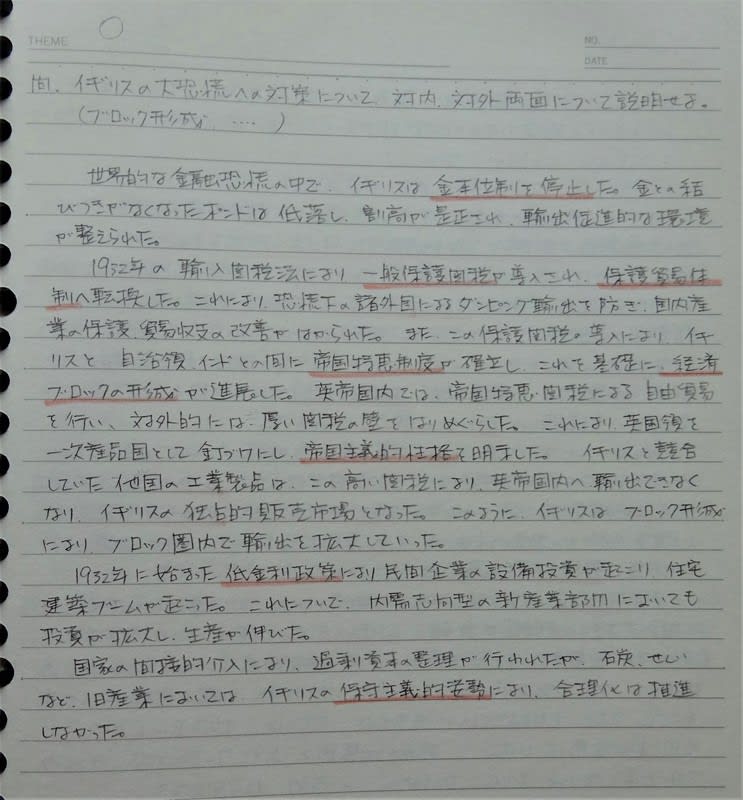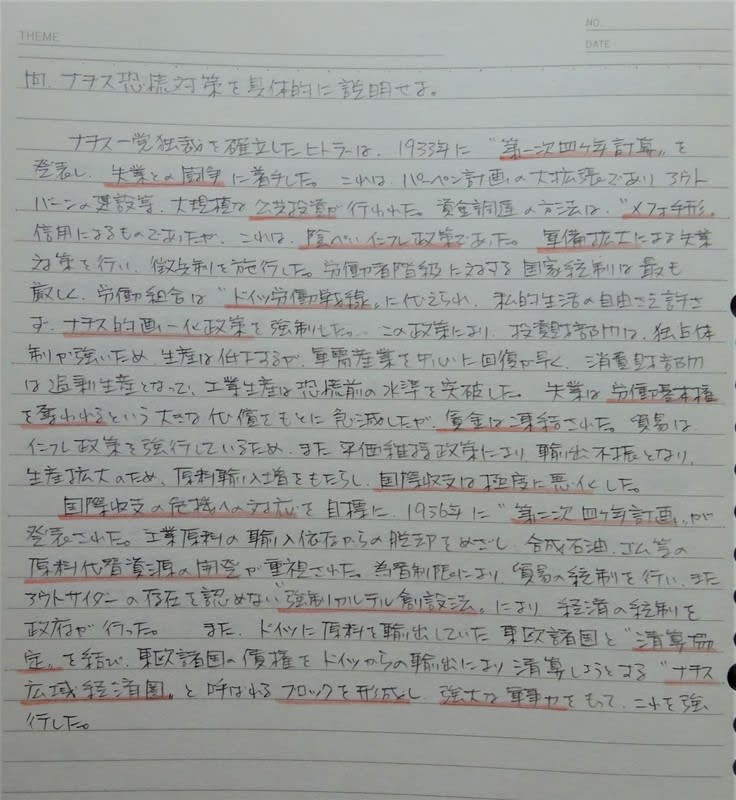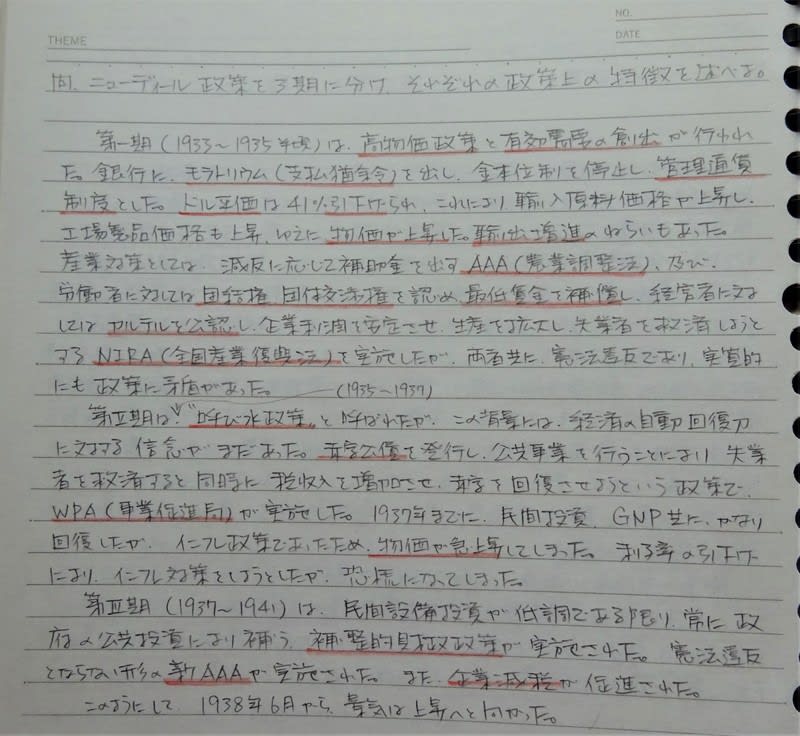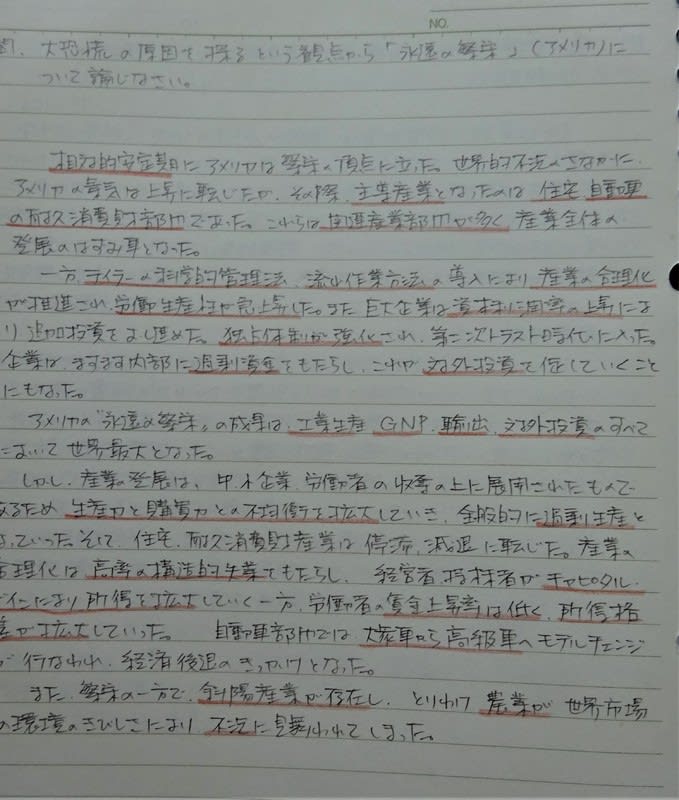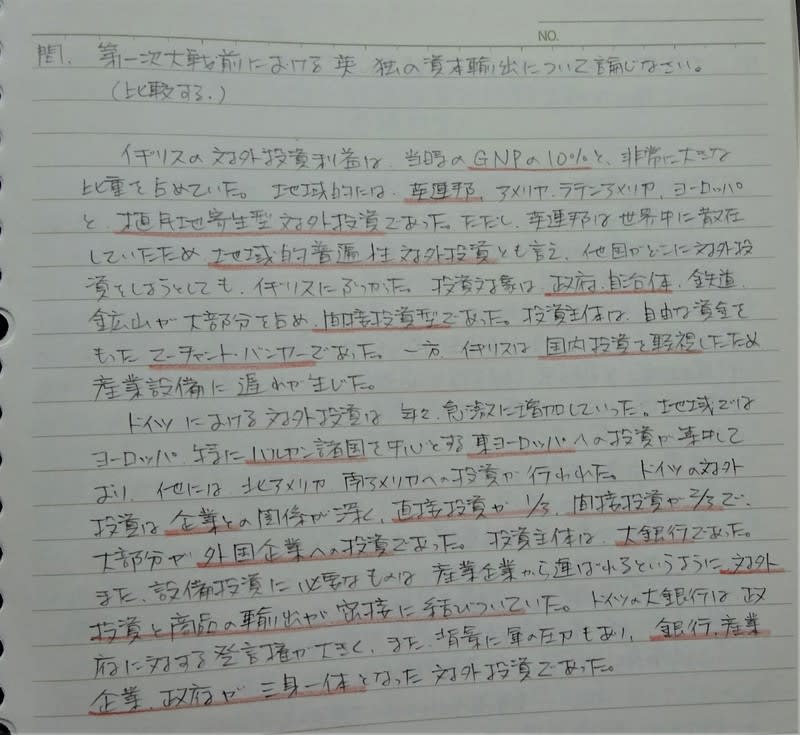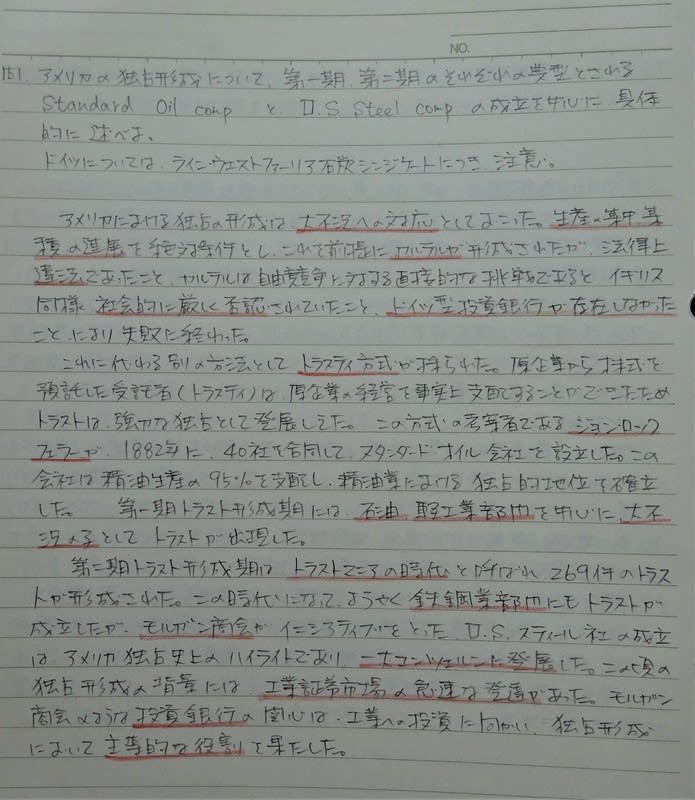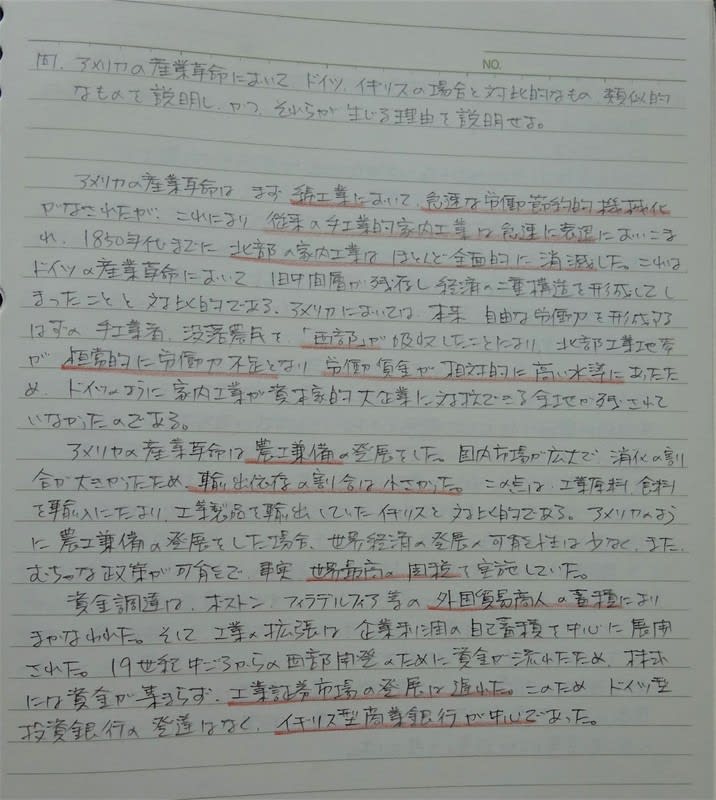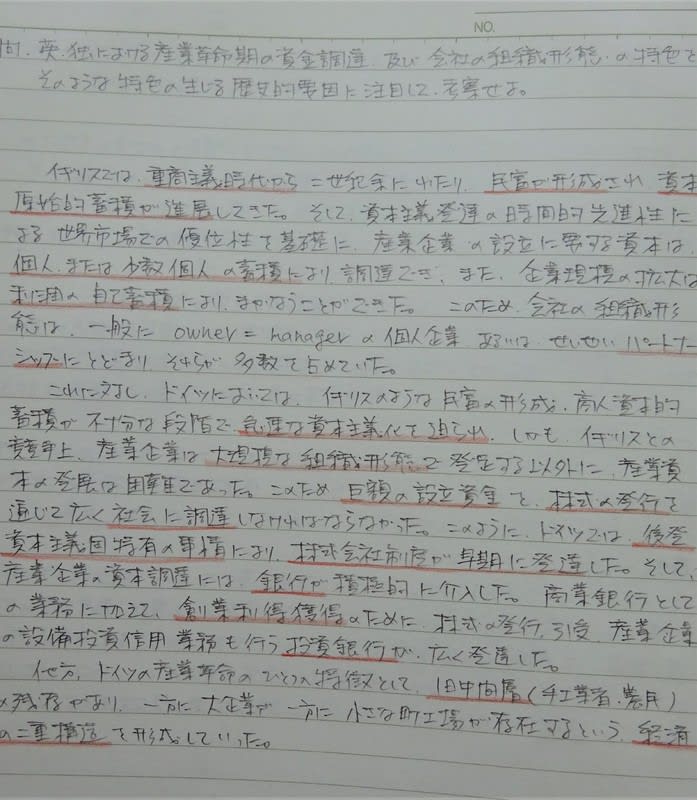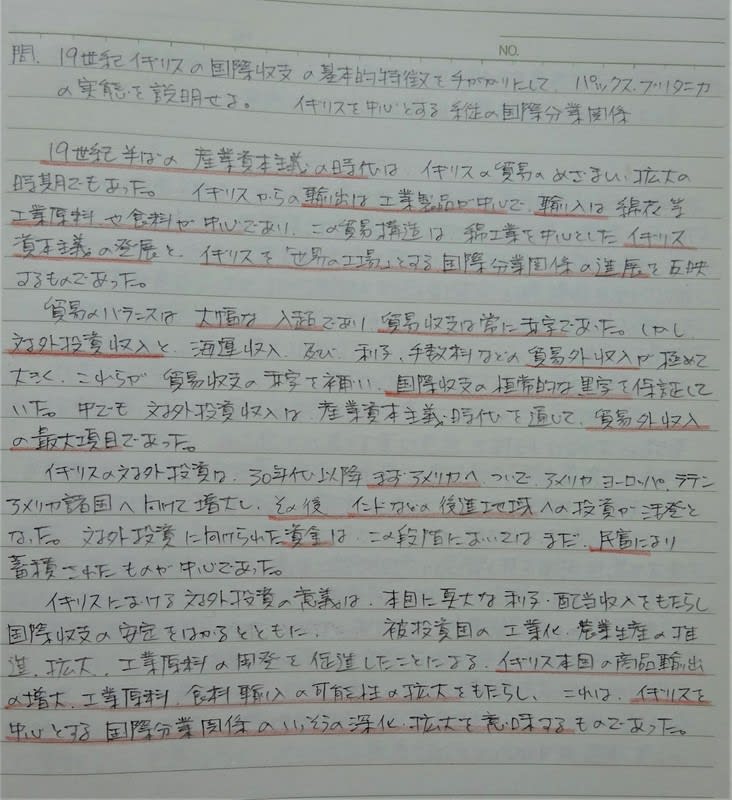(冒頭写真は、2025.02.15付 朝日新聞記事「冥王星『キス』で衛生獲得?」より転載したもの。)
早速、当該朝日新聞の一部を以下に要約引用しよう。
ハート形の地形を持つ冥王星は、衛星カロンを短い「キス」にって獲得した可能性がある。 米アリゾナ大などの研究チームが、ユニークな衛星獲得シナリオを科学史ネイチャー・ジオサイエンスに発表した。
冥王星は太陽系の外縁にある準惑星。 カロンは冥王星に5つある衛星のうち最大で、半径は冥王星の半分ほどあり、衛星としては非常に大きい。 ただ、衛星がどのように形成されたのかよくわかっていない。
アリゾナ大学のアディーン・デントン博士(惑星地球物理学)らは、冥王星とカロンを、実際の組成である氷と岩石の強度を考慮したモデルとして考え、太陽系が生まれた約46億年まえのじょうたいをシミュレーションした。
その結果、二つの天体が穏やかにくっつき、雪だるまのような形で一緒に回転し、その後離れていき、今の状態になったことがわかった。 デントンさんはこのシナリオを「キスと捕獲」と表現し、キスは最大15時間ほど続いたとみている。
月は巨大な天体が地球に衝突し、飛び散った残骸が集まって生まれたとされる。 ただ、冥王星とカロンは、お互い無傷で存続できたようだ。
太陽系の外縁部には、冥王星とカロンのようなペアが数多く見つかっており、同じシナリオで誕生したのではないか、と研究チームはみている。
(以上、朝日新聞記事より引用したもの。)
原左都子の感想に入ろう。
私が遠い昔(今からおよそ60年程前の時代)に理科の授業にて受けた「天文学」(それほどの名を名乗れるほどの分野として未だ進化していない時期に、私はそれを学んだ記憶があるが…)の事を思い浮かべるのだが。
その当時には、太陽系惑星の一番外側の惑星である「冥王星」に関しては解明が遅れていて。
「冥王星」だけは、他の惑星とは別建ての扱いで、そんな名の惑星が存在する、程度の授業内容だったと記憶している。
あれ(我が小学生時代)から、既に60年以上の年月が経過した現在では。
その冥王星が衛星を獲得した、との歴史的発見を語れる時代に進化している事実に 恐れ入るし、拍手を贈りたいものだ!!
しかもその冥王星が 衛星である「カロン」を獲得していて、その写真映像がこれ程(冒頭写真を参照下さい。)までに鮮明リアルに撮影されている事実に驚くばかりである!!
まったくもって、世の科学研究の進化を嬉しく思えるこんなニュースに触れることが叶う、奇跡とも言えそうな学問分野の発展に拍手だ!!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
最後に別件に移り申し訳ないですが。
明日、先だって亡くなったばかりの義母の葬儀をごく少人数の家族葬にて実行します。
火葬を実施する訳ですが。
義母は、どんな星に生まれ変わるのかな、なんて。
少しはロマンを持って、義母の死後を見つめてみたい思いになりました。
綺麗に夜空にキラキラ輝く星に生まれ変われるといいですね、お義母さん!!