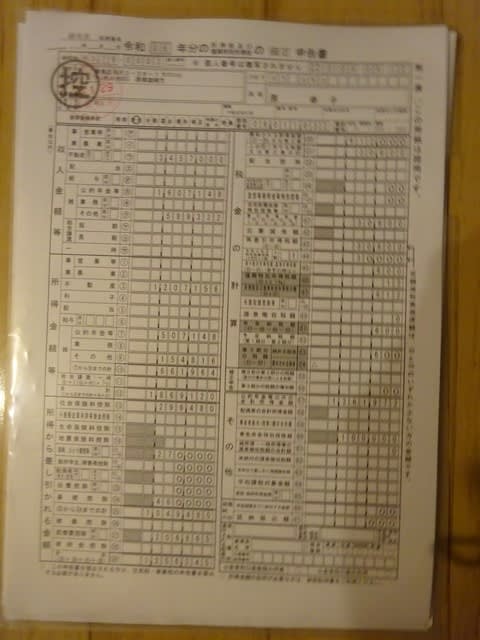かく言うこの原左都子は「終身雇用」に身を浸すことなく、自ら主体的に職業チャレンジを幾度も成しつつ今までの人生を歩んできた人材であると言えよう!!
国立大学医学部出身の私であり、新卒当時のうら若き時代には我が専門の医学業務がより取り見取り放題に存在する時代背景だった。
そんな私がチャレンジしたのは、郷里を捨て上京して医学業務に励むとの選択だった。
これが、大正解!!
とにかく好奇心旺盛な私は、医学業務はもちろんの事。 大都会・東京にて遊び放題、好き放題の天真爛漫な生き方を主体的に成したものだ。
そんな暮らしに多少飽きが来る30歳直前期に、私は自身の経済力一本で首都圏に単身で暮らすマンション物件を買い求めると同時に。
2度目の大学入学との思い切ったチャレンジをした。
生活費に関しては、大学長期休暇時に医学業務を集中的に頑張ったり、また夜間はラウンジコンパニオンをしつつ、生活費を稼いだ。 これらの経験も、我が新たなキャリアとして人間の幅を広げるのに大いに役立った。
晩婚ながら37歳にて婚姻に至り、38歳で一女をもうけ。
しばらく育児に励みつつも娘幼稚園時に医学業務に舞い戻り、理化学研究所にて医学実験に励んだものだ。
それ以前の独身時代には 「高校教諭」の誘いがあり、その業務にも数年精を出した。
4年半との短期業務だったが、2度目の大学での専門を活かしつつ全く異業種分野でも活躍することが叶ったのは、我が人生において何ともラッキーだったと言えよう。
その後 (上述の如く)またもや医学業務に舞い戻り、その専門を活かして業務に励むことが叶った。
そんなこんなで 我が職業人生活はその後も面白おかしく、しかも長く続行することが叶ったものだ。
さて、話題を変えて2025.04.05付朝日新聞夕刊記事内に「変わる終身雇用 必要な備えは」と題する記事があった。
早速以下に要約引用しよう。
定年まで同じ会社で働き、老後は余生を楽しむ。 こんな人生を思い描いた人もいるのでは? でも今や、終身雇用は崩れ、長寿社会の中で老後の年金に不安が募るなど、「定年まで」の人生は終わりつつある。
会社を辞めて次のステージに進んだり、定年後も働き続けたりするため、どんな備えが必要か。
臨床心理士の広川進氏(65)に話を聞いた。
「今までうは55歳になってキャリアの終盤で不本意な仕事になっても、あと数年我慢すれば定年まで勤めることができた。 でも、これからは畑違いの仕事でかなりの期間、働くことも十分あり得ます。」
企業は激しい競争にさらされ、全ての社員を安定して雇用し続けることは難しい。 (中略)
とくに1990年代前後のバブル期に入社した人が持つ「会社への根拠のない愛」に気を付けねばならないと言う。 (中略)
では、どう備えればよいのだろうか。 最近仕事に必要なスキルを学び直す「リスキリング」という言葉もよく聞く。 (途中大幅略)
むやみに転職したり、会社を辞めたりすることをすすめるわけではない。 今の仕事を何歳までやれるか、他の部署で経験を活かせるところはないか、などを考えることが大切だと言う。 収入が減っても、別の好きなことをした方が幸せかもしれない。 そうしたことを考えるきっかけになる。」
とは言え、中高年が再就職するには勇気がいる。
そこで大切なのは「人間関係」だ。
(以下略すが、以上朝日新聞記事より一部を要約引用したもの。)
我が人生において 大きく2度転職をして。
両者共々成功したと自負している原左都子の意見を、述べさせていただこう。
職業の専門に関してだが。
確固とした専門力を誇れる分野の専門資格を(国家資格等々の形で)まずはゲットするべきと、アドバイス申し上げたい。
参考だが、原左都子がゲットした資格は主に2つだが。 両者共々「国家資格」である。
医学分野の資格は「臨床検査技師」であり、教育関連資格は「教職免許高校『社会科』『商業科』」だ。
これらをゲットしていなければ、その種にありつけない職種であるからこそ、(特に教職など)比較的高齢域に達した後に高校教育現場への教諭としての就業が難なく叶ったといえよう。
とにもかくにも「終身雇用時代」が終焉しようが、どうなろうが。
職業界にて自身の身を立てるためには。
理屈抜きで その分野の確固とした資格(特に国家資格)をゲットするのが、大いに有効な手段であろう。