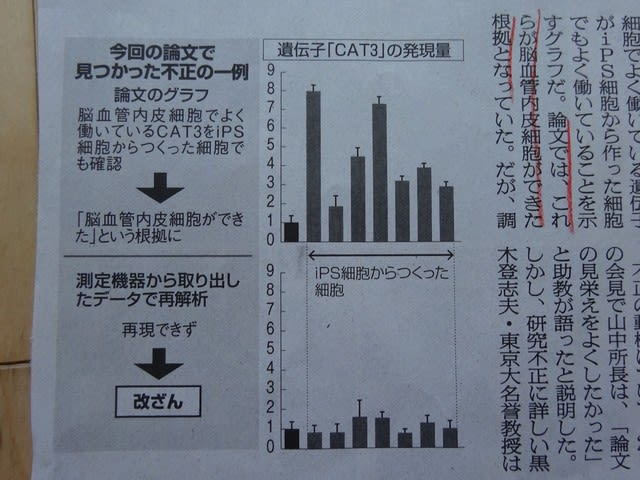上記表題に関してだが。
何もAI分野素人の私が“遊び半分”で下手に論じずとて、既に世界中のAI研究者達が類似の論文や著書を星の数ほど世に発表している事だろう。
今回のエッセイは、2018.01.22付朝日新聞記事 哲学者森岡正博氏による寄稿「AIは哲学できるか」に触発されて、我がエッセイ執筆に着手せんとするものだ。
森岡氏といえば、過去に朝日新聞紙上で若者対象の相談コーナーを担当されていた人物だ。
その当時の森岡氏の相談回答内容は、我がエッセイ集バックナンバーに於いて数本紹介している。 いずれのご回答にもほぼ賛同できた私は、ずっと森岡氏との人物を好意的に捉えさせていただいていた。
早速、森岡正博氏による「AIは哲学できるか」の内容を以下に要約して紹介しよう。
AIの進歩は目覚ましい。 囲碁や将棋の世界では、もう人間は人工知能に勝てなくなってしまった。 学者もその例外ではない。これまで学者たちが行ってきた研究が、AIによって置き換えられていく可能性もある。 特に私が専門としている哲学の場合、考えることそれ自体が仕事内容のすべてであるから、囲碁や将棋と同じ運命を辿るかもしれない。
まず、過去の哲学の思考パターンの発見は、AIのもっとも得意とするところだ。 たとえば、AIに哲学者カントの全集を読ませ、そこからカント風の思考パターンを発見させ、それを用いて「人工知能カント」というアプリを作らせることはいずれ可能になろう。 人間の研究者が「人工知能カント」に向かっていろいろ質問をして、その答えを分析することがカント研究者の仕事になると私は想像する。 この領域ではAIと哲学者の幸福な共同作業が成立する。
次に、AIに過去の哲学者たちすべてのテキストを読み込ませて、そこから哲学的な思考パターンを可能な限り抽出させてみると、およそ人間が考えそうな哲学的思考パターンがずらりと揃うことになる。 加えて、過去の哲学者たちが見逃していた哲学的思考パターンも沢山あるはずだから、AIにそれらを発見させる。
その結果、「およそ人間が考えそうな哲学的思考パターンのほぼ完全なリスト」が出来上がるだろう。 こうなるともう人間によるオリジナルな哲学的思考パターンは生み出されようがない。 将来の哲学者たちの仕事は、哲学的AIのふるまいを研究する一種の計算機科学に近づくだろう。
しかし、この哲学的AIは本当に哲学の作業を行っているのだろうか、との根本的疑問が起きて来る。 外部入力データ中に未発見のパターンを発見したり、人間により設定された問いに解を与えたりするだけならば、それは哲学とは呼べない。
そもそも哲学とは、自分自身にとって切実な問いを内発的に発するところからスタートする。 その問いに関して、どうしても考えざるを得ないところまで追い込まれてしまう状況こそが哲学の出発点なのだ。 AIは、このような切実な哲学の問いを内発的に発することがあるのだろうか。 そういうことは当分は起きないと私(森岡氏)は予想する。
しかし、もし仮に、人間からの入力がないのにAIが切実な哲学の問いを自発的に発し、ひたすら考え始めたとしたら、その時「AIが哲学をしている」と判断するだろうし、AIは正しい意味で「人間」の次元に到達したと判断したくなるだろう。
哲学的には、自由意思に基づいた自律的活動と、普遍的な法則や心理を発見できる思考能力が、人間という類の証しであると長らく考えられてきた。
AIが人間の次元に到達するためには、内発的哲学能力が必要と私は考えたい。 AIの進化により、そのような「知性」観の見直しが迫られている。 この点をめぐって人間とAIの対話が始まるとすれば、それこそが哲学に新次元を開くことになると思われる。
(以上、哲学者 森岡正博氏による「AIは哲学できるか」より要約引用したもの。)
引き続き、ウィキペディア情報より、同じくAIに於ける「哲学」に関する記述を以下に紹介しよう。
強いAIとは、AIが人間の意識に相当するものを持ちうるとする考え方である。 強いAIと弱いAI(逆の立場)の論争は、まだAI哲学者の間でホットな話題である。 これは精神哲学と心身問題の哲学を巻き込む 。特筆すべき事例として、ロジャー・ペンローズの著書『皇帝の新しい心』と、ジョン・サールの「中国語の部屋」という思考実験は、真の意識が形式論理システムによって実現できないと主張する。 一方ダグラス・ホフスタッターの著書『ゲーデル、エッシャー、バッハ』やダニエル・デネットの著書『解明される意識』では、機能主義に好意的な主張を展開している。 多くの強力なAI支持者は、人工意識はAIの長期の努力目標と考えている。
また、「何が実現されれば人工知能が作られたといえるのか」という基準から逆算することによって、「知能とはそもそも何か」といった問いも立てられている。 これは人間を基準として世の中を認識する、人間の可能性と限界を検証するという哲学的意味をも併せ持つ。
更に、古来「肉体」と「精神」は区別し得るものという考え方が根強かったが、その考え方に対する反論として「意識は肉体によって規定されるのではないか」といったものがあった。 「人間とは異なる肉体を持つコンピュータに持たせることができる意識は果たして人間とコミュニケーションが可能な意識なのか」といった認識論的な立論もなされている。 この観点から見れば、すでに現在コンピュータや機械類が意識を持っていたとしても、人間と機械類との間では相互にそれを認識できない可能性があることも指摘されている。
(以上、ウィキペディア情報より引用したもの。)
上の近い場所にあるウィキペディア情報に関して、少しだけ原左都子の私見を語らせて頂こう。
「肉体と精神は区別し得るものか」「意識は肉体によって規定されるのではないか」の論争に関してだが。
私見(と言うよりも私自身の日頃の感覚)としては、むしろ「精神」こそが「肉体」を規定している実感がある。
更には、そもそもコンピュータは「肉体」を持っているのか? との疑問と共に、コンピュータの「意識」とはあくまでも人間が与えた「意識」に過ぎないであろうとも考える。
当然の結果としてコンピュータには人間との「コミュニケーション能力」はなく、人間と機械類との間での相互認識力は無いと結論付けたい。
最後に、原左都子が今回のエッセイ表題に掲げた 「AIは“恋”ができるか 」の結論に入ろう。
その結論とは。
上記哲学者森岡正博氏による朝日新聞寄稿文内の、「哲学」を「恋」と書き換えたものとさせて頂きたく思う。
それではあまりにも“手抜き”だとのバッシングを読者の皆様より頂きそうなため、以下に少しだけ森岡氏による寄稿より「哲学」を「恋愛」に置き換え再度記載させていただこう。
過去の人間たちによる恋愛経験すべてのテキストをコンピュータに読み込ませて、そこから恋愛思考パターンを可能な限り抽出してみると、およそ人間が営んで来た恋愛パターンがずらりと揃うことになる。 加えて、過去に於ける人類の恋愛において見逃していたパターンも沢山あるはずだから、AIにそれらを発見させる。
その結果、「およそ人間が今までに成し遂げた恋愛パターンのほぼ完全なリスト」が出来上がるだろう。 こうなるともう人間によるオリジナルな恋愛パターンは生み出されようがない。 将来の人間の恋愛は、恋愛的AIのふるまいを研究する一種の計算機科学に近づくだろう。
しかし、この恋愛AIは本当に人間が成している恋愛分析作業を行っているのだろうか、との根本的疑問が起きて来る。 外部入力データ中に未発見のパターンを発見したり、人間により設定された問いに解を与えたりするだけならば、それは恋愛とは呼べない。
そもそも恋愛とは、自分自身にとって切実な問いを内発的に発するところからスタートする。 その問いに関して、どうしても考えざるを得ないところまで追い込まれてしまう状況こそが恋愛の出発点なのだ。 AIは、このような切実な恋愛の問いを内発的に発することがあるのだろうか。 そういうことは当分は起きないと私(原左都子)は予想する。
本エッセイの最後に、哲学者 森岡正博先生に対し、大変失礼なエッセイを綴り公開致しました事、お詫び申し上げます。
何もAI分野素人の私が“遊び半分”で下手に論じずとて、既に世界中のAI研究者達が類似の論文や著書を星の数ほど世に発表している事だろう。
今回のエッセイは、2018.01.22付朝日新聞記事 哲学者森岡正博氏による寄稿「AIは哲学できるか」に触発されて、我がエッセイ執筆に着手せんとするものだ。
森岡氏といえば、過去に朝日新聞紙上で若者対象の相談コーナーを担当されていた人物だ。
その当時の森岡氏の相談回答内容は、我がエッセイ集バックナンバーに於いて数本紹介している。 いずれのご回答にもほぼ賛同できた私は、ずっと森岡氏との人物を好意的に捉えさせていただいていた。
早速、森岡正博氏による「AIは哲学できるか」の内容を以下に要約して紹介しよう。
AIの進歩は目覚ましい。 囲碁や将棋の世界では、もう人間は人工知能に勝てなくなってしまった。 学者もその例外ではない。これまで学者たちが行ってきた研究が、AIによって置き換えられていく可能性もある。 特に私が専門としている哲学の場合、考えることそれ自体が仕事内容のすべてであるから、囲碁や将棋と同じ運命を辿るかもしれない。
まず、過去の哲学の思考パターンの発見は、AIのもっとも得意とするところだ。 たとえば、AIに哲学者カントの全集を読ませ、そこからカント風の思考パターンを発見させ、それを用いて「人工知能カント」というアプリを作らせることはいずれ可能になろう。 人間の研究者が「人工知能カント」に向かっていろいろ質問をして、その答えを分析することがカント研究者の仕事になると私は想像する。 この領域ではAIと哲学者の幸福な共同作業が成立する。
次に、AIに過去の哲学者たちすべてのテキストを読み込ませて、そこから哲学的な思考パターンを可能な限り抽出させてみると、およそ人間が考えそうな哲学的思考パターンがずらりと揃うことになる。 加えて、過去の哲学者たちが見逃していた哲学的思考パターンも沢山あるはずだから、AIにそれらを発見させる。
その結果、「およそ人間が考えそうな哲学的思考パターンのほぼ完全なリスト」が出来上がるだろう。 こうなるともう人間によるオリジナルな哲学的思考パターンは生み出されようがない。 将来の哲学者たちの仕事は、哲学的AIのふるまいを研究する一種の計算機科学に近づくだろう。
しかし、この哲学的AIは本当に哲学の作業を行っているのだろうか、との根本的疑問が起きて来る。 外部入力データ中に未発見のパターンを発見したり、人間により設定された問いに解を与えたりするだけならば、それは哲学とは呼べない。
そもそも哲学とは、自分自身にとって切実な問いを内発的に発するところからスタートする。 その問いに関して、どうしても考えざるを得ないところまで追い込まれてしまう状況こそが哲学の出発点なのだ。 AIは、このような切実な哲学の問いを内発的に発することがあるのだろうか。 そういうことは当分は起きないと私(森岡氏)は予想する。
しかし、もし仮に、人間からの入力がないのにAIが切実な哲学の問いを自発的に発し、ひたすら考え始めたとしたら、その時「AIが哲学をしている」と判断するだろうし、AIは正しい意味で「人間」の次元に到達したと判断したくなるだろう。
哲学的には、自由意思に基づいた自律的活動と、普遍的な法則や心理を発見できる思考能力が、人間という類の証しであると長らく考えられてきた。
AIが人間の次元に到達するためには、内発的哲学能力が必要と私は考えたい。 AIの進化により、そのような「知性」観の見直しが迫られている。 この点をめぐって人間とAIの対話が始まるとすれば、それこそが哲学に新次元を開くことになると思われる。
(以上、哲学者 森岡正博氏による「AIは哲学できるか」より要約引用したもの。)
引き続き、ウィキペディア情報より、同じくAIに於ける「哲学」に関する記述を以下に紹介しよう。
強いAIとは、AIが人間の意識に相当するものを持ちうるとする考え方である。 強いAIと弱いAI(逆の立場)の論争は、まだAI哲学者の間でホットな話題である。 これは精神哲学と心身問題の哲学を巻き込む 。特筆すべき事例として、ロジャー・ペンローズの著書『皇帝の新しい心』と、ジョン・サールの「中国語の部屋」という思考実験は、真の意識が形式論理システムによって実現できないと主張する。 一方ダグラス・ホフスタッターの著書『ゲーデル、エッシャー、バッハ』やダニエル・デネットの著書『解明される意識』では、機能主義に好意的な主張を展開している。 多くの強力なAI支持者は、人工意識はAIの長期の努力目標と考えている。
また、「何が実現されれば人工知能が作られたといえるのか」という基準から逆算することによって、「知能とはそもそも何か」といった問いも立てられている。 これは人間を基準として世の中を認識する、人間の可能性と限界を検証するという哲学的意味をも併せ持つ。
更に、古来「肉体」と「精神」は区別し得るものという考え方が根強かったが、その考え方に対する反論として「意識は肉体によって規定されるのではないか」といったものがあった。 「人間とは異なる肉体を持つコンピュータに持たせることができる意識は果たして人間とコミュニケーションが可能な意識なのか」といった認識論的な立論もなされている。 この観点から見れば、すでに現在コンピュータや機械類が意識を持っていたとしても、人間と機械類との間では相互にそれを認識できない可能性があることも指摘されている。
(以上、ウィキペディア情報より引用したもの。)
上の近い場所にあるウィキペディア情報に関して、少しだけ原左都子の私見を語らせて頂こう。
「肉体と精神は区別し得るものか」「意識は肉体によって規定されるのではないか」の論争に関してだが。
私見(と言うよりも私自身の日頃の感覚)としては、むしろ「精神」こそが「肉体」を規定している実感がある。
更には、そもそもコンピュータは「肉体」を持っているのか? との疑問と共に、コンピュータの「意識」とはあくまでも人間が与えた「意識」に過ぎないであろうとも考える。
当然の結果としてコンピュータには人間との「コミュニケーション能力」はなく、人間と機械類との間での相互認識力は無いと結論付けたい。
最後に、原左都子が今回のエッセイ表題に掲げた 「AIは“恋”ができるか 」の結論に入ろう。
その結論とは。
上記哲学者森岡正博氏による朝日新聞寄稿文内の、「哲学」を「恋」と書き換えたものとさせて頂きたく思う。
それではあまりにも“手抜き”だとのバッシングを読者の皆様より頂きそうなため、以下に少しだけ森岡氏による寄稿より「哲学」を「恋愛」に置き換え再度記載させていただこう。
過去の人間たちによる恋愛経験すべてのテキストをコンピュータに読み込ませて、そこから恋愛思考パターンを可能な限り抽出してみると、およそ人間が営んで来た恋愛パターンがずらりと揃うことになる。 加えて、過去に於ける人類の恋愛において見逃していたパターンも沢山あるはずだから、AIにそれらを発見させる。
その結果、「およそ人間が今までに成し遂げた恋愛パターンのほぼ完全なリスト」が出来上がるだろう。 こうなるともう人間によるオリジナルな恋愛パターンは生み出されようがない。 将来の人間の恋愛は、恋愛的AIのふるまいを研究する一種の計算機科学に近づくだろう。
しかし、この恋愛AIは本当に人間が成している恋愛分析作業を行っているのだろうか、との根本的疑問が起きて来る。 外部入力データ中に未発見のパターンを発見したり、人間により設定された問いに解を与えたりするだけならば、それは恋愛とは呼べない。
そもそも恋愛とは、自分自身にとって切実な問いを内発的に発するところからスタートする。 その問いに関して、どうしても考えざるを得ないところまで追い込まれてしまう状況こそが恋愛の出発点なのだ。 AIは、このような切実な恋愛の問いを内発的に発することがあるのだろうか。 そういうことは当分は起きないと私(原左都子)は予想する。
本エッセイの最後に、哲学者 森岡正博先生に対し、大変失礼なエッセイを綴り公開致しました事、お詫び申し上げます。












 私が一人で出かけようとしてもこんな事をわざわざ確認する亭主ではないのだが。 どうしたのかと思いきや。
私が一人で出かけようとしてもこんな事をわざわざ確認する亭主ではないのだが。 どうしたのかと思いきや。
 (私のマラソン大会などただの一度とて応援しに来たこともないのに。)
(私のマラソン大会などただの一度とて応援しに来たこともないのに。)