非難悔いしかさっと洒落。
(洒落本(しゃれぼん)・仕懸文庫(しかけぶんこ))(寛政期)(山東京伝(さんとうきょうでん))
[ポイント]
1.寛政期を代表する山東京伝の主著は、洒落本の『仕懸文庫』。
[解説]
1.山東京伝(1761~1816)は、洒落本をはじめ黄表紙・読本・合巻作者。江戸深川の質屋の長子で通称は京屋伝蔵。山東京伝の名は「紅葉山の東に住む京橋の伝蔵」の意味。天明期に黄表紙・洒落本の第一人者になる。
2.寛政の改革が始まると。第一人者ゆえにスケープゴート的な立場に追い込まれ、洒落本『仕懸文庫』(1791)が風俗を乱したかどで手鎖50日の刑を受けた。
3.『仕懸文庫』は鎌倉時代の仇討ちで有名な曾我兄弟を題材に、深川の遊里の交情をえがいたもの。黄表紙の代表作が『江戸生艶気樺焼(えどうまれうわきのかばやき)』(1785)。弾圧後は、敵討(かたきうち)などを題材にした合巻・読本を書き続けた。
〈2016明大・情報:「
問1 下線部ア17世紀後半の時期の説明として、もっとも正しいものを、つぎの1~4のうちから1つ選べ。
1.幕府は、糸割符制度を設けて、貿易統制を始めた
2.上方を拠点とする井原西鶴が『好色一代男』を刊行した
3.角倉了以は西廻り航路を整備し、北前船が就航しはじめた
4.江戸の山東京伝が『仕懸文庫』を著した」
(答:2)
〈2015明大・商:「
なかにはB『【1鸚鵡返文武二道 2的中地本問屋 3春色梅児誉美 4江戸生艶気樺焼 5好色一代女】』で知られる山東京伝のように自ら小間物・売薬店を営み、自分の商品をたびたび自作に登場させることで宣伝広告に邁進する作家もいた。」
(答:4)〉
〈2014大学入試センター:「
問6 下線部『北越雪譜』の著者鈴木牧之は、1770年に生まれ、1842年に没した。次の文a~dについて、この人物の生存中に起きた出来事として正しいものの組合せを下の1~4のうちから一つ選べ。
a 幕府は、風俗の乱れを取り締まるために、遊里を描いた洒落本作者の山東京伝を処罰した。
b 幕府は、天皇が幕府の許可を得ずに与えた紫衣を無効とし、これに抗議した僧を処罰した。
c 幕府は、湯島聖堂の学問所において、朱子学以外の学問を教えることを禁止した。
d 幕府は、歌舞伎が民衆に人気を博するにつれて、女性が演じることを禁止した。
1a・c 2a・d
3b・c 4b・d」
(答:1 ※b×紫衣事件は1627(寛永4)年、d×女歌舞伎の禁止は1629(寛永6)年)〉
















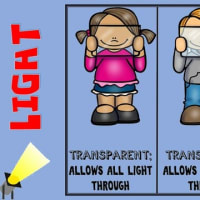


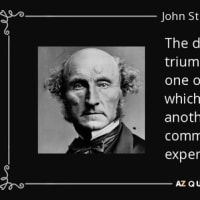






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます