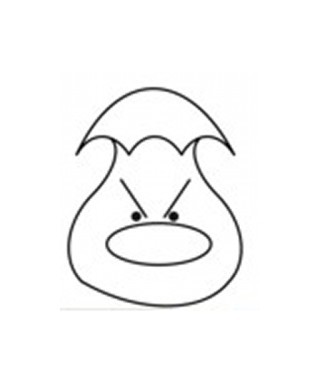まあ、科学的に否定されていることを
感情だけで言い切ってしまうと言うのは
どうかとおもいますが

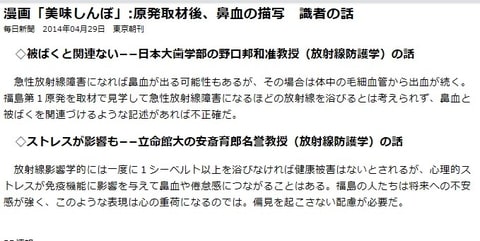
まずこの題名ですが
○○ぽとか「ぼ」って語尾につくのはあまり上品な言葉ではありません
「けちんぼ」(けちん坊吝嗇坊)、いやしんぼ
地域の人をくさして言う「水戸っぽ」「東京っぽ」
あと、差別用語で少し・・・
ここらへんから、おかしいと思ってるんですが
初期のエピソードでトゥールダルジャンで、
鴨を山葵で食う話があります
これが魯山人の著書からの引用(婉曲的な表現)であることは
明白ですが
これ、後日談じゃないですけど、同行の人が
これに関するエピソードを書いていて
鴨を見せに来るけど
それは見せ鴨で、それだけしか出てこないわけじゃない
魯山人が山葵で食ったのは胸肉だけど
その後、腿肉も出てきた
4人だったので4本
まさか、4本足の鴨でもあるまい
見せられた鴨だけじゃなくて、別の鴨も料理するんだ
と書いています
魯山人の本だけですと、結構な武勇伝なんですけど
そういった、エピソードが加わると
また違った見方が出来ます
前にノンフィクションの話をしましたが
「本人の言うことが必ずしも正しいとは限らない」
と言うのはこういうことですね
本人は記憶違いもするし
記憶を美化したりもする
手柄を独り占めする人もいる
魯山人がまだ存命だとして彼の伝記を書くとして
本人の取材から得られるのは
魯山人味道の内容と大差はないでしょう
しかし周辺のこういったことを取材すると
魯山人が迷惑なただの美食家だと言うよりは
ちょっと抜けたところのある好ましい人物に映ってきます
(ホントのところは知らんですよ)
前述のエピソードは、山葵で食ってうまかったと言う話より
それで、トゥールダルジャンのマネージャーが感心して
地下の酒蔵に案内してくれてどれでも好きなのを飲め
といってくれたと言う話と、おごりだからといって
がぶがぶ呑むなよと釘をさした
と言う部分のほうに重きが置かれているように読み取れます
この話の後半で、カツオの刺身を
マヨネーズで食うんですがそのとき登場人物が
かつおの刺身はしょうが醤油で食うんだ!それが決まりなんだ!
というんですが、江戸時代の文献を紐解くと
とき芥子を添えたそうで、山葵は帰って風味を損ねると書いてあるだけで
生姜って出てこないみたいです
ワタシはあるとき、馬刺しにからしが添えられていて
それが美味しかったので血の味の濃いカツオでやったらどうかと思い
試してみたら、美味しかったので得意満面になりましたが
元からあったと知ってがっかりしました(笑)
それと、雄山が、病気だか交通事故だかで
もてなしの指揮をとることができず主人公が
変わって指揮を執る話があるのですが
大瓶に、桜の枝を切って活けるという
大胆な飾りつけ
という描写があるのですが
これも魯山人の花見からの引用ですね
(4/14の記事でも書いたか)
これ実際の花見は、女子大の先生が来たいというから
いいよと招いたら、同行者があれよあれよの20人オーバーになって
先生はまあなんとかんるだろうと連れていったら
魯山人は「ずうずうしなぁ」とあきれながらも
もてなしてくれた、というエピソードだったと思います
なんにつけ、元になったエピソードの方が面白いというのは当たり前ですかね
わたし、美味しんぼのファンでもなんでもなくて
食堂や、風呂屋でちょっと読んだだけで
これだけ突っ込めるんですから
専門の方にはさぞ化す突っ込みどころの
多いマンガなコトでしょう
感情だけで言い切ってしまうと言うのは
どうかとおもいますが

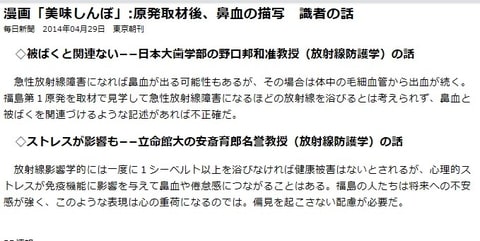
まずこの題名ですが
○○ぽとか「ぼ」って語尾につくのはあまり上品な言葉ではありません
「けちんぼ」(けちん坊吝嗇坊)、いやしんぼ
地域の人をくさして言う「水戸っぽ」「東京っぽ」
あと、差別用語で少し・・・
ここらへんから、おかしいと思ってるんですが
初期のエピソードでトゥールダルジャンで、
鴨を山葵で食う話があります
これが魯山人の著書からの引用(婉曲的な表現)であることは
明白ですが
これ、後日談じゃないですけど、同行の人が
これに関するエピソードを書いていて
鴨を見せに来るけど
それは見せ鴨で、それだけしか出てこないわけじゃない
魯山人が山葵で食ったのは胸肉だけど
その後、腿肉も出てきた
4人だったので4本
まさか、4本足の鴨でもあるまい
見せられた鴨だけじゃなくて、別の鴨も料理するんだ
と書いています
魯山人の本だけですと、結構な武勇伝なんですけど
そういった、エピソードが加わると
また違った見方が出来ます
前にノンフィクションの話をしましたが
「本人の言うことが必ずしも正しいとは限らない」
と言うのはこういうことですね
本人は記憶違いもするし
記憶を美化したりもする
手柄を独り占めする人もいる
魯山人がまだ存命だとして彼の伝記を書くとして
本人の取材から得られるのは
魯山人味道の内容と大差はないでしょう
しかし周辺のこういったことを取材すると
魯山人が迷惑なただの美食家だと言うよりは
ちょっと抜けたところのある好ましい人物に映ってきます
(ホントのところは知らんですよ)
前述のエピソードは、山葵で食ってうまかったと言う話より
それで、トゥールダルジャンのマネージャーが感心して
地下の酒蔵に案内してくれてどれでも好きなのを飲め
といってくれたと言う話と、おごりだからといって
がぶがぶ呑むなよと釘をさした
と言う部分のほうに重きが置かれているように読み取れます
この話の後半で、カツオの刺身を
マヨネーズで食うんですがそのとき登場人物が
かつおの刺身はしょうが醤油で食うんだ!それが決まりなんだ!
というんですが、江戸時代の文献を紐解くと
とき芥子を添えたそうで、山葵は帰って風味を損ねると書いてあるだけで
生姜って出てこないみたいです
ワタシはあるとき、馬刺しにからしが添えられていて
それが美味しかったので血の味の濃いカツオでやったらどうかと思い
試してみたら、美味しかったので得意満面になりましたが
元からあったと知ってがっかりしました(笑)
それと、雄山が、病気だか交通事故だかで
もてなしの指揮をとることができず主人公が
変わって指揮を執る話があるのですが
大瓶に、桜の枝を切って活けるという
大胆な飾りつけ
という描写があるのですが
これも魯山人の花見からの引用ですね
(4/14の記事でも書いたか)
これ実際の花見は、女子大の先生が来たいというから
いいよと招いたら、同行者があれよあれよの20人オーバーになって
先生はまあなんとかんるだろうと連れていったら
魯山人は「ずうずうしなぁ」とあきれながらも
もてなしてくれた、というエピソードだったと思います
なんにつけ、元になったエピソードの方が面白いというのは当たり前ですかね
わたし、美味しんぼのファンでもなんでもなくて
食堂や、風呂屋でちょっと読んだだけで
これだけ突っ込めるんですから
専門の方にはさぞ化す突っ込みどころの
多いマンガなコトでしょう