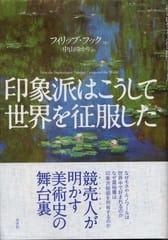
印象派は、日本では以前から人気のあるテーマであったこともあり、画集や解説書などは山のように出版されています。
ただし、どうしてあんなに高額で取引され、世界のコレクターから引く手あまたなのか…という視点から述べた本は、ほとんどないように思われます。
この本は、クリスティーズ、サザビースという二大オークション会社の競売人として活躍し、美術品流通の裏まで知り尽くした英国人が書いています。
最初は当惑と罵倒で迎えられたはずの印象派が、いかにして世界の美術市場を席捲する存在になっていくかがわかりやすくつづられているので、おもしろくないはずがありません。
おしゃれなパリの絵に早くから着目した米国、最初は無視していたが国家間の関係改善とともに受容が進んだ英国、先駆的なコレクターがいた一方で拒絶反応を示す保守派の力も強かったドイツなど、国別に事情がまとめられているのも、読みやすいです。
印象派がなぜ受けいれられるようになったのか。その究極の、決定的な理由については、さすがにこの本でも断定はしていません。
ただ、筆者がこれまで知らなかったいくつかの状況証拠については、なるほど~と思わざるをえませんでした。
ひとつは、世に出た当時は最先端の前衛だった印象派絵画も、その後20世紀に入ると、未来派だのキュビスムだのフォーブだのといったさらに過激な新潮流が続々と出現したため、それに比べれば受け入れやすいとコレクターに思われるようになったということ。
もうひとつは、カタログレゾネ(作品総目録)がしっかりしていること、だというのです。
たしかにねえ。
贋作や、別人の作品という危険性がほとんどないというのは、コレクターにとっては重要なことですよね。
終章に近いほうには、安田火災(現・損保ジャパン)や斎藤了英といった日本のプレイヤーたちも登場します。
筆者は、有名な美術ブログの「弐代目・青い日記帳」が絶賛しておられるのを読んで、この一冊を買い求めました。
賛辞にたがわぬ、おもしろい本でした。難解なところはありません。そのかわりに、愉快なエピソードが満載です。
印象派はもちろん、美術市場に興味のある方にも、イチオシ。というか、すべての美術ファンにおすすめします。
中山ゆかり訳
あき2200円+税
274ページ
2009年7月20日第1刷
白水社
ただし、どうしてあんなに高額で取引され、世界のコレクターから引く手あまたなのか…という視点から述べた本は、ほとんどないように思われます。
この本は、クリスティーズ、サザビースという二大オークション会社の競売人として活躍し、美術品流通の裏まで知り尽くした英国人が書いています。
最初は当惑と罵倒で迎えられたはずの印象派が、いかにして世界の美術市場を席捲する存在になっていくかがわかりやすくつづられているので、おもしろくないはずがありません。
おしゃれなパリの絵に早くから着目した米国、最初は無視していたが国家間の関係改善とともに受容が進んだ英国、先駆的なコレクターがいた一方で拒絶反応を示す保守派の力も強かったドイツなど、国別に事情がまとめられているのも、読みやすいです。
印象派がなぜ受けいれられるようになったのか。その究極の、決定的な理由については、さすがにこの本でも断定はしていません。
ただ、筆者がこれまで知らなかったいくつかの状況証拠については、なるほど~と思わざるをえませんでした。
ひとつは、世に出た当時は最先端の前衛だった印象派絵画も、その後20世紀に入ると、未来派だのキュビスムだのフォーブだのといったさらに過激な新潮流が続々と出現したため、それに比べれば受け入れやすいとコレクターに思われるようになったということ。
もうひとつは、カタログレゾネ(作品総目録)がしっかりしていること、だというのです。
過去の巨匠の作品は、たとえそれがどんなに重要なものであれ、画家の親筆であるかについては、常に批評にさらされる不確実性をもつ。しかし、先見の明のあったデュラン=リュエルやベルネーム=シュヌのような初期の画商たちは、自身が扱った画家たちの作品を写真記録として包括的に残しておくことにこだわった。そのおかげで、主要な印象派の画家たちの全作品の図版を収録した、反論の余地のない作品総目録をつくることが比較的容易になった。したがって、ギリシアの船主であろうが、ハリウッドの映画スターであろうが、ロンドンの不動産王であろうが、美術についてさほど詳しく知る必要もなく、ただ自らが買いたいと思えば、目にしたマネやモネ、ルノワール、シスレー、ピサロ、ドガといった画家たちの作品が本物であるかどうかを確実に知ることができるのだ。なぜといえば、作品のきちんとした記録があるからだ。ある朝起きたら突然に、イカレた研究者の一団によって、「あなたがおもちの作品は、画家本人のものではなく、その追随者によって描かれたものでした」などということを言い渡され、作品を格下げされるような可能性は印象派絵画にはなかった。だが、レンブラントの不運な所有者には、ときにはそういった出来事がおこったのである。(212~213ページ)
たしかにねえ。
贋作や、別人の作品という危険性がほとんどないというのは、コレクターにとっては重要なことですよね。
終章に近いほうには、安田火災(現・損保ジャパン)や斎藤了英といった日本のプレイヤーたちも登場します。
筆者は、有名な美術ブログの「弐代目・青い日記帳」が絶賛しておられるのを読んで、この一冊を買い求めました。
賛辞にたがわぬ、おもしろい本でした。難解なところはありません。そのかわりに、愉快なエピソードが満載です。
印象派はもちろん、美術市場に興味のある方にも、イチオシ。というか、すべての美術ファンにおすすめします。
中山ゆかり訳
あき2200円+税
274ページ
2009年7月20日第1刷
白水社



















