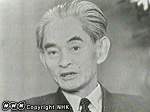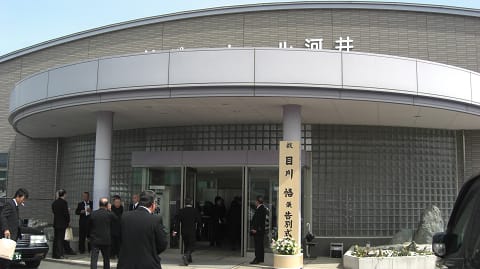恩徳讃(讃佛歌より)in光明寺~今泉ひとみ~
全く・・・春の天気は猫の目のように変わる・・・。昨日はいい天気だと思っていたら、今日は曇って肌寒い一日になった・・・。だから・・鼻水が出たり止まったり・・・。身体の調子もおかしくなるというものだ・・。
で・・、今日は高松市内へ出かけて行って、咸臨丸に乗り組んだ水夫の子孫の方を訪ねて行こうとしたんだけれど、教えてくれてた住所も電話番号も違うみたい・・・。でも、私の送った「咸臨丸と塩飽諸島」という本は届いた・・という連絡があったのだから、住所はそんなにもは違わないのだと思うのだけれど・・・。

でも、「このあたりでは、そんな方は知らないわねぇ・・」とか、「その方はずっと先の方よ~」などと・・相手にもしてくれない。最近は・・個人情報なんたらだから・・うかつに・・知っていても教えない人が多くなったせいもある・・。
確かに・・教えられた場所には・・大きな倉庫会社があったが、そんな会社に押しかける訳にもいかず・・・。倉庫会社だとは聞かされていなかったせいもあったし・・。
電話番号も少しばかり違うようで・・・呼び出し音は出るが、誰も出てはくれないし・・。ということで、今日の作業はあきらめた。

で、今日のお昼はここになった・・。高松市多肥下町になるんだろうか・・。「国安うどん」っていうお店。

ここも案外とマイナーなうどん屋さんなのか、検索エンジンでも引っかからない・・。けっこう早くから開店してるんだけれど、場所が場所なものか、どうなんだか、あんまりメジャーにはなっていないが、そこそこ・・お馴染みさんでやってるみたいなお店。

これが店内の様子。ま、一般的なお店風で、カウンター席もあればテーブル席もあって。おうどんがあがるまでに間があれば、新聞なども持ってきてくれて、細やかなサービスもある。

で、注文したのは・・きつねうどん・・。少しばかり・・マイブームかな。かけ小ばかりでは能がないし、かといって、カレーうどんばかりでもおもしろくないし。しっぽくうどんの時期は終わったし、ざるうどんの季節でもないしね・・。
で・・・。

こんな・・デザートまでサービスしてくれた。みかん系のものを寒天でかためたもの。どういう表現をすればいいものかわからんけれど。朝の間のサービスみたいだった・・。
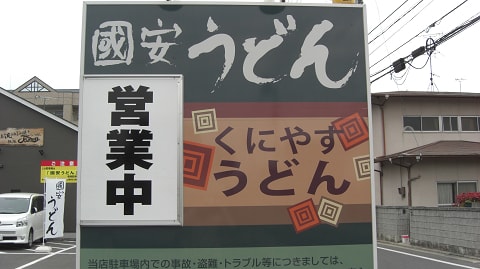
で、午後からは・・、お坊さんたちが集まっての「組内会:そないかい」という会合に出席した。ま、うちのお寺の場合、北海道教区・大和教区・阪神教区・東讃教区・西讃教区・鹿児島教区・特設中央教区という七つのブロックがあって、私らは・・「東讃教区」に属する。その東讃教区にも、十の組(班みたいなもの)がある。今日は、その「東讃第一組」、いわゆる、昔の「大川郡」に相当する地区のお寺さんの会合やね・・。

で、いつもは・「お佛讃」っていうことで、短いお経をあげるのだけれど、今日は・・「真宗宗歌」になった・・。こういうのも新鮮でいいね。最後は・・「恩徳讃」だったし。そんな話をされても、一般の人にはわからんと思うけれど・・。ま、お経ばかりではなくて、お坊さんも歌も歌うよ・・・みたいなことかな・・・。
ここの地域に、およそ十六の寺院があって、そこいらのお坊さんたちが集まって、いろんな相談をする場やね・・。

ま、ご本山の法要をどうするかだの、高松別院の修理をどうするか・・みたいなお話だとか・・いろいろやね。
先には・・塩飽本島とさぬき広島の話をして、横に動けば簡単なのに、縦・縦に動くから時間の浪費だって書いたけれど、今日は・・お坊さんたちの横と横のつながりのお話。お寺対本山・・・という縦の社会に対して、個々の寺院や僧侶らの横の連携をつなげる場。

で、ようやくに咸臨丸乗り組み水夫さんのご子孫に連絡がついて、明日の午前十時に・・今朝方に見た・・倉庫会社の事務所にお伺いすることが決まった。やはり、あの・・倉庫会社だったんだ・・。で、目が覚めたら会社の事務所に行くっていうのだから・・家に電話してもいないはずらしい・・・。働き者のやねぇ・・・。

じゃぁ、また、明日、会えるといいね。
全く・・・春の天気は猫の目のように変わる・・・。昨日はいい天気だと思っていたら、今日は曇って肌寒い一日になった・・・。だから・・鼻水が出たり止まったり・・・。身体の調子もおかしくなるというものだ・・。
で・・、今日は高松市内へ出かけて行って、咸臨丸に乗り組んだ水夫の子孫の方を訪ねて行こうとしたんだけれど、教えてくれてた住所も電話番号も違うみたい・・・。でも、私の送った「咸臨丸と塩飽諸島」という本は届いた・・という連絡があったのだから、住所はそんなにもは違わないのだと思うのだけれど・・・。

でも、「このあたりでは、そんな方は知らないわねぇ・・」とか、「その方はずっと先の方よ~」などと・・相手にもしてくれない。最近は・・個人情報なんたらだから・・うかつに・・知っていても教えない人が多くなったせいもある・・。
確かに・・教えられた場所には・・大きな倉庫会社があったが、そんな会社に押しかける訳にもいかず・・・。倉庫会社だとは聞かされていなかったせいもあったし・・。
電話番号も少しばかり違うようで・・・呼び出し音は出るが、誰も出てはくれないし・・。ということで、今日の作業はあきらめた。

で、今日のお昼はここになった・・。高松市多肥下町になるんだろうか・・。「国安うどん」っていうお店。

ここも案外とマイナーなうどん屋さんなのか、検索エンジンでも引っかからない・・。けっこう早くから開店してるんだけれど、場所が場所なものか、どうなんだか、あんまりメジャーにはなっていないが、そこそこ・・お馴染みさんでやってるみたいなお店。

これが店内の様子。ま、一般的なお店風で、カウンター席もあればテーブル席もあって。おうどんがあがるまでに間があれば、新聞なども持ってきてくれて、細やかなサービスもある。

で、注文したのは・・きつねうどん・・。少しばかり・・マイブームかな。かけ小ばかりでは能がないし、かといって、カレーうどんばかりでもおもしろくないし。しっぽくうどんの時期は終わったし、ざるうどんの季節でもないしね・・。
で・・・。

こんな・・デザートまでサービスしてくれた。みかん系のものを寒天でかためたもの。どういう表現をすればいいものかわからんけれど。朝の間のサービスみたいだった・・。
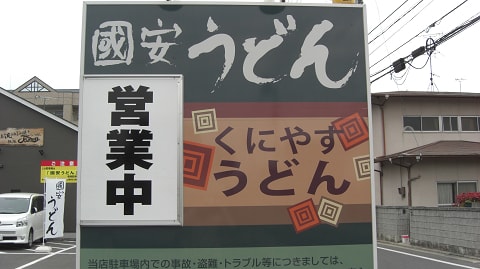
で、午後からは・・、お坊さんたちが集まっての「組内会:そないかい」という会合に出席した。ま、うちのお寺の場合、北海道教区・大和教区・阪神教区・東讃教区・西讃教区・鹿児島教区・特設中央教区という七つのブロックがあって、私らは・・「東讃教区」に属する。その東讃教区にも、十の組(班みたいなもの)がある。今日は、その「東讃第一組」、いわゆる、昔の「大川郡」に相当する地区のお寺さんの会合やね・・。

で、いつもは・「お佛讃」っていうことで、短いお経をあげるのだけれど、今日は・・「真宗宗歌」になった・・。こういうのも新鮮でいいね。最後は・・「恩徳讃」だったし。そんな話をされても、一般の人にはわからんと思うけれど・・。ま、お経ばかりではなくて、お坊さんも歌も歌うよ・・・みたいなことかな・・・。
ここの地域に、およそ十六の寺院があって、そこいらのお坊さんたちが集まって、いろんな相談をする場やね・・。

ま、ご本山の法要をどうするかだの、高松別院の修理をどうするか・・みたいなお話だとか・・いろいろやね。
先には・・塩飽本島とさぬき広島の話をして、横に動けば簡単なのに、縦・縦に動くから時間の浪費だって書いたけれど、今日は・・お坊さんたちの横と横のつながりのお話。お寺対本山・・・という縦の社会に対して、個々の寺院や僧侶らの横の連携をつなげる場。

で、ようやくに咸臨丸乗り組み水夫さんのご子孫に連絡がついて、明日の午前十時に・・今朝方に見た・・倉庫会社の事務所にお伺いすることが決まった。やはり、あの・・倉庫会社だったんだ・・。で、目が覚めたら会社の事務所に行くっていうのだから・・家に電話してもいないはずらしい・・・。働き者のやねぇ・・・。

じゃぁ、また、明日、会えるといいね。