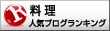14日付の日本農業新聞の一面に「有機農業法案固まる 国、地方に推進責務/超党派議連 」という見出しが踊っています。何でも、「国と地方自治体に対し、農業者や消費者らの協力を得ながら、有機農業を進めるための施策を総合的に行う責務を課す画期的な内容。」なのだそうです。
確かJAS法では「有機○○」という表現は、規格に適合するかどうか検査を受けた結果、これに合格して有機JASマークが付けられたものでなくては表示をしてはならないはず。ということは、この法律は「有機JAS」を後押しするものなのかも知れません。
個人農家が有機JASの認証を受けるためには、最低でもおよそ150,000円程度が必要になります。認証はほ場ごとなので、ほ場(畑や田んぼ)が多ければその分費用がかかります。認証を受ける機関によっては、さらに認証を受けた農産物の売り上げの0.5~0.1%を納めなければならない認証機関もあります。
また毎年検査があるので、毎年相応の負担があります。
農産物の価格はというと、べらぼうに高値という訳ではありません。
そんな状況の中で、この法律。わが家のような零細農家は、「有機」という表現を取り上げられ、さらにこの法律に沿って農業経営をしようと思ったら、JAS認証を受ける必要がある。小さな畑が点在しているわが家の場合は、認証コストは(単価×ほ場数)で見ると相当な額になる。
大規模経営をしている農場は、ほ場の面積も大きいのである意味単価を抑えることが出来ます。いま農地の集積化の動きが活発になっていますが、これも効率のよい作付けや作業のためのものだと思います。
ぐたぐた書きましたが、認証を受けなければ”有機栽培”をしていても「有機農産物」ではないし、
”有機農産物”と表現することも許されないという現状で、”有機JASに準ずる”わが家の栽培法を、「こだわり栽培」と表現しています。
記録や使用資材などの記録はきちんと保管していますので、単に認証を受けていないだけ。こんな矛盾を感じながら、有機JASを超える自主規制を策定して日々の作業をしています。
議員さんたちは議員さんたちなりに、食料確保のためいろいろとお考えなのでしょう。でももはや、”商標登録”に近い「有機農業」を何も法律の名称にしなくても良いじゃないですか。私は特定の栽培方法を奨励するのではなく、現行の栽培法の長所と短所を比較し、短所を減らすような政策があっても良いのではないかと思います。
自然や言葉というのは、特定の人のためにあるのではありません。
適切な表現とルールで、農業者や消費者を含めた関係者全体に関係のある決めごと(法律)を”食”の分野に於いては特に整備していただきたいと思います。
確かJAS法では「有機○○」という表現は、規格に適合するかどうか検査を受けた結果、これに合格して有機JASマークが付けられたものでなくては表示をしてはならないはず。ということは、この法律は「有機JAS」を後押しするものなのかも知れません。
個人農家が有機JASの認証を受けるためには、最低でもおよそ150,000円程度が必要になります。認証はほ場ごとなので、ほ場(畑や田んぼ)が多ければその分費用がかかります。認証を受ける機関によっては、さらに認証を受けた農産物の売り上げの0.5~0.1%を納めなければならない認証機関もあります。
また毎年検査があるので、毎年相応の負担があります。
農産物の価格はというと、べらぼうに高値という訳ではありません。
そんな状況の中で、この法律。わが家のような零細農家は、「有機」という表現を取り上げられ、さらにこの法律に沿って農業経営をしようと思ったら、JAS認証を受ける必要がある。小さな畑が点在しているわが家の場合は、認証コストは(単価×ほ場数)で見ると相当な額になる。
大規模経営をしている農場は、ほ場の面積も大きいのである意味単価を抑えることが出来ます。いま農地の集積化の動きが活発になっていますが、これも効率のよい作付けや作業のためのものだと思います。
ぐたぐた書きましたが、認証を受けなければ”有機栽培”をしていても「有機農産物」ではないし、
”有機農産物”と表現することも許されないという現状で、”有機JASに準ずる”わが家の栽培法を、「こだわり栽培」と表現しています。
記録や使用資材などの記録はきちんと保管していますので、単に認証を受けていないだけ。こんな矛盾を感じながら、有機JASを超える自主規制を策定して日々の作業をしています。
議員さんたちは議員さんたちなりに、食料確保のためいろいろとお考えなのでしょう。でももはや、”商標登録”に近い「有機農業」を何も法律の名称にしなくても良いじゃないですか。私は特定の栽培方法を奨励するのではなく、現行の栽培法の長所と短所を比較し、短所を減らすような政策があっても良いのではないかと思います。
自然や言葉というのは、特定の人のためにあるのではありません。
適切な表現とルールで、農業者や消費者を含めた関係者全体に関係のある決めごと(法律)を”食”の分野に於いては特に整備していただきたいと思います。