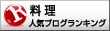開催時間は、10:30~16:30です。
”売り切れ御免”方式です。品切れの際はどうか御勘弁を!
今回も大根・カブ・春菊・みずな・ブロッコリーなど、鍋料理にピッタリの野菜がたくさんあります。
他にもルッコラやケール、島カボチャなどもあります。
種類を多くするため、少量のものもありますが味はおまかせ下さい!!
うちの子供が社会勉強の一環として店番をしていることがありますが、
きちんと指示を出してあります。値段の違いなどの心配は無用です。
場所がわからない方は、ここをクリックしてください。
直売に来られない方は、究極の直売(通信販売)をぜひご利用下さい。
野菜セットは、送料込みの2,500円です。季節のとれたて野菜をギュッと詰めてお届けします。お申込は、こちらからどうぞ!
越谷市内及び周辺地域へは、宅配をします。ぜひご利用下さい!
”売り切れ御免”方式です。品切れの際はどうか御勘弁を!
今回も大根・カブ・春菊・みずな・ブロッコリーなど、鍋料理にピッタリの野菜がたくさんあります。
他にもルッコラやケール、島カボチャなどもあります。
種類を多くするため、少量のものもありますが味はおまかせ下さい!!
うちの子供が社会勉強の一環として店番をしていることがありますが、
きちんと指示を出してあります。値段の違いなどの心配は無用です。
場所がわからない方は、ここをクリックしてください。
直売に来られない方は、究極の直売(通信販売)をぜひご利用下さい。
野菜セットは、送料込みの2,500円です。季節のとれたて野菜をギュッと詰めてお届けします。お申込は、こちらからどうぞ!
越谷市内及び周辺地域へは、宅配をします。ぜひご利用下さい!