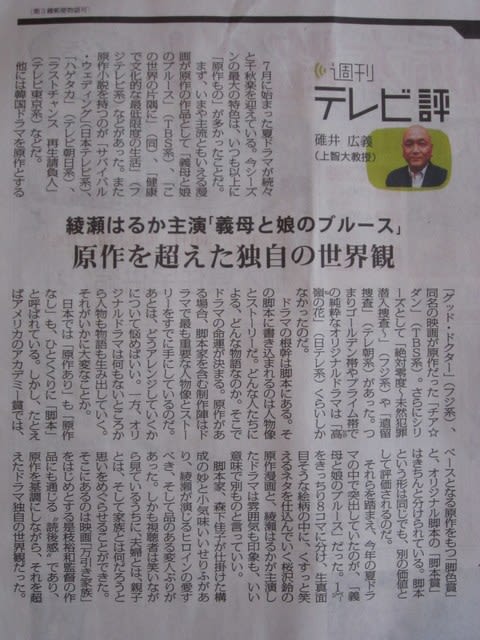<週刊テレビ評>
番組制作会社誕生50年
「創造する人」に権利と敬意を
日本でテレビ放送が始まったのは1953年だ。そして長い間、「番組を作ること」と「放送すること」の両方を放送局が行っていた。それが変わるのは70年である。番組作りのプロ集団として番組制作会社が登場してきたのだ。
その第1号が「テレビマンユニオン」だった。それまでTBSに在籍していた萩元晴彦、村木良彦、今野勉など先駆的な制作者たちが、「テレビ制作者を狭い職能的テリトリーから解放する組織」、つまり「テレビマンの組織」を創るべく退社して、日本初の独立系制作会社を興したのだ。
50年前はたった1社だった制作会社だが、現在は全国に数百社ある。業界団体の「全日本テレビ番組製作社連盟」の加盟社だけでも124社。総計1万人のクリエーターがドラマ、バラエティー、ドキュメンタリー、報道など多彩なジャンルの番組を作り続けている。
しかも、それは民放に限らない。例えばNHKの人気番組「チコちゃんに叱られる!」にも共同テレビジョンやスタッフラビといった複数の制作会社が参加している。
70年から続く「遠くへ行きたい」(読売テレビ)、86年に始まった「世界ふしぎ発見!」(TBS)、NHKの「サラメシ」などで知られるテレビマンユニオンは、来月、創立50周年を迎える。それは同時に、日本の制作会社の歴史が半世紀に達したということであり、大いに祝したい。
その一方で、制作会社が抱え続ける課題も忘れてはならないだろう。たとえば、50年前にテレビマンユニオンの創立メンバーたちが目指した、放送局との「イコールパートナー(仕事上の対等な関係)」は、どこまで実現できたのか。いわゆる「下請け構造」は過去のものになっているのか。
何より現実的な問題として、制作会社が果たしている役割とその対価(制作費)は見合ったものなのか。実際の作り手であるにもかかわらず、「制作協力」という曖昧なクレジット表記が象徴するように、著作権の帰属も、番組の関連商品化やインターネット配信など2次展開も十分に認められていないのが現状だ。
近年、テレビを取り巻く環境は激変した。今や番組はテレビ受像機だけでなく、さまざまな経路で見ることができる「映像コンテンツ」であり、「デジタルコンテンツ」である。ネットを通じて常時同時配信でさえ現実となってきた。
しかし、そんな状況下でも番組を作るのが「人」であることに変わりはない。いや、そのことがますます重要になってきた。「創造すること」と「創造する人」への敬意が、今ほど必要な時代はない。
(毎日新聞「週刊テレビ評」2020.01.18)