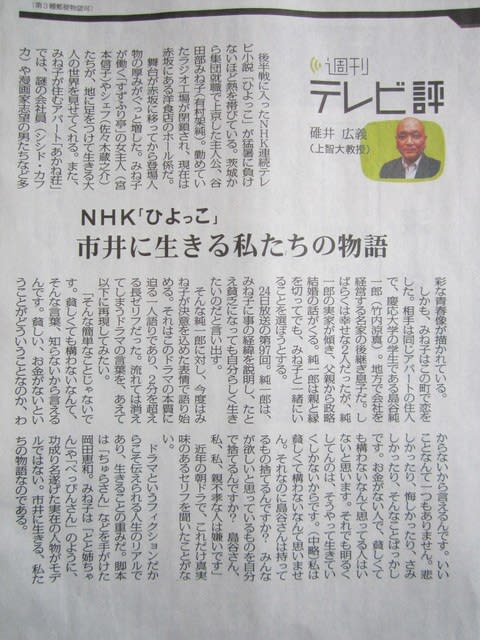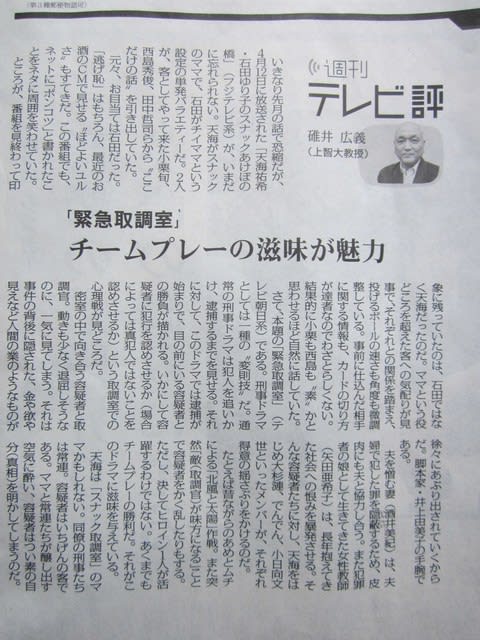週刊テレビ評
NHK「夕凪の街 桜の国2018」
73年後の広島「原爆の日」を思う
NHK「夕凪の街 桜の国2018」
73年後の広島「原爆の日」を思う
8月6日夜に放送された「夕凪(ゆうなぎ)の街 桜の国」(NHK総合)は、NHK広島放送局開局90年ドラマだ。石川七波(常盤貴子)は東京に住む編集者。リストラの対象となっているだけでなく、父親の旭(橋爪功)に認知症の疑いがあることも悩みの種だった。
ある日、旭が1人で家を出る。七波がめいの風子(平祐奈)と尾行すると、旭の向かった先は広島だった。まるで聞き込み調査のように街を歩き回る旭。やがて亡くなった姉、皆実の足跡を追っていることがわかり、ドラマの舞台は1955年の広島へと移っていく。
て働いている。同僚の打越(工藤阿須加)が彼女に思いを寄せるが、素直に受け入れることができずにいた。それは自分が被爆者だったからだ。原爆症の恐怖と、生き延びたことへの後ろめたさが常に消えなかった。
皆実が幸せを感じたり、美しいと思ったりするとき、彼女の中で原爆投下直後の地獄のような光景(市民が描いたと思われる絵が有効に使われている)がよみがえる。「お前の住む世界はここではないと誰かが私を責め続けている」というのだ。脚本の森下直は、「この世界の片隅に」などで知られる、こうの史代の原作漫画を丁寧にアレンジしながら、印象的なセリフを物語に埋め込んでいく。
打越との未来が見えた直後、皆実は原爆症で短い生涯を終えた。最期に胸の内で語る言葉は厳しく、そして切ない。「うれしい? 10年たったけど、原爆を落とした人は『やった! また1人殺せた』って、ちゃんと思うてくれとる?」
しかもドラマはここで終わらない。大人になった旭(浅利陽介)は広島の復興のために建設会社に入り、皆実を姉のように慕っていた被爆者で孤児の京花(小芝風花)を妻に迎える。それが七波の母だ。老人となった打越(佐川満男)から皆実の話を聞いた七波と風子はそれぞれに思いを巡らせる。
見終わって、あらためて痛感するのは、戦争や原爆はあまりにも多くの命を奪っただけでなく、辛うじて生き残った者たちをも長く苦しめてきたことだ。さらにこのドラマからは、そうした人たちを単なる被害者として描くのではなく、厳然たる事実と声なき声を継承し、静かに伝えていこうとする意思が感じられた。
戦後73年という長い歳月を経て、どこかぼんやりしかけていた戦争の、そして原爆の輪郭がはっきりとした像を結んだ。広島放送局の制作陣、加えて明るさと陰りの両方をみずみずしい演技で表現した川栄李奈に拍手を送りたい。
(毎日新聞 2018.08.18)