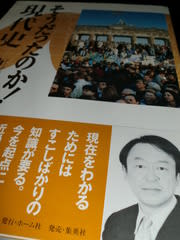ロシア文学“古典新訳”シリーズの亀山郁夫さんは、東京外語大の学長さんでもある。
近著『ドストエフスキーとの59の旅』(日本経済新聞出版社)は自伝的エッセイ。
『罪と罰』のラストが示しているのは、かりに法が罪を裁くことができるにしても、それはあくまで外形のみであり、罪人の内面まで裁くことはできないという真実である。
『罪と罰』はできるだけ早い時期に読んだほうがいいが、『悪霊』はできるだけ遅くまで読まないほうがよい。何ならいっさい手をつけずにおいてもよい、と。『悪霊』は、それほど危険な小説である。
――亀山郁夫『ドストエフスキーとの59の旅』