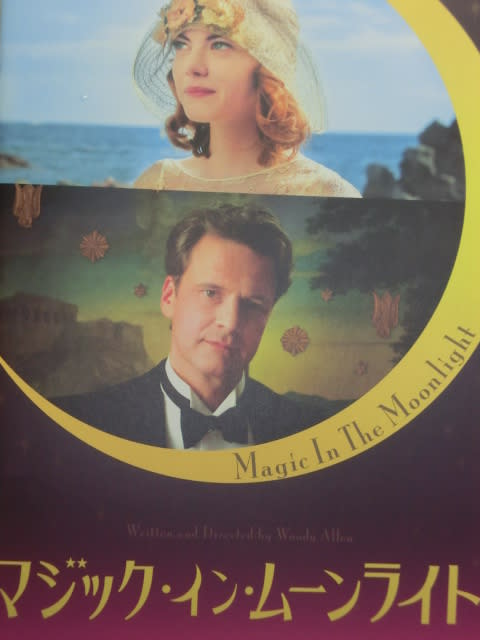ビジネスジャーナルに連載しているメディア時評、
碓井広義「ひとことでは言えない」。
今日(4月21日)は「民放の日」。
テレビの“原点”について考えてみました。
かつてのテレビは、なぜ面白かったのか
“本物”の番組は
とてつもない力を持っている!
今から30年前のことだ。当時、番組制作者だった私は、取材で広島県の尾道市にいた。朝から歩き回り、遅い昼食をとるため、一軒の食堂に入った。老夫婦がやっている店で、時間がピークを過ぎていたこともあり、客は私ひとりだった。定食を注文して待っていると、おばあさんが「いつも見ているドラマが始まる」と言って、神棚のような位置に置かれたテレビのスイッチを入れた。
ところが、画面に映ったのは見慣れたドラマではなく、まったくの別番組だった。おばあさんはチャンネルを間違えたと思ったらしく、大急ぎでカチャカチャとリモコンを操作した。ところが、どの局も同じ番組しか映らない。慌てたおばあさんは、厨房のおじいさんを呼んで助けを求めた。
その時、すぐに説明してもよかったのだ。今日、つまり4月21日が、ラジオ16社に民放初の予備免許が与えられた、1951年4月21日を記念する「放送広告の日」(現在は「民放の日」)であること。毎年この日の、この時間に、日本中のテレビ局が一斉に同じ特番を流すこと。つくっているのは私が所属していた制作会社、テレビマンユニオンで、自分がディレクターを務めているのだと。だが、結局は言わなかった。
●ローカルのユニークな番組たち
85年4月21日、午後4時から5時まで、全民放ぶち抜きで放送されていたのは、放送広告の日特別番組『民放おもしろ物語』である。日本民間放送連盟(民放連)の番組だった。
取材などで全国各地を歩いていると、その地方でしか見られないユニークなローカル番組に遭遇できるため、宿泊先でそれらの番組を見ることを楽しみにしていた。同時に、一体どんな人たちが、どんなふうにつくっているのか、ずっと気になってもいた。それが企画として実現したのだ。北海道、福井、大阪など縦断ロケを行い、それぞれの現場に密着した。
『いやはやなんとも金曜日』(福井テレビ)のプロデューサーは、東京からやって来る司会者・高田純次さんを「経費節約だ」と言って、毎週空港まで自分の車で送り迎えしていた。また、「予算はないけれど、魚は豊富」と豪快に笑い、反省会と称する番組終了後の自前の飲み会は、毎回明け方まで続いた。生放送の自社制作バラエティはハプニングの連続で、見ているほうも冷や汗をかくが、目が離せないほど面白かった。
また『夜はクネクネ』(大阪・毎日放送)の制作チームは、街で偶然出会った素人にカメラを向け、そのまま自宅までお邪魔したりしていた。収録の夜は毎回、街の中を複数のカメラマンや照明用のバッテリーを背負った技術スタッフたちが練り歩く。ちょっとした大阪名物だった。
素人と話をするのは、角淳一アナウンサーとタレントの原田伸郎さん。もちろん台本もなく、すべての展開はその場の流れ次第だ。ロケも何時に終わるのか、皆目わからなかい。そんな制作のプロセスも番組の中に取り込んでいく手法は、まさにドキュメント・バラエティーだった。
●本物をつくる
尾道の食堂では、制作者たちの奮闘ぶりがテレビから流れていた。しばらくは当惑していた店主夫妻も、途中から楽しそうに視聴している。
今この瞬間、全国のテレビ局で放送されているはずの同じ番組を、自分も旅先で見ず知らずの人たちと一緒に見ていることの不思議。「つながり」や「共有」といった大仰な話ではないが、テレビが持つ何かとてつもない力に触れた体験だった。
あれから30年。社会もメディアも大きく変化した。もちろんテレビも例外ではない。しかし、どんなに時代が変わっても、人の心が激変したとは思えない。何に笑い、何に泣き、何に感動するのか。その基本的な部分は崩れていないのではないか。目指すは、偽物ではなく本物をつくること。表層ではなく本質を伝えること。テレビだからこそ可能なトライの中に、このメディアの明日があるはずだ。
(ビジネスジャーナル 2015.04.21)