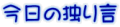【小説風 傘寿】 老いぼれコンサルタントの日記 11月1日 ◇温かい管理の源泉は【心 de 経営】 ◇考え続ける人は成長する ◇小説 竹根好助の経営コンサルタント起業
平素は、私どものブログをご愛読くださりありがとうございます。
この度、下記のように新カテゴリー「【小説風 傘寿】 老いぼれコンサルタントの日記」を連載しています。
日記ですので、原則的には毎日更新、毎日複数本発信すべきなのでしょうが、表題のように「老いぼれ」ですので、気が向いたときに書くことをご容赦ください。

紀貫之の『土佐日記』の冒頭を模して、「をとこもすなる日記といふものを をきなもしてみんとてするなり」と、日々、日暮パソコンにむかひて、つれづれにおもふところを記るさん。
【 注 】
日記の発信は、1日遅れ、すなわち内容は前日のことです。
■【小説風 傘寿の日記】
私自身の前日の出来事を小説日記風に記述しています。
11月1日
私の小学生時代の同級生のI氏が、「はじめで最後の能面展」を開催しました。
案内を頂いたこともあり、数年前のクラス会以来のことなので、訪れてみました。
仕事を抱えながら、能面作家の五指の一人といわれる石原良子氏のもとで5年間修行をしたセミプロです。
そうとは知らず、訪れて、その作品にの素晴らしさに驚きました。
「獅子口」という作品が、全国能面展で最優秀賞を受賞したそうです。
厳選された作品だけの展示ですが、能に感心も知識もない私でも、間近に見られて感動した次第です。
会場 ギャラリー椿(フィオーレの森)
川崎市高津区(溝ノ口) <無料>
*
早朝ウォーキング塗中で、体操のためによる公園のザクロがだいぶ色が濃くなり、食べられるのではないかと思っています。

コンサルタントを目指す人達の集まりで、【あたりまえ経営のすすめ】について、お話をしています。
本日は、下記のようなテーマでお話しました。
*
◆ 1-30 温かい管理の源泉は【心 de 経営】 Aa18
「管理とは、温かいモノ」という言葉が、私の口癖です。その根底に流れていますのが「心で経営」です。
では、なぜ「で」がアルファベット表記されているのでしょうか?
ご存知のとおり、「de」は、フランス語の前置詞で、発音としましては「ドゥ」に近い発音ですが、ここではローマ字式に「で」と読んでいます。
このdeは、英語の「オブ」にあたる意味あいですので、「of 経営」とみなして、それを英訳的に、うしろにあります「経営」を先に表記し、前置詞の前にある「心」に戻って全体を捉えます。すなわち経営を行う本質という意味で用いています。
一方で、deを、ローマ字式に読みますと、ひらがなの「で」ですので、「で」として表記します。「心で経営」すなわち、「心を用いて、あるいは、心ある経営」、「温かい、思いやりのある経営」ということで、人間性を重視した経営のあり方を示しています。
*
私達「人間」は、心を持つ生き物です。「感情を持つ」ともいわれます。
頭では理解できても、気持ちのほうが納得できていないという状況に直面することはしばしばあります。
心ある言葉に勇気づけられて、元気に活動できるようになることもあります。
言葉の持つ力や意味合いを重視し、相手は人間であることを忘れないで経営できる企業づくりを目指したいという思いで、私は、経営コンサルタントになって以来、心を大切にしたいという思いでやってきました。

■【今日は何の日】
当ブログは、既述の通り首題月日の日記で、1日遅れで発信されています。
この欄には、発信日の【今日は何の日】と【きょうの人】などをご紹介します。

■【今日のおすすめ】
【知り得情報】 有能なビジネスパーソンといわれる成功している人の特徴
人間、等しく生まれても、その環境や遺伝などで個性が出てきます。
学生時代優秀でも、社会に出てからうまく行かない人もいます。
では、成功しているビジネスパーソンは、われわれ凡人外床が異なるのでしょうか。

■【小説】 竹根好助の経営コンサルタント起業
私は、経営コンサルタント業で生涯現役を貫こうと思って、半世紀ほどになります。しかし、近年は心身ともに思う様にならなくなり、創業以来、右腕として私を支えてくれた竹根好助(たけねよしすけ)に、後継者として会社を任せて数年になります。
竹根は、業務報告に毎日のように私を訪れてくれます。二人とも下戸ですので、酒を酌み交わしながらではありませんが、昔話に時間を忘れて陥ってしまいます。それを私の友人が、書き下ろしで小説風に文章にしてくれています。
原稿ができた分を、原則として、毎週金曜日に皆様にお届けします。
【最新号】
https://blog.goo.ne.jp/keieishi17/e/e0049546a2cb2a1d23abfb6846dcea76
【これまでのお話】 バックナンバー
https://blog.goo.ne.jp/keieishi17/c/c39d85bcbaef8d346f607cef1ecfe950

■【経営コンサルタントの独り言】
その日の出来事や自分がしたことをもとに、随筆風に記述してゆきます。経営コンサルティング経験からの見解は、上から目線的に見えるかも知れませんが、反面教師として読んでくださると幸いです。
*
■ 考え続ける人は成長する
経営コンサルタントとして成功する人としない人の違いは何か、ということを考えることがあります。
かつては、「頭が良い人」が成功しているのではないかと思い込んでいました。ところが、頭の良い人というのは、あれこれと考えすぎてしまうのか、成功しているコンサルタントというのは、学歴が低かったり、有名国立大学卒でなかったりという人が多いのです。
また、「一芸に秀でる人は、多芸に通ず」という茅誠司先生の名言がありますが、このような人も、経営コンサルタントとしてはあまり成功していません。コンサルタントというのは、アイデンティティが明確である必要があり、このような人は、なんでもできてしまうので、専門性が薄れて見えてしまうのです。
*
サラリーマン時代に、デスクの上が、整理整頓できている人に仕事ができる人が多いと感じたことがあります。デスクの上が整理・整頓されていますと、気分がいいです。それが仕事への意欲を高めてくれているように思えます。
一芸に秀でる人は、多芸に通じるので、頭の中がごちゃごちゃになってしまっているのではないでしょうか。
真に頭の良い人は別にして、大半の頭の良い人の頭の中も、机の上の整理・整頓ができていないように、頭の中も整理・整頓ができていないのではないでしょうか。
*
「頭の良い人」として、ここでは「真に頭の良い人」は除いて考えます。
頭の良い人というのは、ちょっとうまく行かなかったり、想定通りに進まなかったりすると、考えすぎて、「これはうまく行かない案件なのだ」と、考えてしまうのではないでしょうか。すなわち先が見えすぎて、リスクを早めに感知して、リスク回避行動を起こしてしまうのではないでしょうか。
「自分は高い能力を持っていない」と思っている人は、成長の可能性が残されています。そのような人は、自分を過信していません。ですから、ビジネスがうまくいかなかったとしても「いつものこと」としてとらえることができます。それで終わりにしてしまう人は成長がストップします。
うまく行かなかったときに「では、どうするか?」と考える人は、うまくいかないことの改善策・善後策を考えるので、前進していくのです。
*
■ 1メートルの決め方 b01
1952(昭和27)年に日本でメートル法が適用されるようになりました。
その経緯は、国際標準に合わせて日本も近代国家の道を歩み、先進国の仲間入りをしようということにあります。
世界中が、メートル法を用いるように切り替えをしました。
ところが、アメリカだけは、ヤード・ボンド法から抜けきれません。
世界一のアメリカがなぜ、馴れないメートル法を使わなければならないのだ、という傲慢さから、いまだにヤード・ポンド法を使っています。
道路標識もヤード・ポンド法とメートル法の両方が併記されています。
ところが、私がアメリカに駐在していた1970年代というのは、まだマイル表示でした。
カナダに入るとメートル法表記になるという現象があったのです。
*
ところで、1メートルはどのように決められ、メートル原器はどこにあるのでしょうか?
1メートルは地球の円周の40万分の1を基準として決められたといわれています。
しかし、18世紀末に正確に算出する技術があったのでしょうか?
*
1983年(昭和58年)に基準が見直され、現在は1秒の 299792458 分の1の時間に光が真空中を伝わる距離として定義されています。(Wikipedia)

■【老いぼれコンサルタントのブログ】
ブログで、このようなことをつぶやきました。タイトルだけのご案内です。詳細はリンク先にありますので、ご笑覧くださると嬉しいです。