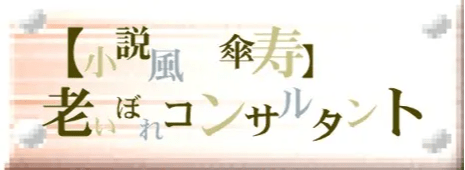【日本庭園を知って楽しむ】4-03 自然風景式庭園 - 代表的な浄土式庭園
若い頃からひとり旅が好きで、経営コンサルタントとして独立してからは、仕事の合間に旅をしたのか、旅行の合間に仕事をしたのかわかりませんが、カメラをぶら下げて【カシャリ! ひとり旅】をしてきました。
*
旅のテーマは寺社や庭園めぐりです。
*
日本には「日本庭園」と呼ばれる庭園だけではなく、「イングリッシュガーデン」など、海外の庭園形式をした庭園も多数あります。寺社を訪れたときに、想定していなかったところに、庭園を発見することがあります。
下手の横好きで、【カシャリ! ひとり旅】を続けていますが、その一環で訪れた庭園を順次紹介してまいりたいと思います。
*
■■4 三分類法による日本庭園の鑑賞法
既述の通り、ここでは、日本庭園を自然風景式庭園、枯山水庭園、露地庭園という三分類を核にしてご紹介します。
すでに紹介済みであった内容と重複することもありますが、その三分類をさらに細分化したり、切り口を変えたりして、初心者なりの鑑賞法をご紹介します。専門家の先生方には侮蔑されるかも知れませんが、私なりの分類法をご紹介して参ります。
なお、本章でのご紹介は、コトバンク、Wikipediaや上述の宮元健次氏等々を参考にし、宮元健次氏の分類法をもとに、初心者が独断と偏見に基づいた内容です。また、当ブログですでに紹介した内容を繰り返し掲載することもあります。勝手ながら、正式な情報は、読者の皆さんのお考えに基づいてお探し下さると幸いです。
*
■4-03 自然風景式庭園 - 代表的な浄土式庭園
各地の主な浄土式庭園を【Wikipedia】をもとに列記しておきますので、参考にしてみてください。
毛越寺(岩手県平泉町) - 特別名勝、世界遺産
観自在王院(岩手県平泉町) - 名勝、世界遺産
無量光院(岩手県平泉町) - 世界遺産
白水阿弥陀堂(福島県いわき市) - 国宝
円成寺(奈良県奈良市) - 名勝
平等院(京都府宇治市) - 名勝、世界遺産
浄瑠璃寺(京都府木津川市) - 特別名勝
*
前項で代表的な浄土式庭園を紹介しました。これ以外にも多数ありますが、その中でも、特徴的な庭園をいくつか見て行きましょう。
*
◇鳥羽離宮
鳥羽離宮(とばりきゅう)は、11世紀、院の近臣である藤原季綱が鳥羽の別邸を白河上皇に献上しました。およそ80年間にわたり造営されましたが、離宮としては現存していません。今日では、鳥羽上皇が利用していました鳥羽離宮の東殿が、安楽寿院としてその姿を見ることができます。邸内に自らの墓所として三重の塔を中心とした安楽寿院を造営したのです。
ここは、平安京の南、現在の京都市南区上鳥羽、伏見区下鳥羽・竹田・中島の付近で、朱雀大路の延長線上にありました。鴨川と桂川の合流地点で、風光明媚な土地にあり、従来からも別荘地として知られています。
この地に東西1.5キロメートル、南北1キロメートルの区域を占めた離宮が造営されました。池は東西6町、南北8町あり、池に数個の中島が浮かんでいました。白河院が自慢にしていた庭園で、池を中心に南殿、北殿などの住宅と安楽寿院などの堂塔が同居した浄土形式の構成でした。
12世紀から14世紀頃まで代々の上皇により使用されていた院御所で、鳥羽殿(とばどの)・城南離宮(じょうなんりきゅう)とも呼ばれていました。
鳥羽離宮は、南殿・泉殿・北殿・馬場殿・東殿・田中殿などから構成されています。それぞれの御所には、御堂が付属していました。
安楽寿院の木造阿弥陀如来坐像などが国の重要文化財に指定されているほか、1977年から1991年までの発掘調査で発見された出土品300点以上が「鳥羽離宮金剛心院跡出土品」として、京都市指定有形文化財に指定されています。
*
◇平泉の浄土式庭園
浄土形式の建築と庭は、12世紀初期には、京都だけではなく、遠く離れた東北の平泉にも造られ、今も庭園の遺跡をとどめています。
中尊寺や藤原基衡のつくった毛越寺は、比較的原形をとどめ、新たに石組みも発掘されています。また基衡の夫人がつくった観自在王院、娘のつくった白水阿弥陀堂は、庭園を発掘復原して公開されています。
*
◇そのほかの浄土式庭園
そのほかに特筆すべき庭園としては、藤原道長の法成寺、藤原頼通の平等院などが挙げられます。また阿弥陀堂の東面に池が掘られるという浄瑠璃寺も忘れることができません。
平安時代中期には池亭をはじめとして法界寺、法勝寺、末期には鳥羽院殿、法金剛院、円成寺、法住寺殿、鎌倉時代には永福寺(ようふくじ)、北山殿、称名寺など、多数あると言えます。
*
(【Wikipedia】、重森完途氏・コトバンクを参照して作成)
*
■ 日本を代表する庭園
都道府県別
リスト http://www.glomaconj.com/butsuzou/meisho/indexmovie.htm
- 写真・旅行
- 【カシャリ!ひとり旅】 北海道
- 【カシャリ! ひとり旅】 青森
- 【カシャリ! ひとり旅】 岩手
- 【カシャリ! ひとり旅】 秋田
- 【カシャリ!ひとり旅】 福島
- 【カシャリ!ひとり旅】 宮城県
- 【カシャリ!ひとり旅】 山形県
- 【カシャリ!ひとり旅】 茨城
- 【カシャリ!ひとり旅】 埼玉
- 【カシャリ!ひとり旅】 群馬県
- 【カシャリ!ひとり旅】 神奈川県
- 【カシャリ!ひとり旅】 東京散歩
- 【カシャリ!ひとり旅】 静岡県
- 【カシャリ!ひとり旅】 山梨県
- 【カシャリ!ひとり旅】 兵庫
- 【カシャリ!ひとり旅】 京都
- 【カシャリ!ひとり旅】 北陸
- 【カシャリ!ひとり旅】 九州
*
![]()
ユーチューブで視る 【カシャリ!庭園めぐりの旅】
写真集は、下記URLよりご覧いただくことができます。
静止画: http://www.glomaconj.com/butsuzou/meisho/indexmeisho.htm
映像: http://www.glomaconj.com/butsuzou/meisho/indexmovie.htm
【 注 】 映像集と庭園めぐりは、重複した映像が含まれています