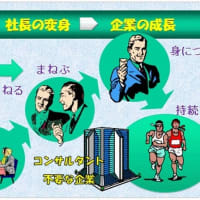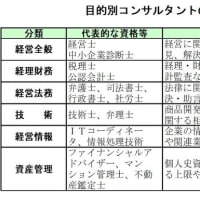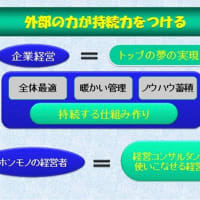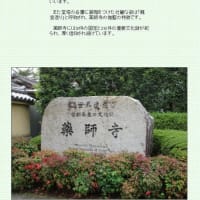■■杉浦日向子の江戸塾 34 江戸時代にアイシャドーがあった
江戸のエコや風俗習慣などから、現代人は、エコという観点に絞っても学ぶところが多いと思っています。杉浦日向子の江戸塾から学ぶところは多く、話のネタとなります。エッセイ風というと大げさになりますが、独断と偏見で紹介してみたいと思います。
私がはじめて杉浦日向子女史を知ったのは、「お江戸でござる」というNHKの番組でした。お酒が好きで、飾らない人柄、江戸時代に生きていたかのような話しぶり、そこから江戸のことを知ると、われわれ現代人に反省の機会が増えるような気がします。
■■ 江戸時代にアイシャドーがあった 34-60-1307
吉原へ行くときに、男はずいぶんファッションに気を遣ったようです。なにしろ外見で値踏みされるのですから当然でしょう。
髭の先からつま先まで、練りに練ったといわれています。ファッション・コーディネーターよろしく、指南役がいるのです。
また、事前にジョークを仕入れておきます。中には手帳もどきモノをもっていて、20ものジョークを書いておいたそうです。その中で、花魁がいくつくらい喜んでくれるのかを楽しみ行くのです。
本多髷(まげ)という髪型が流行していました。「本多にあらずば通人にあらず」といわれる程でした。
中剃りを耳のぎりぎり上まで剃りあげて薄く盛り上げる結い方です。耳の上がバーコードのようになるのだそうです。細い鶴の足のような髷を、鼠の尻尾のようにして、頭頂部にたらすのです。近年では珍奇に見えるのか、最先端に見えるのか解りません。
そろそろと、すり足で歩かないと崩れてしまうほどだそうです。
眉毛は抜きあげて、細くし、剃った額に、青黛(せいたい)という顔料です。現代のアイシャドーに相当するようで、それをべったりと塗るのだそうです。それも剃ってすぐというのは粋ではなく、二日目くらい経って、ビロード状に生えた頭がカッコいいのだそうです。
■ 「杉浦日向子の江戸塾」バックナンバー ←クリック
杉浦日向子女史の江戸塾は、江戸時代のエコ生活から飽食時代を迎えている我々に大きな示唆を与えてくれます。