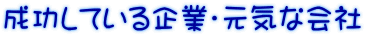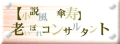【経営コンサルタントのお勧め図書】 明るい未来を語る国家戦略 日本を守る 強く豊かに
【経営コンサルタントのお勧め図書】 明るい未来を語る国家戦略 日本を守る 強く豊かに
『「日本を守る 強く豊かに」―次世代の日本を築くための政策を訴えるー』
(高市 早苗著 ワック文庫)
出版社 : ワック 新書 : 232ページ
発売日 : 2024/9/21
ISBN-10 : 4898319076
ISBN-13 : 978-4898319079
![]()
■ 総裁選で高い評価を得た、著者の明るい未来の国家戦略をみる(はじめに)
今月のおすすめ本は、次の首相を決める自由民主党の総裁選において、決選投票で敗れたものの、第1回投票ではトップに立った、著者・高市早苗の国家戦略についての著書です。
今回の総裁選の候補者9人の中で、日本の未来を俯瞰的に語っていたのは、著者、高市早苗です。著者が画く日本の未来を、紹介本から見てみましょう。紹介本と併せて、紹介本の集約版である、2024年9月9日に著者が総裁選の出馬表明に当たり発表した、政策集も見てみましょう。
(著者の出馬表明に当たり発表した政策集は以下URLを参照下さい。)
https://sosaisen.sanae.gr.jp/policycontent/#policy
ところで、私達コンサルタントは、経営戦略策定に於いて、PEST(Politics、Economy、Society、Technology)分析を行います。著者の示す政策は、今後の日本企業の経営に、良い意味で、大きな影響をもたらすことは間違いありません。その様な意味において、PEST分析の視点から、著者の政策を見てみたいと思います。
著者の政策・国家戦略を、より正しく理解するために、著者の国家戦略を、マネジメントの基本である、「理念、ビジョン、戦略、戦術」に纏めてみました。以下URLの〔図1〕を参照下さい。
URL: http://www.glomaconj.com/joho/keiei/sakai20241126-1takaichi.pdf
纏めてみて、著者の国家戦略は素晴らしいことが解ります。理念、ビジョン、戦略、戦術が「エコシステム」的に繋がっており、政策の実現性は極めて高いと期待できます。総裁選に立候補した他の8名の候補者の方々で理念、ビジョン、戦略、戦術を体系的に示せたのは著者だけでした。
著者のこの素晴らしい国家戦略は6つPOLICY(分野戦略;実行計画)として表現されています。『①大胆な「危機管理投資」と「成長投資」で「安全・安心」の確保と「強い経済」を実現』『②「全世代の安心感」を、日本の活力に』『③「防衛力」と「外交力」の強化で、日本を守る』『④「令和の省庁再編」に挑戦する』『⑤今を生きる日本人と次世代への責任を果たす』『⑥信頼される自民党、強い自民党へ』の6つです。(詳細は〔図1〕を参照ください。)
6つのPOLICYの中の<POLICY1>『大胆な「危機管理投資」と「成長投資」で「安全・安心」の確保と「強い経済」を実現』政策から、「危機管理投資」と「成長投資」について次項で見てみましょう。![]()
■ 明るい日本の未来を築く、「危機管理投資」と「成長投資」
著者の考えは、「危機管理投資」と「成長投資」に国家が積極的に投資を行い、経済安全保障を確保しながら、同時に、経済を活性化させ、強い日本を創り上げる好循環を創出しようとの発想です。その好循環における、スタートライン的な位置づけである、「危機管理投資(PLAN1~PLAN5)」と「成長投資(PLAN6)」に焦点を当ててみましょう。
詳細は、〔図1〕のP4~P6の『「POLICY1」を達成するための「戦術・行動計画;PLAN1~PLAN6」』を参照下さい。
【食糧安全保障の確立(PLAN1)】
著者は、日本の食料自給率は、カロリーベースで38%であり、世界の食料需要増加とサプライチェーン・リスクを考えると、農林水産業・食品産業を成長産業に発展させ、安定的に安全な食料を確保出来る様にする必要があると主張します。
対応政策として、中山間地域も含め全ての田畑をフル活用できる環境作りのために、耕作放棄地解消対策、新規就農者支援、鳥獣被害対策などを講じ、持続的な食料供給の仕組みの導入を提言します。
また、天候に左右されず、自然災害に強く、閉鎖した工場や学校・空き店舗・宇宙でも農作物の生産が可能な、従来型の5倍の生産性を誇るモジュール型の「完全閉鎖型植物工場」や、気候変動に影響されずに水産物を供給する「陸上養殖」の普及に向けて、高額な初期投資に対して、国による支援の強化を提言します。
【エネルギー・資源安全保障の強化(PLAN2)】
著者は、日本のエネルギー自給率は、12.6%で、データセンター等の増加による電力消費量の急増は、大きな懸念事項であり、米・カナダ等でさえ対応策を打っていると指摘します。日本においても、特別高圧の電力を「安定的に」「安価に」供給できる対策を講じなければ、日本の立地競争力は弱くなり、円高で海外に転出した企業の国内回帰も困難になると指摘します。
この、エネルギー安全保障への対応として、2020年代後半に向けては、軽水炉に比べ、小型化による安全性と経済性の向上が期待されるSMR(小型モジュール炉)や、高温ガス炉など「次世代革新炉」に関する取組を支援し、2030年代に向けては、「核融合炉(ウランとプルトニウムが不要で、高レベル放射性廃棄物が出ない高効率発電設備)」の実装を、着実に推進すべしと提言します。
また、様々な産業に欠かせない重要鉱物については、国際情勢や地政学リスクに左右されない「国産資源開発」についても積極的な投資が必要であると指摘します。
この、資源安全保障については、戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)で取り組んできた南鳥島海域のレアアース泥の、探査・採鉱・ 揚泥・製錬まで一連で行うシステム技術の開発を急ぎ、また、日本のEEZ及び公海における海底熱水性硫化物鉱床、コバルトリッチクラスト、マンガンノジュールについて、採鉱・揚鉱、選鉱・製錬、等の取組を推進すべしと提言します。(南鳥島とEEZについては下記URLの〔図2〕「海洋における危機管理投資と宇宙における成長投資」を参照ください。)
URL: http://www.glomaconj.com/joho/keiei/sakai20241126-2takaichi.pdf
【「現在と未来の生命」を守る『令和の国土強靭化計画』(PLAN3)】
首都直下地震で855兆円、南海トラフ地震で1541兆円。土木学会が試算した被害額です。著者は、このような甚大な被害額を念頭に、「事前防災」と「事後防災」強化の必要性を強調します。また、気候変動による自然災害も激甚化しており、「現在と未来の生命」を守ることが何よりも大切とします。
これらを踏まえ、現行の『防災・減災、国土強靭化のための5か年加速化対策』は令和7年度までなので、防災科学の知見も活用し、気候リスク管理も含めた有効な後継計画の策定を提言します。
また、集合住宅の老朽化対策に着手するとともに、全国に900万戸以上ある空き家対応は、防災・防犯上の課題とし、都市再生機構(UR)を中心に、街作りと併せて「買取り」「改築」「管理・売却の代行」を一体的に行える制度の構築を提言します。
【サイバーセキュリティ対策の強化(PLAN4)】
著者は、国民の生命、金融資産、個人情報などを守り抜くために、サイバー防衛力を世界最高水準に引き上げていくことを掲げます。同時に、高度なセキュリティとアフターケアを備えた製品・サービスの開発を促進し、国内や友好国に展開することによって、経済力の強化も期待できるとします。
具体的には、「能動的サイバー防御(ACD;Active Cyber Defense)」を可能にするための法制度整備を急ぐとともに、「復旧(レジリエンス)方針」の策定を提言します。高度なサイバー攻撃に対応するAIを用いた技術、衛星量子暗号通信、耐量子暗号技術などの研究開発を加速するとともに、早急な人材育成を提言します。加えて、昨今の情報戦では、偽情報やサイバープロパガンダによる認知領域への攻撃が重大な脅威となっており、国民を守るための法制度整備とともに、偽情報を検知・分析・評価する技術の開発の促進を提言します。
【健康医療安全保障の構築(PLAN5)】
著者は、経済安全保障担当大臣として、原材料の殆どを海外に依存していた抗菌性物質製剤を「特定重要物資」に指定し、国産化に向けた取組を始めました。また、科学技術政策担当大臣として、AMED(日本医療研究開発機構)による「創薬力の強化」「治療方法の研究」「医療機器開発」などに取り組んできました。ワクチンや医薬品の開発・生産は、海外情勢に左右されてはならず、安全保障に関わる課題であり、原材料・生産ノウハウ・人材を国内で完結できる体制の構築を提言します。
【成長投資の強化(PLAN6)】
著者は、日本に強みがある多くの技術の社会実装とともに、勝ち筋となる産業分野につき国際競争力強化と、人材育成に資する国の戦略的支援の構築を提言します。
具体的には、全固体蓄電池、産業用機械・ロボット、積層造形技術、マテリアル、電磁波、電子顕微鏡、核磁気共鳴装置、超電導、宇宙(スペースデブリ除去・軌道上サービス・測位衛星・SAR衛星・ロケット等)、コンテンツ関連を含むクリエイティブ産業などの分野につき、更なる国際競争力強化と人材育成に資する国の戦略的支援の強化を提言します。
加えて、新たな技術領域(6G=Beyond 5G、生成AI、データプライバシー、自動運転、フォーメーションフライト衛星通信など)において、安心・安全・信頼性を確立しながら活用を進めるために、必要な法制度と環境の整備を提言します。
更には、「量子技術イノベーション」を進め、量子計測、量子シミュレーションなどの技術領域への国の支援を提言します。(SAR衛星については下記URLの〔図2〕「海洋における危機管理投資と宇宙における成長投資」を参照ください。)
URL: http://www.glomaconj.com/joho/keiei/sakai20241126-2takaichi.pdf
![]()
■ 総裁選1回目投票でトップの著者の国家戦略に期待。(むすび)
著者の国家戦略には多くの党員の共鳴があり、総裁選の第1回目の投票では、181票(党員票109、議員票72)と2位の石破氏の154票(党員票108、議員票46)を大きく引き離し、トップになりました。しかし、国家戦略の優劣より、私利私欲や権力争い色の強い決選投票では、残念ながら逆転され、著者は、総理にはなれませんでした。
しかし、これだけの支持を得た著者の卓越した国家戦略は、今後の国家運営に影響を与え続けるものと思っています。著者の国家戦略を理解し、将来実現されることを期待し、希望をもって、国家運営を注視していきましょう。
![]()