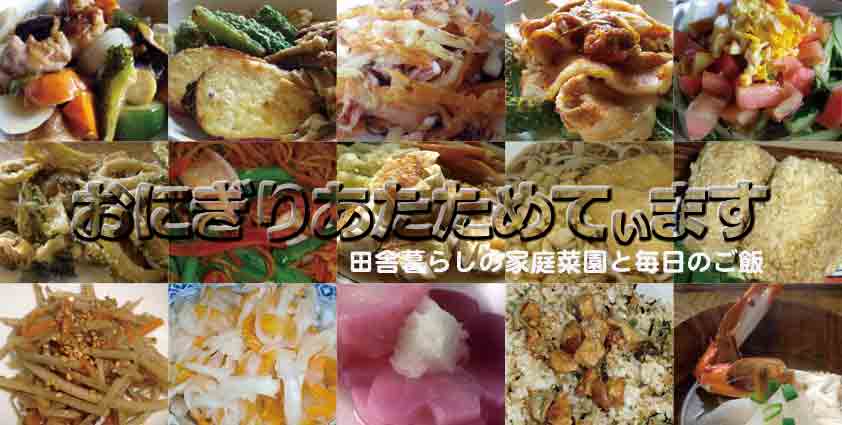
毎日寒い日が続いています。防寒対策はなさっておられますか。我が家は何度もお知らせしましたが、暖房は炬燵のみ。辛いのは風呂ですね。湯船以外は寒い寒い。洗い場も、脱衣所も寒いですよ。これって身体に良くないのですよね。
もう若くないのだから、来年の冬は暖房機を見直すつもりです。といっても旧式の石油ストーブを持ち出すだけですがね。
この石油ストーブ。久し振りに使い、最後に使ったのが、2011年の大地震の時でしたライフラインが止まり、事情が分からなかったのですが、近所の人から、「今夜は電気もガスもとおらないらしい」と聞いて、急遽、石油ストーブに灯油を入れて、やかんをかけました。夕食はカップ麺です。真っ暗な夜、後は蝋燭(ろうそく)を灯して、早々にベッドに入りました。
翌日もライフラインは通じず、風呂にも入れませんでした。そして2日後、TVにて初めて被災地の様子を知った次第です。
こちらも壁ははげ落ち、あちこちに埃が溜まっていましたが、掃除機も使えず、不便な思いをしましたが、被災地の状況を知り、改めて天災の怖さを実感しました。なのに、皆さん、外灯は灯すは、水撒きはするは、他人事でした。
驚きと、落胆を隠せませんでした。被災地や今後を思えば、電気、ガス、水道の使用は最低限度に収めるべきでしょう。我が家でも、完全に日が暮れるまで電気は灯さず、水道もガスも最低限度にしていました。そして、何よりも早い時間に眠り、余計なエネルギーは使わないようにしました。
あれから4年が経とうとしています。いつ、どこで、だれに襲いかかるか分からない天災です。数十秒、いえ、直前まで己の命が絶たれるなどとは思ってもいなかったのです。命は人間だけではありません。訳も分からないまま、突然食を絶たれた動物たち。
決して他人事ではありません。幸いにこの地は、大きな災害もなく、また幕府の天領が長かったことから、年貢の少なく、かつ力のある領主に支配されることもなく、済み易い土地だったようです。
反面、未だに保守的で、余所者への反感が強く、自分たちのルールを守り続け、少しでも革新的な意見を嫌います。土地への出入りも少なく、何世代も同じ家で暮らします。
よって行政も昭和初期のまんま。他県の知り合い曰く、「そこって中国みたいだね」。私もそう思います。発展途上の土地は、人々も考えも中国に類似しています。ただ住んでいる人は、それが当たり前であり、プライドを持っているのです。
まあ、そんな所なので、Uターン組には信じられないことばかりなのですが、天災がないということだけでも、良しとしようか。










