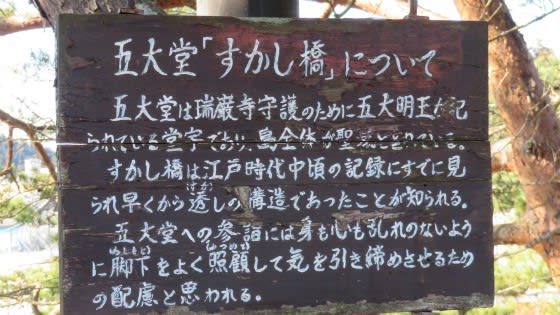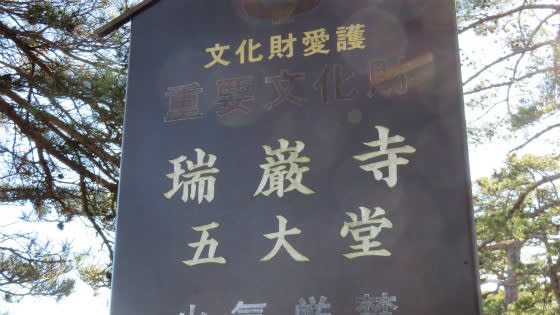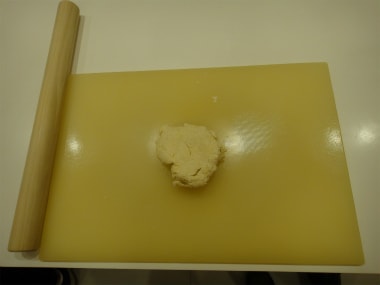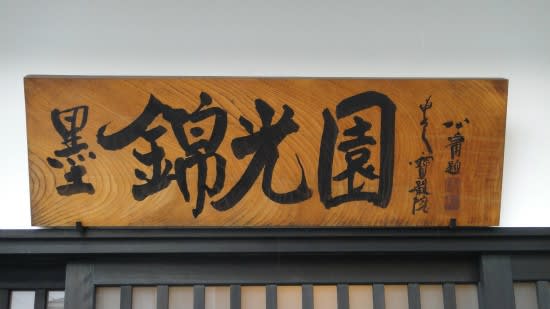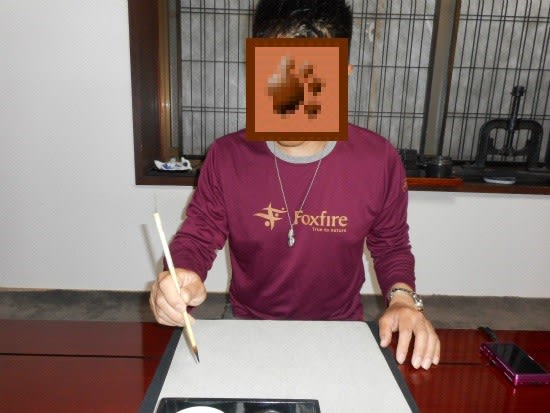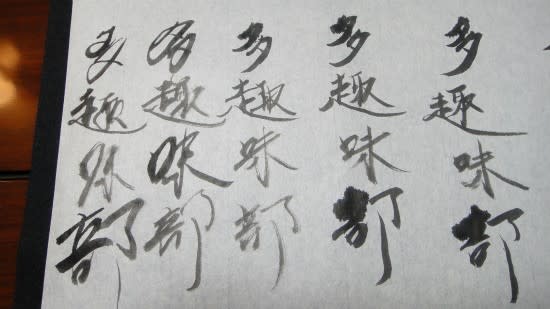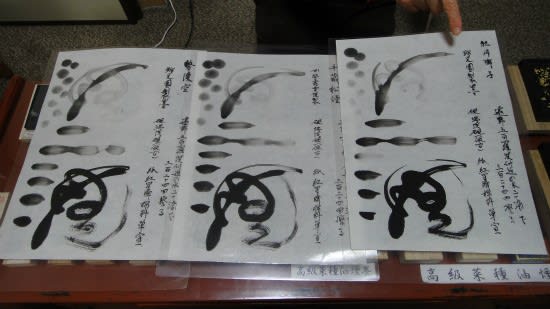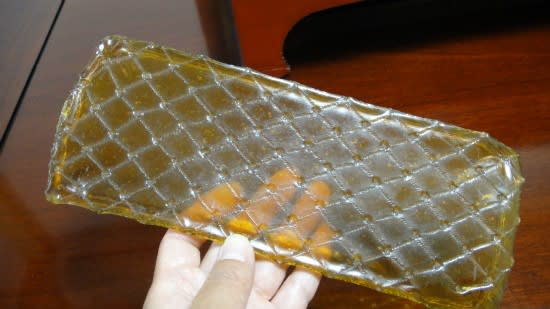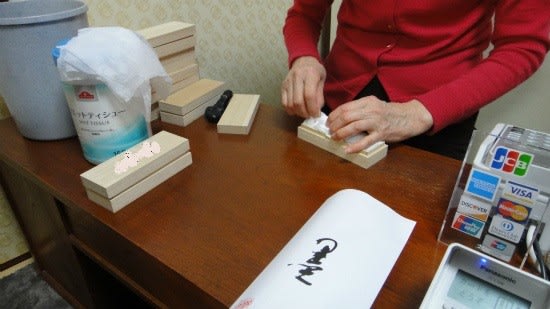庭のベンチでのんびりしたいんだけど・・・じっとしてられないなあ。
こういうの見たことありますか?
『ワイルドストロベリー』の紅葉。
真っ赤に色付いて・・・春までこのまま。

雑草だけど『ホトケノザ』咲きました~。
綺麗だからしばらく放置しておくけど、ある程度で除草しないと庭の土の養分が取られちゃうからね。

『スノーフレーク』は毎年この季節に庭の隅っこで咲いてくれます。
明るい日陰が好きな花です。
春には地上部は消滅しちゃうけど、また来年生えてくるよ。

『チューリップ』も芽を出したよ。
花が咲いた後に掘り起こして保管・・・しないよ。
植えっぱなしで毎年咲きます!

『タラ』が芽を出しました。
あの『タラの芽』が採れる樹なんだけど・・・今年はいっぱい生えてきそうだ~。
ざっと数えて10本以上。
放っておけばタラの藪っていうやたらに贅沢な藪ができそうだけど・・・実際はそう都合よくはいかないんだよね。
育成が悪くなるし、日陰になると他の植物が枯れちゃうし、触れ合うほど近くに密集すると勝手に衰退しちゃうし・・・。
芽が大きくなったら半分は摘んで食べちゃおう。
で、半分を育てよう。
また来年も生えてくるしさ。

これ、あまり見掛ける機会が無いかも。
たいして珍しいものじゃないんだけど、農薬を撒いちゃうとあっさりいなくなる陸貝『キセルガイ』の一種。
形が煙草を吸うための煙管(きせる)に似てるからキセルガイ。
カタツムリに近縁な陸の貝です。
農薬や除草剤を撒いてなければ、枯れ木の下や大きな石の下、鉢の下なんかにいるかも~。

剪定した『ローズマリー』はハーブバスに使うのだ。
あのマリー・アントワネットが若返りのハーブとして使ったんだそうですよ。

・・・あ、ツル薔薇の誘因がまだ終わってないや。
のんびりしてる場合じゃないぞ、と。
こういうの見たことありますか?
『ワイルドストロベリー』の紅葉。
真っ赤に色付いて・・・春までこのまま。

雑草だけど『ホトケノザ』咲きました~。
綺麗だからしばらく放置しておくけど、ある程度で除草しないと庭の土の養分が取られちゃうからね。

『スノーフレーク』は毎年この季節に庭の隅っこで咲いてくれます。
明るい日陰が好きな花です。
春には地上部は消滅しちゃうけど、また来年生えてくるよ。

『チューリップ』も芽を出したよ。
花が咲いた後に掘り起こして保管・・・しないよ。
植えっぱなしで毎年咲きます!

『タラ』が芽を出しました。
あの『タラの芽』が採れる樹なんだけど・・・今年はいっぱい生えてきそうだ~。
ざっと数えて10本以上。
放っておけばタラの藪っていうやたらに贅沢な藪ができそうだけど・・・実際はそう都合よくはいかないんだよね。
育成が悪くなるし、日陰になると他の植物が枯れちゃうし、触れ合うほど近くに密集すると勝手に衰退しちゃうし・・・。
芽が大きくなったら半分は摘んで食べちゃおう。
で、半分を育てよう。
また来年も生えてくるしさ。

これ、あまり見掛ける機会が無いかも。
たいして珍しいものじゃないんだけど、農薬を撒いちゃうとあっさりいなくなる陸貝『キセルガイ』の一種。
形が煙草を吸うための煙管(きせる)に似てるからキセルガイ。
カタツムリに近縁な陸の貝です。
農薬や除草剤を撒いてなければ、枯れ木の下や大きな石の下、鉢の下なんかにいるかも~。

剪定した『ローズマリー』はハーブバスに使うのだ。
あのマリー・アントワネットが若返りのハーブとして使ったんだそうですよ。

・・・あ、ツル薔薇の誘因がまだ終わってないや。
のんびりしてる場合じゃないぞ、と。