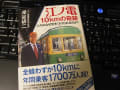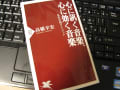この日は雨降ってて寒かったなぁ・・・。
その目的は、いまその公園内にある県立神奈川近代文学館でやっているある展示を見に行ったわけですが。

「絵本作家・西村繁男の世界展」ということで、あの「やこうれっしゃ」の作者、西村繁男さんによる緻密な絵の秘密が見られるとあって、一気に興味がわいてきたもので。
もちろん、展示物の撮影は厳禁でしたので、以降、筆者所有の絵本(とある理由により以前購入)で補足説明もしつつ。
前にこのブログで書いたかもしれないが、この絵本は文章が一切ない。

モデルになっている列車は、上野-金沢を走っていた急行「能登」。先頭の機関車がEF58で、客車も43系、10系寝台車など異型式混合の編成となっている。
表紙をめくると登場する、この親子が、じつは隠れた主人公(!)なのだとか。

上野駅を出発し、一路夜の雪国へまっしぐらな列車を、後ろから前へ

車両も人物も細かく描かれているが、作者自身はとくに鉄道ファンではないらしい。しかし、リアルさを追求するため、車両を描くに当たっては本物の車両形式図を取り寄せたのだとか。

あ、ここにいましたね。
展示品の中に、本の全ページを1枚につなげたものが展示されていたり(全部つなげるとちゃんとひと編成分になる!)、下絵も一緒に展示されているので、この本に興味持った人(とくにこの時代をリアルタイムに過ごしていた大人の方々!?)にはたまらない内容になるんじゃないかと、勝手に思ったわけで。
この展示、今度の日曜(9/25)が最終日だそうなので、今回ぼくのように興味持った方はお早めに、ということで。