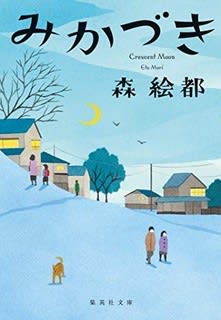森絵都 「みかづき」読了
多分アマゾンのリコメンド機能から見つけた本だと思う。
塾を経営する夫婦とその子供、孫の代までを綴った年代記のような形をとっている。
2016年の出版だけれども、相当たくさんの人が借りたのか、かなり本が傷んでいたので結構有名な作家と著作なのかと読んでいる途中で調べてみたら、作家は直木賞作家で、この本は去年NHKでドラマ化されていた。この作家のことは全然しらなかった。
ドラマでは主人公のひとりである塾経営者の妻は永作博美だったらしいが、途中からは頭のなかの主人公が永作博美になってしまった。読み終わってから調べればよかった・・。
昭和9年生まれの主人公の女性千明は戦前の国民学校の軍国教育と戦後のがらりと変わった民主主義教育を経験し、公教育に小さいころから不信感を募らせ、さらにその後におこなわれた学校教育法改正による教育行政の転換に対して文部省(当時)への怒りを抱いていて、その公教育に反旗を翻すべく、家庭教師をしながら自分が理想とする教育を実践しようとしている。プライベートでは文部官僚の元恋人とのあいだに女子をもうけたが、出産を前に別れてしまった。
千明の夫になる吾郎は父親の事業の失敗のために高校を中退し、住み込みの用務員の仕事を得る。放課後、授業についていけない子供たちの勉強を見るうちに天才的な教育能力を発揮し、それに目をつけた千明の策略というか熱意に負けて千明と学習塾を始めることになる。
このふたりを中心にしたその子供、孫の世代までの長い長い物語だ。
主人公夫婦はもちろん、子供、孫たちも“塾業界”という教育の裏街道にかかわりながらそれぞれの思い描く方向性の違いがありながらもそれぞれの力で道を切り開いていく姿。そしてその中から生まれる家族の危機と和解をふたつの大きな流れとして物語は流れてゆく。
家族の物語を塾業界と合わせて語っていくというのは面白かった。教育とはいえ、それは事業であって利益追求の部分があり、片一方では教育という聖域というか理念のようなものも存在する。そして、高度経済成長から団塊ジュニア、少子化と受験戦争の過熱に合わせて栄枯盛衰を経験した業界についても詳しく書かれていて、それぞれの時代を生きた千明と吾郎の家族もそれぞれに時代に添うかのように教育に対する考え方の違いを見せる。教育の裏街道という表現が面白い。裏街道だからこそ団結できる余地があるということもあるのだろうか。それがうまく物語に反映されている。
物語は時間の流れとともにテンポよく流れていく。しかし、たとえ家族とはいえ、そんなに考え方を異にし、生活まで別にするようなひとたちが長い年月の末といいながら和解するということがあるのだろうか。
そこは僕には共感ができない。「ひとは心の中に思っていないことは口に出さない。」というが、そんな心根を知ってしまったらたとえ家族でも理解しあえる限界を超えてしまうのではないだろうか。
そう思いながらところどころを読み返してみると、確かに登場人物たちはそれぞれの人格に対してはお互いに認め合っているということがわかる。そこを超えない限り人は分かり合えるのかもしれない。
そうやってお互いの隙間をつぎはぎしながら埋めていくものが家族なのだと著者は言いたいのかもしれないが、現実はそんなに簡単に腹を割って話すこともできないし家族だから簡単にしゃべってしまう一言に永遠に傷つけられるということもある。
全員が同じ方向を見ている家族、この物語の場合は教育ということになるのだろうが、そういう家族はどんな時でも強いということだろうが普通の家族はそうでもないと思うのだ。
そこはやっぱり創作なのだと僕は思ってしまうのだ。
電車の中で読みふけっていると気がつけば雨脚が強くなってきた。和歌山駅に到着したら乗り継ぎの路線が運転見合わせ。この先でものすごい雨が降っているらしい。
それでも、意地でも迎えには来てもらわないのだと思うのが僕の現状だ。

多分アマゾンのリコメンド機能から見つけた本だと思う。
塾を経営する夫婦とその子供、孫の代までを綴った年代記のような形をとっている。
2016年の出版だけれども、相当たくさんの人が借りたのか、かなり本が傷んでいたので結構有名な作家と著作なのかと読んでいる途中で調べてみたら、作家は直木賞作家で、この本は去年NHKでドラマ化されていた。この作家のことは全然しらなかった。
ドラマでは主人公のひとりである塾経営者の妻は永作博美だったらしいが、途中からは頭のなかの主人公が永作博美になってしまった。読み終わってから調べればよかった・・。
昭和9年生まれの主人公の女性千明は戦前の国民学校の軍国教育と戦後のがらりと変わった民主主義教育を経験し、公教育に小さいころから不信感を募らせ、さらにその後におこなわれた学校教育法改正による教育行政の転換に対して文部省(当時)への怒りを抱いていて、その公教育に反旗を翻すべく、家庭教師をしながら自分が理想とする教育を実践しようとしている。プライベートでは文部官僚の元恋人とのあいだに女子をもうけたが、出産を前に別れてしまった。
千明の夫になる吾郎は父親の事業の失敗のために高校を中退し、住み込みの用務員の仕事を得る。放課後、授業についていけない子供たちの勉強を見るうちに天才的な教育能力を発揮し、それに目をつけた千明の策略というか熱意に負けて千明と学習塾を始めることになる。
このふたりを中心にしたその子供、孫の世代までの長い長い物語だ。
主人公夫婦はもちろん、子供、孫たちも“塾業界”という教育の裏街道にかかわりながらそれぞれの思い描く方向性の違いがありながらもそれぞれの力で道を切り開いていく姿。そしてその中から生まれる家族の危機と和解をふたつの大きな流れとして物語は流れてゆく。
家族の物語を塾業界と合わせて語っていくというのは面白かった。教育とはいえ、それは事業であって利益追求の部分があり、片一方では教育という聖域というか理念のようなものも存在する。そして、高度経済成長から団塊ジュニア、少子化と受験戦争の過熱に合わせて栄枯盛衰を経験した業界についても詳しく書かれていて、それぞれの時代を生きた千明と吾郎の家族もそれぞれに時代に添うかのように教育に対する考え方の違いを見せる。教育の裏街道という表現が面白い。裏街道だからこそ団結できる余地があるということもあるのだろうか。それがうまく物語に反映されている。
物語は時間の流れとともにテンポよく流れていく。しかし、たとえ家族とはいえ、そんなに考え方を異にし、生活まで別にするようなひとたちが長い年月の末といいながら和解するということがあるのだろうか。
そこは僕には共感ができない。「ひとは心の中に思っていないことは口に出さない。」というが、そんな心根を知ってしまったらたとえ家族でも理解しあえる限界を超えてしまうのではないだろうか。
そう思いながらところどころを読み返してみると、確かに登場人物たちはそれぞれの人格に対してはお互いに認め合っているということがわかる。そこを超えない限り人は分かり合えるのかもしれない。
そうやってお互いの隙間をつぎはぎしながら埋めていくものが家族なのだと著者は言いたいのかもしれないが、現実はそんなに簡単に腹を割って話すこともできないし家族だから簡単にしゃべってしまう一言に永遠に傷つけられるということもある。
全員が同じ方向を見ている家族、この物語の場合は教育ということになるのだろうが、そういう家族はどんな時でも強いということだろうが普通の家族はそうでもないと思うのだ。
そこはやっぱり創作なのだと僕は思ってしまうのだ。
電車の中で読みふけっていると気がつけば雨脚が強くなってきた。和歌山駅に到着したら乗り継ぎの路線が運転見合わせ。この先でものすごい雨が降っているらしい。
それでも、意地でも迎えには来てもらわないのだと思うのが僕の現状だ。