・・・私が育った幼年時代は戦後の物不足の時代だったので、下着も上着も母親が作ってくれた。
従って、普段着る衣類は破れたら、修理して着ていた。
そして、大学時代も、使い捨ての時代ではなかった。
結婚したころから、徐々にモノがあふれだし、そして、私の子供達は、消費社会で育ってきた。
物のない時代を知っている我々の世代は、使い捨ての仕組みは、その中に居ながら、何かおかしいと何時も感じていた。
つい、最近になって、右上がりでない経済状態になって、限られた資源で今の大量消費時代はおかしいのでは、といわれ始めた。
先日観たテレビの番組「消費社会はどこへ」はこれらの事を取り上げたドキュメンタリー番組を見て、改めてそうだったと感じるところがあった。
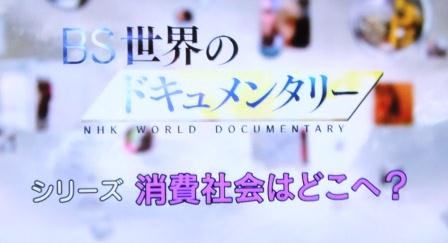
番組のキーワードは「意図的老朽化」という言葉です。
「意図的老朽化」という意味は新製品を投入し、意図的に既存の製品を時代遅れにして市場の拡大を図ることです。
番組ではその例として、パソコンプリンターの意図された寿命、I Podの短く設計された電池寿命、直ぐ破れる工夫をしたナイロン靴下の開発などで、「意図的老朽化」が設計段階から行われた製品開発だったことを紹介していました。
その番組のなかの具体的内容については、省きますが、この後紹介する寿命を短くした白熱電球の開発内容と基本的には同じです。
番組の中で、一番詳しく紹介していたのは「白熱電球」の例でした。
白熱電球はエジソンが発明し、エジソンの時代には白熱電球の寿命は1500時間になっていた。その時代の象徴的な電球として、1901年にアメリカで製造され、誕生してから、百年経った電球として、カルフォリア、リバモアの消防署で、今現在も使われている下の写真の白熱電球が紹介されていました。

「リバモア消防署の百年間使っている電球」
この白熱電球が製造された後の時代、1932年にポイポス・カルテルという世界的電球製造メーカーのカルテルが市場を支配し、白熱電球の市場を拡大するため、寿命を1000時間と短くきめ、管理を強めた、その結果、カルフォニアの消防署にある百年持つような電球は世界から、消えてしまったそうです。
しかし、いま、改めて、地球の限られた資源の枯渇が心配されだしたことから、消費生活の行先を、使い捨てから、循環消費の時代へと行先を変えつつあると番組では解説されていました。















