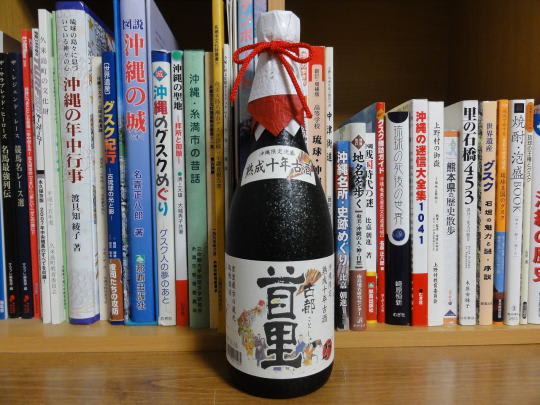湧川マサリャ御嶽の全景

御嶽内部の拝所

道路側から見た御嶽
平良は ( ピサラ ) と称し、人の住むにふさわしい地。
綾道 ( アヤンツ ) は 「 美しい道 」 の意味で、それぞれ宮古コトバである。
平良五箇 ( ピサラグカ ) は、旧藩時代の間切りで、
西里、下里、荷川取、東仲宗根、西仲宗根の五村のことである。
この平良五箇の歴史を探して綾道を歩いたものを紹介して行きたいと思っている。
湧川 ( ばくぎゃー ) マサリャ御嶽は、人頭税石から約300mの場所にあり、
案内の看板がなければ見落としてしまいそうな御嶽 ( うたき ) である。
ここでの祭神は、湧川 ( ばくぎゃー ) マサリャを祀っている。
話しの内容は、「浦島太郎の琉球版」と思ってもらえればいいだろう。
この御嶽は 「 宮古の竜宮伝説 」 を伝える貴重な御嶽である。
昔、荷川取村に湧川マサリヤという漁師がいた。
ある日、漁に出てエイという魚を釣ったが、その魚がたちまち美しい女と化したので、
マサリヤは心浮かれて女と夫婦の契りを結んだ。
その後、二・三か月たって、同じ場所で釣りをしていると、
何処からともなく三人の童が現れ 「 母の使いで父を竜宮に案内するために参った 」 と告げた。
サマリヤは不審がったが、童らがマサリヤの手を取って海に入ったかと思うと、
たちまち金銀ちりばめた楼閣の中にいた。
母は前に契りを結んだ女に間違いなく、睦まじき顔でマサリヤを迎え、
三日三夜、色々なご馳走を出して饗応した。
女は別れ際に涙を流し、 「 これをいつまでも私の形見と思って下さい 」 と瑠璃色の壷を手渡した。
マサリヤは夢の覚めた心地で家に帰ったが、
竜宮でも三日三夜はこの世では三年三ヶ月の月日が流れていた。
瑠璃壷には神酒が入っており、呑めども神酒は尽きることなく口の渇きを癒し、
天の甘露の如き美味な酒であった。
これを呑んだ者は無病息災で長命を保ち、それ故、マサリヤは家宝として秘密にしていたが、
やがて村中の噂となり、大勢の村人が壷を見ようと家へ押しかけて来た。
マサリヤは富貴におごり「この酒は朝晩とも同じ味でもう呑みたくない」と言ったとたん、
壷は白鳥と化して虚空に舞い上がり、東方をさして舞行きて、
宮国村スカブ屋の庭木に留まり、姿を消したという。
また『 平良市史 』 には、少しニュアンスの違うお話となって残っている。
昔、唐から流れ着いた人がいて壷を持っていた。
島の人を娶り、暮らしていたが、畑に出ても用意した食糧を食べる事もなく持ち帰る。
不思議に思い、妻は昼時に畑に行き様子を窺うと壷から次々と取り出して食べている。
驚いて声をあげたとたんに、壷は羽が生え宮国の方へ飛んでいった。
近くには海に流れ出る水の湧き口(ばくぎゃー)あり、御嶽の名の由来とも伝わる。
所在地 : 宮古島市平良 荷川取