「日本の七十二候」を紐解くと、ここ数週間は「菊花開(きくばなひらく)」「蟋蟀在戸(きりぎりすとにあり)」「霜始降(しもはじめてふる)」 と移っていきます。なんとなく肌で感じる季節感を思わせます。そんな土曜休日の朝、畑を覗くと、野菜の苗に毛虫を発見しました。ブロッコリーの葉っぱにも大きなお腹をかかえた青虫がじっとしています。可哀想ですが、ほっておくと苗が跡形もなくなってしまいます。ピンセットで摘み出します。 そのあと、ゴンタ爺さんと朝のお散歩に出かけました。お散歩の時以外は終日横たわっていることが多いのですが、お散歩だけはなんとなく元気です。でも、歩く速度はずいぶんゆっくりしています。いずれ私も同じ運命をたどるのでしょうが、なんとも哀れなものです。15年も一緒に暮らしたゴンタ爺さんです。犬や猫やという前に、家族の一員です。飼い主より先に介護の生活がやってくるのでしょう。あと1ヶ月もすれば16歳のお誕生日会です。
そのあと、ゴンタ爺さんと朝のお散歩に出かけました。お散歩の時以外は終日横たわっていることが多いのですが、お散歩だけはなんとなく元気です。でも、歩く速度はずいぶんゆっくりしています。いずれ私も同じ運命をたどるのでしょうが、なんとも哀れなものです。15年も一緒に暮らしたゴンタ爺さんです。犬や猫やという前に、家族の一員です。飼い主より先に介護の生活がやってくるのでしょう。あと1ヶ月もすれば16歳のお誕生日会です。 さて、今週の半ばの夕刻、再び上洛しました。お目当ては、第6回ブータン文化講座です。数年前に、某経済団体主催の会合で、ブータンのお偉い方から国民総幸福度(GNH)についてお話を聞いて以後、ブータンが頭から離れません。今回のテーマは「輪廻のコスモロジーとブータンの新しい世代」でした。
さて、今週の半ばの夕刻、再び上洛しました。お目当ては、第6回ブータン文化講座です。数年前に、某経済団体主催の会合で、ブータンのお偉い方から国民総幸福度(GNH)についてお話を聞いて以後、ブータンが頭から離れません。今回のテーマは「輪廻のコスモロジーとブータンの新しい世代」でした。 ヒマラヤ山脈の南麓にあって、九州とほぼ同じぐらいの国土におよそ70万人が暮らすブータン王国。中国とインドに挟まれる地政学的なポジションにありながら独自の文化を守ってきました。しかし、時代の流れと無縁ではいられません。明治維新にも似た状況にありながら、国民の多くが国王を慕い国を思う国民性があります。講師の西平先生は、そんなブータンの状況を、急激に変化しているものと、変化していないもの、という視点から見つめていらっしゃる。スクリーンに映し出されるブータンの若者たちの表情を追いながら、日本の古き良き時代を思ったものでした。
ヒマラヤ山脈の南麓にあって、九州とほぼ同じぐらいの国土におよそ70万人が暮らすブータン王国。中国とインドに挟まれる地政学的なポジションにありながら独自の文化を守ってきました。しかし、時代の流れと無縁ではいられません。明治維新にも似た状況にありながら、国民の多くが国王を慕い国を思う国民性があります。講師の西平先生は、そんなブータンの状況を、急激に変化しているものと、変化していないもの、という視点から見つめていらっしゃる。スクリーンに映し出されるブータンの若者たちの表情を追いながら、日本の古き良き時代を思ったものでした。
帰路、暗くなった川端通りを歩きながら思いました。「変化しているもの」と「変化していないもの」。「変わっていくもの」と「変わらないもの」。電車のなかでカバンの中から柳田國男の「山の人生」を取り出して数ページ眺めながら、日本という社会における「変わっていくもの」と「変わらないもの」を考えました。このところ日本の歴史、文化、精神性に関心を寄せるのも、単なる郷愁ということではない、もうひとつの漠とした課題を引きずっているのかもしれません。 ここ十数年来の読書遍歴のなかで、ひとつの象徴的な作品に「鶴見和子の世界」(藤原書店)があります。「水俣・アニミズム・エコロジー」「柳田國男と南方熊楠」「内発的発展論」.......。この本を手にした頃は、職場で大掛かりな制度改革を進めていた時期です。いつまでも右肩上がり、成長という物差しでものごとを考えていくことに対する、心の揺らぎかもしれません。「変えるべきもの」と「変えてはならないもの」という課題認識が見え隠れしています。
ここ十数年来の読書遍歴のなかで、ひとつの象徴的な作品に「鶴見和子の世界」(藤原書店)があります。「水俣・アニミズム・エコロジー」「柳田國男と南方熊楠」「内発的発展論」.......。この本を手にした頃は、職場で大掛かりな制度改革を進めていた時期です。いつまでも右肩上がり、成長という物差しでものごとを考えていくことに対する、心の揺らぎかもしれません。「変えるべきもの」と「変えてはならないもの」という課題認識が見え隠れしています。  お堅い内容になってしまいました。ここらでフルトベングラーのLPでも聴いてみましょう。取り出したのは、「不滅の巨匠フルトベングラーの芸術シーズ」から「ワーグナー名演集」です。ワーグナーなんて聴くのは、ほんと久しぶりのことです。
お堅い内容になってしまいました。ここらでフルトベングラーのLPでも聴いてみましょう。取り出したのは、「不滅の巨匠フルトベングラーの芸術シーズ」から「ワーグナー名演集」です。ワーグナーなんて聴くのは、ほんと久しぶりのことです。
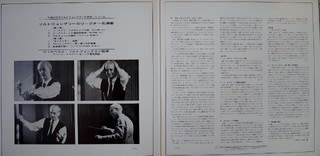 そうそう、来週の日曜日は39回目の結婚記念日です。これまで「絶対に無理」と言っていた家内を口説いてプラハ国立歌劇場のヴェルディ「椿姫」に出かけます。
そうそう、来週の日曜日は39回目の結婚記念日です。これまで「絶対に無理」と言っていた家内を口説いてプラハ国立歌劇場のヴェルディ「椿姫」に出かけます。
















