
3月は22冊読みました。
インフルエンザで会社を3日休んだ分、読書量が伸びたのかも。
◆翔ぶが如く〈8〉〈9〉〈10〉 (文春文庫)(司馬 遼太郎)
やっと読み終わった。長かった。
武士階級とは元々は軍隊、でも江戸時代の長い泰平で、ものすごく効率の悪い官僚組織を形成することになりました。
戊申の軍事クーデターが成功したところで、その本質は変わらない。
知識階級、読書階級であることとか、高邁な精神とかそういうことを別にすれば、近代国家に士族が不必要なことは自明の理。
薩軍は確かに強かった、けど、それは単なる力で、その力を有効に使う頭や、その後どうするといったビジョンが皆無でした。
西郷は、日本の未来を信じて、自ら進んで破滅に向かったのではないだろうか、なんて思ってしまいました。
◆車輪の下 (新潮文庫)(ヘルマン・ヘッセ)
多分中学生の時以来の再読。こんな難しい本、良く読めたな、えらい、中学生の俺!と思わせる小説でした。
今で言えばメンタルヘルスの問題でしょう、先生たちも、本人のためではなく自分たちのためにハンスに期待し、重圧をかけちゃった。純粋真っ直ぐ君は折れやすいです。
ハンスの死は、自殺ではなく、酔ったあげくの過失、そう思いたいです。
◆トム・ソーヤーの冒険 (新潮文庫)(マーク・トウェイン)
この小説の時代の1840年といったら、江戸時代の末期か。古き良き時代の米国の田舎、ですね。
トムとハックの悪ガキと、それに振り回される気の毒な大人たちのお話。適度にずる賢かったり、時には臆病だったり、妙にませてたり、悪ガキぶりがとってもリアル。
◆黒い雨 (新潮文庫)(井伏 鱒二)

複数の人の被爆時の日記をつなぎ合わせたものなので、小説としてはまとまりがなくて読みにくかった。その分、リアリティはあったけど。。。
矢須子の発病には暗い気持ちにさせられた。ピカドン、新型爆弾と言われその正体がわからず、いたずらに二次被災者を増やしてしまったのが残念。
南京大虐殺とかA級戦犯とか言われるけど、それならヒロシマの原爆や東京大空襲も戦争犯罪ではないのか。勝てば官軍、所詮裁かれるのは敗者だけなのか。
◆塩狩峠 (新潮文庫)(三浦 綾子)
良い小説でした。
信仰がどうとかは抜きにしても、このような謙虚な考え方と揺るがぬ行動力を持った、周囲にプラスの影響を与える人になりたい、少しでも近づきたいと思います。
◆檸檬 (新潮文庫)(梶井 基次郎)
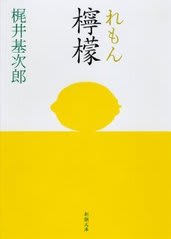
森見さんの小説や万城目さんの「ホルモー六景」、「喫茶店タレーランの事件簿」にも登場した「檸檬」を読んでみました。
最初の「檸檬」を読んだ時は、正直こんな短編をあと18も読むのかと思ったのですが、だんだん引き込まれていって「冬の蠅」「ある崖の上の感情」あたりでは結構マジでした。
寂寥感、焦燥感、退廃、不安といった感情を、決して観念的にではなく、分かりやすいメタファで描いて見せる筆力、とでも言ったらよいのでしょうか。
寡作で早世したにもかかわらず語り継がれる理由が分かったような気がします。
◆オイアウエ漂流記 (新潮文庫)(荻原 浩)

昔11人乗りの単発プロペラ機でフィリピンの小島に行ったときも、搭乗前に体重測定がありました。操縦席の隣にも、犬じゃなく普通に乗客を乗せていたのを思い出しました。
サバイバル生活、やはり男の真価は食料調達能力ですよね。グループを食わせてこそリーダー。部長さんも最後は役に立ってよかったね。
同じ新潮の100冊でも「無人島に生きる十六人」と違ってフィクションな分、キャラも漫画っぽくエンターテインメント要素満載で、分厚さが気にならず、楽しく読めました。
◆オール・マイ・ラビング (5) 東京バンドワゴン (集英社文庫)
東京バンドワゴン・シリーズも、もうこれで5作目。
いつも変わらぬ堀田家と思いきや、少しずつ時は流れていっているんですね。研人が小学校卒業、才能は隔世遺伝みたいですね。頭の中で、登場人物はドラマのメンバーに置き換わり、ビートルズのオール・マイ・ラビングが流れました。
◆四畳半神話大系 (角川文庫)(森見 登美彦)
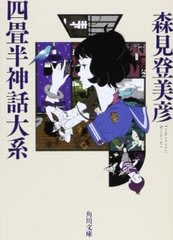
数年前に見たアニメを思い出しながら読みました。
森見さんの小説にいつも出てくる阿呆でヘタレな主人公とちょっと不思議な森見ワールドがこの作品でも馬鹿馬鹿しさ全開でした。
作中頻繁に登場する「海底二万里」はちょうど先月読んだところだったので、、、森見さん、ジュール・ヴェルヌお好きなんですね。
◆珈琲店タレーランの事件簿 2 彼女はカフェオレの夢を見る (宝島社文庫)(岡崎 琢磨)
◆珈琲店タレーランの事件簿 3 心を乱すブレンドは

ビブリアの喫茶店版みたいに言われる節もあるけど、ビブリアよりも伏線の張り方とかは緻密な印象。
でも、ヒロインのキャラ立ち度はやっぱり栞子さんかなー。
2巻は面白かったのですが、3巻は長編の本格ミステリー。
でも、失礼ながらもともとがライトミステリー、アオヤマくんとの仲は、とか、ミステリー以外の要素なしの長編は少々きつかったです。
ビブリアとか古典部シリーズもですけど、こういうのは中編モノが似合うように思います。
◆GOSICKIII ―ゴシック・青い薔薇の下で― (角川文庫)(桜庭 一樹)
シリーズ全編再読中。
本編シリーズの中では、一回休み的な軽めの事件。ブロワ警部のヘアスタイルの謎解きの方が自分にとってはメインでした。
時は20世紀初頭、兵器を中心に科学技術が急発展した時代。古いものが新しいものにとって代わられる、その古いものの叡智の象徴がヴィクトリカ、そんな図式も見え始めました。
◆フラッシュ・ポイント: 天命探偵 真田省吾4 (新潮文庫)(神永 学)
奇想天外、痛快娯楽大作。
◆人間の建設 (新潮文庫)(小林 秀雄・岡 潔)
知の巨人同士の対談。特に岡潔さんがすごい。
数学者でありながら、小林秀雄と対等にドストエフスキーやベルグソンを論じ、日本国憲法前文を小我と切り捨て、「神風」の如く死ねることを日本人の長所と言い切る。
手元に置いて時々読み返したい本です。
ノンフィクションが2冊。
◆絶対貧困―世界リアル貧困学講義 (新潮文庫)(石井 光太)

タイトル通り、リアルな現状が伝わってくる本でした。
徹底的なフィールドワークなくしては語れない真実。自分が知っているアジアなんてほんの一部でした。
この時代の日本に生まれた幸運に感謝します。
この現実に際して、どこからどう手を付ければいいのか、自分が何をすればいいのか、さっぱりわからないです。
◆格安エアラインで世界一周 (新潮文庫)(下川 裕治)
なぜこの本を読んだかと言えば、「新潮文庫の100冊(2013年)」だったからです。
LCCの実態については良くわかりました。でも、乗り物ってのは旅の移動の手段であり、目的ではないと思っているので、この人たちのやっていることの意味、意義が分かりませんでした。
ビジネス書、今月は3冊。
◆Facebookをビジネスに使う本(熊坂 仁美)
2010年の本なので古い感じは否めないが、「なるほどそういうものなのね」という感触はつかめた。
当社も作ってみようかなー。
◆餃子屋と高級フレンチでは、どちらが儲かるか?(林 總)

管理会計の初歩、入門書です。
ストーリー仕立てになっているので、1時間くらいで簡単に読めました。
安曇サンの注文するワインの違いは分かりませんでしたけど。
◆リーダーを目指す人の心得(コリン・パウエル,トニー・コルツ)
今までいろんなリーダーシップ論の本を読んだけど、これが一番心に沁みたかも。
米国で黒人初の陸軍大臣、最年少統合参謀本部議長、国務長官、伊達じゃないっす。
特に第5章「150%の力を組織から引き出す」は、なるほどそうだよねっ!って感じ。ビジネス書のつもりで読み始めたけど、それ以上のものでした。
会社の原書読書会の課題図書でした。
◆Tell Me Your Dreams(Sidney Sheldon)
S.Sheldonは英語が比較的簡単なので会社の原書読書会の課題図書にしたのですが、これほどエログロい話とは思わなかった。
女子社員から、「こんなの読ませて、セクハラです」とか言われちゃうかな。
インフルエンザで会社を3日休んだ分、読書量が伸びたのかも。
◆翔ぶが如く〈8〉〈9〉〈10〉 (文春文庫)(司馬 遼太郎)
やっと読み終わった。長かった。
武士階級とは元々は軍隊、でも江戸時代の長い泰平で、ものすごく効率の悪い官僚組織を形成することになりました。
戊申の軍事クーデターが成功したところで、その本質は変わらない。
知識階級、読書階級であることとか、高邁な精神とかそういうことを別にすれば、近代国家に士族が不必要なことは自明の理。
薩軍は確かに強かった、けど、それは単なる力で、その力を有効に使う頭や、その後どうするといったビジョンが皆無でした。
西郷は、日本の未来を信じて、自ら進んで破滅に向かったのではないだろうか、なんて思ってしまいました。
◆車輪の下 (新潮文庫)(ヘルマン・ヘッセ)
多分中学生の時以来の再読。こんな難しい本、良く読めたな、えらい、中学生の俺!と思わせる小説でした。
今で言えばメンタルヘルスの問題でしょう、先生たちも、本人のためではなく自分たちのためにハンスに期待し、重圧をかけちゃった。純粋真っ直ぐ君は折れやすいです。
ハンスの死は、自殺ではなく、酔ったあげくの過失、そう思いたいです。
◆トム・ソーヤーの冒険 (新潮文庫)(マーク・トウェイン)
この小説の時代の1840年といったら、江戸時代の末期か。古き良き時代の米国の田舎、ですね。
トムとハックの悪ガキと、それに振り回される気の毒な大人たちのお話。適度にずる賢かったり、時には臆病だったり、妙にませてたり、悪ガキぶりがとってもリアル。
◆黒い雨 (新潮文庫)(井伏 鱒二)

複数の人の被爆時の日記をつなぎ合わせたものなので、小説としてはまとまりがなくて読みにくかった。その分、リアリティはあったけど。。。
矢須子の発病には暗い気持ちにさせられた。ピカドン、新型爆弾と言われその正体がわからず、いたずらに二次被災者を増やしてしまったのが残念。
南京大虐殺とかA級戦犯とか言われるけど、それならヒロシマの原爆や東京大空襲も戦争犯罪ではないのか。勝てば官軍、所詮裁かれるのは敗者だけなのか。
◆塩狩峠 (新潮文庫)(三浦 綾子)
良い小説でした。
信仰がどうとかは抜きにしても、このような謙虚な考え方と揺るがぬ行動力を持った、周囲にプラスの影響を与える人になりたい、少しでも近づきたいと思います。
◆檸檬 (新潮文庫)(梶井 基次郎)
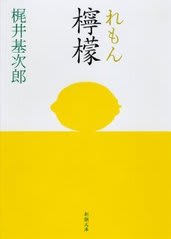
森見さんの小説や万城目さんの「ホルモー六景」、「喫茶店タレーランの事件簿」にも登場した「檸檬」を読んでみました。
最初の「檸檬」を読んだ時は、正直こんな短編をあと18も読むのかと思ったのですが、だんだん引き込まれていって「冬の蠅」「ある崖の上の感情」あたりでは結構マジでした。
寂寥感、焦燥感、退廃、不安といった感情を、決して観念的にではなく、分かりやすいメタファで描いて見せる筆力、とでも言ったらよいのでしょうか。
寡作で早世したにもかかわらず語り継がれる理由が分かったような気がします。
◆オイアウエ漂流記 (新潮文庫)(荻原 浩)

昔11人乗りの単発プロペラ機でフィリピンの小島に行ったときも、搭乗前に体重測定がありました。操縦席の隣にも、犬じゃなく普通に乗客を乗せていたのを思い出しました。
サバイバル生活、やはり男の真価は食料調達能力ですよね。グループを食わせてこそリーダー。部長さんも最後は役に立ってよかったね。
同じ新潮の100冊でも「無人島に生きる十六人」と違ってフィクションな分、キャラも漫画っぽくエンターテインメント要素満載で、分厚さが気にならず、楽しく読めました。
◆オール・マイ・ラビング (5) 東京バンドワゴン (集英社文庫)
東京バンドワゴン・シリーズも、もうこれで5作目。
いつも変わらぬ堀田家と思いきや、少しずつ時は流れていっているんですね。研人が小学校卒業、才能は隔世遺伝みたいですね。頭の中で、登場人物はドラマのメンバーに置き換わり、ビートルズのオール・マイ・ラビングが流れました。
◆四畳半神話大系 (角川文庫)(森見 登美彦)
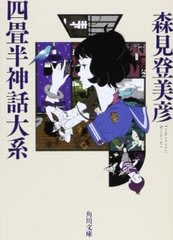
数年前に見たアニメを思い出しながら読みました。
森見さんの小説にいつも出てくる阿呆でヘタレな主人公とちょっと不思議な森見ワールドがこの作品でも馬鹿馬鹿しさ全開でした。
作中頻繁に登場する「海底二万里」はちょうど先月読んだところだったので、、、森見さん、ジュール・ヴェルヌお好きなんですね。
◆珈琲店タレーランの事件簿 2 彼女はカフェオレの夢を見る (宝島社文庫)(岡崎 琢磨)
◆珈琲店タレーランの事件簿 3 心を乱すブレンドは

ビブリアの喫茶店版みたいに言われる節もあるけど、ビブリアよりも伏線の張り方とかは緻密な印象。
でも、ヒロインのキャラ立ち度はやっぱり栞子さんかなー。
2巻は面白かったのですが、3巻は長編の本格ミステリー。
でも、失礼ながらもともとがライトミステリー、アオヤマくんとの仲は、とか、ミステリー以外の要素なしの長編は少々きつかったです。
ビブリアとか古典部シリーズもですけど、こういうのは中編モノが似合うように思います。
◆GOSICKIII ―ゴシック・青い薔薇の下で― (角川文庫)(桜庭 一樹)
シリーズ全編再読中。
本編シリーズの中では、一回休み的な軽めの事件。ブロワ警部のヘアスタイルの謎解きの方が自分にとってはメインでした。
時は20世紀初頭、兵器を中心に科学技術が急発展した時代。古いものが新しいものにとって代わられる、その古いものの叡智の象徴がヴィクトリカ、そんな図式も見え始めました。
◆フラッシュ・ポイント: 天命探偵 真田省吾4 (新潮文庫)(神永 学)
奇想天外、痛快娯楽大作。
◆人間の建設 (新潮文庫)(小林 秀雄・岡 潔)
知の巨人同士の対談。特に岡潔さんがすごい。
数学者でありながら、小林秀雄と対等にドストエフスキーやベルグソンを論じ、日本国憲法前文を小我と切り捨て、「神風」の如く死ねることを日本人の長所と言い切る。
手元に置いて時々読み返したい本です。
ノンフィクションが2冊。
◆絶対貧困―世界リアル貧困学講義 (新潮文庫)(石井 光太)

タイトル通り、リアルな現状が伝わってくる本でした。
徹底的なフィールドワークなくしては語れない真実。自分が知っているアジアなんてほんの一部でした。
この時代の日本に生まれた幸運に感謝します。
この現実に際して、どこからどう手を付ければいいのか、自分が何をすればいいのか、さっぱりわからないです。
◆格安エアラインで世界一周 (新潮文庫)(下川 裕治)
なぜこの本を読んだかと言えば、「新潮文庫の100冊(2013年)」だったからです。
LCCの実態については良くわかりました。でも、乗り物ってのは旅の移動の手段であり、目的ではないと思っているので、この人たちのやっていることの意味、意義が分かりませんでした。
ビジネス書、今月は3冊。
◆Facebookをビジネスに使う本(熊坂 仁美)
2010年の本なので古い感じは否めないが、「なるほどそういうものなのね」という感触はつかめた。
当社も作ってみようかなー。
◆餃子屋と高級フレンチでは、どちらが儲かるか?(林 總)

管理会計の初歩、入門書です。
ストーリー仕立てになっているので、1時間くらいで簡単に読めました。
安曇サンの注文するワインの違いは分かりませんでしたけど。
◆リーダーを目指す人の心得(コリン・パウエル,トニー・コルツ)
今までいろんなリーダーシップ論の本を読んだけど、これが一番心に沁みたかも。
米国で黒人初の陸軍大臣、最年少統合参謀本部議長、国務長官、伊達じゃないっす。
特に第5章「150%の力を組織から引き出す」は、なるほどそうだよねっ!って感じ。ビジネス書のつもりで読み始めたけど、それ以上のものでした。
会社の原書読書会の課題図書でした。
◆Tell Me Your Dreams(Sidney Sheldon)
S.Sheldonは英語が比較的簡単なので会社の原書読書会の課題図書にしたのですが、これほどエログロい話とは思わなかった。
女子社員から、「こんなの読ませて、セクハラです」とか言われちゃうかな。



























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます