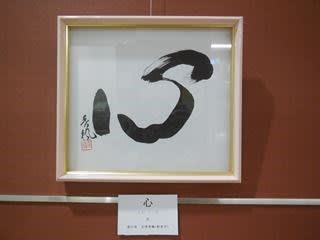東博の運慶展に行った。これは図録表紙。
運慶を見ずして仏像は語れないと思うし、
これまで苦労して見てきた運慶仏たちが勢ぞろいしているのだから
行かないわけにはいかない。
現地では非公開のため拝観できなかったもの、
遠かったりガラス越しだったり暗かったりで拝観状況が悪かったものなども多く、
今回は是が非でも見たかった。
何せ空前絶後の展覧会なので。
本展は「興福寺中金堂再建記念」とのことだが、
2015年春建設中の屋根に上った。

そして帰りにいただいたのがこの鉋屑。

いわばわが家の家宝ですね(笑)。

これは当時の看板。
この度の東博展で私がいちばん期待していたのは円成寺の大日如来坐像。
国宝だ。
3度目の拝観になる。
初回は1970年代。
雨の柳生街道をひとり歩いてたどり着いた。
当時のご住職が大日如来の前で直に説明してくださったのが思い出だ。
二度目は一昨年の秋。
奈良からバスで。
円成寺とは浄土庭園が美しいお寺である。

そして境内の茶店では吉野産と書かれたマツタケが売られていた。


大日如来はこの多宝塔の中に安置されている。
はるばる訪ねてもガラス越しではよく見えないし、遠目なので小さい。
残念至極であった…。

大日如来は運慶のデビュー作として有名だ。
わたし的には本展のハイライトといってもよい。
入ってすぐのところに展示されている。
真っ先に目に入る。
360度ぐるりまわれるように置かれているなんて、こんなことってもう二度とないかもしれない。
将来あったとしても、私にとってはこれが最後のチャンスかも…
という気持ちで何度も仏像の前に立ち、心行くまで眺めてきた。
ありがたかった。
http://unkei2017.jp/
明日13日の「ぶらぶら美術・博物館」で取り上げるそうです。