読書案内「黒澤止幾子伝と渾沌」湯浅由三著
時代に創られた偉人 ① 錫高野から京都まで……

(幻冬舎文庫 2020.6第1刷) (黒澤止幾子 ウィキペディアより)
黒澤止幾子
文化3(1807)年生 明治23(1890)年死去 85歳
名前 登幾子、とき子、時子、止幾、李恭(りきょう) 止幾子
墓碑銘には「止幾子」と刻んであり、一般の呼び名もこれを使用している。
茨城郡高野村(城里町錫高野)の修験道場・宝寿院に生まれるも、
幼い頃に父と離別、祖父や養父から漢学、国学などを学び、
後年「日本初の女性教師」と言われる素地はこの時に養われた。
死後17年たった1907年明治政府から従五位を追贈される。
26歳。夫と死別し錫高野の実家に戻る。
その後20年間、櫛(くし)や簪(かんざし)の行商で生計を立てていが、
漢学や国学の豊かな知識を見込まれ、地元子弟たちの教育にもあたった。
行商をしながら得た各地の文人たちとの交流もあり、
俳諧、漢詩、和歌などにも通暁するようになった。
安政元(1854)年 養父の私塾を受け継ぐ。
止幾子47歳。
ここまでの止幾子の生活に「勤皇の女傑」「初の女教師」という活動は見当たらない。
働き者で当時としては、教養のある女性という以外、
後年語り継がれる偉人としての形跡は見当たらない。
まして、明治40(1907)年(止幾子死去後17年を経て)従五位を追贈されるような痕跡はない。
しかし、私塾を任(まか)され平穏な日々を送ったのはわずか4年であった。
安政5年(1858)年 安政の大獄
大老井伊直弼による、当時の幕政に反対、批判的な人物を捉え、徹底的な弾圧を加えた事件で連
座したものは100名以上に上る。
例を挙げれば、橋本左内、吉田松陰、頼幹三郎等斬罪、獄死、切腹したもの14名。
隠居・謹慎 一橋慶喜、松平春嶽、徳川慶篤、山内容堂等15名
永蟄居 前水戸藩主・徳川斉昭等3名
斉昭は天皇の勅許を得ずに日米修好通商条約を調印した大老・井伊直弼を詰問するため不時登
城したことを理由に謹慎・永蟄居に処せられた。
安政の大獄の始まりです。
尊皇攘夷の世論の急先鋒でもあった水戸の殿様を初め多くの水戸藩士が弾圧され、
罪に問われた。
黒澤止幾子は殿様の幽閉を悲しみ、斉昭らの無実を訴えるために単身京へ上り、
君主の無実を訴える思いを「長歌」にしたため朝廷に献上しようとしました。
安政6年2月22日、茨城・錫高野の故郷の地を単身出立します。
止幾子54歳。
当時、東海道は取り締まりが非常に厳重なため、
錫高野から笠間を経て下館を通り群馬の桐生から草津に到着したのは3月2日だった。
更に、信州路から長野、松本、塩尻をへて、関ヶ原をぬけ大津から京都に入る。
安政6(1859)年3月25日 念願の京都に到着。
24日を費やした老年女の一人旅でした。
幕末の勤皇攘夷の風が世間を騒がせ、世情穏やかならざるあの時代に
なんの後ろ盾もなく、「長歌」を懐中にして、
水戸の殿様(この時点で斉昭はすでに隠居の身)の無実を訴えるべく、
単身京都を目指した止幾子の行動に後年「勤皇の女傑」と言われた所以があったのでしょう。
しかし、これだけの行動で「勤皇の女傑」と称されるのはどうなのか、
という疑問が残ります。
さて、京都に着いた止幾子は、水戸の人がよく利用する扇屋に泊まる。
京都到着3日後の3月28日、朝廷に差し出す献上の長歌を座田右兵衛之大尉に依頼する。
※ 座田右兵衛之大尉は、幕末のころ、実務にたけた官人でありながら、儒学と国学を兼ねた学者にして、
尊皇思想の実践家として重要な働きをした。その立場上、表立って指導していくことはなかったが、
時の関白や大臣、または公卿の間を取り持ち、時には利用し、事を処理していく実務面に能力を発揮した。
(京都産業大学 学術リポジトリ 「座田右兵右衛門維貞」の冒頭より引用)
その日の日記(京都捕之文)に、止幾子は下記のように記している。
いとまを告げて烏丸(扇屋)の旅館に帰りました。その夜は一睡もできずに考えました。
あの長歌をそのまま預け置けば、天朝へ届くか或いは幕府へ届くか二つに一つ、これは
大変なことになると。(引用)
「これは大変なことになる」と夜も眠れぬほど心配した割には、その結果も待たずに、
止幾子は翌朝早朝に宿を出て清水寺や伏見稲荷を詣で、
淀船に乗って大阪へ下って行ってしまいます。なぜ、郷里の錫高野に向かわず、
大阪に向かったのでしょう。
ちょと違和感を感じる止幾子の行動です。
推測される理由は二つ。
① 京都以外に目的地があった。
② 探索の追及が厳しくなった。しかし、これは郷里の錫高野と反対の方向に足を向けた
ことを考えれば、除外してもいい。
(つづく)
(読書紹介№155) (2020.9.23記)
次回 献上「長歌」の結末と「日本最初の女教師」にっいて。














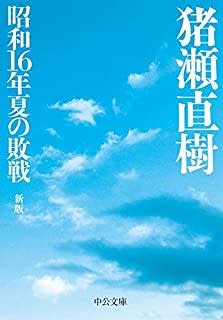 ブックデータ: 中公文庫2010.6 新版として発刊。初版は1983(昭和58)年に
ブックデータ: 中公文庫2010.6 新版として発刊。初版は1983(昭和58)年に





