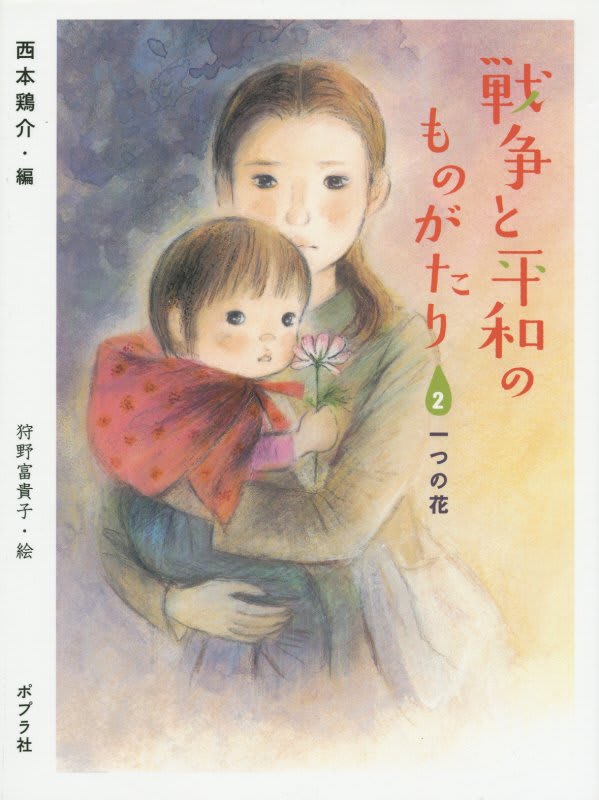ことの葉散歩道(9) (2015.5.13)
老いてゆく
超高齢社会でみんな歳を重ねておとろえていく。
加齢はすべての人が中途障害者になっていくようなもの。
どんな力のあった人もいずれ老いさらばえ、
ボケて人の世話になりながら死んでいく姿をさらす。
…略…要介護になっても、ボケても、
安心できる社会になればいいんです。
社会学者 上野千鶴子
朝日新聞(5月8日夕刊)「わたしの半生」の連載インタビューの中で、単純明快に歯に衣着せぬ論を展開する。
「中途障害者」なんて例えが良くないが、この人らしい表現である。
現実には年老いて、体力、知力とも徐々に減退し、人の助けなしには生きていけない状況が訪れる。
そうは理解していても、できることなら人間らしく生を全うしたいという思いは、万人が望む生き方だろう。
「要介護になっても、ボケても、安心できる社会になればいい」と、社会学者の上野氏は言う。
避けては通れない老いの坂道を下っていく不安は誰にでもある。
果たして、「安心できる社会」は実現できるのだろうか。
介護保険料はわずかではあるが、年々増加し、それでも自治体では資金不足で十分な介護を展開できない。
賃金の安い介護職に就く専門員も不足している。
介護施設の数も、急激な高齢化のスピードに追い付けず、入所待ちの時間は先が見えなほどど遠い。
一般的風潮として、「介護が必要になったら施設へ」という考え方がある。
確かに在宅介護は介護者に多大の負担を強いる。
そのことがわかっているから、「施設入所」という選択肢を安易に選択してしまう。
生まれて、育ち、子どもや孫がいる家で歳をとり、やがて親しい人たちに見守られて人生を全うする。
半世紀以上も前に崩壊してしまった家族の在り方だ。
経済的に満たされても、心に隙間風が吹くような社会は、「安心できる社会」ではなく、「貧しい社会」なのではないか。
豊かさの裏側で人間同士のつながりが少しずつ希薄になっていく「寂しい社会」でもある。