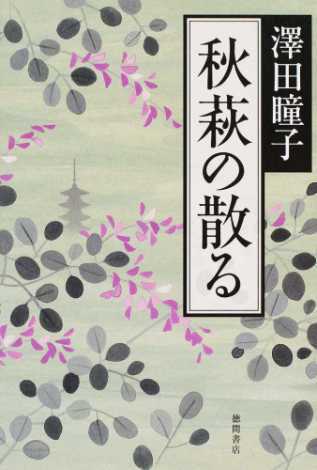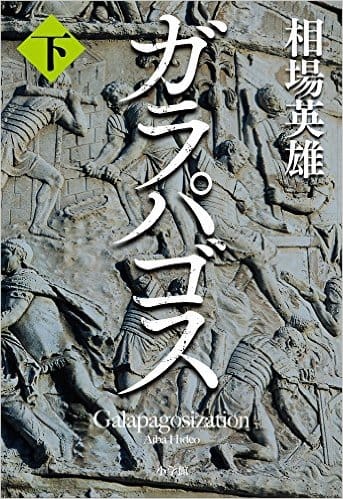読書案内「絵本・母と暮らせば」
文 山田洋次 絵 森本千絵 講談社2015.11 初版
山田洋次監督 吉永小百合 二宮和也で2015年12月に映画化された。これはその絵本版です。
長崎に原爆が落とされ、死者は7万人。
その中の一人に息子の浩二がいた。
母さんに会いたい会いたいと思い続けて、
とうとう亡霊になって3年目の命日に母に会いに出てきてしまった息子と母の物語。
どんなにつらい悲しみも、時間が経てば和らぐ、なんていうけどそれは嘘。
「悲しくて悲しくて、死んで会えるものなら死にたいと何べんも思ったとよ」。
愛する者を喪った悲しみは、当事者にしかわからない。
他者は傍観するしかない。
言葉はいらない、そっと寄り添うことが一番の心の慰めになるのかもしれない。
毎晩のように現れる息子との交流は母の生きる力にわずかながらの光を指したが、
冬の訪れとともに母の身体は衰弱していく。
亡霊の息子には、なす術がない。
毎夜訪れる息子は母の命がもういくばくも残っていないことを悟る。
戦争でひとりぼっちになってしまい、生きる力をそがれた母。
息子の亡霊との語らいは唯一の心のよりどころだったのだろう。
母さんがぼくにしがみつく。
ぼくはその母さんを抱かえるようにして星空に向かう。
死ぬことによってしか得られない、心の安堵。
この場面とアンデルセンのマッチ売りの少女が天国のおばあちゃんのところに召されていくシーンが
オーバーラップする。
「浩二、天国に戦争はないと?」、「なかよ、そがんもん」「じゃあ、きっとよかところね」。
二人は手を取り合って夜の空を駆け登っていく。 (2016.10.29記) (読書案内№89)