読書案内(再掲・改訂) 「霧笛」ルイ・ブラッドベリ著
短編集太陽の黄金の林檎より
2012.9刊 ハヤカワ文庫SF
眠りから覚めた一億年の孤独
孤独岬の灯台。
突端から2マイル(約3200メーター)離れた海上に70フィート(約21メーター)の高さにそそり立つ石造りの灯台。
夜になれば、赤と白の光が点滅し船の安全を見守る。
霧の深い夜には霧でさえぎられた灯りを助けるように、霧笛が鳴り響く。
霧笛の音……。
〔……誰もいない家、葉の落ちた秋の樹木、南めざして鳴きながら飛んでいく渡り鳥にそっくりの音。十一月の風に似た音、硬い冷たい岸に打ち寄せる波に似た音、それを聞いた人の魂が忍び泣きするような音。遠くの町で聞けば、家の中にいることが幸運だったと感じられるような音。それを聞いた人は、永劫の悲しみと人生の短さを知る〕
寂しくて孤独に震え、一度聴いたら忘れられない霧笛の音が、濃い霧に覆われた孤独岬の灯台から流れる。
霧の出始める九月、霧の濃くなる十月と、霧笛は鳴りつづけ、やがて十一月の末、一年に一度、あいつが海のかなたからやってくる。深海の暗闇の眠りから目を覚まし、一族の中の最後の生き残りが、海面に姿をあらわす。
全長九十から百フィート。
長く細長い首を海面に突き出し、何かを探すように、霧笛の流れる霧で覆われた海面を灯台めざして泳いでくる。
永い永い時間のかなたで絶滅してしまった恐竜。
数億年の眠りから目覚めその霧笛に向かって、恐竜が鳴く、霧笛が響く…。
恐竜の鳴き声は、霧笛の音と見分けがつかないほど似ている。
孤独で、悲しく、寂しい鳴き声だ。
霧笛が鳴る…恐竜が吠える…お互いが呼び合い、求め合うように呼応する。
霧笛を仲間の呼び声と錯覚し、深海の深い眠りから目を覚まし、数億年待ち続けた仲間の呼び声に孤独な怪物は灯台に近づいてくる。
その時、燈台守が霧笛のスイッチを切った。たった一匹で気の遠くなる時間にじっと耐え、決して帰らぬ仲間をただひたすら待たなければならなかった孤独。
彼は霧笛の消えた灯台に突進していく……。
喪われ二度と会えないものを待つ孤独が、読む者の心を切なくさせるSF短編である。
ハヤカワ文庫2006年2月刊 評価 ★★★★★
仲間たちが死に絶え、たった一人生き残った恐竜。
深い海の底に潜んで、気の遠くなるような永遠の時間を
仲間の誰かが迎えに来ることをただひたすら待っている。
孤独に絶えて……
霧笛の音が、彼には仲間の呼んでいる声に聞こえる。
失われていくものの孤独が、
絶滅していく生物の無言の声が聞こえてくる。
私たちは、この世に存在するものの希少なものに関心を寄せ、愛でようとする。
先人たちが作った、縄文土器の造形を岡本太郎は、芸術だと称し、
「芸術はバクハツだ」と言った。
古代人たちのまだ文字を持たなかった時代に、
創造した奇妙な形のものを『火焔土器』と名付けた。
体内に満ち溢れ、ほとばしるエネルギーが、
「炎」という形を「土器」写し取り、表現したのだろう。
あるいは洪水を恐れて、高台の日当たりのよい場所に住んだ彼らにとって、
「火」と「水」は大切な自然の恵みであったろう。
同時に、時によっては災難をもたらす元凶でもあったことを彼らは肌で感じていたに違いない。
生活に恵みをもたらす「水」や「火」はこうして土器の形へと発展していったのだろう。
水の躍動を「水紋」で表現したのも、火の躍動を「炎」のイメージとして発展させたのも、
生きるために必要な精神の具現化だったのだろう。
異形のもの 目に見えない存在
私たちは異形のもの、例えば人魚、河童などにも興味をひかれ、
各地に買ってそれらが存在した証として、それらのミイラなどが残っている。
平安の貴族社会では、物の怪など正体不明のものがこの世を跋扈し、
人を呪い殺し、感染症を流行らせた。
雪女も民話の中に座敷童と共に人々の関心を集めている。
現代ではツチノコ騒動があった。ネス湖のネッシーなど、まだみぬものへの興味は、
憧れの的であり、恐れでもある。
縄文人が造形した土器も、自然への恐れであり、自然への畏怖だったのかもしれない。
ゴジラは放射能によって生まれた怪物であり、
どのような理由があってか、文明が作り出したものを徹底的に破壊しつくす。
科学が作り出した放射能の落とし子が、その文明を破壊しつくす姿に、
どこか悲しいゴジラの文明への怒りが見えてくる。
ハリウッド映画のキングコングにも、文明社会で生きていけないコングが美女に
愛情を注ぐシーンに哀れさを感じる。
灯台が発する霧笛を仲間の呼ぶ声と錯覚して、海底の底で眠る生き残りの恐竜が、
孤独の長い時間から目覚め、現代によみがえる姿は、哀れで悲しい。
(読書案内№191) (2024.4.26記)














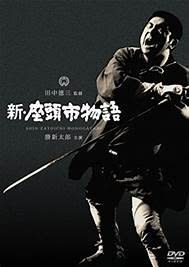

 「北越潜行の詩」詩碑
「北越潜行の詩」詩碑 

 (1994年フジテレビ放映のドラマ 2021年に再放送)
(1994年フジテレビ放映のドラマ 2021年に再放送)
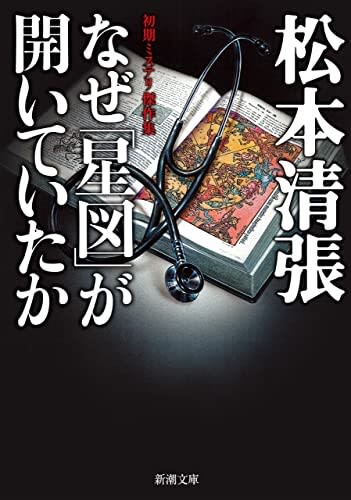 (ブックデーター:新潮文庫初期ミステリー傑作集収録2022.8刊 「殺意」「反射」「市長死す」「張り込み」「声」「共犯者」「顔」「なぜ星図が開いていたか」を収録)
(ブックデーター:新潮文庫初期ミステリー傑作集収録2022.8刊 「殺意」「反射」「市長死す」「張り込み」「声」「共犯者」「顔」「なぜ星図が開いていたか」を収録)





