そのなかで鷲田は、可傷性(傷つきやすさ)について取りあげている。人間同士の会話が「共時的な相互接触へとさらされる場所」となるためには、自分を差しだし、他者の苦しみに苦しむことである。可傷性はホスピタリティという概念に接続される。聴くことで我々は自分自身を変える、というよりも変わらざるをえないのだと論理が展開してゆく。
ここで私は著者と異なる見方で考えてみたい。すなわち人はなぜ話を聴こうとするのか。そもそも聴くという行為の原点は何なのだろうか? 一般に小さな子供は哲学者であるといわれる。かれらは他者にふれることをいとわず、自らの不安定さを無意識のままに提示する。しかしそれは、傷つきたいからという理由ではないはずだ。
たとえば我われは定まらない自己像に出会ったとき、くだけていえば不安や悩みと差しむかいになったとき、その不安定さを解消する手段として他者の言葉を意識しはじめる。企業の未来が心配な人はビジネスフォーラムへゆき、引きこもりの子供をもった親は教育シンポジウムへ足をはこぶ。これらは一対一のコミュニケーションではないものの、聴くことを思考の場として実践しているといえる。しかし、鷲田の論理でゆけば聴くことで自己が固まるのではない、脆くくずれやすいものとなるのだ。
可傷性それ自体が聴くことを求めるのではないし、それだけが場を開かせるのでもない。抽象的になるが、自分の傷つきやすさをみとめ、自己の批判と認知を繰りかえしながら生きてゆこうとするとき、他者との関係はホスピタルな場と変化する。
このレビューは役に立ちましたか? はい いいえ報告する
紙の本 本書を読んで私は息詰まり、そして触発された 2001/01/20 22:34
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
随所に挿入された植田正治の写真が実に素晴らしい。これらの写真がたとえ本文と無関係に配列されているのだとしても、読み手はそこに文脈上の関係を探り、本文とのシンクロを感じてしまうのであって、これは読者の「勝手」に委ねられた愉しみだ。
著者はあとがきで「執筆の過程で言葉を書き継げぬこともしばしばあったが、そのとき、植田さんのあの写真の横に文章を添えたいという一心でかろうじて言葉を絞りだしえたことが何度かある」と書いている。私はそこに、第一章で紹介されている詩人谷川雁氏の「この世界と数行のことばとが天秤にかけられてゆらゆらする可能性」云々ということばとの響き合いを感じた。
文章もいい。「《知識》(グノーシス、knowledge)ではなく《智恵》(ソフィア、wisdom)の粋とされる哲学的な知こそ、経験をくりかえし折り重ねるところではじめて、織り目のように浮かび上がってくるものであって、そういう時間の澱[おり]をたっぷり含み込んだ哲学のことばは、それを哲学研究者がもっとも正しく語るのかといえば、そうではあるまい。」(18頁)など、著者は言葉で遊んでいて、その思索の息遣いが聞こえてくる。
鷲田氏の思考のエッセンスは、たとえば「歴史的に局所づけられた場所で、時代が突きつけている問題を考えることで、結果として逆に、時代や場所を超えた普遍的な視界が開かれるという点に、哲学的思考の逆説的ともいえるありようがよく示されているとおもう。」(52頁)といった文章に濃縮されている。
それはまた、「だれかに触れられていること、だれかに見つめられていること、だれかからことばを向けられていること、これらのまぎれもなく現実的なものの体験のなかで、その他者のはたらきかけの対象として自己を感受するなかではじめて、いいかえると「他者の他者」としてじぶんを体験するなかではじめて、その存在をあたえられるような次元というものが、〈わたし〉にはある。」(129-30頁)という規定へ通じていくのであって、ここに述べられた「現実的なものの体験」の場が、著者のいう「臨床」だ。
臨床とは、「ひとが特定のだれかとして他のだれかに遭う場面」であり、「ある他者の前に身を置くことによって、そのホスピタブルな関係のなかでじぶん自身もまた変えられるような経験の場面」であり、そして「他人の苦しみに苦しむという感受性が、深いディスコミュニケーションのなかで交通(通じあい)が生まれるその瞬間への「祈り」というかたちをとって成就している」接触の場面でもある。
《主張するのではなく〈聴く〉ということ、普遍化が不可能であるということ、そして最後に〈臨床〉が「哲学する」者として臨床の場面にのぞむ者の経験の変容を引き起こすひとつの出来事であるということ、その意味で〈臨床〉が時間のなかにあるということ、この三重の意味において、《臨床哲学》は非‐哲学的であろうとする。》(108頁)
豊富な文献からの当意即妙の引用術といい、触発されるところの多い書物なのだが、途中で一種の息詰まりを感じた。顔、皮膚、身体、声、名、等々の語彙群、そして濃密な関係をめぐる人間学的(?)考察に息詰まる思いがしたのだ。ここで論じられている死や歴史はつねに人間の死であり歴史なのだから、それは当然のことなのかもしれない。
このレビューは役に立ちましたか? はい いいえ報告する
紙の本 私は、何故この本を読む気になったのだろうか? 2003/05/04 12:05
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
私は、何故この本を読む気になったのだろうか? なにか興味深い本の参考文献として、取り上げられていたからだった、と思う。断片的に、納得でき腑に落ちる文章がいくつかあったが、全体として何を言っていて、何故 、『「聴くこと」の力』という書名なのか、ほとんど解らなかった。しかし、臨床哲学、哲学の現場、という雰囲気は、朧げながら感じ取れたように思う。
このレビューは役に立ちましたか? はい いいえ報告する
紙の本 受け入れることの大切さ 2001/04/22 01:55
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
「哲学」という言葉から受ける印象は、なにやら難しいなあということ。哲学が、その学問の性質上どうしても難解だと思われる言葉を用いてしまうこともある。しかし、近年そのいたずらに難解な文章に対し専門家から批判が出ているのも確かだ(たとえば、アラン・ソーカル事件など)。哲学の方法が洗練されるにつれ、専門家の手に委ねられ一般の人から次第に遠い存在となってきてはないだろうかと思う。
鷲田氏は、冒頭で「哲学はこれまでしゃべりすぎた」と言う。これまでの哲学が一方的に語るものだったということを反省し、そして語る前に<聴く>ことを学ばなければならないのではないかという。こうして、本書を通して<聴く>ということが、人にとってどんな意味を持つのか、どんな力があるのか考察されていくことになる。
他者の言葉を<聴く>、あるいはじっと受け止めること。この受身の行為の力をめぐって、「歓待」ということが考察される。「歓待」についてR・シュレールは、「歓待の本質は、客をもてなす主の側には求められない。歓待の本質はあくまでも、やってくる客をめぐって規定される」と述べる。そこから、ホスピタリティというのは、「客」が相手に同化するのではなく、むしろもてなす側がそれまでの自分とは異なる者へと変わるということになる。したがって、もてなすということは、自分の同一性や自分の帰属へのこだわりを捨てなければならない。もてなす側の<掟>よりも客の側の優位であること、それがホスピタリティだという。
このような自己の同一性へのこだわりをすて、他者を受け入れるという受身の行為にホスピタリティを見出す背景には、この<わたし>という存在が、ひとりでは完結できない、自分自身で閉じるということが不可能だからだ。つまり他者の他者としてしか<わたし>を確認できない。この<わたし>が存在するためには、誰かの呼びかけが必要であり、誰かに世話を受けたので生きてこれたのだ。従って、<わたし>というのは、他者との応答からそのつど確証されるだろう。
一人では<わたし>というものを確証できない。だから、他者に無条件に受けいれてもらうという経験が大切なこととなる。
「わたし、ほんとに、生きてていいんですか?」
「いいんだよ、おまえは、そのまま」
こうして他者の存在を無条件にまるごと受容すること。無条件に存在を肯定されること。こうした経験をもてなかった者には、無条件に存在を肯定された経験をもつものがこの経験を贈り物として送る。これがケアの根っこにあるべき経験ではないか。
それにしても、この本は読みやすい。全体を一気に読みとおして気がつくのはそのことだ。それは、やはり鷲田氏の言葉へのこだわりがあるだろうし、なにより哲学がいつでもどこでも誰にでも始められるということの実践だろうか。<臨床哲学>とは、そういうものなのだろうと理解した。












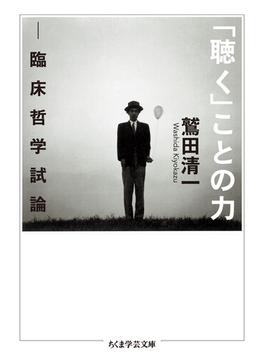 </picture>
</picture>