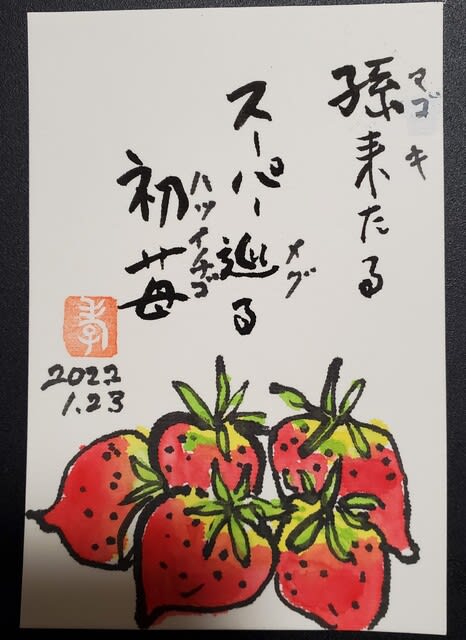ヨハン・ガルトゥング博士
1930年ノルウェー生まれ。
平和学の第一人者で世界的に「平和学の父」として知られる。
1959年に世界初の平和研究の専門機関、オスロ国際平和研究所(PRIO)を創設。
主張
戦争のない状態を平和と捉える「消極的平和」に対し、貧困、抑圧、差別など構造的暴力のない状態を「積極的平和」とする概念を提起した。
これまでに、スリランカ、アフガニスタン、北コーカサス、エクアドルなど、世界で40ヶ所以上の紛争の仲介者をした。日本においても中央大学、国際基督教大学 (ICU) 、関西学院大学、立命館大学、創価大学などで客員教授を務める。
尖閣諸島の領有権を巡って日中が対立している状況に対し、中国と日本がそれぞれ40%ずつの権益を分けあい、残りの20%を北東アジア共同体のために使うという解決案を示している。
----------------------------------------------------
「平和学の父」 ヨハン・ガルトゥング講演と映画『コスタリカの奇跡』特別上映会
2017年06月13日に開催 logmi
世界的に「平和学の父」として知られる「積極的平和」の提唱者ヨハン・ガルトゥング博士が緊急来日。
軍隊を1948年に撤廃し、社会福祉国家の道を選び、積極的平和国家作りにチャレンジしてきた中米コスタリカについての映画『コスタリカの奇跡 ~積極的平和国家のつくり方~』(配給:ユナイテッドピープル)の上映に伴い、ガルトゥング博士が「日本人のための平和論」をテーマに緊急提言を行いました。
コスタリカと比べて日本に欠けている点
関根健次氏(以下、関根):次の質問。はい、どうぞ。
質問者3:映画から、コスタリカは外交と対話から平和を構築したというのがわかったんですけど、その点において日本人はあまり自分たちの未来とか、特に政治に関することについて、対話することを避ける傾向があると思います。そういう点では、未来に対することへのイマジネーションが欠けているんじゃないかなぁと私は思ったんですけど、そのことについてどう思われますか。
ヨハン・ガルトゥング氏(以下、ガルトゥング):ご質問に関係して、3つ日本に欠けている点があると思います。1つ目は知識がもっと必要だと思います。つまり、今の世界の状況に関する知識。過去の歴史だけじゃなくて今の現状に関することの知識です。それを日本人は十分に持っていない。例えば、知識としてコスタリカがどういう状況にあるか。あるいはスイスがどういう歴史をたどってきたか。そういう知識も欠けている。
日本は表向き専守防衛となっていますが、非常に政治手腕のある安倍首相ですら、ディフェンシブ・ディフェンスと攻撃的兵器の区別をつけないで話をする。それも知識のなさだと私は思うのです。つまり、短距離の防御的な武器というのは、他の人たち、他の国に対して脅威にならないのです。
だから今、日本が武装しているような長距離を目指していて、他国を攻撃できるようなそういう武器を持つということは、決して本当の意味での国防にならないということを理解していないのではないか。
それからビジョンということをおっしゃいまいた。まさにそれが2つ目に欠けている点です。
右派にしても左派にしてもそれぞれのビジョンを持っているのですが、それは決して十分なものではない。欠陥が多すぎる。例えば、右派の人たちは外交や対外関係における日本の独立性を主張される。それは非常にいい点です。だからそれは取り入れる。
それから、左派の方の反戦的発想、ネガティブなピースで消極的平和ではありますが、それはいい点ですからそれも取り入れる。これは今でも言えるかわからないんですけども、これくらい通信網が発達しているにも関わらず、いまだに日本が島国根性的な想いがあるんじゃないかと思います。
国境を接しているお隣さんがいないということで、本当の意味でのお隣さんがいない。だから近所でもめ事があって敵みたいに思っているんですけど、あることを通して非常に友好なお隣さんになるという経験をしていないわけです。
ところが、他の世界の国々、特にヨーロッパの諸国をみてみます。血で血を洗う戦争をして、でもそれを克服して仲間になった。それはラテンアメリカについてもアフリカについても言えると思います。ところが日本はそういう経験をしていない。
そしてビジョンをもっただけでは十分ではなくて、政治家として政治的な強い意志をもって実践する、実行するという意志の力です(これが3つ目の欠けているところ)。
なぜ日本が被占領国であるのかというその一例として、例えば米軍の要人、高官その他が日本への入国手続きなしで横田米軍基地からヘリコプターで都心へ行く。そして主要省庁の上級官僚に指示を出すという米国の対日支配構造は、まさに日本は独立国とは程遠い、今なお占領下にある状態と言えます。
政府に頼らないで、例えば、いいお手本になるようにNGOが中心で手を差し伸べる。そういうことを考えたらどうかと思います。特に女性が中心となっているNGOは非常に将来有望だと思います。でも男性も除外してしまうと困るので、男性の中にも手を携えてできる人がいますから、どうぞシャットアウトはしないでください。
(会場笑)
男性にもちょっとはいい点がありますからね(笑)。
(会場笑)
関根:そういっていただいてホッとしました(笑)。
(会場笑)
今回のうちのスタッフもほとんどが女性です。最近では女性の方が活発で男性がね、もっとがんばらなきゃと思います。えー、いい時間になってきましたけれども、最後どうしても聞きたいぞっという人、短めにクエスチョンを。手を挙げていただけたらなと思います。
市民の力で戦争をやめさせるには
今回が来日最後の講演です。はい、ありがとうございます。どうぞ。
質問者4:僕はシリア和平ネットワークという組織をつくって、それはシリアでシリアの難民を人道的に助ける数々の団体が集まっているんですけれども。今は性格をちょっと変えて、シリアにおける殺戮をストップさせるための活動を去年から始めています。
伊勢志摩サミットとか、今回の定例サミットにおいて、外務省に圧力をかけてシリア人の人を呼んで大学でシンポジウムをやったりして、なんとかシリアの市民の声が今のシリアの状況に影響を与えられるように活動しています。
でも今までブレイクスルーは全然達成できていないんです。市民の力を使って戦争を止めさせるには、いったい何が足りないんでしょう?
ガルトゥング:私もシリアも含めてそういう環境の仕事をずっとやっています。あの問題に関するキーとなるアクターといいますか、当事国はイスラエルです。1985年ぐらいからイスラエルがとった対外政策で、近隣諸国をなるだけ分断しようという方針を打ち出したわけです。それが関係しています。
つまりイラクではこれが成功したわけですね、イスラエルの(分断)政策が。でシーアのセクションとか、クルドのセクションとか、スンニのセクションとか、つまりセクショナリズム的に民族間の対立を深めました。ということは分断することに成功したわけです。
それでアメリカは外交政策において、イスラエルが主張することをそのまま実行する傾向にあるということです。でもいろいろお話していると時間がすぎてしまいますから結論として言えることは、根本的に大切になるのは、真のイスラムとは何か? どんなものか? ということです。トゥルー・イスラムとは何か?
それで真のイスラムという視点から見ると、イラクにしてもシリアにしても余りにも「欧米」ではなくて「欧化」されている。ヨーロッパ化されてしまっている。イラクの場合は英国。シリアの場合はフランス。その影響が強すぎてせっかくの真のイスラムが 水増しされているのが気になっているわけです。
それでIS(イスラミック・ステイツ)が主張しているのが、真のイスラムに帰るということです。ですからシリアとイラクとかが問題なんじゃなくて、1番の問題は、メッカやメディーナの問題なんです。シリアのアサド政権、これはお父さんの代からですけれども、これはマイノリティーの政権なんですね、多数派じゃなくて。
それで彼らISからみれば、シーア派のマイノリティーが、しかも独裁者として国を統治している。それに対する反発心がある。シリアではスンニの方が多数派です。多数派なんだけれど他の要素が入ってくることをがんとして受け付けない。そういう態度をとっているわけです。
だからいずれに転んでも、それは専制的な政治になってしまう。少数派の独裁政権か、多数派の独裁政権か。いずれにしても独裁政権に終わる。そういう状況にあるわけです。こういう状況の中では勝者はISになってしまう可能性がある。それが「カリファット」という昔のイスラム圏を形成することになる。
イスラム圏では、イマーム(指導者)は発言権というか大きな力をもっているわけです。つまり聖職者であるイマームなんですけれども、それは宗教的な力を持っているだけではなくて、法制度、シャリーアのロー、法廷、司法の力も持っているのです。
イマームの地位を確固としたものにしているのは、いわゆるカリファットをベースとした力をもってサポートしていると。そういうことを理解できてないのが欧米の国だと思うんです。今、同じことがフィリピンのミンダナオ島で起こっています。
残念ながらアメリカのメディアの力が強く、日本も含めてその影響下にある国のメディアは、いったい何が起きているのか見る眼をもっていない。アメリカ的見方になってしまっている。
本当の目的はイマームに対する影響力なんですけども、それをサボタージュするかのように、いわゆるISの兵士が蛮行に及ぶことをむしろサボタージュするためにやっている。その可能性もあると思います。
私は理想主義者と思われることがありますが、実は頭の中の私は極めて現実主義者です。しかし、心の中の私は理想主義に燃えています。しかし、現実と離れた理想主義ではいけない。日本の有名な三大紙とかNHKから情報を得れば正確な情報が得られると思われたら、ちょっと間違いだと思います。
かえってYouTubeの方が適した情報が得られるかもわかりません(笑)。
(会場笑)
関根:ありがとうございます。YouTubeってオチがありました(笑)。
(会場笑)
ビックリしましたけれども。もうお時間となりますが、今回、博士は3年連続の来日でした。今回がパブリックでの最後のイベントになるわけですが、何か一言これを伝えたいというラストメッセージがありましたら是非お願いします。
ガルトゥング:創造力、独創力です。問題にうちひしがれないで創造力をたくましくもってアイデアをだす、ということです。つまり新しいアイデアをだして、もちろん明日それが実現するわけではないけれども、それで諦めないでいいアイデアをだしつづけてください。幸いこの部屋には若い方たちがたくさんおられる。その柔軟な頭で未来を考えてください。素晴らしい未来を築くための大きな責務を持っておられるのです。
本日はありがとうございました。
関根:ありがとうございました。
(会場拍手)
Occurred on 2017-06-13, Published at 2017-07-26 17:30
















![「現人神」「国家神道」という幻想 近代日本を歪めた俗説を糺す by [新田 均]](https://m.media-amazon.com/images/I/51aOTo-LtWL.jpg)