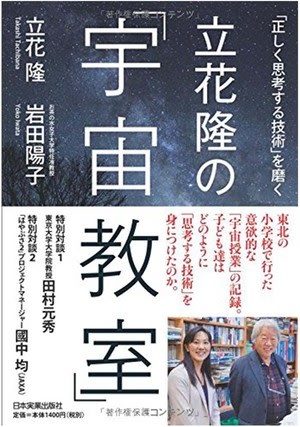『衝撃的なタイトルの本「全体主義の中国がアメリカを打ち倒す」』
『独裁的リーダーが多くなった中で、二大大国の中国と米国は!』
 『ウエブ情報から引用』
『ウエブ情報から引用』
中国人の多く住む地域、香港とシンガポールに、合わせておよそ16年間住んだことがあります。 香港は、一国二制度の前の英国のクラウンコロニーの良き時代で、中国(大陸)から香港に、事情があって移り住んだ人々との付き合いを通して中国を見ていました。 パール・バックの『大地』も読みました。一方、シンガポールは、華僑の子孫たちとの付き合いを通して、華僑のルーツ、中国を見てきました。
香港は半世紀前、シンガポールは四半世紀前でした。 その間、半世紀前・四半世紀前・最近の中国の発展ですが、その各々の時代が目を見張るスピードの変化でした。 特に、半世紀前の香港の新界(ニューテリトリー)と中国の国境の『羅湖(ローウー)駅』近くの展望台から見た深圳(シンセン)は牧歌的な田園風景でした。
その中国ですが、今では、アメリカのみならず世界中が、あらゆる面で脅威を感じています。 先ずは、この著書『衝撃的なタイトルの本「全体主義の中国がアメリカを打ち倒す」』の著者・副島隆彦氏のプロフィールのウキペデイア情報からの引用です。
1953年5月1日、福岡県福岡市生まれ。 1978年早稲田大学法学部卒業。 吉本隆明・久野久・小室直樹・岡田英弘・片岡鉄哉を師と仰ぎ、政治思想・法制度論・経済分析・社会時事評論の分野で評論家として活動。 それ以外にもカール・マルクスやフランシス・フクヤマやアイン・ランドやマックス・ヴェーバー、中村元、富永仲基、竹本久美子にも多大の影響を受け尊敬する。 日米の政財界・シンクタンクに独自の情報源を持つとのことで、「民間人・国家戦略家」として、「日本は国家として独自の国家戦力を持つべきだ」と主張している。 作家の佐藤慶からリバータリアン(*)と評されている。』
(*)リバタリアニズムを主張する人。自由至上主義者。完全自由主義者。
この著書の『そで』にこうあります。
全体主義(トータリタリアニズム)という言葉は、そのまま共産主義(コミュニズム)という言葉と置き換えても構わない。 この全体主義国家の別名がディストピア(dystopia)である。 ディストピアはユートピア(理想郷)の反対語である。 私たち人類が向かっている方向は、どうも理想社会の実現ではなくて、その反対のディストピアであるようだ。 「絶望郷」である。
半世紀も昔、お世話になった会社の香港駐在時代のことですが、元経団連会長で異名『財界総理』の石坂泰三顧問と会食(築地の老舗料亭の「金田中」香港支店で)の末席に参加させて頂きました。 顧問は、現役を引退されて、傘寿をとっくに過ぎて、なお多くの会社の顧問をされていました。 と同時に、大きなビーフステーキをいただく健啖ぶりに、呆気にとられた記憶があります。
この会食の後で、大手造船会社の香港駐在の代表の方が、顧問に、二つのお願いをしていました。 一つは『香港の中国百貨店で購入した「毛筆セット」の筆おろし』でした。 あと一つは『将来、共産主義はどうなるのでしょうか、特に中国の!』、半世紀も前のことで、うろ覚えですが、顧問のお答えは、『資本主義も、共産主義もこのまま、今のままではなく、かなり近づいた、モノ・カタチになっていくでしょう。 人間には「業」がありますので。』と。 この時の『業』は、半世紀たってもはっきりと覚えています。 『業=欲』と!
当時の中国の人口は6-7億人だったと記憶しています。 これだけの人口を養うには、共産主義か社会主義体制で、食糧と富を平等化し、個人の私利私欲『業=欲』をできるだけ避けていかないと、治めていけないだろうと素人なりに考えていましたが、過去も現在も、どこのリーダーを見ても、なかなか理想的にはいかず、貧富の差と、かなり広い範囲で飢餓が拡大しています。
この著書にはこうあります。
中国は全体主義国家である。 その別名が「共産中国」である。 みんなに嫌われるはずだ。 だが、今後、世界中がどんどん中国のようになる。 その代表的な具体例且つ証拠は、監視カメラ(CCTV。今はコミュニテイー・サーキットTVと呼ぶ)が、街中のあらゆるところに取り付けられていることだ。 アメリカも、ヨーロッパも、日本だって監視カメラだらけの国になっている。
中国では監視カメラによる民衆の動きの把握のことを『天網(ティエン・ワン)』という。 『天網恢恢疎にして漏らさず』の天網である。
監視カメラのネーミングですが、『天網(ティエン・ワン)』これほど的得ていることには驚きです。 カタカナ英語に慣れた日本語ではCCTV(Closed-circuit Television)を監視カメラと呼びます。
『天網恢恢疎にして漏らさず』ですが。 由来を探ると、
出典 老子(ろうし)・七十三章 原文
天之道、不争而善勝、不言而善応、不招而自来、繟然而善謀。 天網恢恢疏而不失(天の道は、争わずして善く勝ち、言わずして善く応じ、招かずして自ら来り、繟然として善く謀る。 天網恢恢疏にして失わず。
『天網恢恢疎にして失わず』の出典は『老子』です。 また、『天網恢恢疎にして漏らさず』の出典は『魏書』です。そして、出典が異なるだけでこの2つの言葉の意味は同じです。
この意味は『悪事をすると必ず罰を受ける』という格言ですが、これが監視社会の象徴たるツールの名前になったことです。 この格言の微妙な違いは、『漏らさず』と『失わず』の由来だけですが、簡単に分かってしまう便利な時代に生きていることが感無量です。
さて、大変横道にそれました。 表題『全体主義の中国がアメリカを打ち倒す』の引用と読後感に戻ります。
世界は中国化し、しかもディストピアに向かうという。 最先端技術の発達によって、『技術の進歩を利用して便利で豊かな生活が実現するも、一枚めくると厳しい監視社会』に世界が向かっている。 『世界政府』がないこの地球ではでは避けられないことです。
世界中のすべての国が、中国化するのである。 その代表的な具体例かつ証拠は、監視カメラ(CCTV(シーシーティヴイ。 今はコミュニティ・サーキットTV[ティビー]と呼ぶ)が、街中のあらゆるところに取り付けられていることだ。アメリカも、ヨーロッパも、日本だって監視カメラだらけの国になっている。
これからの人類がたどるのは、このディストピア(幻滅の国。絶望郷[ぜつぼうきょう]。監視国家)への道である。 中国だけがますますひどい国になるのではない。ディストピア(dystopia)はユートピア(utopia、理想郷[りそうきょう])の反対語(アントニム)である。(『全体主義の中国がアメリカを打ち倒す』
上記のようになるかは、最近の状況では微妙に変化している面もありそうです。
(記事投稿日:2022/11/10、#598)