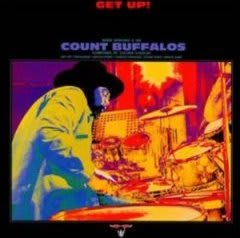金属恵比須「ハリガネムシ」
収録曲
01:蟷螂の黄昏 00:43
02:ハリガネムシ 04:19
03:光の雲 11:33
04:嵐が丘の向こうに 01:45
05:紅葉狩(第三部・第四部) 08:31
06:イタコ 02:28
07:川 05:31
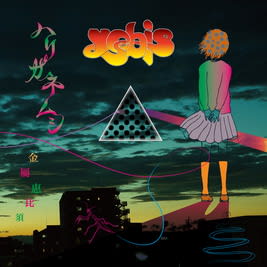
一曲目から「おお、これから『四重人格』が始めるのか!?」と
思わせてくれるSEでスタート。
※導入部ともいえる「蟷螂の黄昏」
光のような鍵盤サウンドにノイジーな効果音が重なり
一気にハードなギターが炸裂!
アルバム・タイトル曲「ハリガネムシ」だ!
なんという音圧!
アルバム全体の音圧がとにかく凄い!
「オーディオスレイヴ1st」か!?

フェイセズの「馬の耳に念仏」か!?
※結構「ジュディズ・ファーム」の音圧が凄いのよ
つ~か、ハードロックじゃん!
初めて四人囃子を聴いたときを思い出した。
和製プログレの名盤と聞いた「一触即発」だったが、ハード
ロック色も強くて驚いたものだ。
※そのうえ森園さんはデュアン・オールマンみたいな音色も
使ってたし・・・
「金属恵比須」も長い曲・短い曲を交え、変拍子とメロトロン、
アナログ・キーボードの音塊で「おお、プログレだ!」と思わせて
くれたが。
やはり70年代ロック最良のエキスを血肉として再放出する熱量が
素晴らしい!
※その辺はキュアメタルの高梨康治さんに通じるな
ダイナミックで安定したリズムセクションも秀逸。
時にアヴァンギャルドに、そして時にしっとりと聴かせる女性Vo.
・・・60~70年代の名曲フレーズや音色が見え隠れする確信犯的な
曲展開も堪らない。
※「一触触発」も隠れてますな
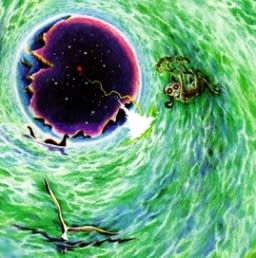
歌詞も「人間椅子」や「筋肉少女帯」系の猟奇、幻想、怪奇を
感じさせるモノで、日本独特な表現は海外ロックに対する強烈な
カウンターになっている。
今で言うヴィンテージ・キーボードを始め機材からスタジオまで
こだわってるのが窺えるサウンドも嬉しい限り。
※そういえば、ワタクシ秋に目黒のブルースアレイに
串田アキラさんのR&Bコンサート見にいきましてな。
その時、同会場の予定で「アナログ・シンセ狂時代@
プログレ秋祭り」なんてイベントを発見して、大いに
気になったモノですが。
さすがに「そんなにライヴばっかり見に行けないよなぁ」と
諦めてしまいましてな。いま実に後悔しておるんですわ。
勤め人、家族を持つ者の辛いトコロですなぁ・・・。

さてさて
「金属恵比須」のライヴはゼヒ見たいトコロです。
次回のワンマン公演は2016年4月16日(土)20周年記念として、
吉祥寺シルバーエレファントで行われるそうな。
すごい人混みになるんじゃないの?
私みたいな新規ファンが激増してそうだし。
※「ハリガネムシ」、amazon・タワレコ・ディスクユニオンで
売り切れ続出らしいですからね
出来れば
その後は、もっと大きなハコでのライヴをお願いしたいと思います。
椅子がある会場なら嬉しいです。
盛り上がったら、ちゃんと立って拍手しますから・・・。
【金属恵比須】
メンバー
高木大地(G、Kb、Vo)
稲益宏美(Vo)
多良洋祐(B)
諸石和馬(D)
宮嶋健一(Kb)
今後の活躍に期待・・・・です。
収録曲
01:蟷螂の黄昏 00:43
02:ハリガネムシ 04:19
03:光の雲 11:33
04:嵐が丘の向こうに 01:45
05:紅葉狩(第三部・第四部) 08:31
06:イタコ 02:28
07:川 05:31
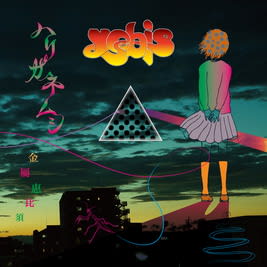
一曲目から「おお、これから『四重人格』が始めるのか!?」と
思わせてくれるSEでスタート。
※導入部ともいえる「蟷螂の黄昏」
光のような鍵盤サウンドにノイジーな効果音が重なり
一気にハードなギターが炸裂!
アルバム・タイトル曲「ハリガネムシ」だ!
なんという音圧!
アルバム全体の音圧がとにかく凄い!
「オーディオスレイヴ1st」か!?

フェイセズの「馬の耳に念仏」か!?
※結構「ジュディズ・ファーム」の音圧が凄いのよ
つ~か、ハードロックじゃん!
初めて四人囃子を聴いたときを思い出した。
和製プログレの名盤と聞いた「一触即発」だったが、ハード
ロック色も強くて驚いたものだ。
※そのうえ森園さんはデュアン・オールマンみたいな音色も
使ってたし・・・
「金属恵比須」も長い曲・短い曲を交え、変拍子とメロトロン、
アナログ・キーボードの音塊で「おお、プログレだ!」と思わせて
くれたが。
やはり70年代ロック最良のエキスを血肉として再放出する熱量が
素晴らしい!
※その辺はキュアメタルの高梨康治さんに通じるな
ダイナミックで安定したリズムセクションも秀逸。
時にアヴァンギャルドに、そして時にしっとりと聴かせる女性Vo.
・・・60~70年代の名曲フレーズや音色が見え隠れする確信犯的な
曲展開も堪らない。
※「一触触発」も隠れてますな
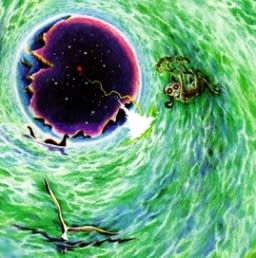
歌詞も「人間椅子」や「筋肉少女帯」系の猟奇、幻想、怪奇を
感じさせるモノで、日本独特な表現は海外ロックに対する強烈な
カウンターになっている。
今で言うヴィンテージ・キーボードを始め機材からスタジオまで
こだわってるのが窺えるサウンドも嬉しい限り。
※そういえば、ワタクシ秋に目黒のブルースアレイに
串田アキラさんのR&Bコンサート見にいきましてな。
その時、同会場の予定で「アナログ・シンセ狂時代@
プログレ秋祭り」なんてイベントを発見して、大いに
気になったモノですが。
さすがに「そんなにライヴばっかり見に行けないよなぁ」と
諦めてしまいましてな。いま実に後悔しておるんですわ。
勤め人、家族を持つ者の辛いトコロですなぁ・・・。

さてさて
「金属恵比須」のライヴはゼヒ見たいトコロです。
次回のワンマン公演は2016年4月16日(土)20周年記念として、
吉祥寺シルバーエレファントで行われるそうな。
すごい人混みになるんじゃないの?
私みたいな新規ファンが激増してそうだし。
※「ハリガネムシ」、amazon・タワレコ・ディスクユニオンで
売り切れ続出らしいですからね
出来れば
その後は、もっと大きなハコでのライヴをお願いしたいと思います。
椅子がある会場なら嬉しいです。
盛り上がったら、ちゃんと立って拍手しますから・・・。
【金属恵比須】
メンバー
高木大地(G、Kb、Vo)
稲益宏美(Vo)
多良洋祐(B)
諸石和馬(D)
宮嶋健一(Kb)
今後の活躍に期待・・・・です。